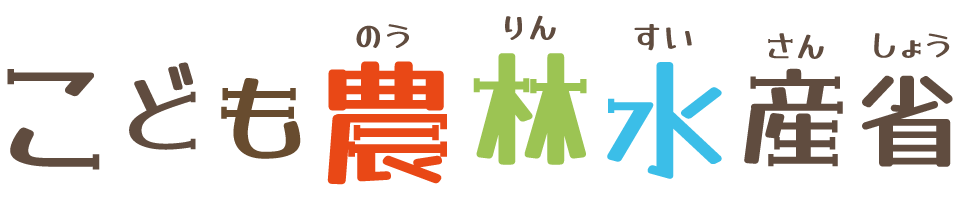イネはどこからきたの?


イネの生まれは中国南部の山岳地帯と言われているよ。
世界への広がりかた
イネは、中国南部の雲南~ラオス、タイ、ビルマ周辺に広がる山岳地帯で生まれたとされています。
そこから北の方に広がっていったのが、寒さにつよいジャポニカという種類です。中国などの温帯での栽培にむくイネです。
南に下って、インドや東南アジアに広がったのがインディカという種類になりました。湿度と気温が高いところ、雨季と乾季がある気候での栽培にむいています。
そしてインディカとおなじく南に広がり、熱帯の高地でつくられるようになったのがジャバニカという種類のイネです。寒さにつよく、乾燥した土地でも育ちます。
やがてイタリア、アフリカの地中海沿岸、マダガスカル、南米にまで広がっていきました。
日本での広がりかた
縄文時代後期に、朝鮮半島か中国の揚子江あたりから、ジャポニカが北九州に伝わりました。およそ2,000年前の弥生時代中期には、本州の一番北(今の青森県あたり)でも、イネがつくられていたようです。北海道は一番遅く、明治時代になって、やっとつくられるようになりました。
令和4年度では、日本人1人あたりで年間50.9kgのコメを食べていますが、昭和40年代までは、1人あたり約100kgも食べられていました。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3073)
ダイヤルイン:03-3501-3779