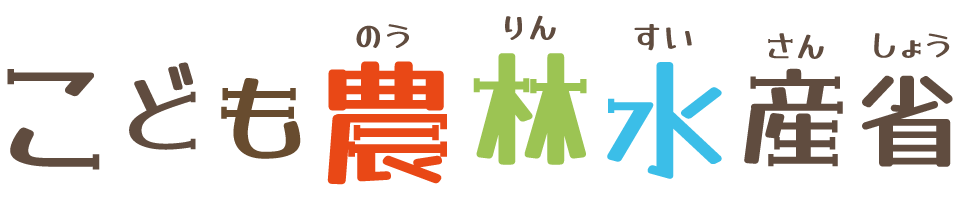サツマイモができるまで

農家でのサツマイモのつくりかたを見てみよう!
1. 苗をつくる
サツマイモは種をまくのではなく、苗を畑に植えます。種いもを消毒してから、適当な湿度をあたえて芽を出させます。これを苗床でちょうどいい長さに育てたものを、切りとって使います。最近では、ウイルス病にかかっていないバイオ苗を使うことも多くなってきました。

2. 植えつけ
空気を通りやすくしたり、水はけをよくするために、畑をたがやします。この時いっしょに、肥料をやり、うねをつくります。地面の温度が18℃以上になったら、苗を植えつけます。早すぎてもおそすぎてもじょうずに育たないので、九州など西日本では4月の終わりごろ、東北では5月終わりごろまでに終わらせます。

3. 施肥
チッソが多いと、「つるぼけ」といって葉やつるだけが元気よく育ち、サツマイモが大きくなりません。化成肥料だけでなく、家畜の堆肥を使うのもよいのです。
4. 防除
サツマイモは病気や虫の被害が出にくいですが、農家もいろいろな努力をしています。
- よい種いもを使う:病気や虫がついていないものを選び、消毒します。
- 土を消毒する:センチュウという虫がでないように、畑に薬をまいて消毒します。
- 輪作:同じ畑につづけて長くつくっていると、連作障害といって、とれる量が少なくなってしまいます。そこで、2、3年交たいで、いろいろな作物をつくったり、夏はサツマイモを、その前後に野菜をつくったりします。
5. 収穫
つるを切ってからいもをほり取り、よいものだけを選びとります。収穫は植えつけとならんで、最も時間のかかる作業です。

6. 貯蔵
貯蔵するのに一番よい状態(温度13~15℃、湿度80~90%)に保って、次の年に収穫したものが出回るまで、少しずつ出荷しています。
サツマイモは根の太ったもの

サツマイモは根が太ったもので、その根には2種類あります。根は肥料を吸う力が強いので、ほかの植物が使えないところの肥料まで吸い上げることができます。
吸収根:苗の切り口近くから出る細い根で、水や肥料を吸い上げます。
不定根:葉柄の付け根から出る太い根で、これが太ってサツマイモになります。

茎は地をはってのびていき、6~7mの長さになるものもあります。葉は6枚ごとに同じ向きについて、かさなり合わないようになっています。

アサガオのような花がさき、あとには実がなって、種もとれます。もともと熱帯の植物なので、日照、養分などの条件がそろわないと花はさきません。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3073)
ダイヤルイン:03-3501-3779