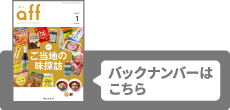みんなで動植物を守ろう
動物や植物の病気を防ぐため、私たちにはどのようなことができるのでしょうか。クイズを通して考えてみましょう。
動植物の検疫に関する
○×クイズ
- ヨーロッパで売られているものであれば、
ハムやソーセージなどの肉製品は
すべてお土産として日本に持ち帰ることができる。 -
動物検疫が必要な肉、ハム、ソーセージなどの肉製品を外国から国内に持ち込む場合、輸出国政府機関発行の検査証明書が必要です。ヨーロッパには、日本向け検査証明書が添付されて販売されているものはありません。
- 免税店で売られている肉製品であれば
持ち込むことができる。 -
販売員から「日本に持ち込める」といわれたものでも、検査証明書の無い肉やハム、ソーセージなどの肉製品を持ち込むことはできません。
- 肉製品を国内に持ち込んでも
罰せられることはない。 -
法律に基づき、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになっています。
- 日本国内のスーパーで購入したハムやソーセージは
すべて国外へ持ち出せる。 -
渡航先の国が持ち込みを認めており、受入条件を満たす場合は持ち出せます。渡航先の国によっては、違法な肉製品の持ち込みにより処罰されることがあるので、動物検疫所のWebサイトなどで受入条件を確認してください。
- 免税店など海外で購入した果物などは、
病害虫がついていなければ、そのまま日本に持ち込める。 -
病害虫の付着の有無にかかわらず、法律で日本に持ち込むことのできない果物や植物が多くあります。また、持ち込めるものであっても、植物検疫証明書の取得などさまざまな条件をクリアする必要があります。持ち込みを希望する場合、事前に植物防疫所のWebサイトで調べるか、お近くの植物防疫所に問い合わせてください。
- 精米などの穀類・豆類は植物検疫の対象ではない。
-
精米や大豆などの穀類・豆類も病害虫が付着するおそれがあることから対象となっています。ただし、レトルト食品や缶詰などは対象外です。
- 日本の空港には肉類だけでなく、
植物を探知する犬がいる。 -
手荷物の中からリンゴやマンゴウなどの果物を発見するため特別な訓練を受けた検疫探知犬が全国の主要な空港で活躍しています。
- 現在、病害虫により国内での
移動が禁じられている植物がある。 -
例えば、沖縄県や鹿児島県の奄美群島では、アリモドキゾウムシなどの病害虫が発生しています。これらの病害虫が広がってしまうのを防ぐため、生のサツマイモは本土などへの持ち出しが禁じられています。その他にも、規制されている地域や植物があるので、詳しくは植物防疫所のWebサイトをご覧ください。
- 日本で購入した果物なら、病害虫がついていなければ、
そのまま海外に持ち出せる。 -
そのまま持ち出せる国も一部ありますが、各国それぞれが植物検疫制度を持っており、持ち出せない植物の種類や証明書の取得などさまざまな条件を定めています。詳しくは、植物防疫所のWebサイトをご覧ください。
- 日本で輸出入植物の検査が始まったのは、
1926年(昭和元年)以降だ。 -
植物検疫は1914年(大正3年)に輸出入植物取締法が制定されるとともに、農商務省植物検査所が設置されて始まりました。
ペットの健康に関する
○×クイズ
- 2000年以降、狂犬病で亡くなった日本人がいる。
-
2006年に海外で犬に咬まれて感染した人が、帰国後に発症して亡くなった例があります。
- 狂犬病は犬と人間だけがかかる病気だ。
-
人を含むすべての哺乳類に感染します。感染した動物に咬まれ、唾液中のウイルスが体内に侵入すると感染します。海外ではキツネやアライグマ、コウモリなどに咬まれてかかった例があります。日本は数少ない清浄国(発生のない国)の1つです。
- くしゃみや鼻水など風邪のような症状のある
犬や猫と接触しても人間にはうつらない。 -
人獣共通感染症には狂犬病やレプトスピラ病、犬糸状虫症(フィラリア症)、トキソプラズマ症などさまざまな種類があります。その1つ、細菌が原因となるコリネバクテリウム・ウルセランス感染症は動物のくしゃみを吸い込むことで人にもうつります。
- 何の症状もない犬や猫であれば咬まれても問題ない。
-
犬や猫の口の中の菌が原因となるパスツレラ症は、動物に症状はありません。しかし、人間はひっかかれたり咬まれたりして感染すると、傷口が腫れるだけでなく、気管支炎や肺炎などを起こすことがあります。
- 耳が臭いのは病気のサイン。
-
菌の感染などによる外耳炎や中耳炎、内耳炎などの病気などにより、耳が臭くなることがあります。
- 犬のふけは自然な現象だから、多くても心配はない。
-
ツメダニなどの寄生虫などを原因とする感染性皮膚炎にかかるとふけが多くなります。また、皮膚にいる真菌の増殖による皮膚糸状菌症は脱毛が起こります。特に、ふけの他、かゆがっている様子や脱毛などが見られるときは注意が必要です。
- 犬や猫もアトピー性皮膚炎になる。
-
ダニやハウスダストへのアレルギー反応は犬や猫の皮膚にも出ます。
- 犬や猫もマダニによる病気にかかることがある。
-
バベシアという原虫が原因のバベシア症や細菌が感染するライム病などがあります。特に夏場の外出は、マダニがつかないよう、できるだけ草むらに入らせないようにしてください。定期的に駆除する薬を使うのも有効です。
- 犬を水辺で散歩させるとき、
河川の水を飲ませても問題はない。 -
主に野ネズミの尿中から排出されたレプトスピラ菌に汚染された水を飲むことなどにより、レプトスピラ症に感染するおそれがあります。河川敷などでの散歩では注意してください。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449
FAX番号:03-3502-8766