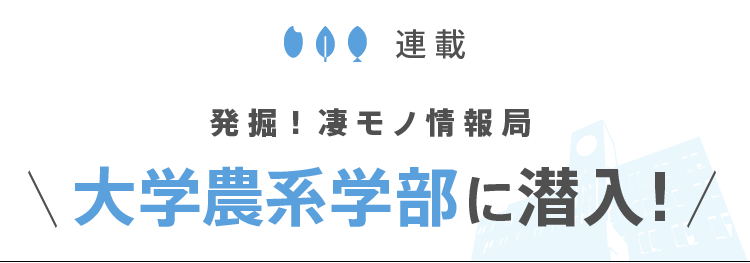
大学の農系学部が研究・開発した製品と、その製品化までの道のりを紹介します。
第4回
耕作放棄地を活用して栽培
地域活性化の糸口に!琉球大学の精油

近年、耕作放棄地を利用して新たなビジネスを起こそうという動きが広まりつつあります。そのひとつが、沖縄県の琉球大学と地元企業の(株)オキネシアによる「琉大精油」の開発です。
琉球大学は、どうやって精油に地域活性化の糸口を見出したのでしょうか? 今回は、琉球大学の研究がビジネスとして発展するまでのストーリーを紹介します。
精油作物の栽培で
地域を元気に!
沖縄県の北部地域は、高齢化による過疎化が進み、県内でも特に耕作放棄地問題が顕著となっている地域です。しかし今、琉球大学と(株)オキネシアが産学連携で精油の開発を進めていることで、一度は荒れ果ててしまった耕作放棄地が、豊かな香りあふれる精油を産み出す土地へ蘇ろうとしています。
木材資源確保のための研究から
発展した精油植物の栽培

琉球大学が精油を開発するきっかけとなったのは、メラルーカ属樹種(ティーツリー)の産業への利用を目的とした植林の可能性を探るための研究でした。沖縄県には山がほとんどないため、木材資源を豊富に揃えることができません。そこで、琉球大学の諏訪准教授は、耕作放棄地を利用し、沖縄の亜熱帯の気候や県北部の酸性土壌に適したティーツリーを栽培すれば、木材資源が確保できるのではないかと考えました。また、ティーツリーは精油原料としても知られていたことから、精油の国内での需要の動向についても調査を行いました。その調査により、高い需要があるにもかかわらず、ほとんど国内供給が満たされていないことが判明したため、ティーツリーの栽培を行うことで、副産物である精油の生産も可能になると判断しました。そして、精油の国産化の一例として研究がスタートしたのです。
また、同県ならではの地域特性と、精油が持つ特質を鑑みたとき、以下の3つのことも精油植物の栽培の研究を後押しする理由となりました。
-
1
県内で
最終製品まで
製造可能沖縄県は本土から遠く離れているため、化学工業や鉄鋼業など多くのエネルギーを消費する産業の集積がありません。また、材料の輸送にもコストがかかります。そのため、沖縄では大量生産・大量消費向けのものづくりは決して現実的ではありません。しかし、高品質であることを求められる精油は比較的少量で取引されるため、大規模な工場を建てる必要がなく、県内で材料の調達から製品化まで全てを管理することが可能です。
-
2
“沖縄県でしか
できない”が
大きな
付加価値に高級精油の原料となる植物には熱帯や亜熱帯地域に生育しているものが多く、日本では沖縄県でしか栽培できない精油植物も存在します。そこで、この気候風土を活かした精油を開発すれば、「日本国内では沖縄県でしか生産できない」という点が大きな付加価値となります。
-
3
精油と
沖縄県が持つ
良いイメージが
リンクしやすい“沖縄県”と聞いたときに、多くの人が美しい海や豊かな自然、独自の琉球文化などを思い浮かべます。精神を豊かにするための手段として利用される精油は、沖縄が持つそうしたイメージとリンクしやすく、地域ビジネスとしての相性がよいと考えられます。
以上の理由から精油の開発に地域活性化への可能性を感じた琉球大学は、原料となる植物の栽培に本格的に取り掛かります。
過疎地でも生産者を
確保しやすい栽培体系づくり
高齢者が多い過疎地でも継続的な生産を可能とするためには、多大な労力や細かなメンテナンスを必要としないことが条件となります。さらに、担い手の拡大を目指すのであれば、生産者がきちんと利益を得られることも重要です。そこで琉球大学は、大学の農業技術を応用し、以下のような栽培体系や生産体制の整備に取り組みました。
-
1
栽培に多大な労力を必要としない植物の選定
耕作放棄地に最初に移植する精油植物には、もともと研究対象であったティーツリーに加え、畑を守るためのグリーンベルトとして活用され、県内ですでに豊富な資源があるベチバーが選ばれました。どちらも生命力が強く、多大な労力をかけなくてもよく育つため、人手が少ない過疎地での栽培にはうってつけの植物です。
現在は上記の2種類に加え、レモングラス、ユーカリ、ミントなどの栽培も行われていますが、いずれも同様の理由から選定されています。
耕作放棄地に移植されたティーツリー。
-
2
栽培から採油までの技術を
生産者へ移転精油の素材として栽培されている植物は、もともとは沖縄県にはなく、ほとんどが外部から導入されたものです。そのため、管理の仕方や収穫のタイミングなど、まずは栽培技術を確立する必要がありました。そして、栽培や採油の技術を生産者に伝え、その過程を一貫して生産者が行うことで、より多くの所得が得られる生産基盤をつくることを目的としています。

収穫したティーツリーの葉。

収穫した葉を裁断し前処理を施す。

葉を抽出用の窯に入れる。

蒸留して精油を採油する。
-
3
(株)オキネシアと生産者の
マッチング栽培から採油までは生産者が行いますが、消費者への販売ルートの確保は、大手の化粧品会社や精油産業が圧倒的シェアを占める中で生産者には困難です。そこで、自社の精油ブランドを持つ(株)オキネシアが生産者と消費者の間に入り、生産者が卸した精油から同社が最終製品を作り消費者へ届ける、というステップを経て、生産者から消費者へ精油を届けることを実現しました。
\卒業生の声/
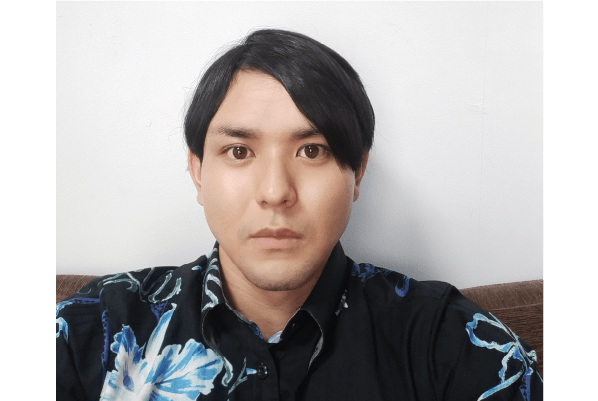
琉球大学 農学部
亜熱帯農林環境科学部 作物学研究室
安里 武尚さん
在学時は、沖縄県北部で栽培したメラルーカ属樹種から採油される精油(通称:ティーツリーオイル)の組成と光量や樹高との関係性を調べ、合わせてメラルーカ属の木材としての利用の可能性に関する研究を行いました。
ティーツリーオイルはアロマや化粧品などに加工されることが多く、沖縄県産ブランドとしてのさまざまな商品開発が期待されます。研究では原料の生産から精油への加工を経験する事ができ、とても貴重なものでした。私は現在、県内の観光関連の会社に勤めていますが、いつか県産の原料から作る商品開発に携わりたいと考えています。
沖縄県産素材のみから誕生した「琉大精油」
こうして、地元企業や生産者と連携して誕生した沖縄県産素材100パーセントの「琉大精油」(ティーツリーとベチバーの2製品)。市場には多種多様な精油製品が存在しますが、「琉大精油」は同大学の研究により、原料となる植物の選定や含有成分の分析など、学術的な裏付けがされていることから、品質的にも信頼性の高いブランドになりました。
マスクスプレーの作り方
精油の用途は美容やリラグゼーション、医療、予防医学など実に様々ですが、私たちが日常で使用するとしたらどんな使い方があるのでしょうか。ここでは、「琉大精油」を使用した手作りマスクスプレーの作り方をご紹介します。
用意するもの
-
- ガラスのスプレーボトル(20ミリリットル)
-
- 植物性グリセリン
- 5ミリリットル
-
- 精製水
- 15ミリリットル
-
- 琉大精油(ティーツリー)
ボトルの中で精油1滴とグリセリンをよく混ぜたら、精製水を加えるだけで完成です。酸化して香りが変わるのを防ぐためにも、なるべく1週間以内を目安に使い切りましょう。
ティーツリーはすっきりとした森林浴系の香りで清潔感があり、リフレッシュしたいときに最適。暑い日はハンカチやタオルにシュッとスプレーをして汗を拭くことで爽快感も感じられます。

琉球大学は今後のミッションとして、沖縄県産の精油製品のラインナップを広げ、販売ルートを確立することで、精油植物の栽培が県内の農業生産者や新規就農者にとって新たな選択肢となること、そしてそれが地域のさらなる活性化につながることを目指しています。
そのためにも、「琉大精油」の種類を増やしていくだけでなく、精油をブレンドしたミストスプレーなど、二次製品、三次製品の開発にも取り組んでいくそうです。さらに、「(株)オキネシア」のオンラインショップで「琉大精油」の取り扱いが始まることで、全国の消費者が製品を手に入れやすくなります。
自由に沖縄県への旅が楽しめない今だからこそ、島の香りが詰まった「琉大精油」のアイテムで、ちょっとした旅気分を楽しんでみるのもよいかもしれません。
琉球大学
沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
098-895-8012
https://www.u-ryukyu.ac.jp/
|今回 教えてくれたのは|

琉球大学 農学部 亜熱帯農林環境科学科
諏訪 竜一 准教授
2009年から琉球大学農学部亜熱帯農林環境科学科 植物機能学講座 作物学研究室所属。作物学を専門とし、熱帯地域および沖縄県の在来の作物の生産方法や、これらの生産物を活用した地域活性化に関する研究を行っている。

琉球大学 研究推進機構研究企画室
主席リサーチアドミニストレーター(教授)
殿岡 裕樹 教授
2015年琉球大学研究推進機構研究企画室のリサーチアドミニストレーター就任。同大学の研究活動をより総合的に幅広く展開することを目指し、産学連携による研究開発などをサポートする。
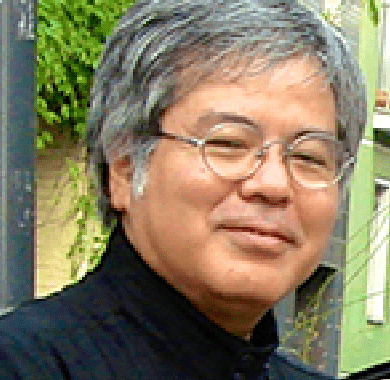
(株)オキネシア
金城 幸隆 社長
沖縄菓子やフレグランスを中心に、沖縄の歴史や文化が感じられるだけでなく、再興や地域活性化につながるような商品開発を目指す。

琉球大学 研究推進機構研究企画室
副主任リサーチ・アドミニストレーター
河野 恵美子 さん
アロマテラピーの資格認定校非常勤講師を経て、2015年から琉球大学研究推進機構研究企画室所属。(公社)日本アロマ環境協会AEAJアロマセラピスト・アロマテラピーインストラクター・環境カオリスタの資格を活かした研究者支援に従事。

この記事のPDF版はこちら
(PDF : 854KB)
こちらの記事もおすすめ
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449















