木が教えてくれること 「木育」のすすめ

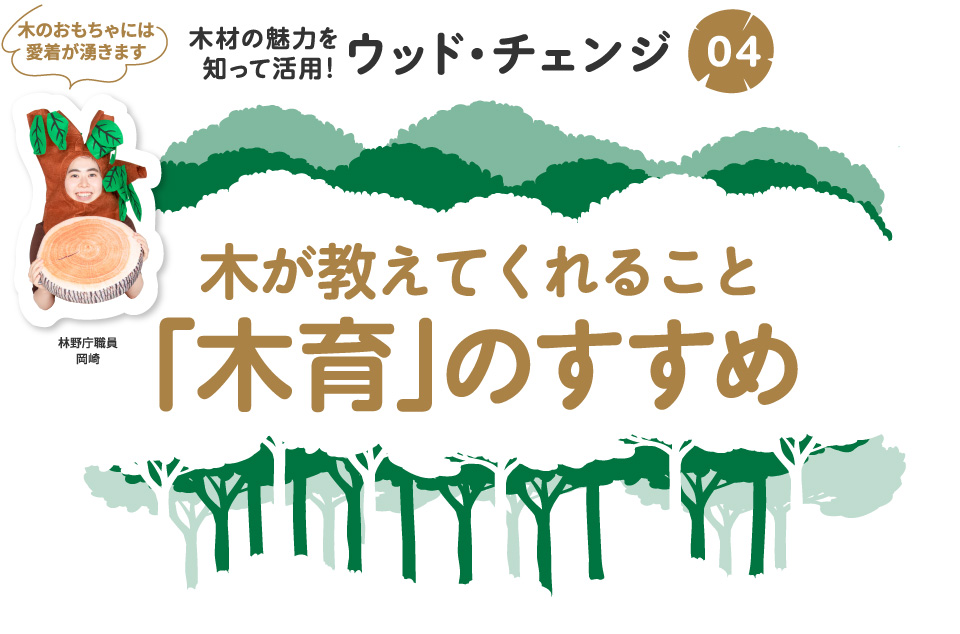

多くの人を「木」のファンにしたい
お話を聞いた方

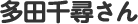
東京おもちゃ美術館 館長
「木育ひろば」では赤ちゃんが泣かない
東京おもちゃ美術館には、「赤ちゃん木育ひろば」という部屋があります。温かく柔らかい無垢のスギ材のフローリングを敷き、大きな木製のオブジェや手のひらサイズの「スギコダマ」をはじめとするたくさんの木のおもちゃを置いています。
不思議なことに、この部屋では赤ちゃんがほとんど泣かないんです。木に触れることで心が落ち着くんじゃないでしょうか。また、子どもに限ったことではなく、保護者の方にも同じことがいえます。お父さんやお母さんも落ち着いて過ごせるから、赤ちゃんといっしょに遊んだり休んだりしています。滞在時間も長いんですよ。

「赤ちゃん木育ひろば」には国内10地域のスギが使われていて、温かな空間をつくりあげている。右下に数十個置かれているのがスギコダマ。

兵庫県産の木製そろばん玉が大きな箱いっぱいに置いてあり、子どもたちは手のひらいっぱいにつかんで遊ぶ。
おもちゃになっても木は「生きている」
木のおもちゃは、何年、何十年経っても使い続けることができます。色は変化しますし、削れたり丸みを帯びたりと形を変えることもあります。それでも捨てられることなく愛され、世代を超えて受け継がれるのは、おもちゃになっても木は「生きている」からなんです。
身近に、ご両親やその上の世代の方の使っていた羽子板やけん玉やコマはありませんか? 大切に使ってきたぬくもりや思い出もいっしょに受け継ぐことができるのは木のおもちゃだからこそだと思います。

北海道産の広葉樹の木玉が2万個入った「木の砂場」はまるでプールのよう。

木の野菜を収穫して、木のキッチンで調理して食べるといった食べ物の流れを体験。
暮らしの中に少しずつ木を取り入れてみて
身近に木がある暮らしは、心を落ち着かせるだけでなく日本の森林の活性化にもつながります。とはいえ、すべてを一度に木で揃えましょうということではありません。

例えば、「国産材の木のおもちゃを誕生祝いにしよう」など、お子さんに木のおもちゃをひとつ、ふたつと用意してあげるところから始めてみてはどうでしょう。木のおもちゃに触れて楽しむことで、みんなが木のファンになってほしいですね。そして、次に何かを買い替えるときに「木の製品にしようかな」と検討してほしい。そんなふうに思っています。
木育というと、「小さなころから木に触れ、木と生きていくこと」と捉えがちですが、年齢を問わず誰にとっても必要な取り組みです。木のおもちゃが、少しずつ暮らしの中に「木」のぬくもりを増やしていくウッド・チェンジのきっかけになるとうれしいです。
農林水産省には
木がいっぱい!
「ウッド・チェンジ」ツアー

農林水産省では、暮らしの中に木材製品を取り入れることで、日本の森林を育てていく「木づかい運動」を推進しています。霞が関にある庁舎内も木がいっぱい使われています。

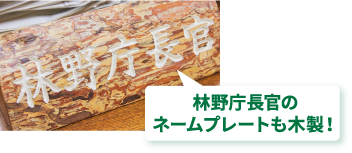
林野庁長官室。壁や床をはじめ、小物まで木がふんだんに使われています。

木目の美しさが目を引く通勤カバンは、高知県のスギの間伐材から作られているのだそう。
小島裕章 林野庁木材利用課長
(※2023年6月撮影当時、現輸出・国際局国際経済課長)

こちらの曲げわっぱのお弁当箱は、田端さんが小学生のとき長野県の木曽へ旅行に行った際、お祖母様に買っていただいたものなのだとか!
田端朗子 林野庁木材利用課 課長補佐


ワークデスクや打ち合わせスペース、棚など至る所に木があふれています。

廊下に設置された自動販売機にもふんだんに間伐材が使われています。


2017年に設置した農林水産省の事業所内保育所も、企画段階から林野庁が関わり、木がいっぱい。内装や設備をはじめ、子どもたちは木製の玩具で楽しそうに遊んでいました。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449









