木材の可能性に感動! 「ウッドデザイン」の魅力

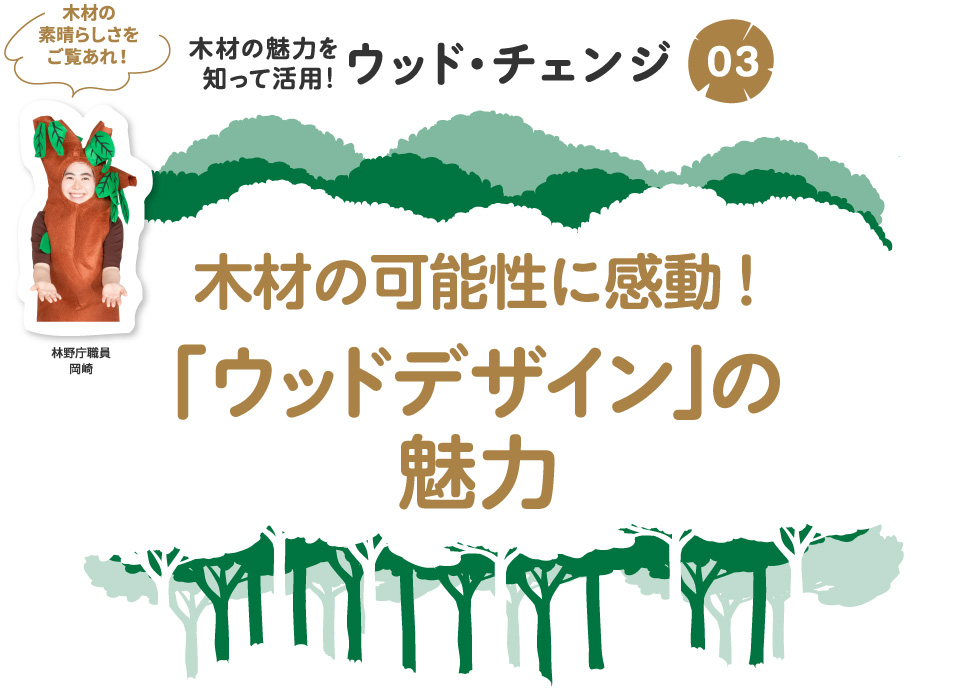

専門家に聞く!
「ウッドデザイン賞」受賞作のここが素晴らしい

9年目を迎えた「ウッドデザイン賞」の役割
「ウッドデザイン賞」は、木で暮らしと社会を豊かにするモノ・コトを表彰し、国内外に発信するための顕彰制度として2015年にスタート。受賞製品について広報・PRの場が提供されるようになったことで、日本の木材利用事例の注目度は年々高まりをみせています。生産から商品に関わる人同士のマッチングも進み、次のイノベーションへとつなげることにより、出品されるプロダクトやビジネスモデルも拡大してきました。現在では、洗練された意匠や機能的な空間提案だけにとどまらず、複数の社会問題を横断的に解決するような取り組みも増えています。

「自然の中にあるもう一つの家」を提供するサービス。月額5万5000円のサブスクに登録することで、都心から好アクセスの自然立地における環境配慮型の木造キャビンを自由に選択し、宿泊することができる。
赤池SANUは、環境配慮型の木造キャビンというウッドデザインに、サブスクで泊まれるという楽しさを組み合わせた点がビジネスモデルとして非常に優れていると感じました。実際、現在の稼働率は8割超と大変人気です。
鈴木木造のキャビンは山との親和性がありますし、柱を立てて建物の基礎を上げるなど環境への配慮をする形で建てられていますね。

木の温もりを感じる室内。窓からは森の風景を望め、まるで木に囲まれているかのよう。
赤池さらに釘やビスを極力使わず、組み立てやすく解体しやすくしているという建築の工夫も。そのためきれいに分解して、よそへ移設することも可能です。さらに収益の一部で植林をするなど、自然への負荷を最小化したサーキュラー型建築となっています。
鈴木いろいろな場所で実践できるので、ビジネスとしても広がりがありますね。
赤池そうですね。サブスク型なので多様な地域への訪問を促進できるのもポイントです。現在国内に11拠点ありますが、これからさらに増えていくそうです。

静岡県浜松市にある、地元食材を使った料理を提供する飲食店。店舗には日本三大人工美林のひとつである天竜の木材がふんだんに使用され、浜松の魅力を五感で味わうことができる。
鈴木2021年に全面改装されたこのお店には、地元の上質な天竜材が使われています。戦後に植林された人工林のスギやヒノキが使いどきを迎えていて、立派な大径木(たいけいぼく)をふんだんに使える状況にあるんですね。フシのないスギの木目の美しさに圧倒されそうです。
赤池このお店は、もともとオーナーが浜松の水産物や農産物を生かした「浜松料理」というものを確立しようという思いからスタートしているんです。それなら、内装にも地元の天竜材を活用しようと。

天竜材の木質を生かした店内で、地元浜松でとれた新鮮な魚や野菜を使った料理が楽しめる。
鈴木食も木材も地域資源を活用し、地域の魅力を発信する。地域の事業者の協働によるウッドデザイン開発の良例ですね。
赤池現在こうした事例は広がりを見せて、例えば新潟県の佐渡島でも地元の食材を使った佐渡料理を確立しようという動きがあります。佐渡は良質な木材の産地でもあるので、店舗はその木材を生かして作る計画がされるなど、今やウッドデザインが地方の産業振興のエンジンにまでなっているんです。

東京都心の木造密集市街地(準防火地域)に建つ木造2階建て住宅。建物外観など木材をあらわにしながらも、地震や火事に負けない設計上の配慮をしている。
鈴木堀切の家が建つのは東京下町の準防火地域なので耐火構造である必要があるのですが、ここは木材をあらわにしながらそれをクリアしています。木材ってすぐに燃えてしまうイメージを持たれている方もいるのですが、そうではないんです。燃焼速度は1分間に約1ミリといわれているので、30分もたそうと思えば燃えしろとなる部分が3センチ厚ければいい。現在は戦後に造林した木の分厚い材が利用しやすくなっているので、それを生かした防火対策が可能です。
赤池近年はコロナ禍により家で過ごす時間が増えたことから、木のある庭を作ったり、内装に木材を生かしたりしたデザインの分譲戸建てが増えてきていますね。

道路に面した側には、板張りの縁側が。近隣住民とのコミュニケーション空間としても機能する。
鈴木今の木造住宅は、日本の建築の良さを残しながらもだいぶ洗練されてきました。木の質感が町にやすらぎを与えると同時に、縁側があることで外にも開かれコミュニケーションが生まれそうなのもこの家の魅力でしょう。
赤池都市部で木造建築物を計画する際のお手本のような住宅ですね。
このほかにも、ウッドデザイン賞には木材の魅力や可能性を感じられる受賞作がたくさんあります。
国内初の高層ハイブリッド木造ホテル
ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園
2021年受賞・優秀賞(林野庁長官賞)

北海道産材を積極活用した木質感のある空間づくりで、宿泊客にリラックスした時間を提供。「内装だけでなく、建物の上層3階を木造にすることで建築物としての重量を抑えるなど、木を生かすメリットが考え抜かれています」(鈴木)
自宅の風呂を公共性のある銭湯に
神水(くわみず)公衆浴場
2021年受賞・奨励賞(審査委員長賞)

2016年熊本地震後風呂に困る人の姿を見て、自宅の1階で銭湯を開業。地域に開かれた交流の場に。「伝統的な重ね透かし梁りとCLTのアーチで、コストを抑えながら大地震に耐える作りに」(鈴木)。災害発生時は避難所としての役割も担う。
最小限のコストと材料で実現した開放的な海の家
TRIAXIS(トライアクシス)須磨海岸
2021年受賞・優秀賞(林野庁長官賞)

「子どもと楽しむ海の家」がコンセプト。海の家という時限的な施設で、木造建設の良さが追究されている。「安価かつ少ない材料で、木の素材感が際立つ開放的な空間を作ることに成功しているのが見事」(鈴木)
中身成分にもパッケージにも樹木を活用
BAUM(バウム)
2021年受賞・奨励賞(審査委員長賞)

樹木の力を中身成分からプロダクトにまで応用。パッケージの木製パーツは繰り返し使用でき、樹木由来の天然香料が心地よく香る。「デザイン性も高くサステナブル。地元の木材を使ったコスメなど、地域企業への広がりも期待」(赤池)
木質を生かし日本の住宅にも馴染む洗練デザインに
木質ペレットストーブ「OU」(オウ)
2020年受賞

外装部品に、山形県産の杉材の圧密成型合板と鋳物を採用。「ストーブの外装を木質化したデザインで、日本の住宅にも調和します」(赤池)。燃料であるペレットが、地域の間伐材や未利用材の活用にもつながるという利点もある。
温もりのある質感と耐久性を兼備した木の自転車
木製自転車スポーツタイプ TR-S型 E-Thruタイプ
2021年受賞・優秀賞(林野庁長官賞)

無機質な自転車に、木目の柔らかな質感で温もりをプラス。木製フレームとしてJISの試験基準をクリアし耐久性も確保。「独創性の高い作品。現在は、木の弾力性を利用し走行性能を上げる研究開発も進んでいるそう」(赤池)

公共施設だけではなく
民間施設もウッド・チェンジ!

2021年に“木材利用促進法”が改正され、法律名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。これにより、法の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物一般に拡大しました。

お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449














