

今や生活になくてはならないデジタルツール。第4次食育推進基本計画を受け、
デジタルを活用した食育の取り組みにフォーカスして、事例を紹介します。

2024年2月、「人々の健康を身体全体で考えるトータルヘルスケアカンパニー」として事業を展開する大塚製薬(株)から、食育ゲームアプリ「もぐもぐタウン」がリリースされました。どんなアプリなのか、また、デジタル食育への取り組みなどをお聞きしました。
画像提供:大塚製薬(株)
啓発活動の一環として食育アプリを開発
医薬品だけでなく、数多くの健康飲料や栄養補助食品を開発してきた大塚製薬(株)は、長年食育活動にも携わってきました。
全国の小中学校などに寄贈してきた健康や栄養をテーマにする「OTSUKAまんがヘルシー文庫」は創刊35周年を迎えます。2018年には食育アプリ「おいしいおえかき SketchCook(スケッチクック)」をリリースし、小学校の授業にも導入されました。このアプリはお絵かきを通して、楽しみながら親子で栄養について学べるという点で、高い評価を得たツールでした。

子どもが描いたごはんの絵をスマートフォンで撮影するとAIが判別し、その絵が料理画像に変身するというもの。
いっしょに食べると栄養バランスがよくなるメニューの作り方もわかるようになっている。
新たに見えてきた課題と方向性
食育活動を推進する中で実態調査のためのアンケートを実施すると、子ども達の食に関する課題が見えてきました。「偏食や食わず嫌いを、どのように解消したらいいかわからない」「食べさせるのに精いっぱいで、栄養バランスのことまで目が向けられない」といった悩みを抱えている親御さんが、数多くいることがわかったのです。
そこで、SketchCookとは異なるアプローチで課題を解決に導くアプリの開発に着手します。大切
なことは前作同様、気軽に家庭でコミュニケーションをとりながら、楽しく、食や栄養について学べる機会を提供すること。
新しいアプリの開発でこだわったのは、正しい知識を、自発的にゲーム感覚で、楽しく継続して学べるものにすること。そして、楽しみながらやっているうちに、自然と食や栄養について知識が身につくという仕かけづくりに取り組んだのです。



子ども達がやってみて、楽しいと思えるものでなければなりません。それには飽きさせない工夫が重要です。「明日もやりたい!と思ってもらえること」を目指しました。

1 ごはんを撮影すると 2 隠れた「もぐみん」を発見! 3 クイズに答えると 4 「もぐみん」が仲間になる 5 「もぐもぐタウン」がレベルアップ!


楽しみながら正しい情報を

「もぐもぐタウン」の開発に携わった大塚製薬(株)ニュートラシューティカルズ事業部の武藤太郎さん
開発に携わった武藤太郎さんは「開発当初、対象は小学生からその親世代だと考えていましたが、実際使っていただくと、幼稚園児もキャラクターの出現に大喜びをしているし、大人でも楽しんでいるという声を聞きます」と話してくれました。「キャラクターを集めるために苦手な食材を克服した」という報告や「親子の会話が増えた」といううれしい報告もありました。
武藤さんは「もぐもぐタウンを通して、食に関するコミュニケーションを醸成できればいいと思っています。これからも健康をサポートする製品を届けるだけではなく、デジタルツールも駆使して、科学的根拠に基づいた正しい情報をきちんと伝えていきたい」と結びました。

「もぐもぐタウン」関連ツールの「もぐもぐタウンかるた」。画像データは無料でダウンロードできる。

3月から6月まで、食育の日(毎月19日)にYouTube上で順次公開した「もぐもぐタウンレディオ」。旬のもぐみんがゲストで登場。
日本古来の米づくりを再現したゲーム

米づくりが重要なカギを握るアクションRPG「天穂のサクナヒメ」を知っていますか。今号1週目に主人公のサクナヒメほかキャラクターたちがQ&Aに登場しましたが、実際にゲームを進めるには、米づくりの知識がものをいいます。そのため農林水産省のWebサイト「お米 作り方」が攻略サイトとして注目され、話題になっています。
お米 作り方: https://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/kome_tukurikata.html

元農林水産省食育推進会議専門委員で、現在オンライン料理教室をはじめ、生成AIを活用したデジタル食育の推進に注力している「パパ料理研究家」滝村雅晴さんにオンライン配信のノウハウなどをお聞きしました。
画像提供:(株)ビストロパパ

滝村雅晴さん
パパ料理研究家、大正大学客員教授、広報PRブランディングコンサルタント。立命館大学産業社会学部卒業後、企業で広報・PR・ブランディング業務などに携わり、2009年4月株式会社ビストロパパを設立。食育、共食(トモショク)、男女共同参画、WLB(ワーク・ライフバランス:仕事と生活の調和)、働き方改革に着目し、男性の家事料理参画を推進するパパ料理研究家。令和6年度消費者支援功労者表彰(消費者庁)において「ベスト消費者サポーター章」を受賞。
デジタル食育が生まれる場所
滝村雅晴さんがデジタルを利用した食育活動に着目したのは、場所を選ばずたくさんの人に料理や食の大切さを伝えることができると思ったからでした。そして、料理教室の生配信なら、料理や食に対する疑問点などもその場で解決してあげられると考え、オンライン料理教室を始めたのです。そんな滝村さんのキッチンスタジオにうかがいました。そこはごく一般的なダイニングキッチンですが、調理台に向けて、さまざまな角度から撮影するための5台のカメラが設置されています。滝村さんはここでZoomを使ってオンライン料理教室の生配信を行うのですが、材料や調理手順の説明をし、料理をしながら視聴者に語りかけ、その上照明から効果音を含む音響操作、カメラの切り替えなどをすべて一人で行うとのこと。
本来、料理を教えるスキルと配信のためのシステム環境オペレーションスキルは別ものです。料理をしながら画面を切り替え、リアルタイムでオンライン教室を行う場合は、一般的には専用のスタジオや、複数の機材を扱うだけのスタッフが必要です。
それを一人でこなし、しかも高画質・高音質の動画を配信できるのは、滝村さんがデバイスツールを扱うICTスキルにたけているからに他なりません。
この方式は、すべて独学で試行錯誤して作り上げたといいます。失敗もしましたが、それが糧となり、的確なリカバリーのスキルや間違いのないオペレーションにつながっていきました。

Zoomで開催しているオンライン料理教室。参加者が100人(100組)いても対応可能。
就職を機に自炊力をつけよう
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、急速に社会全体のデジタル化が進み、本来なら対面が当たり前だった料理教室もオンライン化が浸透していきました。
滝村さんはある企業から、新入社員向けのオンライン料理教室で、自炊を促すような企画ができないかという相談を受けました。
それまでも企業や労働組合向けのオンライン料理教室は行っていたので、その対象を新入社員とし、プログラム構成を新入社員にとってより有益なものに変えました。
「就職すると一人暮らしをする人もでてくる。仕事をしっかりするには、きちんと食を整える必要がある。健康状態を維持するには栄養バランスも必要だ。就職を機に食育の種をまいておけば、いつか本人の気づきになるかもしれない」。それを願って滝村さんはプログラムをブラッシュアップし、2024年2月に「キッチンスタートアップ」プログラムとしてリリースしたのです。

新入社員向けオンライン料理教室。メニューは「親子丼とほうれん草のお浸し、みそ汁」
なぜ「パパ料理」なのか
滝村さんは長女の誕生をきっかけに料理に目覚めたそうですが、ある日、根源的なことに気がつきました。「食べることは生きること。自分で作って食べるということが、本当に自分で生きているということだ」
そして「家庭で、妻や母親が食事を作ることが当たり前ではない。夫、そして父親である自分自身も料理をして、おなかを満たすことができてこそ、人間として自立して生きていると言えるのではないか」と。
その気づきをきっかけに、家族のため、自分のために料理を作り始め、「パパ料理」研究家になったのです。
そして、家族のために当たり前に料理を作るようになってから、料理には献立から買い物、調理、配膳、片付けといったすべての要素が含まれるのだと改めて実感しました。家族が分担してできることをし、料理を楽しむことが大切だと滝村さんは考えています。

生成AIは向き合い方の会得が大切
現在、滝村さんは大正大学で「生成AIを活用した地域の食文化広報」の授業を担当しています。先日は生成AIを使って、大正大学が地域連携協定を結んでいる地域の物産を調べ、「地域のファンを作るための記事」を作るという課題を学生たちに与えました。
その主旨は、まず生成AIで何ができるのか、どんな可能性があるのかを知ること。そして自分が知らないことでも、生成AIを活用すると記事が書けるということを体験します。滝村さんは学生たちに、生成AIの活用で重要なのは、自分が知らない、判断できないものを、やみくもにアウトプットするのではなく、活用しながら自らも経験・成長し、責任が持てる記事を書くことだと指導しています。
教えるのは生成AIの使い方のノウハウではありません。それを教えたとしても、明日にはそれが古くなってしまう。だから、教えるのは生成AIとの向き合い方、取り入れ方なのです。
滝村さんは食育活動においても今後は生成AIの活用が重要だと考えていますが、生成AIを使いこなすことによって得た食の知識を自分のものにできてこそ、精神的な成長や健康につなげていけると考えています。
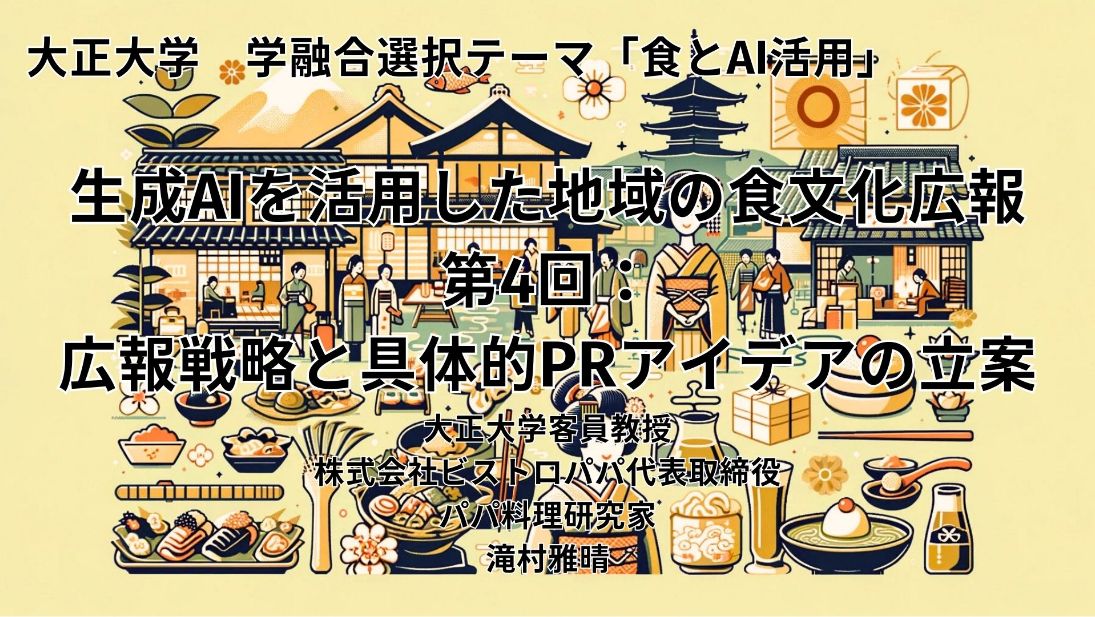
講義のためのトップページ。イラストも生成AIで作った。
今週のまとめ
社会のデジタル化を踏まえ、子どもが取り組みやすいアプリや
どこにいても受講することができるオンラインイベントなど、
デジタル技術を活用した食育活動が展開されています。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449








