食中毒とは、食中毒を起こすもととなる細菌(さいきん)やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、げりや腹痛、発熱、はきけなどの症状(しょうじょう)が出る病気のことです。食中毒の原因によって、病気の症状や食べてから病気になるまでの時間はさまざまです。時には命にもかかわるとてもこわい病気です。
細菌による食中毒にかかる人が多くでるのは気温が高く、細菌が増えやすい6月から9月ごろです。ウイルスによる食中毒は冬に流行します。また、キノコや魚のフグなどには、自然に有毒な物質を含んでいるものがあり、そういったものをまちがえて食べることによって食中毒になることもあります。食中毒を起こす細菌は、土の中や水、ヒトや動物のひふや腸の中にも存在していて、とくべつな菌というわけではありません。そのため、食品を作る途中で菌がついてしまったり、料理したものを、あたたかい部屋に長い時間置いたりすると、細菌が増えてしまいます。
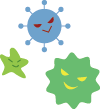
十分に加熱していない卵・肉・魚などが原因となります。
生卵、十分に火が通っていない鶏肉料理
乾燥(かんそう)に強く、熱に弱い特徴があり、十分に加熱すればふせげます。
食後12~48時間で、はきけ、腹痛、げり、発熱、頭痛などの症状が出ます。
ヒトのひふ、鼻や口の中にいる菌です。傷やニキビを触った手で食べ物を触ると菌が付きやすくなります。そのため、加熱した後に手作業をする食べ物が原因となります。
おにぎり、お弁当、巻きずし、調理パン
この菌が作る毒素は熱に強く、一度毒素ができてしまうと、加熱しても食中毒を防ぐことはできません。
食後30分~6時間で、はきけ、腹痛などの症状が出ます。
生の魚や貝などの魚介類(ぎょかいるい)が原因となります。
さしみ、すし
塩分のあるところで増える菌で、真水や熱に弱い特徴があります。
食後6~24時間で、激しいげりや腹痛などの症状が出ます。
生や加熱不十分な鶏肉料理、汚染された飲料水や生野菜などが原因となります。
とりレバーやささみなどの刺身、とり肉のタタキ、十分に火が通っていない焼鳥、汚染された野菜、井戸水(いどみず)やわき水
乾燥に弱く、十分に加熱すればふせげます。
食後1~7日で、げり、発熱、はきけ、腹痛などの症状が出ます。
また、感染して数週間後に、手足の麻痺(まひ)などがみられる「ギラン・バレー症候群(しょうこうぐん)」をおこすことがあります。
十分に加熱されていない肉や生野菜などが原因となります。
十分に加熱されていない肉、よく洗っていない野菜、井戸水やわき水
菌には、O157やO111などの種類がありますが、十分に加熱すればふせげます。
食後平均2~7日くらいで、はげしい腹痛、げり、血が多くまざったげりなどの症状が出ます。
重い合併症をおこすことや、症状が重くなると、死ぬこともあります。
カキなどの二枚貝を生や十分加熱しないで食べた場合や、感染した調理者を介して汚染(おせん)された食品を食べた場合、ウイルスに汚染(おせん)された井戸水などを飲んで感染することもあります。
十分に加熱されていないカキ、アサリ、シジミ
二枚貝などの食品は、中心部を85℃~90℃で90秒以上加熱。ノロウイルスにかかった人の便や、はいたものから感染することもあるので、直接さわらないよう気をつけましょう。
食後1~2日ではきけ、ひどいげり、腹痛などの症状がでます。
豚肉や豚レバー、イノシシやシカなどの野生鳥獣の肉の生食や加熱不十分な肉が原因となります。また、海外の地域によっては生水や生ものから感染する場合もあります。
十分に火が通っていない豚の肉やレバー
熱に弱いので、生食をさけ、中心まで十分に加熱すればふせげます。
ほとんど症状は出ませんが、一部の人は感染から平均6週間たつと、だるくなったり、ひふが黄色くなったり、発熱したりします。







