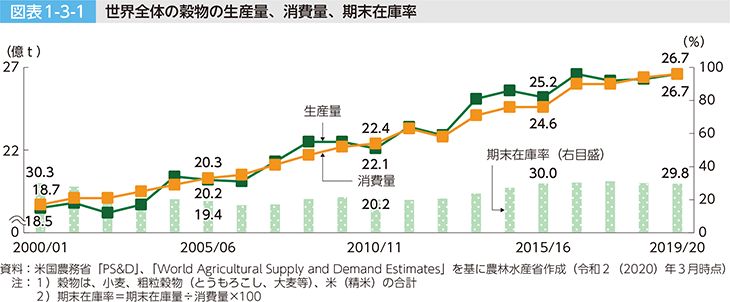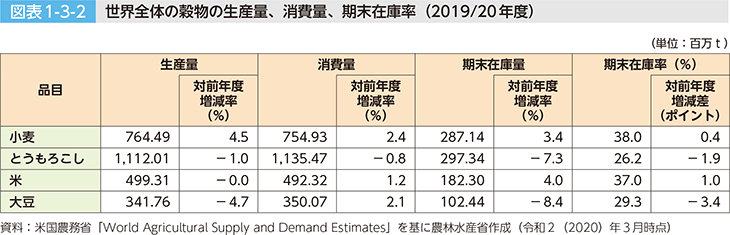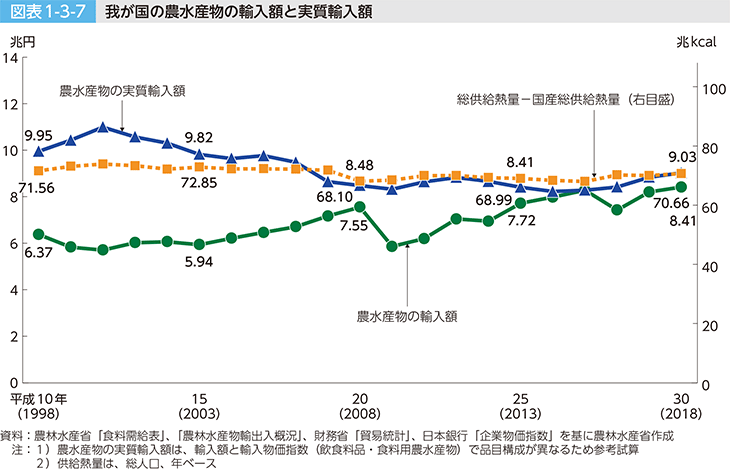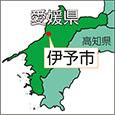第3節 世界の食料需給と食料安全保障の確立
世界の食料需給は、人口の増加や開発途上国の経済発展による所得向上に伴う畜産物等の需要増加に加え、異常気象の頻発、水資源の制約による生産量の減少等、様々な要因によって逼迫(ひっぱく)する可能性があります。このような世界の食料需給を踏まえ、我が国の食料の安定供給は、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これに輸入及び備蓄を適切に組み合わせることにより確保することが必要です。
(1)世界の食料需給の動向
(世界全体の穀物の生産量、消費量は前年度に比べて増加)
2019/20年度における世界の穀物全体の生産量は、とうもろこし、米が降雨過多等による影響で減少するものの、小麦が主に単収の伸びにより増加することから、前年度に比べて0.4億t(1.5%)増加の26.7億tとなり、2年連続で増加する見込みです(図表1-3-1)。
また、消費量は、開発途上国の人口増加、所得水準の向上等に伴い、近年一貫して増加傾向で推移しており、前年度に比べて0.3億t(1.0%)増加の26.7億tとなる見込みです。
この結果、期末在庫量は前年度から0.04億tの減少となり、期末在庫率は29.8%と前年度(30.3%)を下回る見込みです。
2019/20年度における世界の穀物等の生産量を品目別に見ると、小麦は、豪州で乾燥の影響が継続しているものの、EU、ウクライナ、インド、中国等で増加することから、前年度に比べて4.5%増加し、7.6億tとなる見込みです(図表1-3-2)。
とうもろこしは、南アフリカ、中国、ロシア等で増加となるものの、米国、メキシコ等で減少することから、前年度に比べて1.0%減少し、11.1億tとなる見込みです。
米は、タイで減産するものの、インドで増加することから、前年度並みの5.0億tとなる見込みです。
大豆は、ブラジル、中国等で増加するものの、米国等で減少することから、前年度に比べて4.7%減少し、3.4億tとなる見込みです。
また、生産量が消費量を上回った小麦、米の期末在庫率は、それぞれ38.0%、37.0%となる一方で、消費量が生産量を上回ったとうもろこし、大豆の期末在庫率は、それぞれ26.2%、29.3%となる見込みです。
穀物等の国際価格については、主要生産国での天候不順等により、平成20(2008)年には小麦と米が、平成24(2012)年にはとうもろこしと大豆が過去最高水準を記録しました(図表1-3-3)。その後は、世界的なとうもろこし等の豊作や南米での大豆の増産等により、全般的に低下傾向で推移し、落ち着きを見せています。
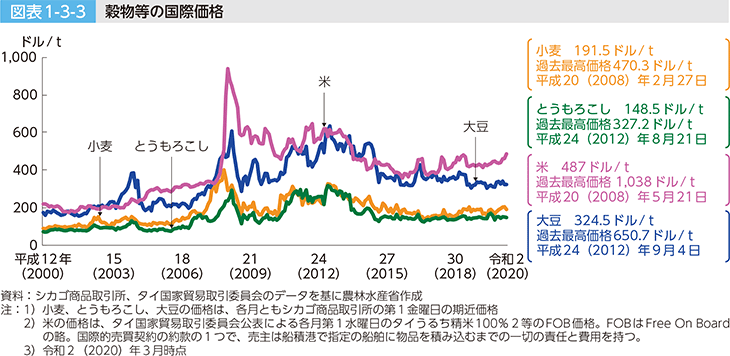
なお、穀物等の国際需給は総じて安定しているものの、内訳は大きく変化しています(図表1-3-4)。例えば、小麦については、この20年間にロシア・ウクライナの増産・輸出増が顕著となり、米国の輸出国としての地位は相対的に低下しています。一方、輸入は、アジア・アフリカ地域で大きく増加し、特に、東南アジアでは、食の西洋化により肉食や小麦食へのシフトが進み、小麦の輸入が大きく増加しています。

(世界の食料需給の見通し)
世界の人口は、令和元(2019)年では77.1億人と推計されていますが、今後も開発途上国を中心に増加することが見込まれており、令和32(2050)年には97.4億人になると見通されています。
このような中、世界の穀物等の需要は、人口増加や食生活の多様化、経済成長に伴い、食用の需要が増加するとともに、多くの穀物等を飼料とする肉類の需要が大幅に増加することから、今後、全体として増加する見込みです。
令和32(2050)年における主要4作物(小麦、とうもろこし、米、大豆)の需給を地域別に見通すと、輸入地域であるアジア、アフリカ等では、人口増加、食生活の多様化等により、生産増加が消費増加に追い付かず、純輸入量が更に増加する見込みです。また、このような輸入地域への食料供給を担う形で、輸出地域である北米、中南米、オセアニア及び欧州では、純輸出量が更に増加する見込みです(図表1-3-5)。
このように、世界の食料需給は、長期的に輸入地域と輸出地域の差が更に拡大すると見込まれており、ひとたび異常気象等により輸出国が減産した場合、需給バランスが崩れ、我が国にとっても、他の輸入国との競合が厳しくなることが想定されます。このため、引き続き、国際需給の動向を注視し、食料安全保障(*1)に万全を期する必要があります。

また、原料の多くを海外に依存する食品加工業者や飼料製造業者に対し、世界の穀物等の需給状況や見通し等の情報を幅広く提供することで、安定的な原料調達につなげることが重要です。情報収集に当たっては、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)との連携により人工衛星から取得した気象データ等も活用し、世界の主要生産地域における穀物等の作柄情報の収集・分析を広範囲に進めることとしています。
*1 用語の解説3(1)を参照
(農産物の生産において気候変動等の不安定要素が存在)
農産物の生産においては、気候変動を始め、水資源の制約や土壌劣化等の不安定要素が存在し、穀物需給が逼迫(ひっぱく)するリスクも指摘されています。
平成30(2018)年10月に公表されたIPCC(*1)の1.5℃特別報告書(*2)では、地球温暖化が現在の度合いで続けば、令和12(2030)年から令和34(2052)年までの間に、工業化以前の水準からの気温上昇が1.5℃に達する可能性が高いとされています。さらに、気温上昇幅が2℃となった場合、1.5℃の場合と比べて、極端な高温が顕著になるとともに、地域によっては強い降雨現象、干ばつ、少雨が増加するといったリスクが更に高まると予測されています。
*1 気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)の略
*2 正式名称は、「気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な発展及び貧困撲滅の文脈において工業化以前の水準から1.5℃の気温上昇にかかる影響や関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関する特別報告書」
(2)総合的な食料安全保障の確立
(不測の事態に備えてリスクを分析・評価し、演習を実施)
国民に対する食料の安定的な供給は、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これに輸入及び備蓄を適切に組み合わせることにより確保することが必要です。しかしながら、世界の人口増加等による食料需要の増大や異常気象による生産減少等、我が国の食料の安定供給に影響を及ぼす可能性のある様々なリスクが顕在化しつつあり、将来の食料需給の逼迫(ひっぱく)が懸念されています。また、自然災害や輸送障害、新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症の発生等の一時的・短期的に発生するリスクも存在しています。
このため、農林水産省では、不測の事態に備えて、食料の安定的な供給に関するリスクの影響等を定期的に分析・評価しています。令和元(2019)年度は、諸外国と比較した我が国の食料安全保障政策の点検を実施しました。その結果、各国の食料安全保障政策は、農業の状況、地理的条件、歴史的背景等、それぞれの国が置かれている環境が影響しており、これらの環境の中で、食料供給の起こり得るリスクを踏まえ、国内の食料供給や、農業貿易、備蓄・不測時対応の考え方が形成され、独自の施策が実施されていると評価されました。このような各国の取組を参考に、我が国として、今後新たな要因を分析し、対応策やこれまでの取組の強化を検討していく必要があります(図表1-3-6)。
また、国内における不作や輸入の大幅な減少等、食料の安定的な供給に影響を及ぼす不測の事態が生じた場合には、その影響を軽減するため、政府として講ずべき対策の内容等を示した「緊急事態食料安全保障指針」に基づき対応することとしています。令和元(2019)年度は、不測時に食料供給の確保が迅速に図られるよう、同指針に即した緊急的な食料の増産等の方策を点検・確認するシミュレーション演習を実施しました。
政府は、国内の生産量の減少や海外における不測の事態の発生による供給途絶等に備えるため、食料等の備蓄を行っています。米にあっては政府備蓄米の適正備蓄水準(*1)に基づき100万t程度を、食糧用小麦にあっては国全体として外国産食糧用小麦の需要量の2.3か月分を、飼料穀物にあっては国全体としてとうもろこし等100万t程度をそれぞれ備蓄しています。また、地方公共団体の備蓄は、大規模な自然災害等に備え、飲料水や食料を対象に行われています(*2)。
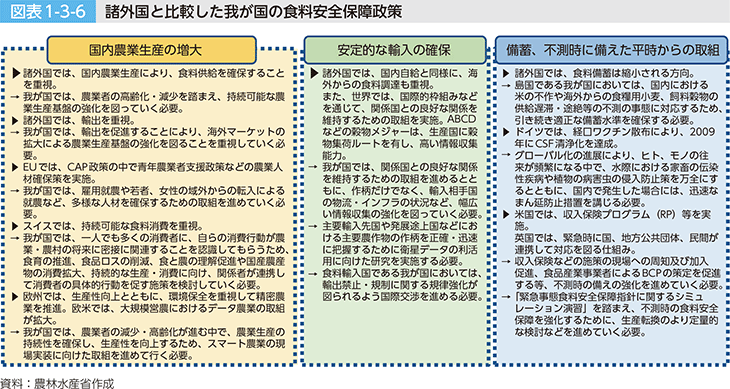
*1 10年に1度の不作や通常程度の不作が2年連続した事態にも国産米をもって対処し得る水準
*2 地方公共団体による備蓄は、都道府県、市町村等の行政と災害時応援協定を締結した民間事業者が実施
(輸入農産物の安定供給の確保に向け相手国との良好な関係の維持・強化等が重要)
我が国の農水産物の輸入金額は、近年、為替の円安を受けた輸入物価の上昇もあり、増加傾向にありますが、物価の変動を除けば長期的には減少傾向で推移してきています(図表1-3-7)。この背景としては、総人口ベースの総供給熱量(*1)が減少していることが考えられます。
令和元(2019)年の輸入額は前年比0.4%減少の6兆5,946億円となりました。
国別輸入額割合を見てみると、米国が21.6%、次いで中国が10.9%、豪州、タイ、カナダと続いています(図表1-3-8)。
また、品目別に見ると、とうもろこしは前年比3.2%増加の3,841億円、牛肉は前年比0.1%増加の3,851億円、豚肉は前年比3.8%増加の5,051億円、鶏肉は前年比3.4%増加の1,357億円となりました。一方、小麦は前年比11.3%減少の1,606億円、大豆は前年比1.6%減少の1,673億円、生鮮・乾燥果実は前年比0.2%減少の3,470億円となりました。
海外からの輸入に依存している主要農産物の安定供給を確保するため、輸入相手国との良好な関係の維持・強化や関連情報の収集等を通じて、輸入の安定化や多角化を図ることが重要です。

データ(エクセル:1,314KB / CSV:4KB)
*1 用語の解説3(1)を参照
(3)農産物の貿易交渉
(EPA/FTA交渉が進展)
世界の貿易ルールづくり等が行われるWTO(*1)では、これまで数次の貿易自由化交渉が行われてきました。平成13(2001)年に開始されたドーハ・ラウンド交渉は、依然として、開発途上国と先進国の溝が埋まらず、農業については交渉に進展がみられていません。
一方、特定の国・地域間で貿易ルールを取り決めるEPA/FTA(*2)の締結が世界的に進み、令和元(2019)年12月時点では320件(*3)に達しています。
我が国においても、海外の成長市場の取り込みを図るため、戦略的かつスピード感を持ってEPA/FTA交渉を進め、近年では、TPP11(平成30(2018)年12月発効)や日EU・EPA(平成31(2019)年2月発効)が発効しています。この結果、令和元(2019)年度末時点で、18のEPA/FTAを発効済・署名済です(図表1-3-9)。
このほか、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)、日中韓FTA、日コロンビアEPA、日トルコEPAが交渉継続中、日・湾岸協力理事会(GCC)FTA、日韓FTA、日カナダEPAが交渉延期又は中断となっています。
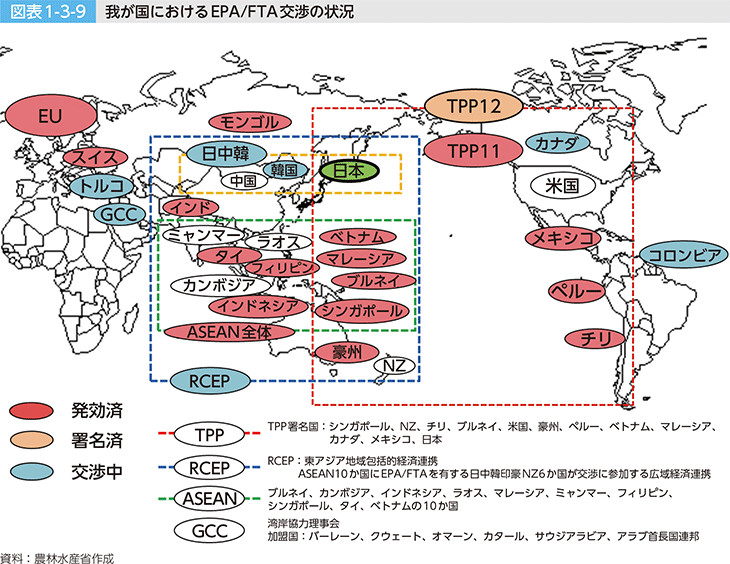
*1、2 用語の解説3(2)を参照
*3 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)「世界と日本のFTA一覧(2019年12月)」
(日米貿易協定が発効)
日米貿易協定はトピックス2参照
(4)国際関係の維持・強化
(対話と協力を通じた国際関係の維持・強化)
国民生活に必要となる農産物の輸入の安定、拡大する世界の食市場をターゲットとした農産物の輸出増加、さらには、我が国の食産業(*1)の海外展開の加速化を通じて、我が国の食料安全保障の確立を目指すには、良好な国際関係の維持・強化が必要です。
このため、農林水産省では日常的に諸外国の食料・農業担当部局や国際機関と情報交換を行い、関係の維持・強化を図っています。
また、多くの国や国際機関が参加する国際会議等の際には、参加国・機関の閣僚等と二国間会談等を実施し、輸入規制の撤廃や緩和等の要請を行っています。令和元(2019)年度には、5月に新潟県新潟市(にいがたし)で開催されたG20新潟農業大臣会合、8月にチリで開催された第5回APEC食料安全保障担当大臣会合、同じく8月に神奈川県横浜市(よこはまし)で開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD7)や令和2(2020)年1月にドイツで開催されたベルリン農業大臣会合に農林水産大臣が出席し、会議の合間に参加国・機関の閣僚等との会談を行いました。
さらに、我が国の農林水産物の輸出や農業技術に関する連携等の観点から重要な国とは、定期的に二国間政策対話を実施しています。例えば、8月に開催された大臣級の第4回日ブラジル農業・食料対話においては、税制・通関等の各種手続の改善、穀物輸送インフラの改善等、ブラジルでの投資・ビジネスの改善に向けた意見交換を行いました。また、11月に開催された第9回日中農業担当省事務次官級対話では、日中両国の農業政策の動向及び農業交流・協力の状況を紹介し、今後とも二国間の交流・協力を発展させることで一致しました。
*1 食産業とは、農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に係る幅広い産業を指し、花き、種苗、農業関連資材、農業機械・食品機械等の関連する産業も含む。
コラム:日本の魅力を世界に発信!~G20新潟農業大臣会合~
令和元(2019)年5月、農林水産大臣を議長とする、G20新潟農業大臣会合が新潟県新潟市(にいがたし)で開催され、「人づくり・新技術」「フードバリューチェーン」「SDGs」の3つの主議題について、34の国・国際機関の代表が議論を行いました。農林水産大臣からは、持続可能な農業の取組事例として、スマート農業の農業生産現場への導入、東日本大震災の被災地域での高品質農産物の生産を紹介しました。
また、新潟市立高志(こうし)中等教育学校の生徒が英語で、効率的水利用を可能とする技術導入や、先進国と途上国が協力して低コストの技術開発を行う「農業オリンピック」の開催を提案しました。
さらに、現地視察においては、自動走行トラクター、自動走行田植機、ドローン、情報一元化システム等の水田農業における先進技術の実演を視察しました。
また、会合には米国、EU、中国を含む18人の農業担当大臣が参加しましたが、農林水産大臣はこの全てと二国間会談を行い、農産物の輸出解禁の要請や農業分野での連携について意見交換し、我が国の農業の持続的発展のための二国間関係の維持・強化に努めました。
(グローバル・フードバリューチェーン(GFVC)の構築の推進)
我が国には、長年培ってきた高度な農業生産・食品製造・流通システム、高品質コールドチェーン、環境負荷軽減技術等、「強み」となる様々な食関連の技術・ノウハウがあります。これらを生かし、アジア・アフリカ等の途上国を含め、フードバリューチェーン(*1)の構築を推進することは、我が国の農林水産物の輸出促進や、海外展開を通じた我が国の食産業の発展にとって重要です。
このため、農林水産省においては、平成26(2014)年に海外展開を検討する企業、政府関係機関等からなるGFVC推進官民協議会を立ち上げ、官民参加の二国間対話や官民ミッション等を通じて、日本企業の海外展開を支援してきました。
令和元(2019)年度においても、ロシア、ブラジル等6か国と二国間対話等を行うとともに、インド、モザンビーク等4か国に官民ミッションを派遣したところですが、これまでの取組により、例えば、以下のような成果が得られています。
平成28(2016)年、平成29(2017)年にロシア極東への官民ミッションに参加した機械製造業者は、訪問先のウラジオストク漁業港との間で水産物用冷却施設の納入契約を締結するに至りました。また、平成30(2018)年以降のインドとの二国間協議等においては、日本醤油の輸出・現地生産の障壁となっていた、粘度の高いものしか醤油と認めないインド独自基準について見直しを要請したところであり、現在、インド側において、この基準を見直すための国内手続の検討が進められています。さらに、カンボジアにおいては、現地企業の要請に応じて農林水産省が日本の製菓会社を紹介したことが契機となり、平成30(2018)年に米菓を製造する合弁会社が設立され、平成31(2019)年1月以降、豪州向けの輸出が行われているところです。
以上のような成果も踏まえつつ、今後とも、輸出と海外展開の一体的な推進、地方の中小企業の海外展開の支援、複数企業の連携による海外展開の推進に重点的に取り組み、我が国の食産業の海外展開を促進していくこととしています。
*1 農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値を高めながらつなぎ合わせ、食を基軸とする付加価値の連鎖をつくること
事例:メイド・イン・マラウイを支える日本のものづくり(愛媛県)
愛媛県伊予市(いよし)の合同会社エヌエスコーポレーションは、平成11(1999)年に設立され、社員7人で運営されています。農業者や漁業者の求めに応じ、農水産物の殺菌装置、低温乾燥装置を製造し、国内のみならず、中国で開催された「大連日本商品展覧会」等の機会も活用し、東南アジア・アフリカ等の開発途上国でも販路を開拓しています。
マラウイに進出したのは、同国から愛媛大学に留学した学生が同社に来た際に「祖国は貧しいにもかかわらず、農産物が適切に保管されないままになっている。これを使って産業を興したい」「メイド・イン・マラウイの製品を作りたい」と語ったのがきっかけです。マラウイは、サブサハラの内陸部にある人口約1,814万人の国です。労働人口の8割が農業関連に従事し、タバコ・紅茶等を輸出する一方、主食用食料を輸入に頼っており、モノカルチャーからの脱却と新産業の育成が喫緊の課題となっています。
このため、同社創業者の仲井利明(なかいとしあき)さんは、同社の装置を現地に持ち込み、衛生管理方法を伝えつつ、おいしい乾燥食品の開発・製造を支援しています。仲井さんは「国際協力は一過性ではダメ。現地で使ってもらえる装置を作って現地で教え、マラウイの発展にも貢献していきたい」と語っています。
(TICAD7を契機としたアフリカとの関係強化)
アフリカでは、農業は人口の5割以上が従事する主要産業ですが、小規模農家による自給自足的農業が中心となっており、農業者の組織化、生産性の向上、加工・保存・流通等の技術導入が課題となっています。
このため、我が国は、平成20(2008)年に開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)において、今後10年間でサブサハラ・アフリカにおける米の生産量を1,400万tから2,800万tに倍増させる目標を掲げ、「アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)」を立ち上げました。この目標については、アフリカの努力と我が国の高収量イネの開発・普及、稲作やかんがいに関する技術指導等により達成することができました。
また、令和元(2019)年8月に開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD7)においては、令和12(2030)年までにサブサハラ・アフリカにおける米の生産量を5,600万tまで更に倍増させることを目標とするCARDフェーズ2が発表され、更なる米の増産と高付加価値化に向けた取組が開始されることとなりました。
このような取組に貢献するため、農林水産省は、平成30(2018)年以降、農林水産省の職員や元職員をケニア、ザンビア、セネガルの3か国に派遣し、派遣された職員等は、開発協力案件の形成や派遣先国政府への助言等を行いました。また、令和元(2019)年からは、園芸作物や稲作に関する知見を有する地方公共団体の元職員のアフリカ派遣にも取り組んでいます。
このほか、アフリカの農業の産業化や栄養改善を進めるため、小規模農業者のグループがICT(*1)技術を活用して共同購入・共同販売を行えるようにするための電子プラットフォームを構築する取組や、日本の農業技術・機械をアフリカ地域へ展開する取組を、官民一体となって進めているところです。
*1 用語の解説3(2)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526