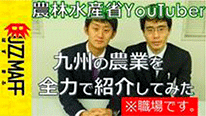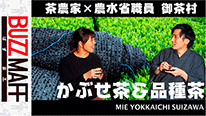第4節 食料消費の動向と食育の推進
今後、人口減少や高齢化により国内の食市場が量的に縮小する中で、消費者ニーズは多様化、個別化し、食の外部化(*1)が一層進展していくことが見込まれています。国産志向や食べることへの関心の向上を目指し、国産農林水産物の消費拡大のため、食育の推進や和食文化の保護・継承に向けた様々な活動が展開されています。
*1 用語の解説3(1)を参照
(1)食料消費の動向
(飲食料の最終消費額は83.8兆円となり4年前に比べて増加)
我が国で生産された食材及び輸入された食材は、流通・加工等の段階を経て、最終消費されます。平成27(2015)年においては、食用農林水産物11.3兆円(国内生産9.7兆円、輸入1.6兆円)と輸入加工食品7.2兆円が食材として国内に供給されました(図表1-4-1)。これらの食材は、食品製造業、食品関連流通業、外食産業を経由することで流通経費、加工経費、調理サービス代等が付加され、飲食料の最終消費額は83.8兆円となりました。

消費者が支払う飲食料の最終消費額は、平成7(1995)年以降、減少傾向にありましたが、平成27(2015)年は、円安に伴う輸入食品の価格上昇等により平成23(2011)年に比べ10%増加しました。
平成27(2015)年の飲食料の最終消費額の内訳を見ると、生鮮品等は14.1兆円、加工品は42.3兆円、外食は27.4兆円となり、食の簡便化や外部化等を背景として、加工品と外食の合計で、全体の8割を超えています。また、業種別の帰属額について見ると、食品製造業、食品関連流通業、外食産業の合計で、全体の87%を占めています(図表1-4-2)。
(60歳以下の食料消費額は長期的に減少傾向)
二人以上の世帯において、1人1か月当たりの食料消費額を平成12(2000)年から令和元(2019)年にかけて年齢別に見てみると、70歳以上は304円増加の27,972円、60歳代は91円増加の28,723円と微増となっていますが、29歳以下、30歳代、40歳代ではいずれも1,500円以上減少しています(図表1-4-3)。60歳を目安に食料消費支出の傾向が異なり、60歳以下の年齢では長期的に減少傾向にあることがうかがえます。
なお、令和元(2019)年は、外食、調理食品、飲料の需要の増加や消費税率引上げ実施前の酒類、飲料の需要の増加とあいまって、食料消費額は増加しました。60歳代では前年比1,015円増加、50歳代では889円増加しました。
(年代によって分かれる食の志向)
公庫が令和2(2020)年3月に公表した調査によると、消費者の食の志向を年齢別に見るとおおむね「健康志向」、「手作り志向」、「国産志向」は年齢に従って高くなる傾向にあります。一方で、「簡便化志向」、「経済性志向」、「美食志向」は年齢が低いほど高くなる傾向が見られます。支出が伸びている調理食品は、若年世代に需要があると言えます(図表1-4-4)。また、10年前と比べると「簡便化志向」は全ての年代で伸びており、特に20から40代ではいずれも10ポイント以上増加しています。「経済性志向」は、50代で8ポイント増加した一方、30代で7ポイント、40代で10ポイント減少しました。「安全志向」は、20から30代で5ポイント以上増加した一方、50から60代で5ポイント以上減少しました。
食べることへの関心度に関する調査によると、食べることに関心があるのは全体の8割となっていますが、令和元(2019)年を平成28(2016)年と比較すると、60代を除く全ての年代で関心が低下しています(図表1-4-5)。年齢別にみると、年齢が高くなるほど食べることに関心を持っている割合が高くなる傾向にあります。
「食べることに関心がある」とした理由は、「おいしいものを食べること」(66.8%)が最多となり、平成28(2016)年から9.9 ポイント増加しています。若い世代では「おいしいものを食べること」、「おなか一杯になること」の割合が高く、高齢世代では「色々な種類・味のものを食べること」、「人と一緒に食べること」の割合が高くなっています。
高齢世代は食べることに対して多様な志向・目的を意識しており、若年世代は経済性と美食を意識してると言えます。
また、食料消費額の内訳を平成20(2008)年、平成25(2013)年、平成30(2018)年で比較してみると、各年代で生鮮食品の消費額は減少した一方、調理食品と外食の消費額は増加しています(*1)。
二人以上の世帯で調理食品の支出を平成21(2009)年、平成26(2014)年、令和元(2019)年で比較してみると、10年前と比べて弁当、すし等の主食的調理食品は294円増加し、サラダ、総菜、ミールキット等の他の調理食品は361円増加しています。年齢別に調理食品の支出を見ると、特に60歳代では1,040円増加と大きく支出が伸びています(図表1-4-6)。
一方、単身世帯では、二人以上の世帯に比べて調理食品の支出が多く、10年前と比べて主食的調理食品は83円増加し、他の調理食品は542円増加しています。特に35から59歳以下では862円増加と支出が伸びています。
*1 平成30年度食料・農業・農村白書 第1章第4節を参照
(2)食育の推進と国産農林水産物の消費拡大、和食文化の保護・継承
(「日本型食生活」の実践、フード・アクション・ニッポン、農林漁業体験機会の提供等を推進)
農林水産省では、食育の取組の一環として、消費者に健全な食生活の実践を促すため、栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践に向けた調理講習会や食育授業等の開催を支援しています。
「日本型食生活」は、我が国の気候風土に適した多様性のある食生活であり、地域や全国各地で生産される豊かな食材を用い、健康的で栄養バランスに優れています。ごはんと組み合わせる主菜、副菜等は、家庭での調理だけでなく、中食(*1)、冷凍食品、レトルト食品等も活用する形で普及を図っています。
また、国産農林水産物の消費拡大に向けた取組として、民間企業・団体・行政等が一体となった国民運動「フード・アクション・ニッポン(*2)」を進めています。令和元(2019)年度末時点で11,157社の「推進パートナー」が、国産農林水産物を使用した商品販売や国産の魅力発信等を行っています。この一環で、消費者に向けて国産農林水産物の魅力を発信するとともに、それらを広く消費者に届け、食する機会を増やすため、魅力ある優れた国産農林水産物を表彰する「フード・アクション・ニッポン アワード」を毎年開催しています。令和元(2019)年度は入賞100産品、その中から受賞10産品、プレイベントでの消費者投票によって特別賞5産品が選定されました。受賞産品は、審査員である大手百貨店、流通、外食事業者、宿泊サービス10社が販売し、都市の消費者が地域の逸品を手にする機会につながっています。
さらに、消費者が生産者と直接会話したり、収穫体験等をすることで、国産農林水産物の魅力を知って、消費拡大につなげるため、我が国の農業や農林水産物、食文化について、見て、触れて、食べて、体験できるイベント「ジャパンハーヴェスト 2019丸(まる)の内(うち)農園」を令和元(2019)年11月に開催しました。2日間で12万人が来場し、来場者アンケートでは85%の人が「国産農林水産物の魅力や日本の食文化を再発見できた」と回答しました。
また、国産農林水産物の消費拡大の前提となる食や農林水産業への理解増進につながる農林漁業体験の機会が、全国の教育ファーム等で提供されています。酪農においては、一般社団法人中央酪農会議(ちゅうおうらくのうかいぎ)が体験の受入れや学校への講師派遣等を行う牧場を酪農教育ファームとして認証しており、平成30(2018)年度末時点で認証牧場数は289牧場となっています。
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 民間企業・団体・行政等が一体となって、国民運動として推進する国産農林水産物の消費拡大の取組
コラム:農林水産省職員自らがYouTubeで国産農林水産物等の魅力を発信
農林水産省の職員が、省公式YouTubeチャンネルでYouTuberとなり、その人ならではのスキルや個性を活かして、我が国の農林水産物の良さや農林水産業、農山漁村の魅力を発信するプロジェクト「BUZZ MAFF」が、令和2(2020)年1月から始まりました。
チャンネルの一つである「タガヤセキュウシュウ」では、九州農政局職員の白石(しらいし)くんとノダさんが九州の農業の魅力を発信しています。令和2(2020)年2から3月にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベントの中止等により、花きの需要が落ち込みました。農林水産省は「花いっぱいプロジェクト」を立ち上げ、「タガヤセキュウシュウ」で発信したところ、白石くんとノダさんの人柄や表現方法が話題となって、再生回数64万回(令和元(2019)年度末時点)と多くの反響を呼び、花きや生産農家に対する国民の関心を高めることができました。
また、「日本茶チャンネル」では、農林水産省職員の御茶村(おちゃむら)さんが、お茶会の様子やおすすめのお茶の入れ方を紹介しています。今後も、お茶について勉強しながら様々な内容の動画で、お茶の魅力を発信することとしています。
さらに、「さつまいも大好きチャンネル」では、さつまいもを愛してやまない農林水産省職員の渡邊(わたなべ)さんが、毎回個性豊かなさつまいも好きをゲストに迎え、いつものいもが違って見えるきっかけづくりを目指して、さつまいもの魅力を発信しています。
BUZZ MAFFでは、令和元(2019)年度末時点で本省・地方の14組の職員が発信しており、農山漁村の美しい景観や棚田等の魅力、特産品を活用したレシピ、農産物の豆知識等の様々な内容の動画を投稿していく予定です。
(和食文化の保護・継承の取組を推進)
「和食;日本人の伝統的な食文化」(*1)が平成25(2013)年12月にユネスコ無形文化遺産に登録されましたが、我が国では、食の多様化や家庭環境の変化等を背景に、和食文化の存在感が薄れつつあります。和食文化の保護・継承に当たっては、食生活の改善意識が高まりやすい子育て世代や若者世代等に対し、和食文化の良さを理解してもらい、実践してもらうことが重要です。令和元(2019)年度には、各地域が選定した郷土料理の歴史・レシピ等の調査・データベース化等を通じて情報発信を行うとともに、栄養士・保育士等を対象に、子供たちや子育て世代に対して和食文化の継承活動を行う中核的な人材を育成するための研修会等を開催しました。また、次世代を担う子供たちを対象に、和食や郷土料理に関するお絵描きや和食の知識と技を競うイベントとして、第4回「全国子ども和食王選手権」を実施しました。さらに、和食に関わる事業者と行政が一体となって子供たちや子育て世代に、中食・外食等も活用しながら身近・手軽に健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やしてもらうための活動を推進しています。
第3次食育推進基本計画では、令和2(2020)年度までに「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合」を50%以上、「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している若い世代の割合」を60%以上とすることを目標としています。令和元(2019)年度の食育に関する意識調査では、「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合」は47.9%(図表1-4-7)、「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している若い世代の割合」は61.6%でした(図表1-4-8)。前年度よりそれぞれ1.7ポイント、4.7ポイント減少していますが、第3次食育推進基本計画作成時(*2)の調査結果と比べて、それぞれ6.3ポイント、12.3ポイント増加しています。
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 平成28(2016)年3月食育推進会議決定
(文化財としての和食文化の価値の見える化)
平成29(2017)年の文化芸術基本法の改正により、生活文化の一つとして「食文化」が明文化され、平成30(2018)年には、「食文化」から約30年ぶりに文化功労者の顕彰がなされました。このような流れを受け、国内の有形・無形の文化財の保存・活用に取り組む文化庁において、和食文化の文化財としての価値を評価し、見える化するための検討が開始されています。和食文化の保護・継承を担う農林水産省としては、和食文化を支える農林水産業や農山漁村の様々な関係者が引き続き誇りを持って農林漁業活動に従事できるよう、文化庁と連携して取り組んでいきます。
コラム:健康的で栄養バランスに優れた食事の認証制度
健康的で栄養バランスにも優れた食事を取るためには、家庭での食事だけでなく、外食や中食(持ち帰り弁当)でも健康に配慮した食事選択ができる商品を増やし、適切な情報提供がなされる環境を整備することが必要です。
このため、平成29(2017)年12月、特定非営利活動法人日本栄養改善学会(にほんえいようかいぜんがっかい)と日本給食経営管理学会(にほんきゅうしょくけいえいかんりがっかい)が中心となって、外食・中食・事業所給食における、健康的な食事に関する基準を設け、継続的に、健康的な環境(適切な情報提供や完全禁煙等に取り組んでいる環境)で提供する店舗や事業所を認証する「健康な食事・食環境」認証制度(通称:スマートミール)を創設するとともに、「健康な食事・食環境」コンソーシアム(*1)を立ち上げました。
スマートミールとは、科学的根拠に基づき、主食・主菜・副菜が組み合わさっており、エネルギー量や食塩相当量、エネルギー産生栄養素バランス(*2)にも配慮した食事です。このような食事を外食や中食で体験し、家庭での食事にもフィードバックすることで、国民の「健康寿命の延伸」の実現を目指しています。
平成30(2018)年9月に第1回認証を行い、68事業者が認証を受けました。その後も認証事業者は増加し、令和元(2019)年12月現在で、外食部門、中食部門、給食部門合計で304事業者、16,000店舗以上でスマートミールが提供されています。
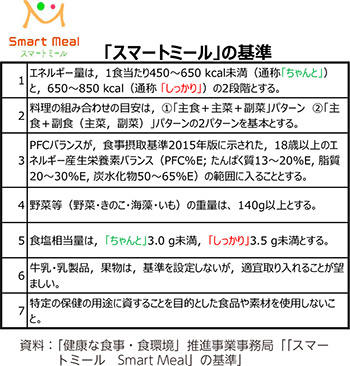
スマートミールの基準
*1 令和元(2019)年12月現在、日本栄養改善学会、日本給食経営管理学会、日本高血圧学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本公衆衛生学会、健康経営研究会、日本健康教育学会、日本腎臓学会、日本動脈硬化学会、日本補綴(ほてつ)歯科学会、日本産業衛生学会、日本がん予防学会(計13学会)
*2 エネルギー産生栄養素バランスは、「エネルギーを産生する栄養素(energy-providing nutrients、macronutrients)、すなわち、たんぱく質、脂質、炭水化物(アルコールを含む)とそれらの構成成分が総エネルギー摂取量に占めるべき割合(%エネルギー)」としてこれらの構成比率を示す指標(出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」)
事例:公益社団法人日本給食サービス協会における取組
社員食堂等の事業所給食においては、従業員の健康維持・管理の観点から、ヘルシーメニューの提案や減塩の取組、野菜を多めに取り入れた食事の提供が増えています。
このため、事業所や学校、病院・介護施設での給食を行う事業者等から構成される公益社団法人日本給食(にほんきゅうしょく)サービス協会(きょうかい)では、スマートミールの考え方に賛同し、ユーザーのニーズに合った食事を提供できるよう、事業者を集めた講習会や取組を紹介する発表会を開催しています。
このような機会を得ることで、各事業者においても様々な取組がなされています。ある給食事業者は、魚中心の食事を提供していますが、客を飽きさせないため、煮魚やバター醤油焼き、ホイル焼き等と調理法を変えています。また、白身魚を使用すると脂質量が少なくなるため、から揚げにしたり、付け合わせでイモ類を使うなど、脂質量やエネルギー量をコントロールして適切なエネルギー産生栄養素バランスを保つよう工夫しています。
さらに、体に良い食事でも「見た目」、「味」、「腹持ち」が悪いと売れないことから、満腹感が得られやすいよう食材を大きく切ったり、歯ごたえのある食材を使用するなどの工夫をしています。減塩については、下味をつけず、薄味でもとろみがあるソースやあんをかけることで味を強く感じられるようにしたり、出汁を利かせることで、できる限り調味料を減らすよう工夫しています。
また、卓上の醤油差しをプッシュ式容器に変更したり、各テーブルの卓上調味料を一か所に集約するなど、客に塩分摂取量を気付かせるための工夫することで、減塩の取組を行っています。
このようなスマートミールの取組を行う事業者は増えており、「健康な食事・食環境」認証制度により給食部門で認証を受けた事業所数は令和元(2019)年12月現在で195事業所となっています。
事例:花王株式会社の社員食堂における取組
花王(かおう)株式会社では健康経営の一環として、社員食堂で“しっかり食べて内臓脂肪をためにくい”バランスのとれた食事、「スマート和食」(*)を提供しています。
内臓脂肪の過大な蓄積は、食事や生活習慣に起因し、メタボリックシンドロームが「内臓脂肪症候群」と称されるように、脳卒中や糖尿病を始めとする様々な疾患の原因で、その対策が「健康」への第一歩とも言われています。
花王では600キロカロリー前後でボリュームたっぷりのスマート和食ランチを、定期的な内臓脂肪測定や食育セミナーと合わせて提供し、社員の健康意識や生産性の向上を図っています。この取組は本社を含む11の事業場の社員食堂に広がり、さらに、岩手県・福島県等の地方公共団体や、健康経営を志向する企業からの依頼を受け、社外の社員食堂や弁当等での提供も開始されており、食を通じた健康改善の取組が着実に広がっています。実施先では「いわゆる健康メニューとして想像していたよりもボリュームがありおいしい」という声と共に、多くの利用者で内臓脂肪が減るという成果が得られています。
* 花王は内臓脂肪蓄積と食生活の関係を研究した結果、1970年代の日本型食生活には、食後に燃えやすく、内臓脂肪として蓄積しにくいという特性があったことを見いだし、その健康有益性を現代の食生活にスマートに取り入れる食事法、「スマート和食」を開発しました(同社において商標登録)。スマート和食は、米飯を中心に多様な食材を活用し、主食+主菜+2副菜の食卓を構成します。それにより、食事摂取基準の範囲内でできるだけ「たんぱく質/脂質」「食物繊維/炭水化物」「n-3脂肪酸/脂質」の3つの比を高め、その結果、“エネルギーはあるのに内臓脂肪になりにくい”という特性が発揮されます(ヒト試験により確認済み)。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526