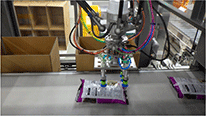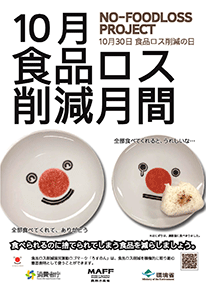第7節 食品産業の動向
食品産業は、農林水産業と消費者の間に位置し、食品の生産、流通、消費の各段階において品質と安全性を保ちつつ食品を安定的に供給するとともに、消費者ニーズを生産者に伝達する役割を担っています。我が国の食品製造業は、高い品質やブランド力等の強みを持つ一方で、他の製造業と比べ、雇用人員が不足していること、労働生産性が低いこと等の課題を抱えています。
また、食品ロス等の社会的な環境問題への意識が高まっている中、食品関連事業者による食品ロスの削減目標の設定や、商慣習の見直し等の取組が進められています。
(1)食品産業の現状と課題
(食品産業の国内生産額は99.9兆円)
食品産業の国内生産額は、近年増加傾向で推移しており、平成30(2018)年は、前年から0.6兆円増加し、99.9兆円となりました(図表1-7-1)。なお、全経済活動に占める割合は前年並の9.6%となりました。
前年と比較すると、食品製造業は水産食料品、そう菜等の工場出荷額、関連流通業は卸売業のマージン額、外食産業は飲食店の売上高等が増加しました。
また、食品産業は国内の農林水産業と密接に関係しており、国内で生産されている食用農林水産物の67%が食品産業を仕向先としています(*1)。
*1 農林水産省「平成27年(2015年)農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表(飲食費のフローを含む。)」
(地域の雇用において重要な役割を果たす食品製造業)
各都道府県の全製造業の従業員数に占める食品製造業の従業員数の割合を見ると、多くの都道府県で1割を超えており、特に北海道と沖縄県では40%を超えています(図表1-7-2)。また、全製造業の従業員数に占める食品製造業の従業員数の割合の順位を見ると、1位が26道府県、2位が13都府県、3位が4県と、ほとんどの都道府県において1位から3位に入る結果となりました。このことから、食品製造業が地域の雇用において重要な役割を果たしていることがうかがえます。
(食品製造業の労働生産性は低い水準)
平成29(2017)年度における食品製造業の有効求人倍率は2.78倍であり、全職業平均の1.38倍を上回っています(*1)。欠員率は3.2%で、有効求人倍率同様に高い水準であることから、雇用人員不足がより深刻な状況にあることがうかがえます(*2)。また、食品製造業の労働生産性を見ると、緩やかな上昇傾向にはあるものの、依然として製造業全体に比べて低い水準にとどまっています(図表1-7-3)。
公庫が食品関係企業を対象に実施した調査によると、食品製造業における労働力不足の解決策として期待できるものとして、66.2%が労働条件の改善を、54.0%が作業工程の機械化と回答しています(図表1-7-4)。食品製造業は、小さく、やわらかく、形状が不安定な食品を取り扱うことや、高い衛生性、安全性が求められること等から機械の導入が困難な場合が多く、多くの人手に頼らざるを得ませんでした。しかし、現状を打破するためには、従業員が働きやすい環境の整備に努めるとともに、機械化による省人化に取り組むことが重要です。
*1 厚生労働省「一般職業紹介状況」
*2 厚生労働省「雇用動向調査」
(「食品製造業における労働力不足克服ビジョン」を取りまとめ)
平成30(2018)年4月、農林水産省は食品産業の2020年代のビジョンを示した「食品産業戦略」を策定し、需要を引き出す新たな価値の創造による付加価値額の3割増加、海外市場の開拓による海外売上高の3割増加、労働生産性の3割向上という3つの目標を掲げました。令和元(2019)年度は、特に食品製造業における労働力不足や人材確保難に焦点を当てた議論を行い、令和元(2019)年7月に「食品製造業における労働力不足克服ビジョン」を取りまとめました。同ビジョンでは、今後の施策の方向性として、「従業員のやる気を育てる」、「IT・機械設備の導入による生産性の向上」、「多様な人材の活用」の3本柱を整理し、それらに関してアプローチを行うことが重要としています。また、平成31(2019)年4月から開始した新たな外国人材受入れ制度の活用や、女性、高齢者の活用促進も有用であると指摘しています。
(新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れを開始)
令和元(2019)年10月末時点での外国人雇用状況は、食品製造業では、総数が13万1千人となっています。このうち、主な在留資格は、技能実習生が5万6千人、身分に基づく在留資格が4万3千人、留学生等の資格外活動が2万7千人となっています。また、外食業では、総数が18万4千人となっています。このうち、主な在留資格は、留学生等の資格外活動が12万7千人、身分に基づく在留資格が3万5千人、専門的・技術的分野が1万5千人となっています。
深刻化する人手不足に対応するため、平成31(2019)年4月に改正された出入国管理及び難民認定法により、新たな外国人材の受入れのための特定技能制度が創設されました。この制度では、飲食料品製造業及び外食業を含む14の特定産業分野が受入対象分野となっており、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることとしています。
この制度により令和2(2020)年3月末時点で、飲食料品製造業分野で1,402人、外食業分野で246人の外国人材が働き始めています。農林水産省では、食品産業特定技能協議会を設置し、大都市圏への外国人材の過度な集中防止への対応や、制度や情報の周知、法令遵守の啓発等を実施しています。また、この制度を活用し、日本での就労を希望する外国人材の働きやすい環境が整備されるよう、地域や受入事業者における優良事例の収集・周知等を行っています。
事例:食品製造業における生産性向上による労働力不足の克服(群馬県)
東京(とうきょう)カリント株式会社群馬工場(ぐんまこうじょう)は、昭和26(1951)年から、かりんとうの製造を行っています。かりんとうは商品の特性上、作り置きができず、受注生産を行っていることから、繁忙期の人材確保が課題となっています。
これまでに製造工程では、計量工程までは自動化されていましたが、箱詰め工程から先の作業が手作業となっていたため、繁忙期の対応は無理な残業に頼らざるを得ない状況でした。
そこで、食品産業イノベーション推進事業の革新的技術活用実証事業に応募し、計量・包装機器の改良や、箱詰めロボット、自動製函機(じどうせいかんき)の導入により箱詰め工程の自動化を図りました。
これにより、作業者の負担が大幅に削減されるとともに、袋詰め作業に要する人数が、10人から3人で対応できるようになりました。また、製造速度に合わせた包装速度に調整した結果、不良品の発生頻度が減少したことで、生産性は事業実施前と比較して333%向上しました。
同社では、今後、現在の3人から2人で作業できるように、社内での教育・訓練を進めたいと考えています。
(2)食品流通の合理化
(サプライチェーン全体で食品流通の合理化を推進)
トラックドライバーを始め人手不足が深刻化する中で、国民生活や経済活動に必要不可欠な物流の安定を確保するには、サプライチェーン全体で合理化に取り組む必要があります。特に食品や花きの輸送は、荷物の手積み、手降ろしといった手荷役作業が多い、小ロット・多頻度での輸送が多いなどの事情から、取扱いを敬遠される事例が出てきています。このような中、農林水産省、経済産業省、国土交通省は、食品流通合理化検討会を設置し、具体的な方策の検討を進めているところです。
食品流通の合理化は、令和元(2019)年12月に決定された農業生産基盤強化プログラムにおいても主要な施策の一つに位置付けられました。具体的には、物流拠点の整備・活用等による共同輸配送の推進、トラック輸送から船舶・鉄道輸送へのモーダルシフト(*1)、統一規格輸送資材(パレット等)の導入による手荷役から機械荷役(*2)への転換等、サプライチェーン全体での合理化を推進することとしています。
また、卸売市場については、市場の実態に応じて、商物分離等取引ルールの設定が可能となったところであり、食品流通における卸売市場のハブ機能の強化、低温物流センターの整備等によるコールドチェーンの確保や情報通信技術等の利用による効率的な商品管理等に取り組んでいます。
*1 トラック等の自動車で行われている貨物輸送を、鉄道や船舶の利用へと転換すること
*2 パレットに積載した荷物をフォークリフト等で積み込み、積み降ろしすること
(食品等流通合理化計画の認定数は48件)
平成30(2018)年10月に改正された食品等流通合理化法(*1)に基づき、事業者による流通合理化のための取組を支援するため、食品等流通合理化計画の認定制度が創設されました。同計画の認定を受けた事業者は、公庫による資金の貸付け等の支援措置を受けることができ、令和元(2019)年度末時点での認定数は48件となっています。
*1 正式名称は「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」。食品流通構造改善促進法から名称変更
(3)環境問題等の社会的な課題への対応
(我が国の食品ロスの発生量は年間612万t)
食品ロスとは、売れ残りや規格外品、返品、食べ残し、直接廃棄等の、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品のことを言います。平成29(2017)年度における我が国の食品ロスの発生量は、前年度より31万t減少し、年間612万tと推計されます。平成24(2012)年度からの納品期限緩和の働きかけなどにより、食品ロス削減の取組が進展してきたこと等が減少した要因と考えられます。これを国民1人当たりに換算すると年間48kgとなり、我が国の1人当たりの米の年間消費量54kgに相当する量です。また、1日当たりに換算すると132gとなり、茶碗1杯のごはんの量に相当します。
食品ロスの発生場所の内訳を見ると、一般家庭における発生が最も多く284万t、次いで外食産業127万t、食品製造業121万t、食品小売業64万t、食品卸売業16万tとなっています(図表1-7-5)。
(食品ロス削減推進法を施行)
食品ロスを削減するためには、事業者、消費者、行政機関等の多様な主体が連携し、フードチェーン全体での国民運動として取り組むことが重要です。令和元(2019)年10月に施行された食品ロスの削減の推進に関する法律では、国、地方公共団体、事業者の責務を明らかにするとともに、消費者の役割、関係者相互の連携協力について規定されました。また、同法に基づき、関係大臣及び有識者で構成される食品ロス削減推進会議において、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針について検討が行われ、令和2(2020)年3月に閣議決定されました。
加えて、同法では、毎年10月を食品ロス削減月間、10月30日を食品ロス削減の日と定め、法律施行後初めての食品ロス削減月間となった令和元(2019)年10月には、全国の食品小売事業者に対して食品ロス削減に向けた消費者啓発ポスターの掲示を呼びかけました。具体的には、掲示を行った事業者名(75事業者)を公表したほか、「飲食店等の食品ロス削減のための好事例集」への新たな事例(28事例)の追加、食品ロス削減国民運動ロゴマーク「ろすのん」の活用事例(19事例)及び活用者(299者)の公表等を行い、食品ロスの削減に積極的な食品関連事業者の取組を見える化し、業界全体の取組につなげました。また、G20首席農業研究者会議から派生した取組として、令和元(2019)年10月、東南・東アジアを対象とした食品ロス削減に関する国際ワークショップを我が国で開催しました。
さらに、令和2(2020)年2月の恵方巻きシーズンには、予約販売等の需要に見合った販売に取り組む食品小売事業者を公表するとともに、恵方巻きのロス削減に取り組む小売店である旨を消費者に情報発信するための資材を提供し、消費者に対して食品小売事業者の取組への理解を促しました。また、個々の食品企業の努力だけで事業系食品ロスを大幅に削減させることは容易ではないことから、異業種と協働した食品ロス削減を進めるため、ICT(*1)やAI(*2)等の新技術を活用した食品ロス削減に効果的なビジネスを募集し、農林水産省Webサイトで紹介しました。
*1、2 用語の解説3(2)を参照
(飲料、菓子、カップ麺の納品期限の緩和を推奨)
食品業界における食品ロス削減のため、食品製造業、食品卸売業、食品小売業の話合いの場である「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」において、(1)納品期限の緩和(*1)、(2)賞味期限の年月表示化、(3)賞味期間の延長を三位一体で進めています。特に、食品小売事業者による納品期限の緩和については、賞味期間が長く、かつ購入後の家庭での消費が早い飲料、賞味期間が180日以上の菓子、カップ麺の3品目について推奨しています。納品期限を緩和している食品小売事業者は、平成31(2019)年3月時点で39事業者でしたが、令和2(2020)年3月時点では108事業者となりました(*2)。農林水産省では、更なる食品ロス削減に向け、令和2(2020)年10月30日(*3)までに全国一斉で商慣習を見直すことを呼びかける運動を展開することとし、上記3品目の納品期限の緩和について食品小売事業者へ呼びかけるとともに、食品製造事業者による賞味期限表示の大括り化(*4)についても取組を促しています。
*1 商慣習に基づく小売事業者の加工食品の納品期限について、製造日から賞味期間の3分の1に相当する日数を経過した日(いわゆる3分の1ルール)から2分の1を経過した日にまで緩和するというもの
*2 食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム事務局調べ。令和2(2020)年3月時点の調査は、実施を予定している事業者を含む。
*3 食品ロス削減推進法において「食品ロス削減の日」に制定
*4 賞味期限の表示を年月日から年月にすることや、異なる製造日の商品の賞味期限を統一すること
(東京2020大会に向けて食品ロス削減手法を検討)
世界的に食品ロスへの関心が高まる中で、環境に配慮した持続可能な大会を目指す東京2020大会では、「Zero Wasting~資源を一切ムダにしない~」との目標の下、食品ロスの削減に取り組んでいくこととしています。
この目標の達成に貢献するため、大規模スポーツイベントにおける食品ロス削減手法を検討しました。ラグビーワールドカップ2019の期間中には、選手の宿泊するホテルや競技会場周辺の飲食店において、食べ残しを発生させないことを呼びかける多言語の啓発資材を掲示し、その効果を検証しました。この結果、「食べ残しゼロにトライ!」と呼びかけたポスターや卓上ポップを掲示した飲食店では、利用客1人当たりの食べ残し量が2割減少するなど、食品ロスの削減効果が示唆されました。また、これら飲食店の利用客へのアンケート調査(*1)では、9割の利用客が食品ロス削減に取り組む店舗について好印象を持つとともに、6割の利用客がこのような店舗を積極的に利用したいと回答しており、食品ロスの削減に取り組むことで、利用客から高く評価されることが示されました。
今後は大会本番に向けて、これらの啓発手法をホテルや飲食店に普及させることにより、大会期間中に食品ロスをできるだけ発生させない取組を推進し、世界中に「もったいない」を発信するとともに、大会後も継続して取り組んでいくこととしています。
*1 農林水産省委託事業「スポーツイベントにおける食品ロス削減手法等に関する調査」(居酒屋の利用者119人とファミリーレストランの利用者83人を対象とした調査。居酒屋の利用者の回答数114人、回答率95.7%、ファミリーレストランの利用者の回答数83人、回答率100%)
事例:飲食店の食品ロス削減の取組(愛知県)
株式会社ナゴヤキャッスルは、愛知県名古屋市(なごやし)等でホテルとレストランを経営する事業者です。
同社では、国際的な枠組みであるSDGs等環境に配慮したおもてなしを目指し、省エネ・節水等の基本的な環境対策に加え、食品ロス削減等持続可能性を意識した多様な取組を行っています。
特にブッフェレストランにおいては、食品廃棄物削減のため、厨房単位で削減目標を設定するとともに、過去の予約人数に応じた食材の使用量をデータ化し、適切な仕入れ量・仕込み量を把握しています。加えて、食品廃棄物の排出量も記録し、増加した場合は要因の分析を行っています。
このほか、ブッフェレストランで残ったパンを二次活用し、フレンチトーストやチョコラスク等にリメイクして提供したところ、顧客には好評で満足度も向上しています。
これらのことから、同社では、削減目標の達成に向けて、引き続き取組を継続していくこととしています。
(食品リサイクル法に基づく基本方針を見直し)
食品リサイクル法(*1)に基づく基本方針では、食品関連事業者による食品廃棄物等の発生抑制と飼料や肥料等への再生利用を促進するため、発生抑制の目標を設定するとともに、食品循環資源の再生利用等実施率の目標を業種別(食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業)に定めています。SDGs(*2)において、食品ロス削減に関する目標が設定されたこと等の社会情勢を踏まえ、令和元(2019)年7月に新たな基本方針を公表しました。
新たな基本方針においては、発生抑制の目標について、達成した業種(*3)の目標値を見直すとともに、新たに3業種(*4)で設定しました。また、食品廃棄物等のうちの特に食品ロスに着目し、令和12(2030)年度までに食品関連事業者から発生する食品ロスをサプライチェーン全体で平成12(2000)年度の発生量(547万t)から半減させるという目標を新たに設定しました。
再生利用等実施率については、食品製造業で目標値を達成し、食品卸売業・小売業では目標値の達成に向けて向上しつつありますが、外食産業では目標値と実績値に乖離(かいり)が生じています(図表1-7-6)。このため、今後5年間の新たな目標の設定に当たっては、外食産業は機械的に目標値を引き上げるのではなく据え置いて、発生抑制の取組を優先して進めていくこととしました。その結果、食品関連事業者の業種別の再生利用等実施率の目標は、令和6(2024)年度までに食品製造業は前回目標と同じ95%、食品卸売業は5ポイント増加の75%、食品小売業は5ポイント増加の60%、外食産業は前回目標と同じ50%となりました。
目標達成に向けて食品関連事業者の意識の向上と取組の促進を図るため、食品ロス削減やリサイクルの取組等の状況を、食品リサイクル法の定期報告に基づく公表対象としました。
*1 正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
*2 トピックス1及び用語の解説3(2)を参照
*3 みそ製造業、ソース製造業、パン製造業等、19業種
*4 水産練製品製造業、食用油脂加工業、食肉小売業
(海洋プラスチックごみ対策アクションプラン等を策定)
プラスチックは、軽量で破損しにくいことや、加工・着色が容易であること、水分や酸素を通しにくく食品を効果的に保護できること等から、農林水産・食品産業において幅広く活用されています。一方で、我が国を含む世界各国から多量の廃プラスチックを輸入し再生利用してきた中国が輸入禁止措置を講じたことや、海岸での漂着ごみやマイクロプラスチック等の海洋プラスチック問題の顕在化を受け、国内におけるプラスチックの資源循環を推進するための体制整備が急がれています。このような中、令和元(2019)年6月のG20大阪サミットにおいて、令和32(2050)年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロとすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。また、これに先立ち、令和元(2019)年5月に、国全体の方針として、海洋プラスチックごみ対策アクションプラン、プラスチック資源循環戦略が策定されました。農林水産・食品産業においては、容器包装の薄肉化(うすにくか)・軽量化による減容化、生分解性プラスチック等の代替素材の活用、リサイクルしやすい素材・製品の研究開発、地域と連携した環境美化活動等、プラスチック資源循環に向けた取組が行われています。これまでの取組の結果、例えば、ペットボトルのリサイクル率は84.9%と欧州の4割や米国の2割と比べ、高水準にあります(*1)(図表1-7-7)。清涼飲料業界では、ペットボトルが海洋ごみとして注目されていることから、使用済みペットボトルを更に回収、リサイクルし、100%有効利用する目標を掲げています。その実現に向け農林水産省も連携し、消費者が利用しやすい業界横断的な回収体制を構築する取組を進めています。
*1 PETボトルリサイクル推進協議会調べ
(地方の企業や中小企業においても自主的取組を推進)
農林水産省では、企業・団体による自主的取組を「プラスチック資源循環アクション宣言」として募集し、広く情報発信すること等により、国民理解の促進や農林水産・食品産業におけるプラスチック資源循環に向けた自主的取組を推進しています。この中で、地方の企業や中小企業、また食品小売業や外食産業の取組を促していくため、令和元(2019)年度は、これらの企業を中心としたセミナーを全国9か所で開催しました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526