トピックス6 植物新品種の海外流出対策

植物の新品種は、我が国農業の今後の発展を支える重要な要素となっています。これまでも、環境や消費者の嗜好(しこう)に合った新品種の開発は、農産物の生産性の向上や付加価値の増加をもたらし、農業者、消費者ともにその利益を享受してきました。
また、このような植物の新品種に係る知的財産の重要性に鑑み、近年、我が国の登録品種が海外に流出する事例が見られたことも踏まえ、優良な植物品種の育成者権を保護し、新品種の開発を促進するため、令和2(2020)年12月に「種苗法の一部を改正する法律」(以下「改正種苗法」という。)が成立しました。以下では、植物の新品種の海外流出対策について紹介します。
(我が国で開発された品種の潜在力)
優良な品種は、我が国農業の強みの一つであり、輸出品目として海外でも高い評価を得ています。一方で、シャインマスカットやイチゴ等の種苗が海外に持ち出され、中国や韓国で産地化された上で東南アジア等にも輸出され、我が国からの輸出産品と競合するなどの問題も指摘されています(図表トピ6-1)。
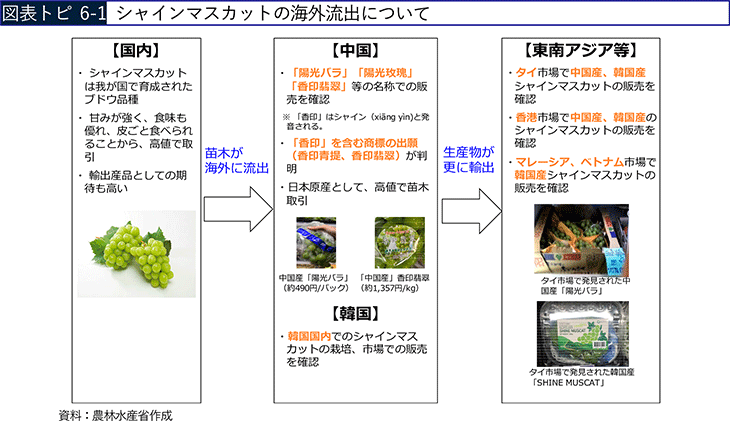
我が国で開発された優良な植物品種の流出により、我が国の農業者が本来得られるべき利益が失われることは大きな問題です。一方で、このような海外における栽培の拡大は、我が国の品種の海外における潜在力が大きいことを示しているともいえます。令和2(2020)年9月に植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム(*1)が公表した調査結果では、我が国の登録品種(*2)と同名の種苗が中国や韓国のインターネットで36品種販売されていることが確認され、我が国の品種の人気の高さが裏付けられました(図表トピ6-2)。
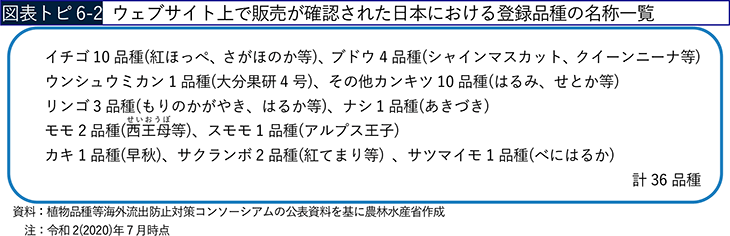
1 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会、一般社団法人日本種苗協会、一般社団法人日本果樹種苗協会、全国食用きのこ種菌協会、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センターで構成
2 種苗法に基づき品種登録を受けている品種
(新品種の展開方向)
都道府県等が開発した新品種のブランド化等が図られる場合、大きく2つの戦略に整理することが可能です。一つは、福岡県が開発したイチゴの「あまおう」(*1)や、北海道が開発した稲の「ゆめぴりか」のように、栽培地域を自らの都道府県内に限定するなどにより品質管理を徹底し、高付加価値の農産物として販売していくものです。もう一つは、栃木県が開発したイチゴの「とちおとめ」(平成23(2011)年11月から一般品種(*2))や、山形県が開発した稲の「つや姫」のように、自らの都道府県外を含めて栽培を許諾し、その新品種の知名度を高めた上で、自らの都道府県内で栽培された生産物をトップブランドとして販売していくものです。いずれの戦略も、品種を開発した都道府県内の産地づくり、ひいては生産者の高収益につながります。
改正種苗法により、許諾を得ていない登録品種の利用が防止しやすくなったことで、こうしたブランド化戦略を更に後押しできることとなります。
1 登録品種名は福岡S6号
2 一般品種には、<1>在来種、<2>品種登録されたことがない品種、<3>品種登録期間が切れた品種が含まれる。とちおとめは平成23(2011)年に登録期間満了
(改正種苗法を活用した海外展開)
農産物輸出に当たっても、国内で都道府県が行っているブランド化戦略と同様の戦略が有効と考えられます。しかし、我が国の種苗法のような品種の保護を受けることができる制度や仕組みが世界の全ての国・地域で設けられているわけではありません。同様の制度のある国・地域では、各国・地域の国内法である品種保護制度に基づき品種登録を行えば、当該国・地域における無断栽培を防止することや、我が国の品種の開発者が特定の現地生産者等をパートナーとして品質や数量、出荷時期、輸出先等を管理させた上で栽培を許諾することは可能です。一方で、品種登録を行っていない国・地域や品種の保護を行う制度そのものが十分でない国・地域では、無断栽培を止めることはできず、海外におけるブランド管理に限界があったというのが現状です。
改正種苗法では、これまで持ち出しを止めることができなかった登録品種の種苗について、育成者権者が海外へ持ち出しが可能な国・地域の指定や国内で栽培可能な地域を指定できるようになり、これに違反した登録品種の海外持ち出しを止めること等が可能となりました。この仕組みを活用すれば、育成者権者の許諾がない登録品種の海外への持ち出しに対する抑止力が高まることとなります。これにより、我が国の新品種を活用した海外展開の選択肢が広がることが期待されます。
→第1章第4節を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




