第1節 農村人口の動向と地方への移住・交流の促進

我が国の農村では、高齢化と人口減少が並行して進行する一方、近年、若い世代を中心に地方移住への関心が高まっており、農村の持つ価値や魅力が再評価されています。また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、ワーケーション(*1)の取組が広がりを見せています。
本節では、農村人口の動向や地方移住の促進に向けた取組等について紹介します。
1 ワーク(仕事)とバケーション(休暇)を組み合わせたもので、リゾート地や帰省先等でパソコン等を使って仕事すること
(1)農村人口の動向
(約9割が農村地域の持つ「食料を生産する場としての役割」を重視)
農村は、国民に不可欠な食料を安定供給する基盤であるとともに、農業・林業等様々な産業が営まれ、多様な地域住民が生活する場でもあり、さらには、国土の保全や水源の涵養(かんよう)等多面的機能が発揮される場としても重要な役割を果たしていることから、その振興を図ることが重要です。
令和3(2021)年6~8月に内閣府が行った世論調査によると、農村地域の持つ役割の中で特に重要と考える役割として、「食料を生産する場としての役割」を挙げた人の割合が86.5%と最も高くなりました(図表3-1-1)。農村地域が食料を安定供給する基盤として認識されていることがうかがわれます。
(農村において高齢化と人口減少が並行して進行)
農村において高齢化と人口減少が並行して進行しています。総務省の国勢調査によれば、令和2(2020)年の人口は、平成27(2015)年に比べて都市(*1)で1.6%増加したのに対して、農村(*2)では5.9%減少しています(図表3-1-2)。農村では生産年齢人口(15~64歳)、年少人口(14歳以下)が大きく減少しているほか、総人口に占める老年人口(65歳以上)の割合は、都市の25%に対して、農村が35%となっており、農村における高齢化が進んでいることがうかがわれます。
1 本節では「都市」の人口を国勢調査における人口集中地区(DID)の人口で算出
2 本節では「農村」の人口を国勢調査における人口集中地区以外の人口で算出
(2)田園回帰の動き
(若い世代を中心として地方移住への関心が高まり)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、若い世代を中心に地方移住への関心の高まりが見られます。
令和4(2022)年6月に内閣府が行った調査によると、東京圏在住者で地方移住に関心があると回答した人の割合は34.2%で、その割合は増加傾向となっています(図表3-1-3)。特に、関心がある人の割合は20歳代において45.2%と高く、若い世代を中心に地方移住への関心が高まっていることがうかがわれます。また、同調査において、地方移住への関心がある理由としては、「人口密度が低く自然豊かな環境に魅力を感じたため」、「テレワークによって地方でも同様に働けると感じたため」と回答した人の割合が高くなっています。
また、地方暮らしやUIJターンを希望する人のための移住相談を行っている認定NPO法人ふるさと回帰支援(かいきしえん)センター(*1)への相談件数は、近年増加傾向で推移しています。令和4(2022)年の相談件数は前年に比べ6%増加し、過去最高の5万2,312件となりました(図表3-1-4)。
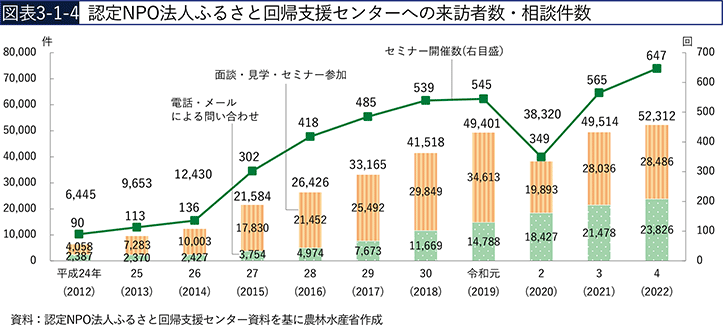
地方への移住・交流の促進に向けて、内閣府は、令和元(2019)年度から地方創生推進交付金により、東京圏外へ移住して起業・就業する者に対する地方公共団体の取組を支援しています。また、総務省は、就労・就農支援等の情報を提供する「移住・交流情報ガーデン」の利用を促進しています。さらに、農林水産省は新規就農者への支援(*2)や同省Webサイト「あふてらす」における移住・就農に関する情報の提供のほか、農的関係人口の創出・拡大(*3)の取組を推進するなど、関係府省による地方移住促進施策により、将来的な農村の活動を支える主体となり得る人材の確保を図っています。

あふてらす「田舎に移住して、農業を営む」
URL:https://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/country/index.html
1 正式名称は「特定非営利活動法人100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター」
2 第2章第2節を参照
3 第3章第7節を参照
(事例)人材育成を通じ移住者等新たな人の流れを創出(和歌山県)

和歌山県田辺市(たなべし)では、地域課題の解決や地域資源の活用をビジネスの視点で考える人材の育成を核として、移住者も含めた新たな人の流れを創出する取組を推進しています。
同市では、人口減少が全国平均より早いスピードで進行する中、移住・定住の促進を図るため、移住関心者への情報発信や、移住希望者への相談対応のほか、移住者に対する住まいや起業等の支援を行っています。
また、平成28(2016)年には、地域の課題を解決しながら、新たな価値を創出できる人材を育成するため、地域企業や金融機関、大学、行政が一体となって運営を行う「たなべ未来創造塾(みらいそうぞうじゅく)」を創設しました。
塾生は、生産・流通・消費等のサプライチェーン全体を網羅した多様な人材を意識して構成されているため、卒業後も塾生同士が有機的なつながりを形成しながら新たな価値を創出しており、地元若手農業者グループによる地域活性化や複数の店舗等を開業する移住者等多くの塾生がローカルイノベーターとして様々な分野で活躍しています。
さらに、同市は首都圏で塾卒業生等による講座を開催するなど関係人口の拡大にも取り組んでおり、受講者の中には同市に移住し新たに塾生になるケースも見られています。同市は、今後とも、新たな人の流れを創出する取組を積極的に推進していくこととしています。

「たなべ未来創造塾」の講義
資料:和歌山県田辺市

塾生が代表を務める農業者グループ
(第8回ディスカバー農山漁村の宝選定)
資料:株式会社日向屋

田辺市で食品加工販売店を営む
塾生の移住創業者
資料:金丸知弘さん
(約4割が農山漁村地域でのワーケーションに関心)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ワーケーションの取組が広がりを見せており、農山漁村への移住の増加や農泊(*1)宿泊者数の増加等につながることが期待されています。令和3(2021)年6~8月に内閣府が行った世論調査では、農山漁村でワーケーションを行いたいと回答した人の割合は41.5%になりました。若い世代ほどその割合が高くなる傾向があり、18~29歳の階層では54.1%となっています(図表3-1-5)。
1 用語の解説(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








