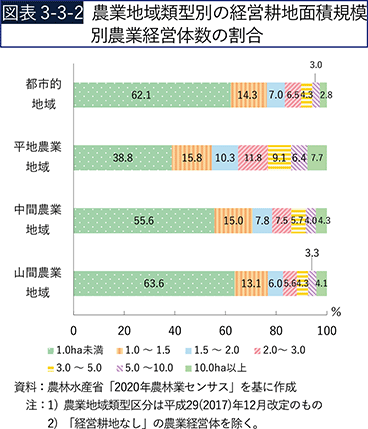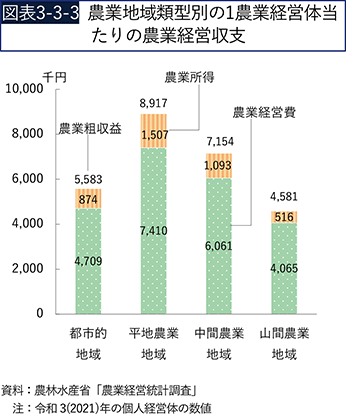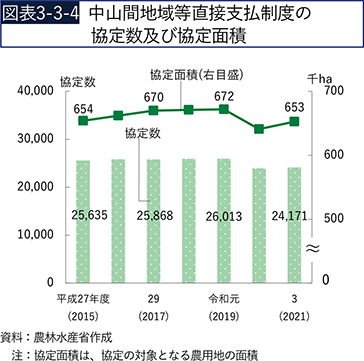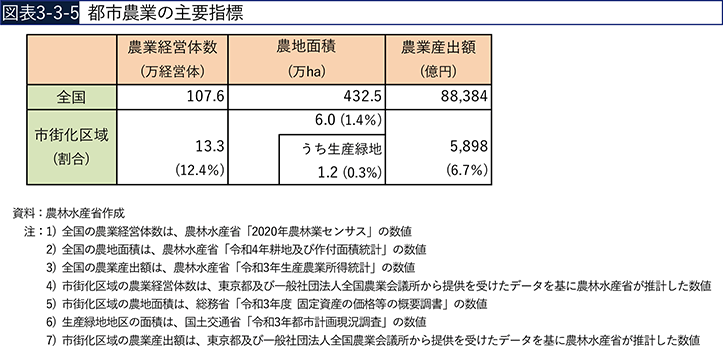第3節 中山間地域の農業の振興と都市農業の推進

中山間地域(*1)は、食料生産の場として重要な役割を担う一方、傾斜地等の条件不利性とともに鳥獣被害の発生、高齢化・人口減少、担い手不足等、厳しい状況に置かれており、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を推進していく必要があります。
一方、都市農業は、新鮮な農産物の供給や農業体験等において重要な役割を担っており、都市農地の有効活用により計画的にその保全を図ることが必要です。
本節では、中山間地域の農業や都市農業の振興を図る取組等について紹介します。
1 農業地域類型区分の中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域のこと
(1)中山間地域の農業の振興
(中山間地域の農業産出額は全国の約4割)
我が国の人口の約1割、総土地面積の約6割を占める中山間地域は、農業経営体数、農地面積、農業産出額ではいずれも約4割を占めており、我が国の食料生産を担うとともに、豊かな自然や景観の形成・保全といった多面的機能の発揮の面でも重要な役割を担っています(図表3-3-1)。
一方、傾斜地が多く存在し、圃場(ほじょう)の大区画化や大型農業機械の導入、農地の集積・集約化(*1)等が容易ではないため、規模拡大等による生産性の向上が平地に比べて難しく、高齢化や人口減少による担い手不足とあいまって、営農条件面で不利な状況にあります。
経営耕地面積規模別に農業経営体数の割合を見ると、1.0ha未満については、平地農業地域で約4割であるのに対し、中間農業地域、山間農業地域では共に約6割となっています(図表3-3-2)。
また、1農業経営体当たりの農業所得を見ると、平地農業地域で151万円であるのに対し、中間農業地域、山間農業地域ではそれぞれ109万円、52万円となっています(図表3-3-3)。
1 用語の解説(1)を参照
(中山間地域等直接支払制度の協定数は前年度に比べ増加)
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方公共団体による支援を行う制度として平成12(2000)年度から実施してきており、平成27(2015)年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。

中山間地域等直接支払制度
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/
令和2(2020)年度から始まった中山間地域等直接支払制度の第5期対策では、高齢化や人口減少による担い手不足、集落機能の弱体化等に対応するため、制度の見直しを行いました。人材確保や営農以外の組織との連携体制を構築する活動のほか、農地の集積・集約化や農作業の省力化技術導入等の活動、棚田地域振興法の認定棚田地域振興活動計画(*1)に基づく活動を行う場合に、これらの活動を支援する加算措置を設けています。
令和3(2021)年度の同制度の協定数は、前年度から約200協定増加し2万4千協定、協定面積は前年度に比べ1万1千ha増加し65万3千haとなりました(図表3-3-4)。
中山間地域等における集落機能の維持を図るため、農林水産省は、協定参加者による話合い等を通じて、集落の将来像を明確化する集落戦略の作成を推進しています。同年度の協定数のうち、体制整備単価(*2)を活用するものは、前年度に比べ約200協定増加し1万8千協定となりました。
また、同年度の協定数のうち、棚田地域振興活動加算(*3)を活用するものは、前年度に比べ68協定増加し314協定となり、その取組面積は前年度に比べ1,369ha増加し5,978haとなりました。
1 第3章第7節参照
2 集落戦略の作成を要件としており、農業生産活動等の体制整備のための前向きな活動を行う場合に当該単価の10割を交付
3 認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算
(事例)良好な棚田の環境維持や景観形成を図る取組を推進(山口県)

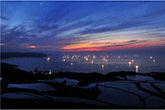
イカ釣り漁船の漁り火が輝く棚田の風景

荒廃農地を再生し開園した「棚田の花段」
山口県長門市(ながとし)の東後畑(ひがしうしろばた)地区では、中山間地域等直接支払交付金等を活用し、良好な棚田の環境維持や景観形成を図る取組を推進しています。
同市では棚田保護条例が制定され、地域で6次産業化(*1)やグリーンツーリズムへの機運が高まったことを契機として、平成18(2006)年に同地区でNPO法人ゆや棚田景観保存会(たなだけいかんほぞんかい)が設立されました。同保存会では、「日本の棚田百選」や「つなぐ棚田遺産(*2)」にも選定された優美な景観を保全するため、同交付金を活用し、荒廃農地(*3)の増加が懸念される棚田での生産活動を継続しています。同地区は令和2(2020)年6月に指定棚田地域に指定され、中山間地域等直接支払制度の棚田地域振興活動加算も活用し、棚田地域の振興を図っています。
また、多数のため池や用排水路、農道等の維持管理に加え、環境教育や食育、都市住民との交流や特産品の開発等を実施しているほか、高齢者が集まれる場所として交流カフェを開設し、地域福祉や地域づくりにも寄与しています。さらに、平成28(2016)年から3年間で同市の事業支援を受け、1.3haの荒廃農地を再生しました。
同地区では今後とも、地域住民のみならず、幅広い関係者が連携して棚田地域の振興を図っていくこととしています。
1、3 用語の解説(1)を参照
2 第3章第7節を参照
(中山間地域等の特性を活かした複合経営等を推進)
高齢化・人口減少が進行する中山間地域を振興していくためには、地形的制約等がある一方、清らかな水、冷涼な気候等を活かした農作物の生産が可能である点を活かし、需要に応じた市場性のある作物や現場ニーズに対応した技術の導入を進めるとともに、耕種農業のみならず畜産、林業を含めた多様な複合経営を推進することで、新たな人材を確保しつつ、小規模農家を始めとした多様な経営体がそれぞれにふさわしい農業経営を実現する必要があります。
このため、農林水産省では、中山間地域等直接支払制度により生産条件の不利を補正しつつ、中山間地農業ルネッサンス事業等により、多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現や、地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承に向けた取組を総合的に支援しています。また、米、野菜、果樹等の作物の栽培や畜産、林業も含めた多様な経営の組合せにより所得を確保する複合経営を推進するため、農山漁村振興交付金等により地域の取組を支援しています。
(山村への移住・定住を進め、自立的発展を促す取組を推進)
振興山村(*1)は、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全や良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担っているものの、高齢化や人口減少等が他の地域より進んでいることから、国民が将来にわたってそれらの恵沢を享受することができるよう、地域の特性を活かした産業の育成による就業機会の創出、所得の向上を図ることが重要となっています。
農林水産省は、地域の活性化・自立的発展を促し、山村への移住・定住を進めるため、平成27(2015)年度から地域資源を活かした商品の開発等に取り組む地区を支援しています。
1 山村振興法に基づき指定された区域。令和4(2022)年4月時点で、全市町村数の約4割に当たる734市町村において指定
(2)多様な機能を有する都市農業の推進
(市街化区域の農業産出額は全国の約1割)
都市農業は、都市という消費地に近接する特徴から、新鮮な農産物の供給に加えて、農業体験・学習の場や災害時の避難場所の提供、住民生活への安らぎの提供等の多様な機能を有しています。
都市農業が主に行われている市街化区域内の農地が我が国の農地全体に占める割合は1%である一方、農業経営体数と農業産出額ではそれぞれ全体の12%と7%を占めており、消費地に近いという条件を活かした、野菜を中心とした農業が展開されています(図表3-3-5)。
農林水産省では、都市住民と共生する農業経営の実現のため、農業体験や農地の周辺環境対策、防災機能の強化等の取組を支援するなど、多様な機能を有する都市農業の振興に向けた取組を推進しています。
(都市農地貸借法に基づき貸借された農地面積は拡大傾向で推移)
生産緑地制度(*1)は、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内の農地の計画的な保全を図るものです。市街化区域内の農地面積が一貫して減少する中、生産緑地地区(*2)面積はほぼ横ばいで推移しており、令和3(2021)年の同面積は前年並の1.2万haとなっています(図表3-3-6)。
令和4(2022)年には生産緑地地区の約8割が生産緑地の指定から30年が経過し、農地転用の急激な増加が懸念されましたが、平成29(2017)年に、生産緑地の買取申出期限を所有者の意向により10年延期する「特定生産緑地制度」の導入により、平成4(1992)年に生産緑地法に基づき都市計画に定められた生産緑地のうち、特定生産緑地に指定された割合は、令和4(2022)年12月末時点で約89%となっています。
また、都市農業の振興を図るため、意欲ある農業者による耕作や市民農園の開設等による都市農地の有効活用を促進しています。農地所有者が、意欲ある農業者等に安心して農地を貸付けすることができるよう、平成30(2018)年に創設された都市農地貸借法(*3)に基づき貸借が認定・承認された農地面積は、令和3(2021)年度は、前年度に比べ25万9千m2増加し77万5千m2となりました(図表3-3-7)。
農林水産省では、都市農地貸借法の仕組みの現場での円滑かつ適切な活用を通じ、貸借による都市農地の有効活用を図ることとしています。
1 三大都市圏特定市における市街化区域農地は宅地並に課税されるのに対し、生産緑地に指定された農地は軽減措置が講じられる。
2 市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500m2以上の農地
3 正式名称は「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」
(事例)宅地を農地転換し、生産緑地を拡大する取組を展開(東京都)


農地転換後の圃場
東京都練馬区(ねりまく)にある加藤(かとう)果樹園は、都市住民に対して新鮮な農産物の供給や身近な農業体験の場の提供を行うとともに、自らが所有する宅地を農地転換し、生産緑地を拡大する取組を展開しています。
同果樹園では、かき等を中心に、少量多品目の果樹や野菜を生産するともに、ブルーベリーの摘み取り体験ができる観光農園を運営しています。東京都内での生産という特性を活かした採れたての野菜の販売や、園主の分かりやすい指導の下での摘み取り体験等の取組により、多くの利用者がリピーターとして訪れています。
また、同果樹園は、空き家となっていた母屋を農地へ転換するとともに、生産緑地の指定を受けることにより、長期的な展望の下で農地を保全し、安定的に農業経営を続けることが可能となっています。
新たに農地化した圃場では、かきのジョイント栽培(*)に取り組んでいます。樹勢が均一化することから、作業が容易となる上、車椅子の方でも利用できるため、今後は、障害のある人でも利用できる観光農園の開設も目指すこととしています。
接ぎ木により樹を直線的に連結させる栽培方法であり、早期成園化や省力化、軽労化が期待される。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883