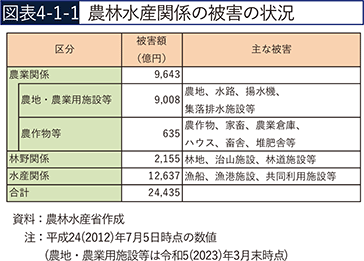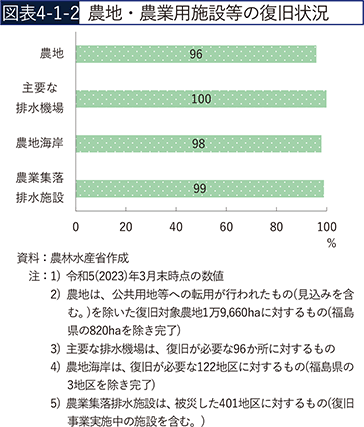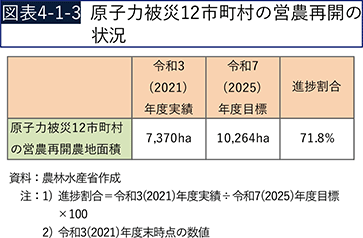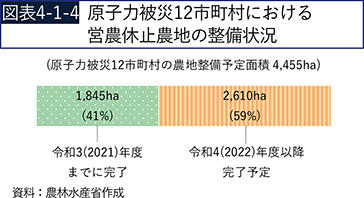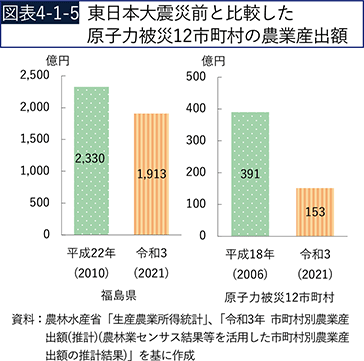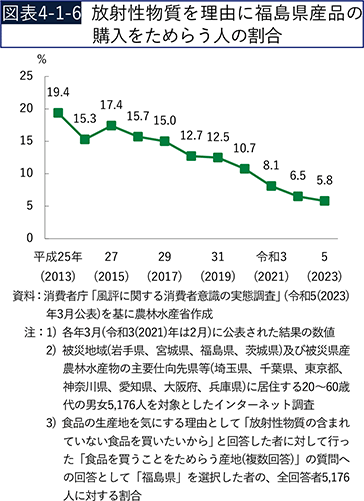第1節 東日本大震災からの復旧・復興
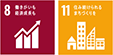
平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県の3県を中心とした東日本の広い地域に東京電力福島第一(とうきょうでんりょくふくしまだいいち)原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故の影響を含む甚大な被害が生じました。
政府は、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間を「第2期復興・創生期間」と位置付け、被災地の復興に向けて取り組んでいます。
本節では、東日本大震災の地震・津波や原子力災害からの農業分野の復旧・復興の状況について紹介します。
(1)地震・津波災害からの復旧・復興の状況
(営農再開が可能な農地は復旧対象農地の96%)
東日本大震災による農業関係の被害額は、平成24(2012)年7月5日時点(農地・農業用施設等は令和5(2023)年3月末時点)で9,643億円、農林水産関係の合計では2兆4,435億円となっています(図表4-1-1)。これまでの復旧に向けた取組の結果、復旧対象農地1万9,660haのうち、令和5(2023)年3月末時点で1万8,840ha(96%)の農地で営農が可能となりました(図表4-1-2)。農林水産省は、引き続き農地・農業用施設等の復旧に取り組むこととしています。
(地震・津波からの農地の復旧に併せた圃場の大区画化の取組が進展)
岩手県、宮城県、福島県の3県では、地域の意向を踏まえ、地震・津波からの復旧に併せた農地の大区画化に取り組んでいます。令和3(2021)年度末時点の整備計画面積8,510haのうち、大区画化への完了見込面積は8,240ha(96.8%)となっており、地域農業の復興基盤の整備が進展しています。
(事例)大規模な高設栽培の導入により、いちご産地の復活を後押し(宮城県)


いちごの高設栽培
資料:宮城県亘理町
宮城県亘理町(わたりちょう)は、大規模な高設栽培の導入によるいちごの生産拡大を推進し、いちご産地の復活を後押ししています。
東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けた同町では、平成25(2013)年に町内3地区で大型園芸施設を備えたいちご団地を整備しました。
同団地では、高収量で管理しやすい高設栽培を導入した結果、生産量が拡大するとともに、単収も東日本大震災前を大幅に上回る水準となっています。
収穫されたいちごの多くは、みやぎ亘理(わたり)農業協同組合を通じて、仙台市中央卸売市場(せんだいしちゅうおうおろしうりしじょう)を始め北海道や京浜(けいひん)地区に「仙台(せんだい)いちご(*)」として出荷されており、復興のシンボルとして大きな期待が寄せられています。平成29(2017)年からは、全国農業協同組合連合会宮城県(みやぎけん)本部を通じて、東日本大震災の影響で停止していた香港向け輸出が再開されるなど、需要拡大に向けた取組も進められています。
「仙台いちご」は、東日本大震災後の平成24(2012)年に地域団体商標に登録
(福島イノベーション・コースト構想に基づく実証研究等を推進)
農林水産省は被災地域を新たな食料生産基地として再生するため、産学官連携の下、農業・農村分野に関わる先端的で大規模な実証研究を行っています。
令和3(2021)年度から、福島イノベーション・コースト構想に基づき、ICTやロボット技術等を活用して農林水産分野の先端技術の開発を行うとともに、状況変化等に起因して新たに現場が直面している課題の解消に資する現地実証や社会実装に向けた取組を推進する「農林水産分野の先端技術展開事業」を実施しています。
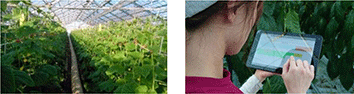
きゅうり生産管理支援システムの実証
資料:福島県農業総合センター(左)、大阪公立大学(右)

農林水産分野の先端技術展開事業
(東日本大震災関連技術情報)
URL:https://www.affrc.maff.go.jp/sdocs/sentan_gijyutu/index.html(外部リンク)
(東日本大震災からの復旧・復興のために人的支援を実施)
農林水産省は、東日本大震災からの復旧・復興や農地・森林の除染を速やかに進めるため、被災した地方公共団体との人事交流を行っています。また、被災地における災害復旧工事を迅速・円滑に実施するため、被災県からの支援要望に沿って、他の都道府県等とともに、専門職員を被災した地方公共団体に派遣しています。特に原子力被災12市町村(*1)については、令和2(2020)年度から12市町村全てに職員を派遣し、市町村それぞれの状況に応じた支援を実施しています。
1 福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
(2)原子力災害からの復旧・復興
(農畜産物の安全性確保のための取組を引き続き推進)
生産現場では、市場に放射性物質の基準値を上回る農畜産物が流通することのないように、放射性物質の吸収抑制対策、暫定許容値以下の飼料の使用等、それぞれの品目に合わせた取組が行われています。このような生産現場における取組の結果、平成30(2018)年度以降は、全ての農畜産物(*1)において基準値超過はありません。
1 栽培・飼養管理が可能な品目
(原子力被災12市町村の営農再開農地面積は目標面積の約7割)
原子力被災12市町村における営農再開農地面積は、令和3(2021)年度末時点で、前年度に比べ793ha増加し7,370haとなっています。しかしながら、特に帰還困難区域を有する市町村の営農再開が遅れていることが課題となっています。農林水産省では、平成23(2011)年12月末時点で営農が休止されていた農地1万7,298haの約6割で営農再開することを目標としています。この目標に対する進捗割合は、令和3(2021)年度末時点で71.8%となっています(図表4-1-3)。
(農地整備の実施済み面積は1,845haに拡大)
原子力被災12市町村の農地については、営農休止面積1万7,298haのうち、営農再開のための整備が実施又は検討されている農地の面積は4,455haとなっています。このうち、令和3(2021)年度末時点で1,845haの農地整備が完了しました(図表4-1-4)。
(原子力被災12市町村の農業産出額は被災前の約4割)
福島県の農業産出額は、県全体では東日本大震災前の平成22(2010)年が2,330億円であったのに対し、令和3(2021)年が1,913億円と約8割まで回復しています。一方、原子力被災12市町村では、東日本大震災前の平成18(2006)年が391億円であったのに対し、令和3(2021)年が153億円と約4割にとどまっています(図表4-1-5)。
(特定復興再生拠点区域において営農再開に向けた取組を推進)
原子力被災12市町村では、避難指示解除の時期や帰還状況(居住率)により、市町村の営農再開割合に差が出ており、特に帰還困難区域を有する市町村の営農再開が遅れています。
福島復興再生特別措置法においては、5年を目途に避難指示を解除し、住民の帰還を目指す「特定復興再生拠点区域」の復興・再生を推進することとしています。
また、令和4(2022)年4月に葛尾村(かつらおむら)、双葉町(ふたばまち)の同区域において生産されるホウレンソウ、キャベツ、ブロッコリー等の野菜の出荷制限・摂取制限が解除されたほか、大熊町(おおくままち)では出荷制限・摂取制限の解除に向けて試験栽培が実施されるなど、営農再開に向けた取組が進められています。
(営農再開に向け、地域外も含めた担い手の確保等が課題)
農林水産省は、福島相双復興(ふくしまそうそうふっこう)官民合同チームの営農再開グループに参加し、平成29(2017)年4月から令和3(2021)年12月にかけて、原子力被災12市町村の農業者を対象として営農再開意向に関する聞き取りを実施しました。その結果、「営農再開済み」が約4割、「営農再開の意向あり」が約1割、「再開の意向なし」が約4割、「再開意向未定」が約1割となりました。また、「再開の意向なし」又は「再開意向未定」である農業者のうち、「農地の出し手となる意向あり」と回答した農業者は約7割に上ることから、地域外も含めた担い手の確保や担い手とのマッチングが課題となっています。
(生産と加工等が一体となった高付加価値生産を展開する産地を創出)

かんしょの高品質苗の供給施設
農林水産省では、令和3(2021)年から、国産需要の高い加工・業務用野菜等について、市町村を越えて広域的に、生産・加工等が一体となって付加価値を高めていく産地の創出に向けて、産地の拠点となる施設整備等の支援を行っています。
令和3(2021)年度に、農業者団体、原子力被災12市町村等で構成する福島県高付加価値産地協議会が設立され、産地の創出に向けた具体的な行動計画を策定・公表しています。令和4(2022)年度においては、かんしょの産地化に向けた高品質苗の供給施設が完成したほか、パックご飯等の加工施設の整備を始めとした産地化に向けた取組が進められています。
(事例)福島再生加速化交付金を活用し、ワイン醸造施設を整備(福島県)


収穫を迎えるシャルドネ
資料:福島県川内村
福島県川内村(かわうちむら)では、新たな農業への挑戦として、村内で収穫するぶどうを原料としたワイン生産の取組を推進しています。
同村では、平成29(2017)年に「かわうちワイン株式会社」を設立するとともに、ワイン醸造用ぶどうの栽培圃場(ほじょう)を整備し、令和4(2022)年には、約4haの圃場で、シャルドネ、メルロー等、約13,500本のワイン醸造用ぶどうの栽培が行われています。
また、同村では、令和3(2021)年度に福島再生加速化交付金を活用し、醸造施設「かわうちワイナリー」の整備を行いました。同施設では、令和3(2021)年9月から醸造が開始され、香り高く仕上がったワインは令和4(2022)年3月から販売が行われています。
今後は、ワインを核として村内事業者とともに、地域資源や地場産品等とのコラボレーションにより、地域経済の活性化を図ることを目指しています。
(放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合は減少傾向で推移)
消費者庁が令和5(2023)年3月に公表した調査によると、放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合は5.8%となり、調査開始以来最低の水準となりました(図表4-1-6)。
風評等が今なお残っていることを踏まえ、復興庁やその他関係府省は、平成29(2017)年12月に策定した「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組のフォローアップとして、「知ってもらう」、「食べてもらう」、「来てもらう」の三つを柱とする情報発信を実施し、風評の払拭に取り組んでいます。
また、福島県の農林水産業の復興に向けて、福島ならではのブランドの確立と産地競争力の強化、GAP(*1)認証等の取得、放射性物質の検査、国内外の販売促進等、生産から流通・販売に至るまでの総合的な支援を行っています。
さらに、「食べて応援しよう!」のキャッチフレーズの下、消費者、生産者等の団体や食品事業者等、多様な関係者の協力を得て被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的な利用を進めており、引き続き被災地産食品の販売促進等の取組を推進することとしています。

第4回食べて応援しよう!in仙台

食べて応援しよう!
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/
1 用語の解説(2)及び第2章第7節を参照
(東京電力ホールディングスによる農林漁業者等への損害賠償支払累計額は9,996億円)
原子力損害の賠償に関する法律の規定により、東電福島第一原発の事故の損害賠償責任は東京電力(とうきょうでんりょく)ホールディングス株式会社(以下「東京電力ホールディングス」という。)が負っています。
東京電力ホールディングスによるこれまでの農林漁業者等への損害賠償支払累計額は、令和5(2023)年3月末時点で9,996億円となっています(*1)。
1 農林漁業者等の請求・支払状況について、関係団体等からの聞き取りから把握できたもの
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883