日本の食文化 日本の食文化に欠かせない 「発酵」の世界




和食に使われている味噌、醤油、酢、みりん、酒はすべて発酵食品です。だしを取るのに欠かせない日本固有の鰹節(枯れ節)は、発酵食品でもあり、世界一かたい食品だといわれています。
発酵は微生物の働きによってつくられるものですが、温暖で湿度の高い気候風土を活かした日本特有の食文化といっていいでしょう。
そんな発酵のスゴさと魅力を東京農業大学応用生物科学部醸造科学科教授で日本の調味料研究者、前橋健二先生にお聞きしました。

─ そもそも発酵とは何ですか。
腐敗と何がちがうのですか。
発酵にはいくつかの意味合いがありますが、ここでは発酵食品という場合の発酵についてお話しします。
発酵とは、食品に微生物が増えることによって起こる変化のことです。それを発酵現象といいます。そして腐敗も、食品に微生物が増えることによって起こる変化のこと。どちらも微生物の活動ということになります。
では、発酵と腐敗、いったい何が違うのか。それは関わる微生物の種類などではなく、人にとって有害か否かの違いです。味や匂いの好みは民族レベル、地域レベルでそれぞれの価値観があるので、実は発酵と腐敗の線引きは難しいところなのですが、一番大事なことは人にとっての安全性です。微生物が増えて変化した時に、安全性が保たれていることが発酵の第一条件です。

─ 日本の発酵食品の特徴は何ですか。
「麹(こうじ)」を使っているということが一番大きな特徴です。麹菌を米や麦、大豆などに加えて培養させ、麹として使うのですが、醤油、味噌、みりん、酢、酒、焼酎はすべて麹を使ってつくられます。
もともと麹は中国から入ってきたといわれていますが、麦や大豆でつくる中国とは異なり、稲作が盛んだった日本では米で麹をつくるようになりました。お供え物のごはんに生えたカビが麹の始まりだとか、湿気の多い日本ならでは、という説など、始まりの物語には諸説ありますが、米で麹をつくるようになってから、発酵技術は格段に進歩します。
米味噌が全国に広がり、その後、各地で独自の味噌がつくられるようになりました。醤油も、麹を育ててから塩水に浸けることで発酵・分解が促進され、香り高いおいしい醤油になりました。酒づくりも然りです。長い年月をかけて、麹をどう使ったらおいしくなるかを追求し、全国各地で個性豊かなお酒や焼酎がつくられています。

清酒の麹づくり。蒸米を麹室に広げ、麹菌をかけて一定の温度・時間を保ったのち、麹の塊をこなし均一にする「切り返し」という作業。
─ 麹を使うメリットは何ですか。
麹菌は分解力の強い酵素を大量につくります。たんぱく質をアミノ酸に分解する酵素やでんぷんを糖に分解する酵素をはじめ、たくさんの酵素を生成します。
たくさんの酵素が生成されるということは、言い換えれば一分子から無数の分子が生まれ、物質の数がすごく増えて、複雑になるわけです。アミノ酸などのうま味物質や甘い糖もできます。そうすると、そのできたものを栄養にして乳酸菌や酵母が勝手に増殖してきますから、発酵をさらに広げていくわけです。縦にも横にも味が広がっていく。複雑さがおいしさなんですね。
麹を使うことで圧倒的に味に奥行きが出ます。乳酸菌や酵母、酢酸菌を使う国は世界中にありますけれど、麹を中心に使っているのは日本の発酵の特徴です。麹菌は和食を支えているといっても過言ではありませんし、食文化だけでなく、日本文化を支えている、日本人にとってなくてはならない菌なのです。

麹菌は日本の食文化に欠かせない存在です。
─ 菌の扱い方に日本ならではの
特徴はありますか。
自然に生えてくる菌を育てて使う文化はどこの国にもあったのですが、日本ではいち早く種麹(麹菌の種、胞子)を純粋培養する技術を確立しました。それよりずっと昔は、種麹に灰などを入れて雑菌を殺して純化するなど、工夫して種麹をつくっていました。日本の発酵技術は科学的な裏付けが取れない時代から、先人が試行錯誤して経験値によってつくり上げてきたものなのです。
麹菌にしても自然界に存在する野生麹菌とはまったく異なるもので、選び抜かれた安全な種を純粋培養して保管しています。
日本では増殖させて麹をつくり、ほかの菌(微生物)を巧みに組み合わせて、発酵食品をつくりあげてきたわけです。和食の素晴らしいところは、発酵調味料によって食材から味を引き出し、それだけで複雑な味をつくりあげる点ですね。

精白米の味噌用米麹(左)と脱脂加工大豆・小麦の醤油用麹。
─ 発酵の利点、
魅力は何だと思いますか。
発酵によって保存性が高まります。食材を保存して時間が経つと、微生物が増殖して発酵が自然に起こり、人類は発酵と出合いました。そして冷蔵技術がなかった時代の保存技術として、発酵技術を確立していったわけです。
そして発酵の魅力は、先ほどもいったように、なんといっても素材のうま味を引き出すこと。発酵する過程で、物質から新しい物資が生まれているのですが、それが機能性成分だったり、健康成分だったりするわけです。
江戸時代の本の多くに「味噌は体にいい」と盛んに書いてあるのですが、あの時代に分析していたわけではありません。でも経験的に認識していて、だからこそ発酵食品はつくり続けられたのです。ただおいしいというだけではなく、健康にいいからずっと続けているわけです。また健康にいいからといって、おいしくなければ続きません。

─ ほかにも皆さんに伝えておきたい
発酵の利点はありますか?
2つあります。
ひとつは麹菌がたんぱく質を分解することで生成されるペプチドという成分に、高い機能性があるということです。このペプチドに血圧を低下させるなど、さまざまな健康効果が期待できることが、長い間の研究で次々にわかってきました。今では特定保健用食品にもかなり利用されています。
日本の発酵食品は麹を使っているので、必ずペプチドが生成されます。ペプチドには味わいが複雑でうま味につながるものもあるので、それがおいしさにつながり健康にもつながっていく。おいしいうえに健康効果を感じられるというのが、麹を使った発酵食品の魅力です。
もうひとつは、菌そのものが体の役に立つということです。腸内の免疫細胞を刺激するのは生きた乳酸菌だけでなく、乳酸菌の死骸も影響することが研究で明らかになりました。殺菌を重視する一般食品とは異なり、発酵食品にはたくさん生きた菌もいるし、中には死んでいる菌もいます。もちろん調理によって生きた菌は死ぬことが多いですが、それでもそれを体内に取り入れることで免疫が刺激され、体調を整えてくれるというのです。乳酸菌だけでなく酵母菌や納豆菌などの発酵菌すべてがそういう効果を持っているだろうと考えられています。
「発酵食品を食べましょう」というと、「匂いやクセが強いものは苦手で、何を食べていいかわからない」と思うかもしれませんが、日本の伝統的な調味料を使えば、発酵の恵みを十分受けることができます。日本に味噌や醤油、みりんなどの発酵調味料がそろっていることはとても素晴らしいことなんです。それを忘れないでほしいですね。
代表的な発酵菌
日本の発酵食品は1種類の菌ではつくれません。複数を組み合わせることによって、複雑なうま味が得られるのです。発酵菌の組み合わせは経験値。そこが日本の発酵食品のすごさです!
では、発酵菌にはどんな種類があるのでしょうか。主なものを前橋先生に解説していただきました。
麹菌

酵素を大量につくるというのが一番のポイント。味噌、醤油、酒、焼酎など用途によって、働きもつくりだす味わいも異なる種麹があります。発酵食品の複雑なうま味や健康効果を作り出すための微生物の力を発揮する発酵菌の代表的存在。日本の食文化を支える存在として、(公財)日本醸造協会によって「国菌」に認定されました。
酵母

際立つ香りが特長。大きく分けるとアルコール酵母と耐塩性酵母の2種類あり、パンにはアルコール酵母を、味噌や醤油をつくる時には耐塩性酵母を使います。
乳酸菌

やや渋味があるようなすっぱさが特長。人間と同じ5大栄養素を必要とするので、人間が生活するところには必ずいる菌です。
納豆菌

納豆づくりに欠かせない菌。納豆菌は増殖速度が速いので、麹菌を扱っている酒蔵などに入る前には納豆を食べないなど、マナーとして気を付けるようにしましょう。
酢酸菌
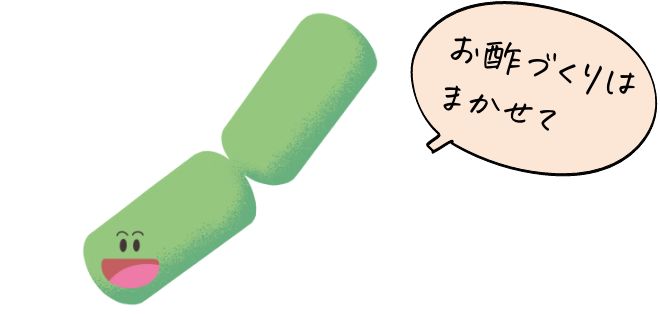
酢をつくるのに不可欠な菌です。酢酸特有のツンと鼻にくる酸味が特長。ナタデココも酢酸菌の仲間がつくる発酵食品です。

「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指して活動している発酵デザイナー小倉ヒラクさんのお話です。

僕が考える発酵のすごさ
発酵食品の優れている点、その第1は保存性、第2に栄養、第3がおいしさ。この順番が大切だと僕は思っています。
まずは保存性。冷蔵庫や保存料がない時代は、食材が偏ります。きゅうりが旬の時期にはたくさんきゅうりが採れて、サバが獲れる時期には大量のサバ。
食べきれない量がとれるか、何も食べるものがないか、昔はそれくらい極端な状況が当たり前だったわけです。煮ても焼いても食べきれないという時に、人々はいかに保存するかということを考えます。塩漬けにしたり、煙でいぶしたりといろいろな方法を試していくうちに、結果として発酵食品が誕生したのではないかと思います。

発酵食品をセレクトしたショップ「発醇デパートメント」の店内。2020年4月、東京・下北沢にオープン。
そして、その発酵しているものを食べている集落の人々に対して、近隣の集落では「あそこの人たちが元気なのはなんでなんだろう」という話になり、やがて「あれ(発酵しているもの)を食べているからではないか」と考えるようになったのでは。人々は、こういうものを食べていると長生きするとか、元気でいられるということに気づいていったのではないか、国内だけでなく世界中の発酵食品を調べ歩くうちに、僕はそう考えるようになりました。これが2番目の優れた点です。
いろんな場所で発酵食品の起源の話をしていると、基本的には最初はみんなイヤイヤ食べていたとか、おいしくなかったという話を聞きます。
毎日取り入れるのなら、おいしいほうがいい。そこで、だんだんレシピが洗練されていき、毎日食べても飽きない、おいしい食品になっていったのでしょう。
今でも発酵食品のおいしさにあまりプライオリティを置かない文化もあるのですが、日本の伝統的な発酵食品がおいしいのは、やはり日本人はおいしくしようと工夫してきたからだと思います。おいしさにこだわるのは日本人の国民性かもしれません。
発酵食品に出会ってから
僕は生まれつき体が弱く、20代の半ばまで日々不調を抱えていました。味噌汁など飲まなかったし、食事を気にすることもありませんでした。それが発酵食品と出会い、積極的に摂ることで体調が良くなっていったという手応えがありました。
人によって体質はいろいろあるので、「発酵食品を摂ったからって、別に何も変わりませんでした」という人もいるかもしれませんが、いろいろな研究によって、伝統的な日本の発酵食品を摂ることで体の新陳代謝がサポートされたり、腸内環境が改善すると報告されています。僕は経験的に実感しているので、「伝統的な発酵食品が日本人を元気にする」といっていいのではないかと考えています。
また、僕の場合は体調が良くなったことだけでなく、発酵食品によって自分の知らなかった味覚を教えてもらえたことも、とても良かったと思っています。
僕はずっと地元の給食センター、保育園などで「手前味噌をつくる」や「麹をつくる」といったワークショップを開催し、延べ何千という人たちと一緒に手づくりしてきました。
発酵文化を実感を持って感じられるのが味噌づくりです。各地域、各家庭で味噌をつくるのもいいですね。味噌は手づくりする中で生きた知識をいろいろ学べるところがいい。だから僕は一貫して「味噌をつくりましょう」といってきました。皆さんもぜひ挑戦してみてください。発酵食品がより身近に感じられるようになりますよ。

農林水産省「うちの郷土料理」から
各地域を代表する「発酵」を
活用した郷土料理を紹介します。

昔は正月をはじめハレの日の料理として作られていました。飯寿司を家で漬け込むことが少なくなっていることから、地域の食文化として継承する取り組みが行われています。

魚や米、野菜を米麹と一緒に樽に入れて漬け込み、乳酸発酵させたなれずしの一種。漁師の家で作られていたものが発祥とされ、使う魚はホッケやサケ、ハタハタ、ニシン、サンマなどさまざま。晩秋から初冬にかけて漬け込まれ低温で発酵させることが特徴です。


別名は「けいとまま」。鶏頭の花のような赤い色とごはんをさす「まま」からの命名。天然の色素と発酵の力を利用した伝統の味。地域によってはきゅうりやみょうがを加えることも。

秋田県北部に伝わる赤漬け、赤ずしはお盆のお供え料理として、その時期の食卓には欠かせない一品。塩で揉んだ赤じそと酢、砂糖を炊いた餅米に混ぜ、数日間寝かせれば出来上がり。さっぱりとした酸味が食欲をそそります。


おなめ味噌は秩父地方の道の駅などで購入できますが、味噌の原料となる「おなめこうじ」が市販されているので手づくりも可能。季節の野菜や漬物を刻んで入れて我が家の味に。

麦麹と大豆で作られるなめ味噌。秩父地方などではごはんがすすむ常備菜として普段から食卓にのぼりますが、冷蔵庫で保存すれば半年以上日持ちすることから保存食としても重宝されています。夏場の食欲増進に一役買う一品です。


身欠きにしんは米のとぎ汁や米ぬかを溶かした水で戻すのがポイント。「春告げ魚」という別名があるにしんは縁起の良い魚とされ、お正月やハレの日の料理にも多用します。

生のにしんは日持ちがしないため、腹の身を欠(か)いて乾燥させて保存したのが「身欠きにしん」。これを水でもどし、ニンジンやキャベツなどの野菜と一緒に塩で下漬けした後、甘酒や酒粕と混ぜ合せて作ります。


正月やハレの日など人が集まる時に出され、かつては各家庭で作られていました。近年はニゴロブナの減少などによって、手作りする家庭は減りつつあるといいます。

塩漬けにした魚を米と一緒に漬け込み、発酵させることで年間にわたって保存できるようにしたもの。よく使われる魚は琵琶湖の固有種のニゴロブナ。発酵の過程で生成される乳酸の働きで骨が柔らかくなり、丸ごと食べられます。


今では鳥取県の土産物として知られ、全国で食べられるようになりました。麹独特の甘さとうま味が好まれています。ごはんやお茶漬け、酒のお供の他、調味料としても重宝します。

生イカではなく、干して臭みが抜け適度な塩気を含んだスルメイカを使うのが特徴。刻んで麹に漬けておくと味が染み込んで柔らかくなり、うま味が増します。食材が手に入りにくくなる冬に向けて各家庭で作られてきた保存食です。


日常的な食材として、家庭では木綿豆腐をしっかり水切りをしてつくることが多い。口どけのよいクリームチーズのような味わいで、ワインや日本酒にもよく合います。

八代市坂本町鮎帰(あゆがえり)地区の「かずら豆腐」、五木村の「樫の木豆腐」はいずれも硬い食感が特長の豆腐ですが、味噌漬けにするにはこの硬さがポイント。平家の落人が伝えたとされる歴史ある郷土食です。


「うちの郷土料理
~次世代に伝えたい大切な味~」が
全都道府県網羅!

2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたのは、世代を超えて受け継がれてきた慣習であることや、日本各地で「和食」の保護のための取り組みが行われていることなどが評価されてのことでした。喜ばしいことでしたが、一方で食の多様化が進み家庭での食習慣が変わる中、日本の食文化を未来にどうつなげるか、が大きな課題となりました。
そこで農林水産省では、和食文化を次世代に継承していくための取組の一環として、2020年に全国各地の郷土料理の歴史やレシピ、郷土料理を生んだ地域の背景等をデータベース化したWebサイトを開設。そして、2022年3月に、47都道府県、1,365品目もの郷土料理が出揃いました。
掲載されている料理はまず、地元で入手できる食材を利用していること。そして、歴史・文化・風習的な特徴、または気候・風土を背景とした特徴があること。加えて、その地域で人気があり愛着を持たれていることなどを重視して選定されました。
簡単に作れるもの、地域のスーパーマーケットや農産物直売所で手に入るものなど、より身近に楽しめる料理も目白押し。そんな各地の料理は「季節」「種類」「50音」から検索できます。
今週のまとめ
「発酵」とは、食品が微生物の
はたらきによって
変化し、
人間にとって有益に作用すること。
地域固有の多様な食文化は、
郷土料理として受け継がれています。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449






