日本食材輸出レポート



農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略とは

世界の農林水産物や食品の市場は拡大しています。そこで政府は、海外のニーズに対応して輸出額を増やしていけるように、2020年に「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を策定しました(直近では2023年12月に改訂)。この戦略には、3つの基本的な考え方と具体的な施策があります。
1つめは、「日本の強みを最大限に発揮するための取組」。海外で評価される日本の強みがある輸出重点品目(現在29品目)を選定し、各品目ごとにターゲット国・地域と輸出目標を設定するなどです。
2つめは、「マーケットインの発想で輸出にチャレンジする事業者の支援」。リスクを取って輸出に取り組む事業者への投資の支援、マーケットインの発想に基づく輸出産地・事業者の育成・展開などです。
3つめは、「政府一体となった輸出の障害の克服」。輸出先国・地域における輸入規制の撤廃・緩和に向けて政府一体となった協議を実施するなどです。
また、戦略に基づき、輸出事業者を支援する「輸出支援プラットフォーム」も立ち上げました。輸出先国や地域の在外公館、JETRO海外事務所、JFOODO海外駐在員が主な構成員となり、現地から輸出事業者をサポートしています。現在、アメリカをはじめとする8か国・地域(14拠点)に設置されていますが、今後も市場として有望な国や地域に拡大することを検討しています。
日本の食材はどれくらい売られているの?
今回は、「輸出支援プラットフォーム」を担当する海外駐在員のお二人に、現地の輸出事情を教えてもらいました。
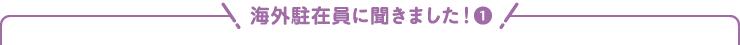
広大なアメリカは食の嗜好も様々!
日本食の浸透で輸出拡大をめざす

日本貿易振興機構(JETRO)
ロサンゼルス事務所
木村恒太さん
アメリカの在ロサンゼルス総領事館で食産業担当官を3年間勤め、2022年8月に日本貿易振興機構ロサンゼルス事務所に着任。アメリカへの輸出拡大に取り組んでいる。
右肩上がりに増える日本食レストラン
私が所属する日本貿易振興機構ロサンゼルス事務所の管轄地域は、南カリフォルニア、アリゾナ、コロラド、ハワイ、ニューメキシコ、南ネバダ、ユタの7州。現在、私はロサンゼルスを拠点として、現地市場の動向、輸出に関わる規制などの最新情報を発信し、日本の輸出事業者を支援する活動を行っています。そのほか、輸出事業者に向けてのセミナー開催や、食品見本市における日本ブース出展といった活動も、力を入れている取り組みです。アメリカで開催される食品見本市は、たとえばシーフードや健康食品のようにジャンル別に分かれており、プラットフォーム事業としては2023年度、60ブースの出展を企画しています。その先に見据えているのは、日本食のニーズの高まりです。ロサンゼルスだけでも、日本食レストランの数は右肩上がりに増えており、外食を通じて日本食が浸透することで、家庭でも日本の食材が求められるようになるのではないかと考えています。

ロサンゼルスで開催されたある見本市では、木村さんが自ら抹茶を点て、来場者に茶道の魅力を伝えた。抹茶は近年、需要が増している食材のひとつ。
アニメや漫画を通じて広まる日本食
アメリカは広いので、カリフォルニア州だけで日本全土の面積を超えるほど。さらには、地域性も人種も多様なため、食の嗜好もさまざまで傾向がつかみにくいのが難点です。そんな実情はありますが、最近は意外な食べ物が注目されています。ロサンゼルスでは、日本食といえば“すし”と“ラーメン”が人気ですが、最近はそこに“おにぎり”が加わるようになりました。また、清涼飲料水の“ラムネ”も人気があります。いずれも、日本のアニメや漫画といったコンテンツ文化の影響のようです。ちなみに、日本産の米は“Sushi Rice(スシライス)”として売られており、商品名やパッケージで用途をはっきり伝える工夫も欠かせません。米はアメリカでもつくっていますが、日本食人気による需要拡大や、気候変動により生産量の乱高下が起きています。中長期的な視点では、さらに日本からの輸出量が増えるのではないかと見込んでいます。
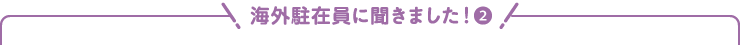
台湾では日本のフルーツが大人気!
輸出拡大のカギは地方都市

公益財団法人 日本台湾交流協会台北事務所
野田広宣さん
農林水産省輸出・国際局国際地域課にて国際業務を担当するかたわら、省内のSNS発信プロジェクトで“国家公務員YouTuber”として活躍。2023年5月、(公財)日本台湾交流協会に着任。
現地の人々と共同でイベントを開催
台湾における私の主な仕事はまず、オールジャパンでの日本産食材のPRです。特に、これまで台湾の消費者向けのイベントを行ってきました。台湾で人気がある日本産食材はなんといっても、フルーツです。昨年の夏は台湾農業部、中華文化総会との共催で、青果物PRイベント「日台フルーツ夏祭り」を開催しました。台湾総統府前の大通りに日本と台湾双方のフルーツをPRするブースが軒を連ね、とても盛り上がりました。ステージでは日本の青果物の生産に携わる方のトークイベントも行い、日本産青果物のおいしさや食べ方、産地の魅力をPRしました。どのフルーツも大人気でしたが、なかでも、日本の桃への反響が大きかったです。会場では、2022年2月に日本から台湾への輸出が解禁されてから初めて輸出された福島県産の桃の試食提供も行われ、多くの来場者が並んでいたのが印象的でした。
一方で、現在は日本産食材のPRイベントも台北に集中しているので、今後は台中や台南といった他の地方都市でも日本産食材の魅力を伝える機会を増やしていくことで、輸出拡大につなげたいと考えています。

台湾総統府前で開催された「日台フルーツ夏祭り」。会場には台湾の蔡英文総統(当時)も来訪した。

「台湾美食展2023」には9万人以上が来場。日本産食材の魅力をPRするステージで、野田さん(写真右)は中国語でも自己紹介。
日本産食材のイメージは“高品質”
台湾における日本産食材の市場動向や輸入規制についての情報発信も大切なミッションの1つです。台湾の生の情報を学ぶため、実際に現地で日本産食材に携わる方々の声を直接聞くことを何より大切にしています。台湾の人々が日本産食材に抱いているイメージを聞いてみると、やはり高品質という印象が強いです。自分へのご褒美として購入したりする人も多くいますが、台湾では旧正月などでの贈答文化が浸透しており、イベントでも人気の高かった日本のフルーツは、贈答用の品物として人気があります。
台湾に来て意外だったのは、日本の皆さんが思っている以上に、台湾では外食文化が浸透しており、家で手間のかかる料理をする人はあまり多くないということです。レストランに行ったり、惣菜やお弁当を買って食べたりする機会の方が多いという人も、よく見られるようです。今後は消費者のみならず、外食等へのPRにも力を入れていきたいと思います。現地の食文化もしっかり理解した上で、輸出促進に取り組んでいきたいですね。

台湾で人気の高い冬の果物といえば、日本のりんご。りんごはシーズンになると台湾ローカルのスーパーにも多く並ぶ。

台湾では外食店が数多くあり、人々にとって身近な存在となっている。トレンドに敏感な台北では、北海道名物のスープカレーを提供する店も登場。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449










日系のスーパーマーケットで、最近人気が高まっているのはなんとラムネ!
根強い人気のすしに加えて、おにぎりも人気上昇中。日本食の浸透と共に、日本産米の需要も増える可能性は高い。