第8節 多面的機能に関する国民の理解の促進
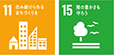
農村では高齢化や人口減少が進行する中、地域の共同活動や農業生産活動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。国民の大切な財産である多面的機能が適切に発揮されるよう地域の共同活動や農業生産活動の継続とともに、国民の理解の促進を図っていくことが重要となっています。
本節では、多面的機能の発揮や国民の理解の促進のための取組について紹介します。
(1)多面的機能の発揮の促進
(農業・農村には多面的機能が存在)
国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承、癒しや安らぎをもたらす機能等、農村で農業生産活動が行われることにより生まれる様々な機能を「農業・農村の多面的機能」と言います。多面的機能の効果は、農村の住民だけでなく国民の大切な財産であり、これを維持・発揮させるためにも農業生産活動の継続に加えて、共同活動により地域資源の保全を図ることが重要です(図表3-8-1)。

(多面的機能支払制度の認定農用地面積は前年度に比べ増加)
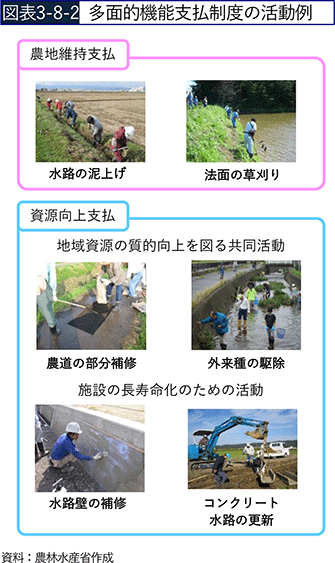
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、日本型直接支払制度が実施されています。
同制度は、多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度(*1)、環境保全型農業直接支払制度(*2)の三つから構成されています。
このうち、多面的機能支払制度は、多面的機能を支える共同活動を支援する農地維持支払と地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する資源向上支払の二つから構成されています(図表3-8-2)。令和3(2021)年度の多面的機能支払制度の活動組織数は前年度に比べ25組織増加し2万6,258組織、認定農用地面積は前年度に比べ2万ha増加し約231万haとなりました(図表3-8-3)。また、活動組織のうち広域活動組織(*3)については、前年度に比べ19組織増加し1,010組織となっています。
令和4(2022)年度から、資源向上支払の対象となる多面的機能の増進を図る広報活動に、地域外からの呼び込みによる農的関係人口の拡大のための活動を追加しました。
農地周辺の水路等の地域資源の保全管理については、小規模経営体を含む多数の農業者の共同活動により行われてきましたが、社会構造の変化に伴い、農業生産活動が少数の大規模経営体に集中し、地域資源の保全活動への参加者が減少しています。
このような中、農林水産省が令和4(2022)年10月に公表した「多面的機能支払交付金の中間評価」では、本交付金の取組を契機として非農業者も含め再び集落全体で地域資源の保全管理活動を支える必要が生じているとする一方、本交付金の効果については、約8割の対象組織が、農村環境保全活動は非農業者や非農業団体が本交付金の活動やその他の地域活動に参加するきっかけとして「かなり役立っている」又は「役立っている」と回答しています。また、本交付金のカバー率が高い市町村では、集落内の寄り合いの開催回数が多い集落の割合が高い傾向が見られ、集落の活動が活性化していると考えられます(図表3-8-4)。さらに、本交付金のカバー率が高い市町村ほど経営耕地面積の減少割合が低く、農地利用集積割合が高くなっています(図表3-8-5、図表3-8-6)。
このことから、本交付金は地域資源の適切な保全管理等に寄与していること、担い手への農地集積といった構造改革の後押しとして地域農業に貢献していることが評価されています。
1 第3章第3節を参照
2 第2章第9節を参照
3 旧市区町村区域等の広域エリアにおいて複数の集落又は活動組織及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立される組織。単独で地域資源の保全管理が難しい集落での活動の継続や、事務の効率化による組織の強化が期待される。
(2)多面的機能に関する国民の理解の促進等
(「農業の多面的機能」の認知度向上が課題)
令和3(2021)年6~8月に内閣府が行った世論調査によると、「農業の多面的機能」という言葉の認知度は約3割となっています (図表3-8-7)。
農業が有する国土保全・水源涵養(かんよう)・景観保全等の多面的機能について国民の理解を促進するため、農林水産省は、これらの機能を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、令和4(2022)年度は、学校や地方公共団体等に約3万部配布するなど、普及・啓発に取り組んでいます。
(「ディスカバー農山漁村の宝」に33団体と4名を選定)
「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向け、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定し、全国に発信する取組により、農山漁村地域の活性化等に対する国民の理解の促進や、優良事例の他地域への横展開を図るとともに、地域リーダーのネットワークの強化を推進しています。第9回選定となる令和4(2022)年度は全国から33団体と4名を選定し、選定数は累計で286件となりました。選定を機に更なる地域の活性化や所得向上が期待されています。

農福連携によるシルク分別作業の様子
(「ディスカバー農山漁村の宝(第9回選定)」のグランプリ受賞)
資料:沖縄県(株式会社沖縄UKAMI養蚕)

ディスカバー農山漁村の宝
URL:https://www.discovermuranotakara.com(外部リンク)
(世界かんがい施設遺産に新たに3施設が登録)
世界かんがい施設遺産は、歴史的・社会的・技術的価値を有し、かんがい農業の画期的な発展や食料増産に貢献してきたかんがい施設をICID(国際かんがい排水委員会)が認定・登録する制度であり、令和4(2022)年10月に、新たに香貫用水(かぬきようすい)(静岡県沼津市(ぬまづし))、寺谷用水(てらだにようすい)(静岡県磐田市(いわたし))及び井川用水(ゆかわようすい)(大阪府泉佐野市(いずみさのし))の3施設が登録され、国内登録施設数は47施設となりました。

香貫用水(静岡県沼津市)

寺谷用水(静岡県磐田市)

井川用水(大阪府泉佐野市)

世界かんがい施設遺産
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/kaigai/ICID/his/his.html
(世界農業遺産及び日本農業遺産に新たに各2地域が認定)
世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業システムをFAO(国際連合食糧農業機関)が認定する制度であり、令和4(2022)年7月に、新たに山梨県峡東(きょうとう)地域と滋賀県琵琶湖(びわこ)地域の2地域が認定され、国内の認定地域は13地域となりました(図表3-8-8)。
くわえて、世界農業遺産の制度が平成14(2002)年に設立されて20周年となることから、令和4(2022)年10月に、FAO本部(ローマ)において世界農業遺産20周年記念イベントが開催され、世界農業遺産認定地域における経験の紹介や課題解決策について議論が行われました。
また、日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林水産大臣が認定する制度であり、令和5(2023)年1月に、新たに岩手県束稲(たばしね)山麓地域と埼玉県比企(ひき)丘陵地域の2地域が認定され、認定地域は24地域となりました。

岩手県束稲山麓地域
資料:束稲山麓地域世界農業遺産
認定推進協議会
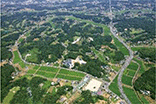
埼玉県比企丘陵地域

世界農業遺産・日本農業遺産
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/index.html
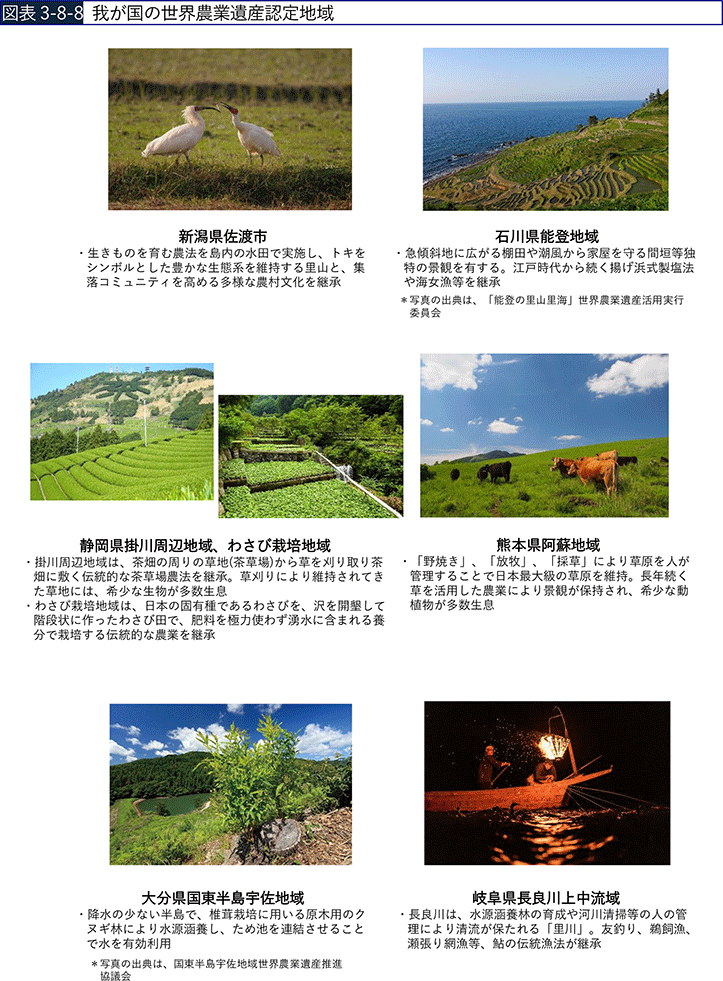

(3)農村におけるSDGsの達成に向けた取組の推進
(農村はSDGsの理念を構成する環境・経済・社会の三要素と密接に関連)
平成27(2015)年の国連サミット以降、SDGs(*1)への関心は世界的に高まっており、国内においても、SDGsに対する取組は官民を問わず着実に広がりを見せています。特に農村では、森林や土壌、水、大気等の豊富な自然環境、それを利用した農業等の経済活動、人々の暮らしを支える地域社会という、SDGsの理念を構成する環境・経済・社会の三要素が密接に関連しており、三要素の統合的向上を図りながら持続可能な地域づくりを進めていくことが重要です。
農林水産省では、農村におけるSDGsの達成に向け、農林水産物の地産地消(*2)や再生可能エネルギーを活用した農林漁業経営の改善等を進め、農山漁村の活性化に資する取組等を推進しています。
1 用語の解説(2)を参照
2 用語の解説(1)を参照
(農村において地域経済循環の形成等を目指す取組が広がり)
農村で環境調和型の農業生産活動等が推進されることは、生態系サービス(*1)の保全や、地域の魅力向上につながるものであり、みどり戦略(*2)の実現にも資するものです。また、食料やエネルギー等の地域の様々な資源が効率的に活用される地域経済循環の形成を目指すことは、地域の雇用と所得の向上だけでなく、「2050年カーボンニュートラル」の実現にも資するものであり、これらの取組はいずれもSDGsの実現に貢献するものです。
農村地域においては、環境調和型の農業生産活動や地域経済循環の形成を目指す先進的な取組も見られており、こうした取組が、全国各地で広がることが期待されています。
1 用語の解説(1)を参照
2 第2章第9節を参照
(事例)庄内スマート・テロワール構想に基づき循環型経済圏形成を推進(山形県)


休耕田の畑地化の実証試験
資料:庄内スマート・テロワール構築協議会
山形県の庄内(しょうない)地域では、食と農を地域の中で循環させ、持続可能な食料自給を目指す「庄内スマート・テロワール構想」に基づき循環型経済圏の形成に向けた取組が行われています。
山形大学や鶴岡市(つるおかし)、食品事業者、農業者等が参画している、庄内(しょうない)スマート・テロワール構築協議会(こうちくきょうぎかい)が中心となり、地域内の農業・畜産業・加工業が連携した循環型の生産等の取組を推進しています。
同協議会では、休耕田を畑地化し、小麦や大豆、飼料用とうもろこし等を輪作で栽培するとともに、その規格外品等を飼料として活用し畜産物を生産するなどの実証試験を行っています。また、生産した農畜産物を原料として地域内で加工食品を製造・販売し、地域内で生じる家畜排せつ物を堆肥化して農地に還元するといった一連の仕組みの効果検証も行っています。
さらに、同協議会は、実証試験で生産した小麦粉を用いたラーメンを同市内の学校給食で提供するとともに、下水処理水や汚泥コンポストを肥料として利用する取組との連携を図るなど、今後とも地域一体となって構想の実現を目指していくこととしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883









