第4節 食品産業の環境負荷低減と消費者の理解醸成の促進
持続可能な食料システムの構築のため、食料システムをつなぐ食品産業においても、持続可能な方法で生産された原材料を使用し、食品ロスを削減するなど、環境や人権に配慮した持続可能な産業に移行することが求められています。また、このような取組の重要性について消費者の理解を深め、環境や持続可能性に配慮した消費行動への変化を促していくことも重要です。
本節では、食品産業の環境負荷低減に向けた取組や、消費者への理解醸成を図る取組について紹介します。
(1)持続可能な食品産業への転換
(食品産業による持続可能性に配慮した取組を促進)
農業・食品産業については、温室効果ガスの排出削減や水質汚濁防止を始め、一層環境と調和のとれたものや、人権に配慮した調達・生産・加工・流通に転換していく方向が国際的にも主流化しています。また、環境に限らず農林水産物の生産現場における強制労働や児童労働といった人権への配慮等を求める声も高まりつつあり、EUでは、環境や人権に関する取組状況の開示やデューディリジェンスを求める指令が発効され、EUで企業活動を展開する日系企業も条件を満たせば同指令の適用対象となります。
このような中、持続可能な食料システムの構築のため、食料システムをつなぐ食品産業においても、持続可能な方法で生産された原材料を使用し、食品ロスを削減する取組を始めとして、環境や人権に配慮した持続可能な食品産業に転換することが求められています。
農林水産省では、食品産業の持続可能性の向上に向けて、国産原材料の利用促進、環境や人権に配慮した原材料調達等を支援することとしています。また、農林水産物を活用する新たなビジネス創出の仕組みの構築等により、地域の食品産業の関係者が連携して行う取組を支援することとしています。
(コラム)進みつつある誰もが利用しやすい飲食店の環境づくり
令和6(2024)年4月に改正障害者差別解消法(*)が施行され、障害のある人からの申出に応じて「合理的配慮の提供」を行うことが求められるようになりました。これを受け、外食産業においても、高齢者や障害者等が手軽に飲食店を利用できる環境づくり(インクルーシブ対応)が進むことが期待されます。
岐阜県岐阜市(ぎふし)の病院が運営するカフェでは、嚥下(えんげ)障害(食べ物や飲み物がうまく飲み込めない状態)がある人も一緒に食事ができるメニューとして、嚥下調整食が提供されています。とろみをつけて飲み込みやすくする飲み物や、細かく切り分けて口腔内で簡単にすりつぶすことができる料理・デザート等が提供されているほか、すくいやすいスプーンを常備するなど、必要に応じて食べやすく、持ちやすい食器の提供も行われています。
同店では、地域の飲食店等に嚥下調整食を広める活動や介護予防教室、地域の大学等とのマルシェの共催といった地域に根ざしたコミュニケーション活動を展開しており、今後、同市内の複数の飲食店のほか、他業種とも連携し、嚥下調整食の開発と普及を目指しています。
* 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」

カフェで提供されている嚥下調整食

店内の様子
資料:医療法人社団登豊会 近石病院
(持続可能性に配慮した輸入原材料調達を促進)
世界的なSDGsの取組が加速し、輸入原材料に係る持続可能な国際認証等が欧米の食品企業を中心に拡大する中で、食品企業が原材料を調達する際には、生産現場の環境・人権に配慮することが世界的に必要とされています。
国内においては、上場食品企業のうち「持続可能性に配慮した輸入原材料調達」に関する取組を実施している企業の割合は、令和5(2023)年は41.6%となっています。
食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料の調達については、短期的には直接的な売上向上につながりにくく、コスト増加等の企業負担が増えるなどの課題が見られることから、農林水産省では、食品企業が持続可能性に配慮した原材料調達に取り組むための入門書や、食品企業による人権尊重の取組を支援するための手引き等を作成しているほか、セミナーの実施や優良事例の横展開の促進等による業界支援、消費者理解の促進を図っています。
(2)ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立
(品質・鮮度保持のための包装資材・保管技術の開発を促進)
青果物や食品の品質や鮮度を保持するためには、収穫後、集出荷・貯蔵、輸送を経て、消費者に届くまでの各段階において、温度や水分、ガスの管理、そして、輸送時の傷み防止のための振動や衝撃の緩和が重要になります。青果物の予冷や低温物流、水分の調節や熟成・劣化を抑える資材、輸送時の傷みを防止するための振動や衝撃を緩和する包装資材や保管技術等の品質や鮮度保持のための開発が進んでいます。

衝撃を緩和したいちごの包材
資料:大石産業株式会社
このような品質・鮮度保持の取組が進むことで、これまで輸送が難しかった、海外への展開も進んでいます。
(農業・食品産業分野におけるプラスチックごみ問題への対応を推進)

プラスチックごみ対策のため
紙包材を採用した製品
資料:株式会社ブルボン
近年、国内外でプラスチックの持続的な利用が課題となっている中、農業・食品産業分野においても、多くのプラスチック製品を活用していることから、プラスチックごみ問題に積極的に対応していく必要があります。
農林水産省では、令和4(2022)年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法(*1)等に基づき、農業・食品産業分野における各企業・団体の自主的な取組を促進するとともに、それらの取組の発信を通じて国民一人一人の意識を高めていくこととしています。
*1 正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
(3)食品ロスの削減、リサイクルの推進
(国内では食品ロスの発生量は減少傾向)

データ(エクセル:27KB)
我が国の食品ロスの発生量については、令和4(2022)年度は前年度に比べ51万t減少し、過去最少の472万tと推計されています(図表5-4-1)。このうち、食品産業における発生(事業系食品ロス)は前年度に比べ43万t減少し236万tとなり、平成12(2000)年度比で令和12(2030)年度までに半減させる目標を達成しました。その要因としては、新型コロナウイルス感染症の影響による市場の縮小等の影響があるものの、納品期限の緩和や賞味期限表示の大括り化といった商慣習の見直し等のサプライチェーン全体で連携した取組や、小売店舗が消費者に対して、商品棚の手前にある商品を選ぶ「てまえどり」の促進等の消費者への呼び掛けといった食品企業の努力が相当程度貢献していると考えられます。一般家庭における発生(家庭系食品ロス)は前年度に比べ8万t減少し236万tとなっています。世界では、UNEP(*1)(国連環境計画)が令和4(2022)年に調査した報告書によると家庭レベルで1日当たり10億食を廃棄していると推計されています。
*1 United Nations Environment Programmeの略
(食品リサイクル法に基づく新たな基本方針を策定)
平成12(2000)年度比で令和12(2030)年度までに60%削減とする新たな事業系食品ロスの削減目標や、国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等の様々な事業者が連携してサプライチェーン全体で発生抑制やリサイクルの取組を更に拡大する方策を定めた、食品リサイクル法(*1)に基づく新たな基本方針の策定を令和7(2025)年3月に行いました。
*1 正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
(事業系食品ロスの削減に向け、納品期限緩和等の商慣習の見直しを推進)

「食の環(わ)」プロジェクト
ロゴマーク
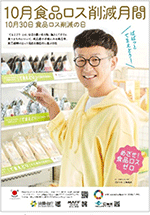
食品ロス削減月間を
呼び掛けるポスター
農林水産省では、新たな事業系食品ロスの削減目標達成に向けて、引き続き事業系食品ロスの削減に向けた取組を推進しています。
令和6(2024)年度においては、同年6月に、関係府省庁において、「食品ロス削減」や「食品寄附促進」に加え、「食品アクセスの確保」に向けた取組を、関係府省庁や地方公共団体が一体的に取り組めるように、3つの施策を包括する概念を「食の環(わ)」と呼ぶことについて申合せをし、共通のロゴマークを使用して、ワンボイスで発信していくこととしました。また、毎年10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日(*1)」と定め、食品小売事業者が賞味期間の3分の1を経過した商品の納品を受け付けない「3分の1ルール」の緩和や、食品製造事業者における賞味期限表示の大括り化(年月表示、日まとめ表示)の取組を呼び掛けました。納品期限の緩和に取り組む事業者は、同年10月時点で339事業者に拡大しています。また、行政・食品業界・消費者で協調して食品ロス削減の取組を更に推進することを目的に設置した「食品廃棄物等の発生抑制に向けた取組の情報連絡会」を同年4月、11月及び令和7(2025)年3月に開催し、政府における施策の検討状況のほか、食品企業の取組として、食品寄附に係る税務上の取扱いや食品ロス削減等の取組に係る情報開示の事例、外食における食べ残しの持ち帰り促進に向けた取組等について情報共有等を図りました。
食品企業における未利用食品のフードバンク等への寄附促進につながる供給体制の構築に向けた検討・実証の推進のほか、食品ロス削減効果が更に期待される取組として、AI等を活用した需要予測の高度化や、外食産業における食べ残しの発生抑制に向けた実証等に対する支援を行っています。
消費者への啓発については、食品ロス削減推進アンバサダーを起用した啓発ポスターの作成のほか、同年10月の食品ロス削減月間において「てまえどり」や、食べきりの推進について、消費者啓発に取り組む55の小売・外食事業者及び43の地方公共団体とともに呼び掛けを行っています。
さらに、国の災害用備蓄食品について、食品ロス削減や生活困窮者支援等の観点から有効に活用するため、農林水産省では「国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト」を設置し、災害用備蓄食品の更新により役割を終えたものについて、原則としてフードバンク団体等に提供しています。
*1 令和元(2019)年10月に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」において、10月が「食品ロス削減月間」、10月30日が「食品ロス削減の日」と定められている。
(食品リサイクルの取組を推進)
農林水産省では環境省とともに、2050年ネット・ゼロ(*1)の実現に向けて、CO2排出量削減の観点から、食品の売れ残りや食べ残しのほか、食品の製造過程において発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品リサイクルの取組を促進しています。
*1 第5章第2節を参照
(コラム)食品廃棄物の発生抑制、リサイクルの取組が拡大
(1)製造過程で発生する未利用資源の有効活用による食品廃棄物の発生抑制
埼玉県さいたま市(し)のコープデリ生活協同組合連合会では、東京都調布市(ちょうふし)のデリア食品(しょくひん)株式会社と共同で、パッケージサラダの製造過程で発生するキャベツの芯を活用したスープ等を開発しました。キャベツの芯は、キャベツ全体の重量の10%を占め、その有効活用が課題になっていました。キャベツの芯には、葉の部分に比べ甘み成分や繊維質が多く含まれており、加熱によって甘みが引き出されることから、スープのような加熱調理する製法の商品に適しており、素材の特性を生かし、資源を有効活用する取組につなげています。
(2)家庭から発生する食品残さを肥料や飼料としてリサイクル
長崎県諫早市(いさはやし)の長崎県立諫早農業(いさはやのうぎょう)高等学校では、家庭から発生する食品残さから作られた肥料を、栽培試験等を通じて、化成肥料と同等の収量が得られることを明らかにし、家庭から発生する食品廃棄物の有効活用につなげています。同校では、市民講座での研修会や地域のこども園等での食育教室を実施するなど、生産された肥料を地域内外の生産者等への普及を進めています。また、この取組は令和5(2023)年度に実施された第11回「食品産業もったいない大賞」において農林水産大臣賞を受賞しています。
食品廃棄物の発生抑制やリサイクルを通じて、新たな商品やサービスの展開が広がっています。
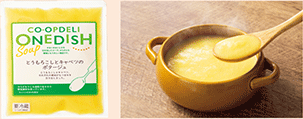
キャベツの芯を活用したスープ
資料:コープデリ生活協同組合連合会

諫早農業高校で生産された
肥料を利用する生産者
資料:長崎県立諫早農業高等学校
(4)消費者の環境や持続可能性への理解醸成
(サステナビリティやフェアトレードの認知度は向上)

データ(エクセル:27KB)
農産物の購入時に、環境に配慮した方法で栽培された農産物かどうか気にかけるかについて、公庫が令和7(2025)年1月に実施した調査によると、42.1%の人が「気にかけている」と回答しました(図表5-4-2)。
サステナビリティ、フェアトレード、エシカル消費(*1)(倫理的消費)といった言葉の認知度については、令和6(2024)年度は令和元(2019)年度と比較して約2~4倍に高まってきています(図表5-4-3)。
また、公庫が令和7(2025)年1月に実施した調査によると、環境に配慮した方法で栽培された農産物の購入における価格許容度については、「割高でも環境に配慮した農産物を選ぶ」としている人が約6割になっています(図表5-4-4)。
近年では、産地と事業者が連携して、不揃いになった規格外農産物等を実店舗やECサイトで販売する取組も見られます。
将来にわたって持続可能なフードチェーンを維持していくためには、消費者が取り組むことができる行動や、持続可能性に配慮した食料生産はコストを要することを事業者が正しく消費者に伝達することを通じ、消費者の理解を醸成しながら、行動変容を促していくことが必要となっています。
*1 地域の活性化や雇用等も含む、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動
(食と農林水産業のサステナビリティを考える取組を推進)
みどり戦略の実現に向け、農林水産省、消費者庁、環境省の連携により、企業・団体が一体となって持続可能な生産・消費を促進する「あふの環(わ)2030プロジェクト∼食と農林水産業のサステナビリティを考える∼」を推進しており、令和7(2025)年3月末時点で農業者や食品製造事業者等210社・団体等が参画しています。
同プロジェクトでは、食と農林水産業のサステナビリティについて知ってもらうため、「サステナブルが“推し”になる」をテーマに「サステナウィーク2024」を開催し、環境に配慮した農産物の販売や、その消費に資する情報の発信を集中的に行いました。また、サステナブルな取組についての動画作品を表彰する「サステナアワード2024」を実施したほか、消費者庁・農林水産省の共催で日経(にっけい)SDGsフォーラム消費者共創(しょうひしゃきょうそう)シンポジウムを開催すること等により、持続可能な消費を推進しています。

あふの環2030プロジェクト
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/
being_sustainable/sustainable2030.html

サステナアワード2024 農林水産大臣賞受賞作品
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






