第3節 農業生産活動における環境負荷低減の促進
みどり戦略においては、農業生産活動における環境負荷低減の促進のため、化学肥料・化学農薬の使用低減や、有機農業の取組拡大を推進しています。
本節では、化学肥料・化学農薬の使用低減等に資する環境に優しい栽培技術を取り入れたグリーンな栽培体系への転換の取組や、有機農業の拡大に向けた取組状況について紹介します。
(1)化学肥料・化学農薬の使用低減の推進
(化学肥料の使用低減に向けた取組を推進)
窒素やりんは、作物の生育に不可欠な栄養素であり、化学肥料にも含まれる一方、過剰施肥等の不適切な使用が行われた場合には、水圏の富栄養化や温室効果ガスの排出等の原因となることから、その資源を適切に利用しつつ、収支バランスを健全に保つことが重要です。
我が国は、主な化学肥料の原料である尿素、りん安、塩化加里のほぼ全量を海外に依存しており、食料安全保障の観点からも化学肥料使用量の更なる低減を図ることが必要となっています。
農林水産省では、みどりの食料システム法(*1)に基づき化学肥料の使用量低減等に係る計画の認定を受けた生産者やその活動を支える事業者に対し、税制措置や融資の特例等の支援措置を講じているほか、有機物の施肥による土づくり、土壌診断や施肥設計に基づく適正施肥、局所施肥技術の導入等の取組を促進しています。このような取組により、令和4(2022)年の化学肥料使用量は、81万t(NPK総量(*2)・生産数量ベース)で、基準年である平成28(2016)年比で約11%の低減となっています。
*1 第5章第1節を参照
*2 肥料の三大成分である窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)の全体での出荷量のこと
(化学農薬の使用による環境負荷の低減に向けた取組を推進)
環境負荷低減のためには、化学農薬を使用しない有機農業の拡大や、化学農薬のみに依存しない、病害虫等の予防・予察に重点を置いた総合防除等を推進し、化学農薬の使用低減を図ることも必要です。
令和5(2023)農薬年度(*1)の化学農薬使用量(リスク換算)は、令和元(2019)農薬年度比で約15.0%の低減となりました。みどり戦略に位置付けられている令和12(2030)年目標を達成しているものの、リスクの低い農薬への切替などの取組の効果だけでなく、資材費上昇による農薬の買控え傾向も寄与したと考えられることから、引き続き対策を進めていく必要があります。
農林水産省では、みどりの食料システム法に基づき化学農薬の使用低減等に係る計画の認定を受けた生産者やその活動を支える事業者に対し、税制措置や融資の特例等の支援措置を講じているほか、化学農薬のみに依存せず、病害虫等の予防・予察に重点を置いた総合防除等を推進するため、産地に適した技術の検証、栽培マニュアルの策定等の取組を支援しています。
*1 農薬年度は、前年10月から当年9月までの期間
(事例)特産品であるピーマンにおける環境負荷低減の生産体制を実現(沖縄県)
(1)安全・安心な「ぐしちゃんピーマン」の生産

沖縄県八重瀬町(やえせちょう)の沖縄県農業協同組合具志頭(ぐしかみ)支店野菜生産部会は、特産品である「ぐしちゃんピーマン」の生産に当たって、環境に優しい持続可能な生産体制を実現することで、「安全・安心」をキーワードに出荷量の拡大や若手農業者等の確保につなげています。
(2)生産者全員がみどり認定へ
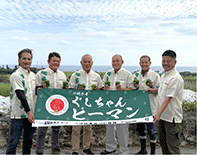
ぐしちゃんピーマンの生産者
資料:沖縄県農業協同組合
ぐしちゃんピーマンは同町具志頭(ぐしかみ)地区で生産される「ちぐさ」という品種のピーマンの商品名で、大玉肉厚でみずみずしく光沢があり、苦みが少なく食味が良いという優れた品種特性を持っていますが、品質と収量を共に向上させることが難しい品種です。
同部会では、地下ダム等からの十分な保水等に加え、土の太陽熱消毒や緑肥作物栽培による病原菌等の抑制、有機物入り肥料の施用と土壌分析に基づく肥料施用といった環境に配慮した独自の土づくりを行うことで、品質と生産量の向上に取り組んできました。また、農薬散布労力や資材費削減を目的にピーマンの害虫に対する天敵の導入にも取り組んでおり、令和5(2023)年8月には、同部会のピーマン専門部長が沖縄県内初となるみどり認定(*1)を取得し、その後、同部会員のみどり認定への切り替えが進んでいます。
(3)地域で一体となった環境負荷低減の取組が若手農業者等の育成やGI登録にもつながる
同部会では、環境負荷低減の栽培技術の共有や講習会等にも取り組んでいます。このような取組が功を奏して、若手の新規就農者や後継者が育ち、生産者の平均年齢は40歳代となり、出荷量も増加する好循環が生まれています。また、令和6(2024)年1月には、さとうきび残さ等の地域資源を活かした土づくりなど、栽培の難しい品種の特性を最大限に引き出す独自の生産技術を確立することにより、差別化されたピーマンを生産し、地域農業を牽引(けんいん)していることが評価され、地理的表示(GI(*2))に登録されました。同部会では、今後とも安全・安心なピーマンの生産と更なる認知向上による差別化・高付加価値化に取り組むこととしています。
*1 第5章第1節を参照
*2 Geographical Indicationの略
(グリーンな栽培体系への転換を推進)

鶏ふん堆肥の活用
資料:世羅町循環型農業推進協議会
化学肥料・化学農薬の使用低減、有機農業面積の拡大を推進するため、堆肥、緑肥等の活用、自動抑草ロボットによる雑草防除等の産地に適した環境に優しい栽培技術と省力化に資する技術を取り入れたグリーンな栽培体系への転換を図ることが求められています。
このため、農林水産省では、みどりの食料システム戦略推進交付金等により、化学肥料・化学農薬の使用低減、有機農業の推進、温室効果ガスの排出量削減等の環境負荷低減やこれに必要なスマート農業機械等の導入に取り組む水稲や野菜等の産地を創出することとしています。
令和6(2024)年度においても、産地に新たに取り入れる技術の検証や、グリーンな栽培体系の実践に向けた栽培マニュアルの作成等を支援しました。
(2)有機農業の推進
(世界の有機農業の取組面積は拡大傾向で推移)
世界の有機農業の取組面積については、令和5(2023)年は9,887万haとなっており、過去15年間で約2.9倍に拡大しています(図表5-3-1)。また、国別の1人当たり年間有機食品消費額は、スイスを始め欧州諸国で高い傾向にあります(図表5-3-2)。一方、我が国は欧米諸国と比較して低位な水準にあり、生産、消費両面での取組が必要となっています。
(我が国の有機農業の取組面積は拡大のペースが加速)
我が国では、「有機農業の推進に関する法律」(以下「有機農業推進法」という。)において、「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業と定義されています。
輸入依存度の高い化学肥料を使用しない有機農業は、生物多様性の保全や地球温暖化防止等に加えて、国際情勢に左右されにくい農業生産体制の確立に資するものとして、我が国でも推進されています。

データ(エクセル:26KB)
我が国の有機農業の取組面積については、近年、漸増傾向でしたが、令和3(2021)年度のみどり戦略の策定等を受け、令和4(2022)年度は前年度に比べ3,700ha(14%)増加と大きく拡大して3万300haとなっており、その耕地面積に占める割合は0.7%となりました(図表5-3-3)。
農林水産省では、有機農業の拡大に向けた現場の取組を推進するため、地域ぐるみでの有機農業の取組や、広域的に有機農業の栽培技術を提供する民間団体の指導活動、農業者の技術習得支援等による人材育成、事業者と連携して行う需要喚起、有機加工食品原料の国産化等の取組を支援しています。
(事例)有機農産物の取組拡大を推進(熊本県)
(1)全圃場で有機栽培及び特別栽培を実践中

熊本県上天草市(かみあまくさし)の農事組合法人大矢野有機農産物供給(おおやのゆうきのうさんぶつきょうきゅう)センターでは、全生産圃場(ほじょう)60haで有機栽培及び特別栽培(化学合成農薬・化学肥料5割削減)を実施しており、このうち8.6haで有機JASを取得しています。また、かんきつのほか9品目以上の露地野菜を特別栽培で生産するなど、環境保全型農業に取り組んでいます。
(2)販路拡大に向けた品質向上のための取組や消費者との交流
販路を拡大していくため、同センターでは、生産者の有機JAS認証やGLOBALG.A.P.の認証取得に係る費用の助成を行っています。また、品質向上のため、生産者同士の目揃え会を実施し、糖度や酸の比率を測る光センサーを導入し、選果基準を統一しました。
大きな販売先である関東圏の生活協同組合と連携し、毎年会員向けに産地訪問会を実施すること等により、消費者との交流にも取り組んでいます。
(3)後継者の育成と今後の展開

かんきつの特別栽培に
取り組む生産者
資料:大矢野有機農産物供給センター
生産者の高齢化が進む中、後継者を確保し、育成していくことが課題です。新規就農を希望する者に対しては、経営スタイルを確立できるよう、同センターの職員として雇い、様々な品目の生産者の下で研修を受けられるような仕組みを構築しています。また、同センターは、集出荷が主な機能でしたが、農地を預けて生産を委託したいという高齢の生産者も出てきたことから、集出荷機能に加えて、生産機能を持つことを計画しており、ゆくゆくは自社農場を経営して生産基盤の安定につなげていく予定です。
(オーガニックビレッジの取組市町村が拡大)
市町村が主体となり、生産から消費まで一貫した取組により有機農業拡大に取り組むモデル産地である「オーガニックビレッジ」については、令和7(2025)年までに100市町村を創出することを目標としていましたが、同年3月末時点で目標を上回る131市町村において取組が開始されています。このうち京都府亀岡市(かめおかし)では、有機農業の取組拡大に向けて令和6(2024)年に「亀岡オーガニック農業スクール」を開校し、有機農業に関心を持つ農業者等に有機農業の経営や栽培技術の指導を行うなど、新たな担い手の確保を図る取組が進められています。
このほか、有機農業を活かして地域振興につなげている又はこれから取り組みたいと考える市町村や、都道府県、民間企業・民間団体の情報交換等の場を設けるための「有機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク」を設置し、地方公共団体間での有機農業の取組推進に関する情報共有等を促進しています。

亀岡オーガニック農業スクールの圃場
資料:亀岡オーガニック農業スクール

亀岡オーガニック農業スクールの授業
資料:亀岡オーガニック農業スクール
(我が国の有機食品市場は拡大傾向で推移)
我が国の有機食品の市場規模は拡大傾向で推移しており、令和4(2022)年11月に実施した調査によると、令和4(2022)年の市場規模は2,240億円と推計されており、平成29(2017)年の1,850億円と比べ約20%増加しています。
有機農業推進法制定10周年となる平成28(2016)年に、12月8日が「有機農業の日」と制定されました。農林水産省では、「有機農業の日」に合わせて、令和6(2024)年10月に農林水産省ウェブサイトに特設ページを開設するとともに、同年11月中旬から12月中旬にかけて特別期間を設け、地方公共団体や事業者に取組の呼び掛けを行い、学校給食での有機農産物の利用や、店舗やECサイトでの有機食品の販売促進、有機農業関連のイベントといった取組が各地で実施されました。
また、国産の有機食品の需要喚起に向け、事業者と連携して取り組むためのプラットフォームである「国産(こくさん)有機(ゆうき)サポーターズ」を立ち上げており、令和7(2025)年3月末時点で112社が参画しています。令和6(2024)年度は、国産有機サポーターズの事業者による「有機農業の日」特別期間中の販売促進や、NIPPON FOOD SHIFT FES.等のイベントにおけるマルシェの出店を通じ、消費者に対する有機食品の理解促進の取組を進めました。
さらに、グリーン購入法(*1)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7(2025)年1月閣議決定)において、食堂での有機農産物等の取扱いについて従来の配慮することが望ましい事項から、より積極的な活用を促す基準(*2)に改定されたことを受け、国等の食堂における有機農産物等の導入を推進しています。
このほか、令和5(2023)年4月に、生産・加工・流通等の事業者で構成される一般社団法人日本有機加工食品(にほんゆうきかこうしょくひん)コンソーシアムが設立され、有機加工食品(パン等)の更なる生産拡大に取り組むとともに、産地・実需間の需給調整の仕組みや国産有機原料の活用を発信する取組を試行的に導入するなど、国産有機農産物等に関わる新たな市場の創出に向けた取組も広がりを見せています。令和6(2024)年度は、有機野菜や有機米粉を活用した加工食品の商品開発を進めるとともに、加工食品原料としての活用が進まないとされている転換期間中有機農産物の活用促進に向けたキャンペーンを実施する等の取組を行っています。
*1 トピックス2を参照
*2 調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り調達を推進していく基準
(学校給食での有機農産物の活用の広がり)

データ(エクセル:26KB)
学校給食における有機農産物等の活用も広がりを見せ、令和5(2023)年度で278市区町村が学校給食で有機食品を利用しており、令和4(2022)年度から85市区町村増加しています(図表5-3-4)。
オーガニックビレッジの取組においては、北海道旭川市(あさひかわし)が、大阪府泉大津市(いずみおおつし)と農業分野での連携に関する協定を締結し、令和6(2024)年度に旭川市で生産された有機米が泉大津市に提供されました。
さらに、令和6(2024)年12月8日の「有機農業の日」に合わせ、東京都内の一部区立小中学校において、富山県南砺市(なんとし)や千葉県木更津市(きさらづし)、宮崎県高鍋町(たかなべちょう)で生産された有機農産物を使った「オーガニックビレッジ連携給食」が提供されるとともに、小学生に対し、有機農業の意義や食に対する意識を高める食農教育が実施されました。このように、全国各地において、産地と消費地が連携した有機農業の推進の取組が行われています。
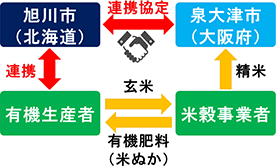
旭川市と泉大津市の連携の概要

オーガニックビレッジ連携給食
資料:東京都内の一部区立小中学校
(3)環境保全型農業直接支払制度の推進
(環境保全型農業直接支払制度の実施面積は前年度に比べ増加)
化学肥料・化学農薬の使用を原則5割以上低減する取組と併せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に対しては、環境保全型農業直接支払制度による支援を行っています。
令和5(2023)年度の実施面積は、前年度に比べ約4千ha増加し8万7千haとなりました(図表5-3-5)。また、支援対象取組別に見ると、全国共通の取組では、「堆肥の施用」が25.8%で最も多く、次いで「カバークロップ(*1)」、「有機農業」の順となっています(図表5-3-6)。
*1 土壌侵食の防止や有機物の供給等を目的として、主作物の休閑期等に栽培される作物
(環境保全型農業直接支払制度の評価)
環境保全型農業直接支払制度については、平成27(2015)年度から、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として実施されており、実施期間は5年間で、令和2(2020)年度から第2期が開始されています。
令和2(2020)年度から令和6(2024)年度までの施策の実施状況や評価について、令和6(2024)年8月に「環境保全型農業直接支払交付金最終評価」として公表しました。この中で、有機農業、カバークロップ等による地球温暖化防止効果について評価したところ、温室効果ガス削減量の合計は、年間で約17万t-CO2となりました(図表5-3-7)。これはスギ林193km2が1年間に吸収する量に相当します。また、生物多様性保全の効果については、「有機農業」、「IPM(*1)」、「冬期湛水(たんすい)管理」を対象に、指標生物スコアに基づく総合評価を行った結果、水稲では、どの取組も慣行栽培に比べ、生物多様性が向上していました(図表5-3-8)。
令和7(2025)年度から新たに始まる第3期では、有機農業の支援単価を引き上げるとともに、地域特認取組のうち全国的に拡大が見込める取組について、一層の推進を図る観点から全国共通取組へ移行することとしています。また、水田からのメタン排出が不必要に増えないよう、堆肥の投入量の見直しや、堆肥や緑肥等の取組の際に、長期中干しや秋耕(しゅうこう)等のメタン排出削減対策を併せて実施することとしています。
さらに、みどり戦略の目標の実現に向けて、令和9(2027)年度を目途に、更なる制度の見直しを検討することとしています。

データ(エクセル:33KB)

データ(エクセル:26KB)
*1 Integrated Pest Managementの略で、総合防除のこと
(4)土づくりや廃プラスチック対策の推進
(堆肥等の活用による土づくりを推進)
農地土壌は農業生産の基盤であり、農業生産の持続的な維持向上に向けて、土壌の物理性や化学性、生物性を堆肥や緑肥作物といった有機物の施用等により改善し、生産力を高める「土づくり」に取り組むことが必要です。
土づくりにおいて重要な資材である堆肥の施用量は、農業者の高齢化の進行や省力化の流れの中で、水田では長期的に減少を続け、近年は横ばい傾向で推移しています。
農林水産省では、農業現場での土づくりを推進するため、土壌診断とその結果を踏まえた堆肥等の施用を支援しています。また、土壌診断における簡便な処方箋サービスの創出を目指し、AIを活用した土壌診断技術の開発を推進しています。さらに、土づくりに有効な堆肥の施用を推進するとともに、好気性強制発酵(*1)による堆肥の高品質化やペレット化による広域流通等の取組を推進しています。
*1 攪拌装置等を用いて強制的に酸素を供給し、堆肥を発酵させる方法
(農業由来の廃プラスチックの適正処理対策を推進)
農業及び畜産業の生産現場では、農業用ハウスやマルチ等のプラスチック資材が使用されていることから、環境への負荷を低減するため、排出抑制や、使用後に適切に回収し、リサイクル等の適正処理を進めることが重要です。また、作物収穫後に土壌中にすき込むことで、土壌中の微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解され、使用後の廃プラスチック処理が不要となる生分解性マルチへの転換を図ることも重要です。プラスチックを使用した被覆肥料は、水田に散布すると作物の生育に応じて徐々に肥料成分が溶け出すことから、肥料の投入量低減や、農作業の省力化につながる一方、使用後の被膜殻が圃場から海洋に流出することによる環境への影響が懸念されています。
農業分野の廃プラスチックの再生処理(焼却に伴い発生する熱エネルギーの回収を含む。)の割合は70%台で推移しており、令和4(2022)年度では70.0%となっています(図表5-3-9)。また、農業用生分解性資材普及会(のうぎょうようせいぶんかいせいしざいふきゅうかい)の調査によると、生分解性マルチの年間利用量(樹脂の出荷量)は年々増加傾向で推移しており、令和5(2023)年度は3,657tとなっています(図表5-3-10)。
農林水産省では、生分解性マルチへの転換に向けた取組のほか、農業用ハウスの被覆資材やマルチといった農業由来の廃プラスチックの適正処理対策を推進していくこととしています。また、プラスチックを使用した被覆肥料については、圃場からの被膜殻の流出実態の調査を行い、その結果を公表するとともに、被膜殻の流出防止技術やプラスチックを使用しない代替肥料等に関する実証等の取組を支援し、これらの技術の普及を推進しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883











