未来の食卓はどうなるの?研究者にインタビュー

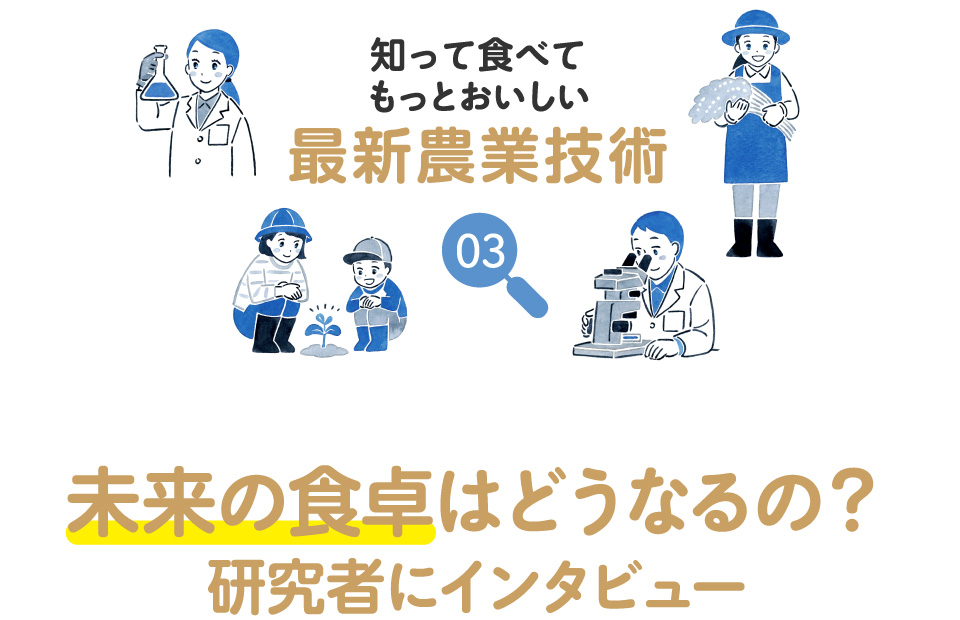

食の未来について、長谷川利拡さんに聞きました

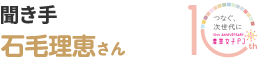
農業女子プロジェクトメンバー
2018年に千葉県で就農。2021年度に実施した「女性農業コミュニティリーダー塾」(農林水産省)に参加。ビーチクリーンなどの環境活動にも取り組む。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)
農業環境研究部門 エグゼクティブリサーチャー(博士(農学))
「農業女子プロジェクト」とは?
農業で活躍する女性の姿を多くの皆さまに知っていただくための取り組みです。女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培った知恵を様々な企業の技術・ノウハウ・アイデアなどと結びつけ、新たな商品やサービス・情報を社会に広く発信しています。

私は千葉県で主に大根を生産しています。今年の夏は猛暑に加えて雨が少なく、種まきに苦労しました。消費者としても不安を感じたのですが、温暖化は私たちの食卓にどのような影響を及ぼすのでしょうか。


私が関わった今回の IPCCの報告書(各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目的としたもの)は2014年から2021年の科学的論文の根拠をもとにしてまとめたもので、人為的起源の温暖化が食料の生産や調達に影響を及ぼしていることや、温暖化に適用する技術が普及し始めていることを盛り込みました。
温暖化の影響は一様ではなく、地域によって異なります。また、温暖化は単に生産だけに限らず、加工、貯蔵、流通といった食卓に至るまでの多くのプロセスに複合的、連鎖的に影響します。このような影響の仕組みを理解することは対策を立てる上で重要です。
食料の供給を維持していくうえで何より大事なのは温暖化の進行のスピードを抑えることですが、同時に進行を前提とした対策を考えていく必要があります。生産者がとれる対策として高温に強い品種を選ぶ、あるいは品目そのものを替えるという選択肢があり、すでに東北地方が北限とされていたサツマイモを北海道で栽培したり、関東地方でパッションフルーツなど亜熱帯産の果樹を手がけたりといった適応が始まっています。
温暖化の場合、地域や作物によっては
収量の増加につながるケースもあります。


私たちの主食である米についてはどのような研究が行われていますか。


私の専門は作物学で、大気中のCO2(二酸化炭素)濃度や気温の上昇がイネの生育や収量に及ぼす影響の予測に役立てるための栽培実験などに取り組んできました。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下、農研機構)での直近の研究として、28都道府県から新米のサンプルを集め、品種ごとの出来を調べています。2023年の夏は温暖化の影響を差し引いても特異な暑さだったとされます。このまれな暑さの影響を検証し、今後の温暖化対策につなげるための調査です。
農研機構では高温でも収量や品質が落ちないイネの品種の開発も進めています。また農業に起因する温暖化ガスも研究テーマです。生産、流通など食料に関わるシステムから発生する温暖化ガスは意外に多く、全体の3割強を占めるほどです。水田も発生源となります。貴重な生産基盤であるとともに大雨の際、「田んぼダム」として機能して周辺の浸水被害を軽減したり、熱い時期には辺りを涼しくしてくれたり、と優れた地域環境を生み出せる土地利用法なのですが、有機物が土壌で分解される際、水が溜まった状態だと炭素が酸化されにくく、温暖化ガスであるCH4(メタン)が発生してしまうのです。農研機構では、水を抜いて土を干す期間を延ばすことでどれだけ発生量を削減できるか調べているほか、水田から発生するメタンは主にイネを通って大気中に放出されることから、メタンが出にくい品種の開発も進めています。
2023年のまれな暑さを将来に備える機会として
調査を行っています。


農業で温暖化ガス対策としてどのようなことに取り組んでいくべきでしょうか。


土壌中の炭素を増やしたり、化学肥料や燃油を減らすような管理方法は温暖化防止に役立ちます。土壌は多量の炭素を蓄える能力があり、その機能を活用すると大気中のCO2(二酸化炭素)の減少につながります。また、窒素肥料は過剰に施用すると一酸化二窒素という強力な温室効果ガスの発生を増加させます。地力の維持は水管理と並び重要な基盤的技術です。これを活用することにより、温暖化防止だけでなく肥料の節約にもなります。ただし、これらがどの程度温暖化防止につながるかというのは目で見にくいのが問題です。そこで農研機構ではこうした管理によってどの程度温室効果ガスを削減できるかを数値化する研究を進めていますし、農林水産省では農産物のラベル表示する仕組みを作り、温室効果ガス削減の「見える化」を図っています。
気候変動の作物への影響は、作物の生育が早まることによる栽培暦の変化に最も早く現れます。これに適応するには、経験や勘だけに頼らず、データに基づいて変化を予測しつつ遅植えにするとか収穫時期を早めるなどの管理ができる体制を整えることが有効です。皆さんの農地における気象を知りたい場合は、「農研機構メッシュ農業気象データ」というシステムがあります。これには、日々の気温、降水量、日照時間など14種の気象要素を、全国1キロメートル四方で1980年から現在まで保存しています。また、26日先までの予報データも提供してます。
生産者を応援するため温室効果ガス削減の
「見える化」を図ります。


生産者が品目を変えずに地元の特産品を守っていくにはどのような取組が必要でしょうか。


なかなか個々の農家の取組だけでは対応が難しいように思います。2023年夏のような異常気象に対しても、効果があった方法を共有してノウハウとして積み上げることで産地の実力が上がることが期待されます。生産者だけでなく地域住民も交わるような情報交換の機会や場が増えれば、産地の応援団も増えると思います。農地は、景観や生物多様性にとっても地域の貴重な財産です。作り手と消費者が目に見える関係にあれば、食料の輸送距離を短くしたり、食品廃棄やロスを減らす行動にもつながり、結果的には温暖化防止にも役立ちます。生産者の皆さんには、このように各地域において人と環境の関わり方を考える機会をつくり、知恵や知識を共有し、行動を変容するきっかけとなる情報発信者としての役割を期待したいです。
地域全体の生産の実力を上げる取組が
大切だと考えています。

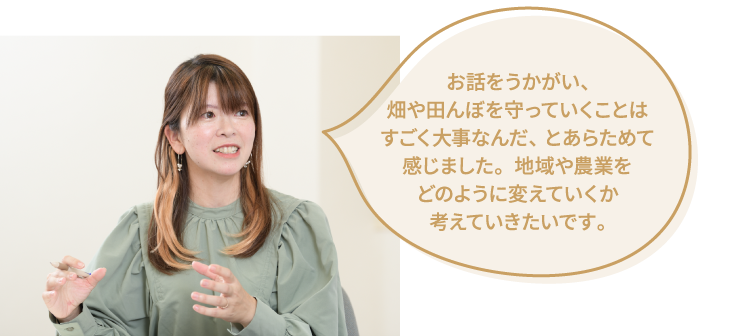
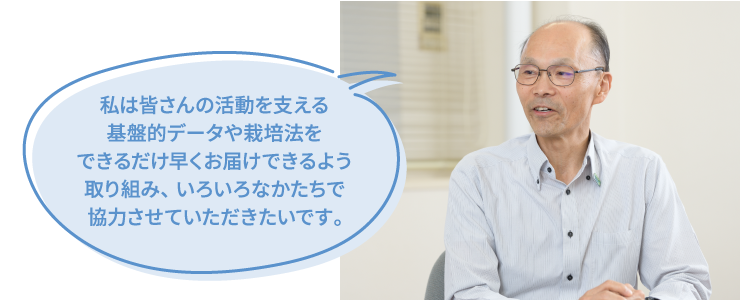
地球の未来のために
何を選びますか?
農林水産省では、持続可能な生産と消費を促進するため、2020年6月に「あふの環2030プロジェクト」を立ち上げました。本プロジェクトは、生産側と消費側それぞれの取組を促進し、互いに意識・行動を変えていくことで、新たな市場をつくることを目指しており、サステナウィークやサステナアワードなどを実施しています(農林水産省、消費者庁、環境省連携)。
本プロジェクトに賛同し、共に活動するメンバーとその事例を紹介します。
持続可能な生産・消費
を当たり前に
イオン九州(株)
イオン九州(株)では、九州で持続可能な生産・消費を当たり前にするため、従業員教育と地域のサステナブル商品の販路拡大が重要と考えています。そこで、各店の20歳代の若手社員でプロジェクトチームを作り、毎月1回オンラインで勉強会を実施しながら自社や他社の様々な取組を学ぶ機会を作っており、そこで習得した知識をもとにイベントの企画を行っています。地元のサステナブルな商品を集めたイベントでは、従業員やお客さまが学ぶだけでなく、出品者の方々もお客さまの声から学び、商品の育成に生かされました。
また、イオン九州と約60の企業・団体が循環型農業について学び、協働し、九州の農業を元気にする商品として、堆肥生産過程で重油の不要化などを実現した「九州力作野菜」と「九州力作果物」の生産に取り組んでいます。

イオン九州での「サステナウィーク2022」の様子。

温室効果ガス削減の
「見える化」に取り組む
(株)サンプラザ
農林水産省では、みどりの食料システム戦略に基づき、消費者の選択に資する環境負荷低減の「見える化」を進めています。化学肥料・化学農薬や化石燃料の使用削減、バイオ炭や堆肥の施用、水管理(水田)などの生産者の栽培情報を用いて、定量的に温室効果ガスの排出と吸収を算定し、削減率に応じて星の数で表したのが「見える化」ラベルです。
スーパーマーケット サンプラザでは、この「見える化」実証事業に2022年より取り組み、コメ、トマト、キュウリ、玉ねぎ、みかん、サツマイモ、大根などの多数の品目を「見える化」ラベルとともに販売しています。2023年9月に実施された「サステナウィーク2023」にも参加し、各店舗で「見える化」の取組を積極的に発信しました。

温室効果ガス削減の「見える化」ラベル。

スーパーマーケット サンプラザ店内の青果売場の様子。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449









