
第1回
夏に涼やか
「透明和菓子」
国産食材を使った、かわいくて初心者でも作りやすい和スイーツのレシピをプロに教えてもらう連載企画。今回のテーマは、暑い季節に涼を呼ぶ「透明和菓子」。涼やかな見た目、さっぱりとした口溶けは夏のおもてなしにもぴったりです。

レシピを教えてくれるのは…
和菓子教室「ももとせ」主宰 安田由佳子さん

貝印(株)でフードコーディネーターを務める傍ら、ケータリングユニット「Tont」を立ち上げ活動。和菓子家・金塚晴子氏に師事。2014年より東京・日本橋で和菓子教室「ももとせ」主宰。著書に『はじめての手づくり和菓子』(学研)、『透明和菓子の作り方』(文化出版局)など。海外での教室開催や茶席の菓子製作を通じて日本の食文化を伝えている。

夏果あんみつ

色と酸味を加えたアレンジあんみつ。
プルンとした寒天の食感がやみつきに
透明和菓子に欠かせない材料が、海藻由来の寒天。その弾力ある食感を存分に楽しめるメニューがあんみつです。半透明な寒天だけでなく、みかんジュースを加えた黄色い寒天も作って酸味と華やかさをプラス。仕上げにかける黒蜜にはバルサミコ酢を加え、ほんのり甘酸っぱい風味に。昔ながらのあんみつとはひと味違う新感覚のおいしさです。和食だけでなく洋食後のデザートにもぜひどうぞ。
材料(4人分)
| <寒天> | |
| 粉寒天 | 2グラム |
| 水 | 250ミリリットル |
| <みかん寒天> | |
| 粉寒天 | 2グラム |
| 水 | 60ミリリットル |
| グラニュー糖 | 40グラム |
| みかんジュース(市販品) | 150ミリリットル |
| <その他> | |
| 黒蜜(市販品) | 70ミリリットル |
| バルサミコ酢 | 小さじ1 |
| 好みの果物 | 適量 |
用意する器具
| 流し型(15×8×5センチメートル程度) | 2個 |
下準備
流し型は水で濡らしておく。
作り方
-
寒天を作る。鍋に水と粉寒天を入れてよく混ぜ、火にかける。粉寒天がダマにならないように混ぜながら沸騰させて煮溶かす。型に流し込み、常温で冷ます。

POINT
粉寒天は必ず沸騰させて煮溶かす。沸騰前に火を止めると固まりにくくなる。
-
みかん寒天を作る。鍋に水と粉寒天を入れてよく混ぜ、火にかける。粉寒天がダマにならないように混ぜながら沸騰させて煮溶かす。そこへグラニュー糖を加えて溶かす。

POINT
グラニュー糖は必ず粉寒天が溶けてから加える。溶ける前に入れると固まりにくくなる。
-
火を止め、粗熱が取れたら❷にみかんジュースを加え混ぜる。型に流し込み、常温で冷ます。

POINT
寒天は酸に弱い。固まりにくくなるので、みかんジュースは一緒に煮ず、火を止め、粗熱が取れてから加える。
-
黒蜜にバルサミコ酢を加え、よく混ぜる。

-
❶と❸が固まったら型から外し、好みの大きさに切って器に盛る。さらに果物を盛り、❹を添える。


金魚のレモン羹

金魚鉢を模した清涼感たっぷりのお菓子。
見て、食べて、季節を味わって
まるで澄んだ水の中を金魚が優雅に泳ぎ回っているよう。夏の風物詩である金魚は、季節感を表現するのにぴったりのモチーフ。こなし生地※に色を付け、抜き型で抜いて作ります。寒天の透明度が高いのは、グラニュー糖を多めに入れているから。寒天は砂糖の量が多いほど透明になります。最後にレモン汁を加えるので、仕上がりはあくまでさっぱり爽やか。ラップを敷いた型で固めるだけで、寒天のふちがアートのようにランダムなギザギザになります。
※白あんに粉を加え、蒸し上げた生地
材料(6個分)
| 粉寒天 | 2.5グラム |
| 水 | 200ミリリットル |
| グラニュー糖 | 130グラム |
| レモン汁(市販品) | 小さじ2弱 |
| こなし生地 | 適量 |
| <こなし生地> | |
| 白こしあん | 50グラム |
| 小麦粉 | 4グラム |
| 色粉(赤・緑) | 各少々 |
用意する器具
| セルクル型(4.5×3.5センチメートル) | 6個 |
| 金魚と丸(大・小)の抜き型 | 各1個 |
| 麺棒 | 1本 |
下準備
色粉はそれぞれ1から2滴の水(分量外)で溶いておく。
作り方
-
こなし生地を作る。耐熱ボウルに白こしあんと小麦粉を入れ、ゴムベラでよく混ぜる。

-
❶の耐熱ボウルにラップをかけ、600ワットの電子レンジで30秒加熱する。電子レンジから取り出して再び混ぜ、生地をラップに包んで冷ます。

-
❷を3等分し、水に溶かした色粉の赤を3分の1生地に、緑を3分の1生地に、それぞれヘラでつける。指や手のひらで生地を押しつぶしながら、全体にムラなく着色する。

-
❸の赤生地と緑生地をそれぞれオーブンペーパーにはさみ、麺棒で2ミリメートル厚に伸ばす。

-
❸で着色していない残り3分の1生地を3ミリメートル厚に伸ばす。そこに❹の赤生地の適量を水玉模様にのせ、麺棒でさらに2ミリメートル厚に伸ばす。金魚の抜き型で抜く。

POINT
・生地が固い場合は、水を少し加え、揉んで調整する。
・生地が抜き型から外れにくい場合は、細めの筆や麺棒を使って優しく落とす。
・抜き型がない場合は、手で形作ってもよい。 -
❹の赤生地を金魚の抜き型、緑生地を丸(大)の抜き型で抜く。抜いた緑生地はさらに丸(小)の抜き型で抜いて、水草を模したわっかにする。

-
寒天を作る。鍋に水と粉寒天を入れてよく混ぜ、火にかける。粉寒天がダマにならないように混ぜながら沸騰させて煮溶かす。そこへグラニュー糖を加えて溶かす。

-
❼をボウルに取り出す。粗熱が取れたらレモン汁を加え混ぜる。

-
各セルクル型にラップを敷き、それぞれに❽を大さじ2ずつ流し入れる。

POINT

セルクル型がない場合は、おちょこや同程度の大きさの器、空き容器などでも代用可能。
-
❾が少し固まってきたら、❺と❻の金魚と水草を好みの絵柄になるように入れる。

-
10の上に大さじ1から2の❽をそれぞれ流し入れる。

POINT
上下の寒天をくっつけて、金魚と水草が中間に浮いた感じにするには、下の寒天が完全に固まりきる前に、上の寒天を手早く流し入れること。
-
常温で冷まし固めてから冷蔵庫でさらに冷やす。ラップから外し、器に盛る。

安田さんの一押し!
和スイーツ店
一文字屋和輔(あぶり餅 一和)
【 京都府京都市北区 】

出来たてが命のあぶり餅を
千年続く門前茶屋で味わう至福

京都に行くたびに必ず訪ねるのが、今宮神社の東門参道沿いにある「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」、通称「あぶり餅 一和(いちわ)」さん。創業がなんと1000年以上前の平安時代という老舗中の老舗です。時代劇に出てくるような風情溢れる茶屋でいただけるメニューは「あぶり餅」のみ。親指大にちぎった餅を竹串に刺して、炭火であぶった昔ながらの和菓子です。香ばしく焼かれた餅に、白味噌仕立ての甘じょっぱいタレをからめて食べると、何ともいえず幸せな気持ちになります。持ち帰りではなく、出来たてをその場で味わうのが断然おすすめ。若い方にこそ知ってほしい逸品です。
所在地
京都府京都市北区紫野今宮町69
(今宮神社の東門前)
電話
075-492-6852
営業時間
10時00分~17時00分
定休日:水曜日(1日、15日、祝日が水曜日の場合は営業し、翌日休業)

aff公式 Instagramでは
暮らしに役立つ情報や
農林水産業の魅力をお届けしています。
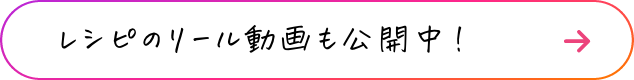
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449









