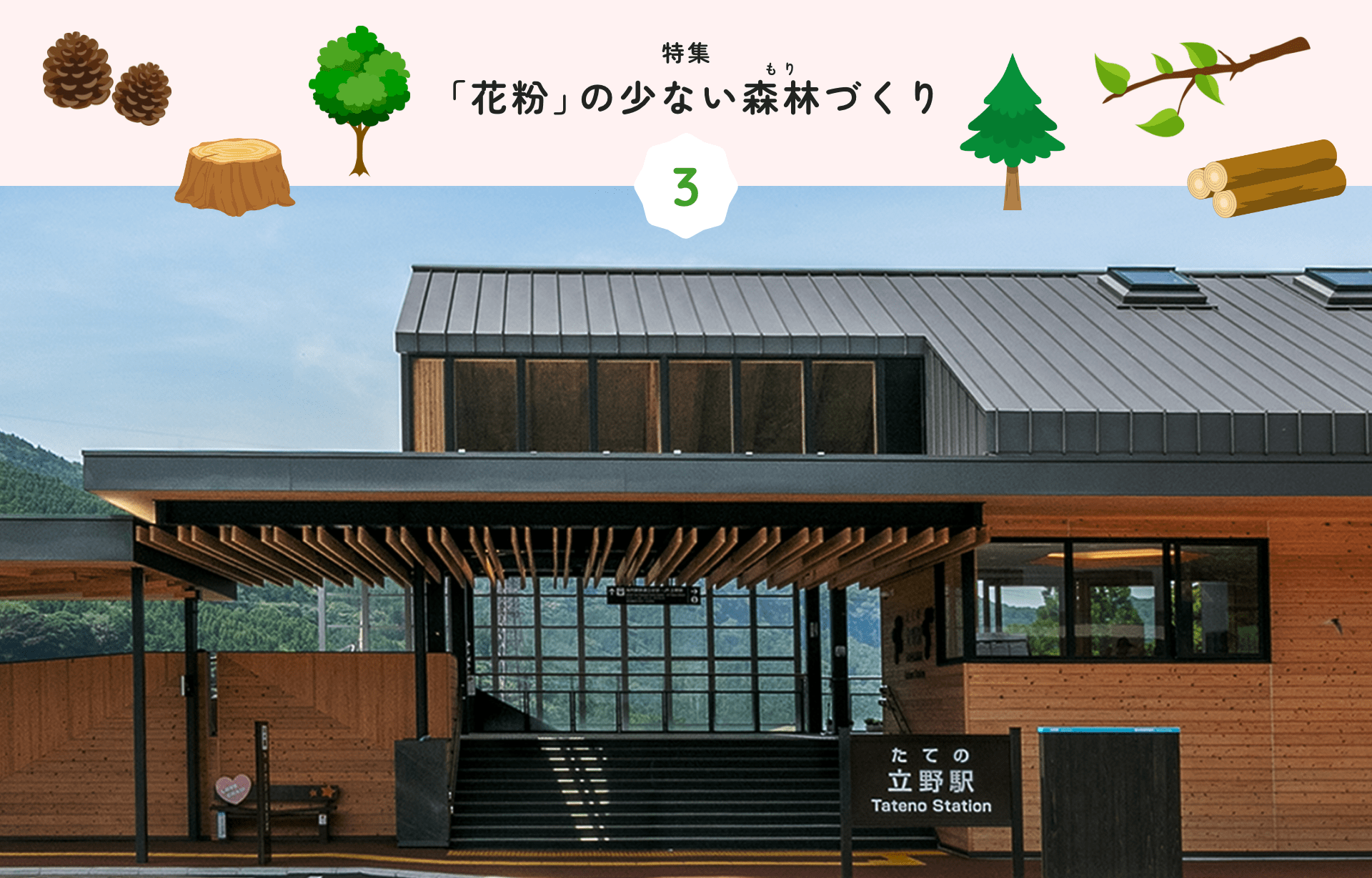
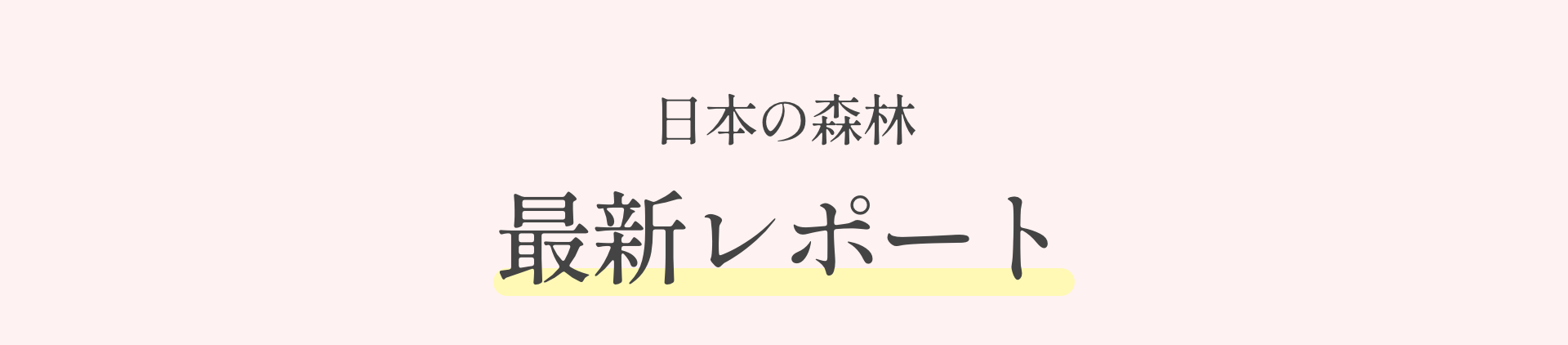
林業の現場では花粉の発生源を減らす
取り組みが進んでいます。
公共施設やオフィスビルなどに
木材を利用する動きも進み、
「伐って、使って、植えて、育てる」資源の
循環利用 が活発になっています。
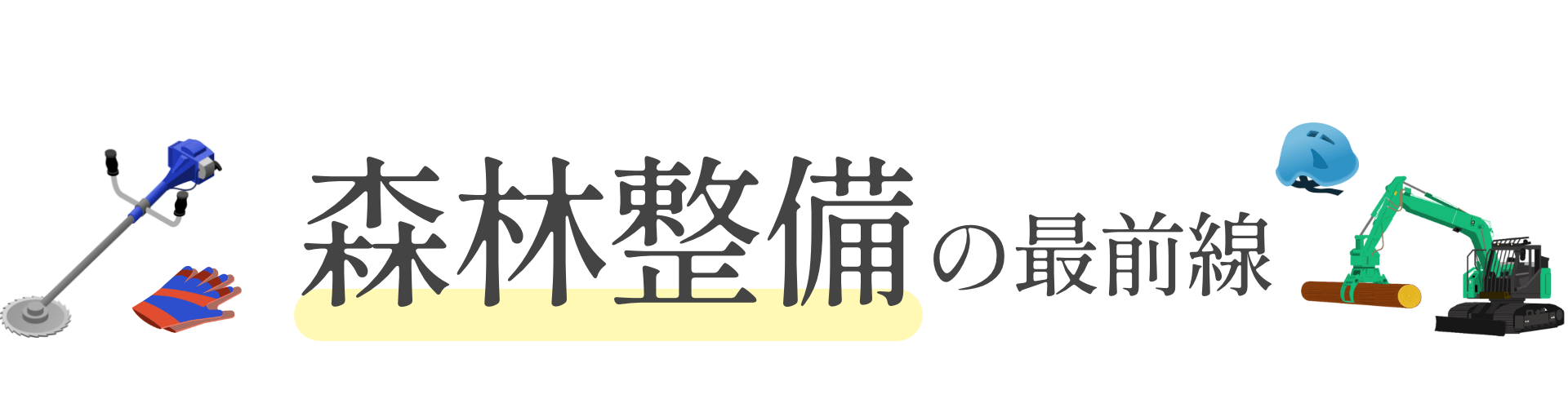
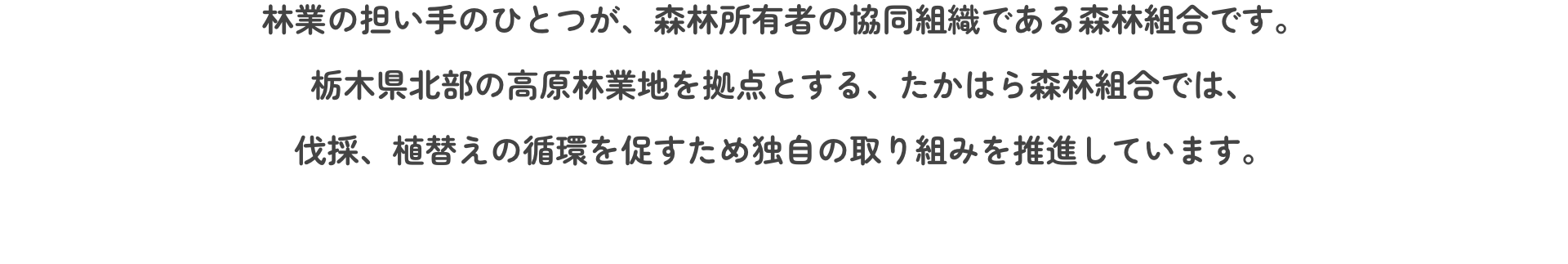
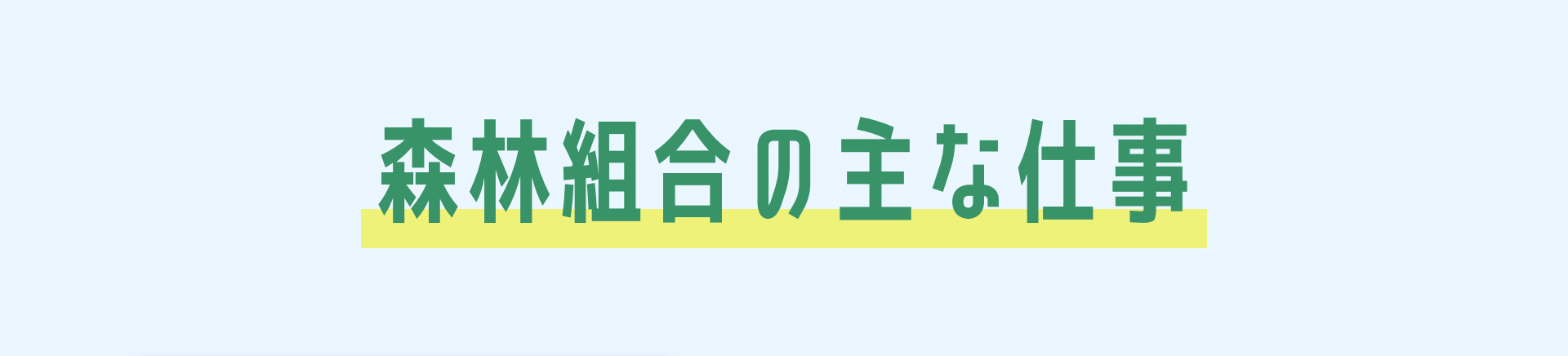
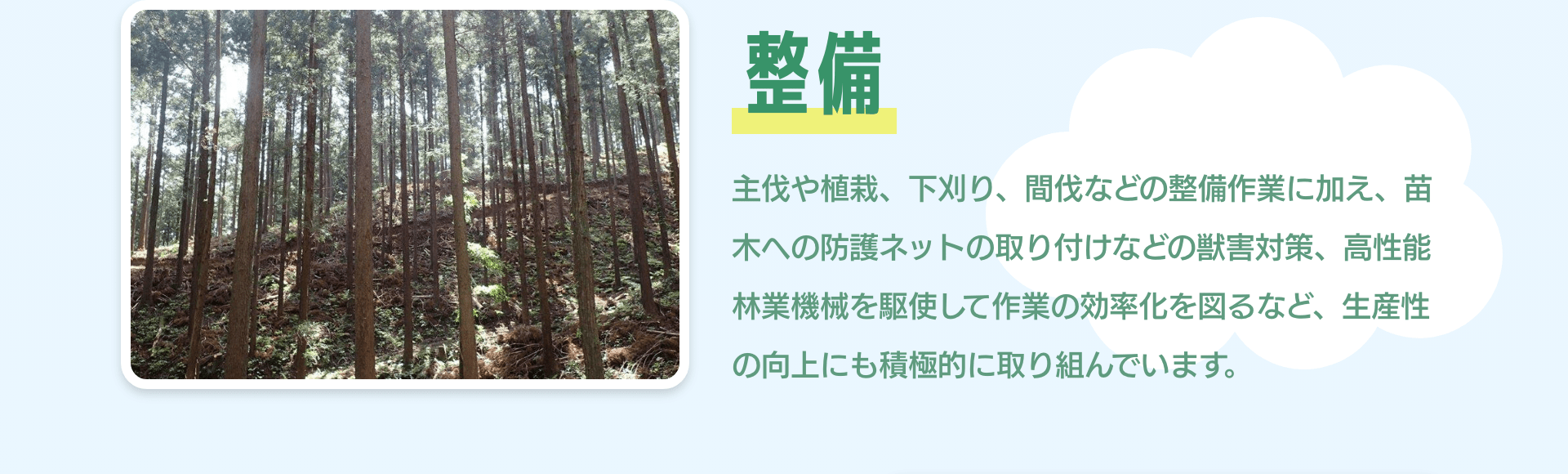
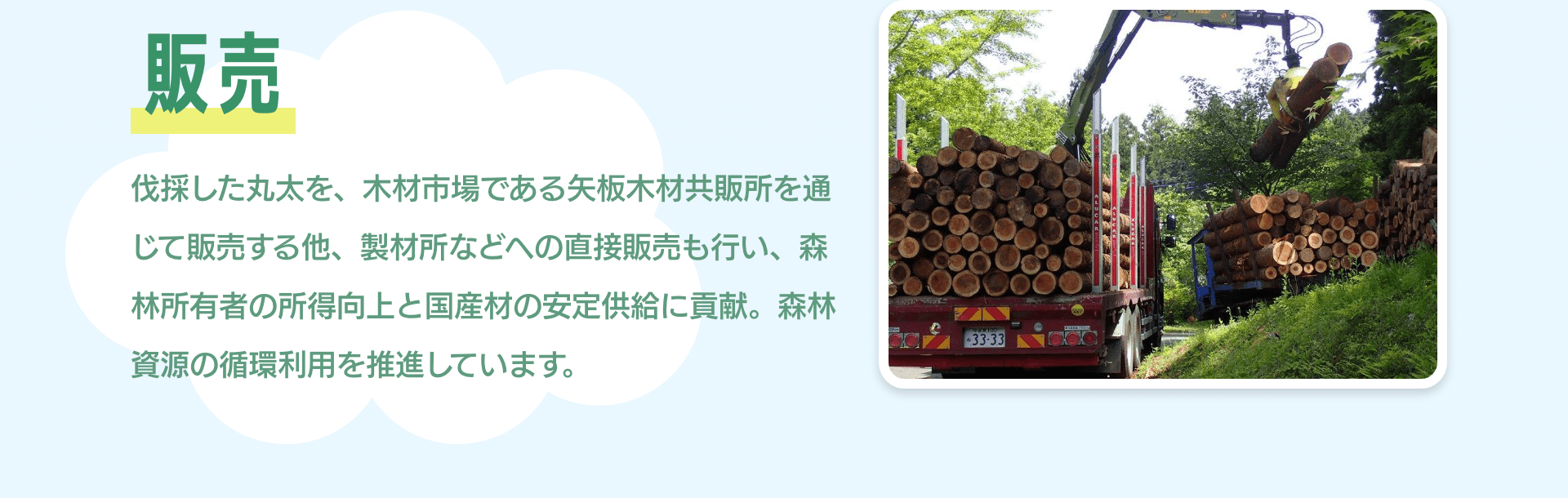
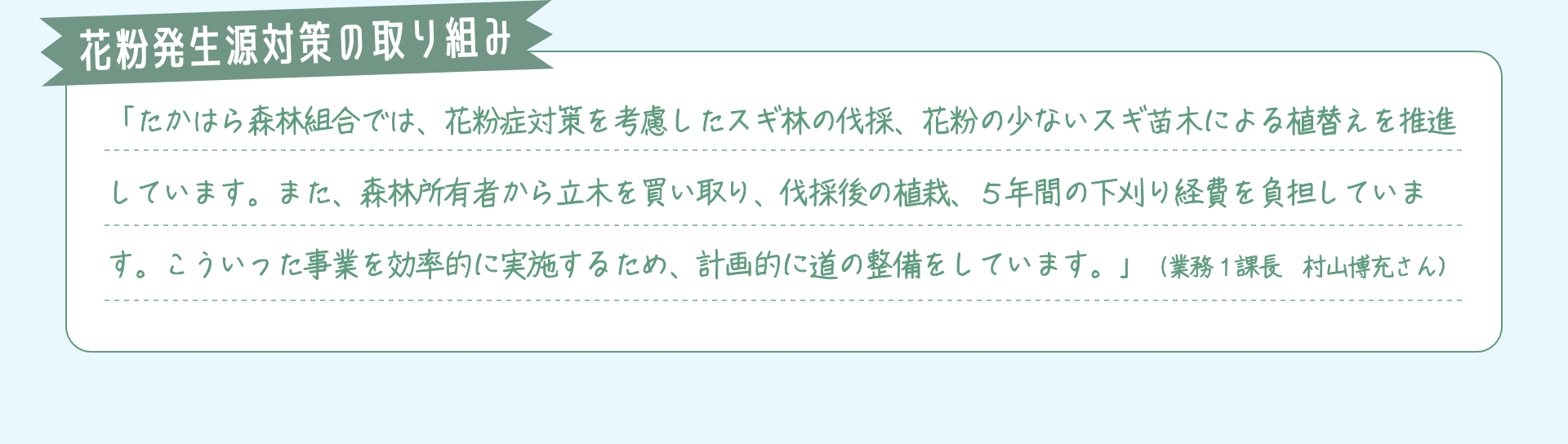
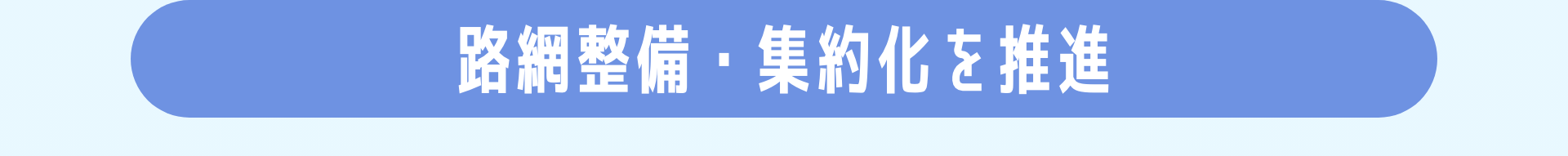
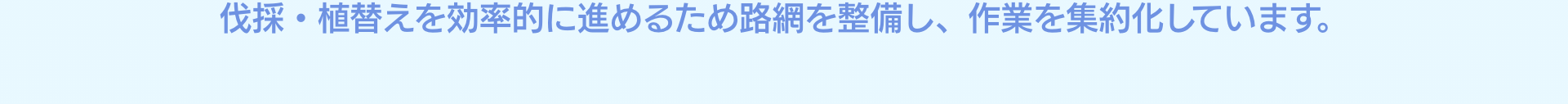
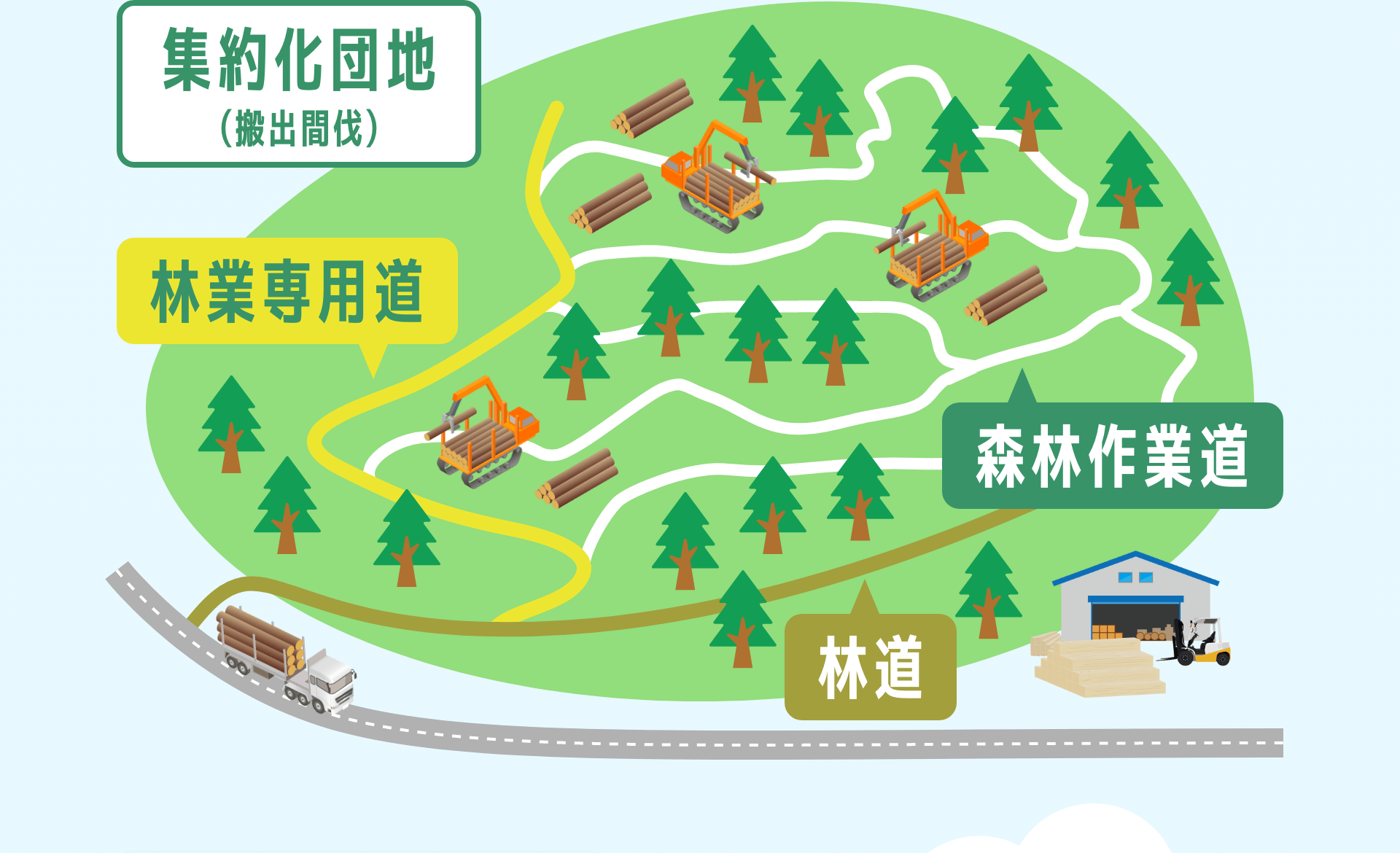
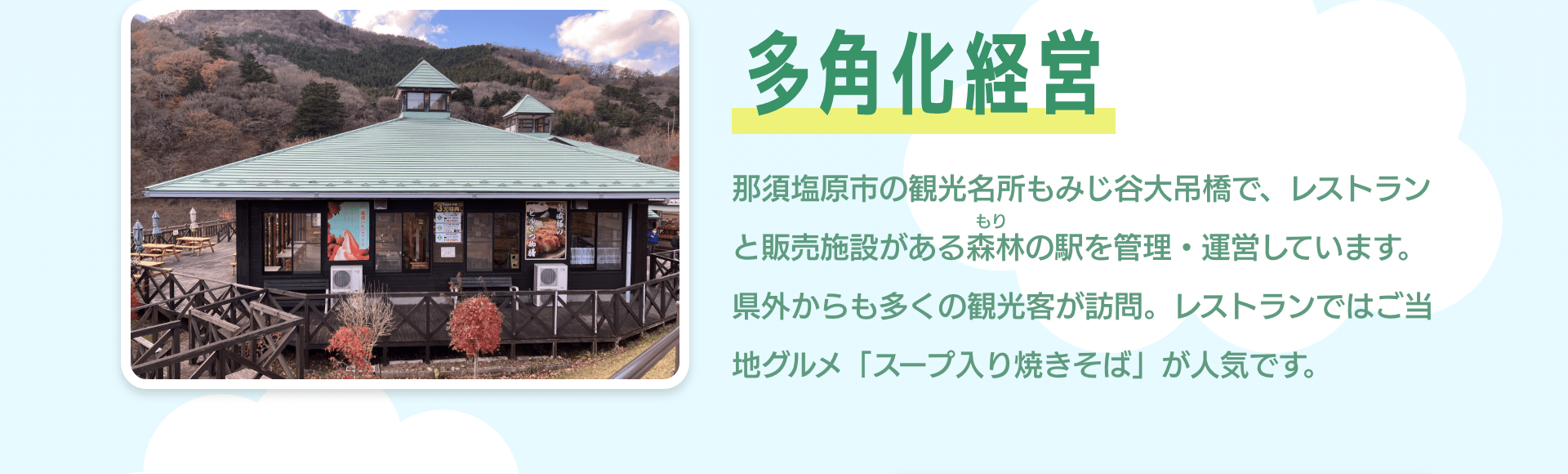
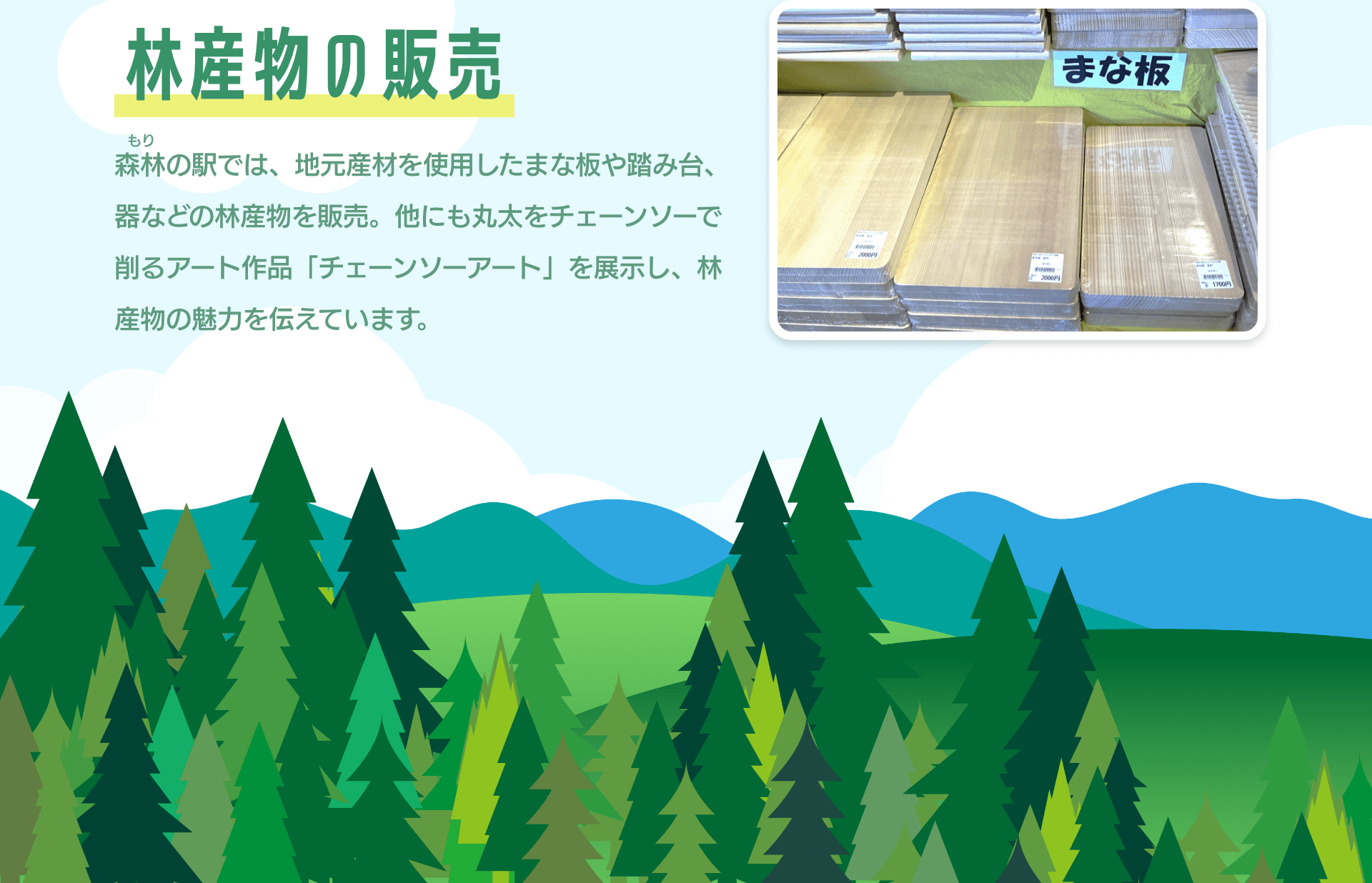
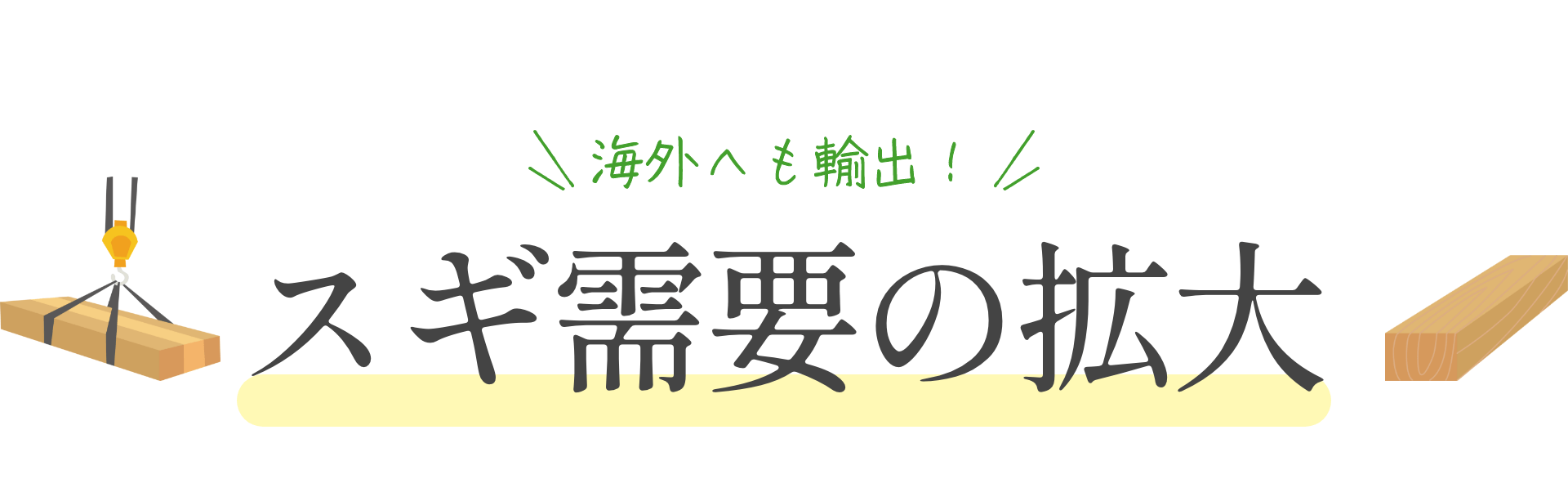
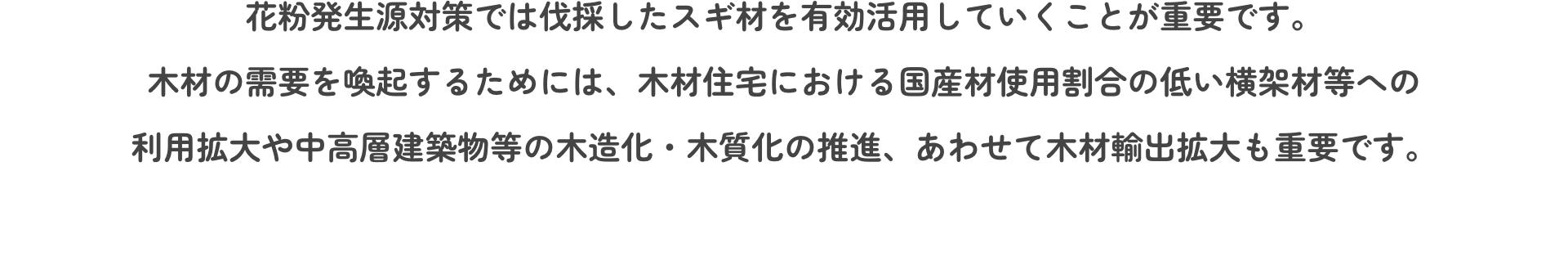
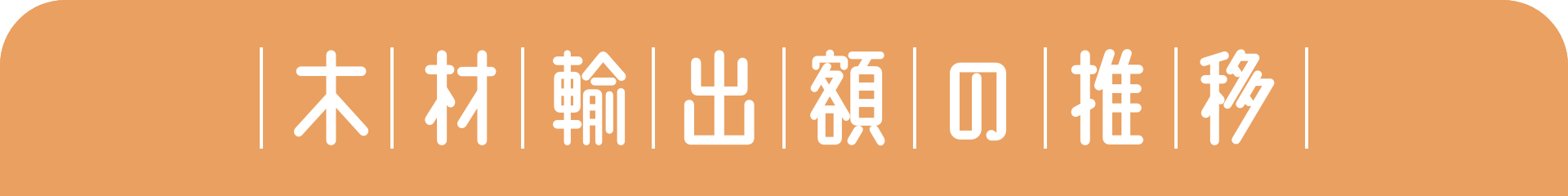
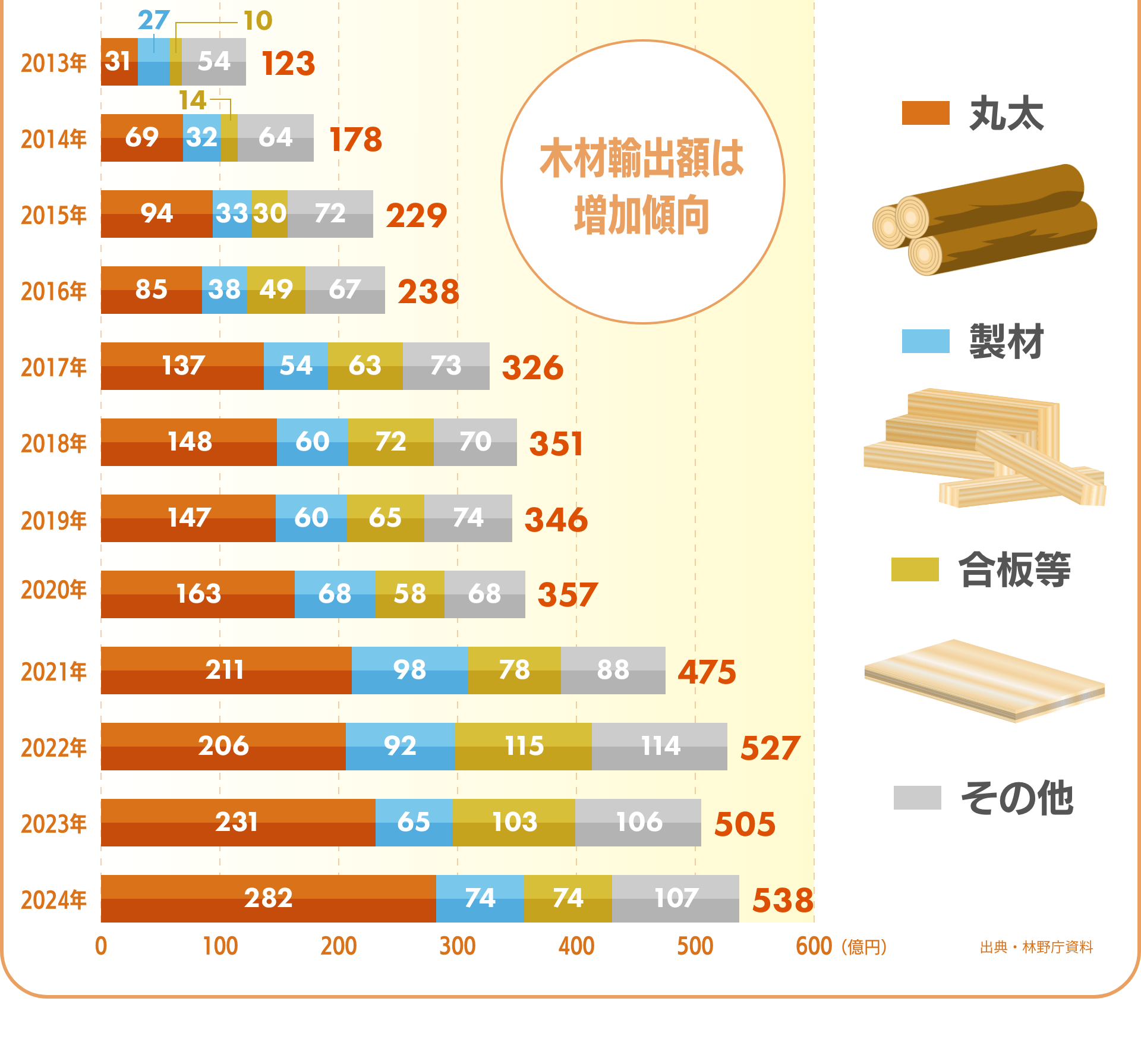
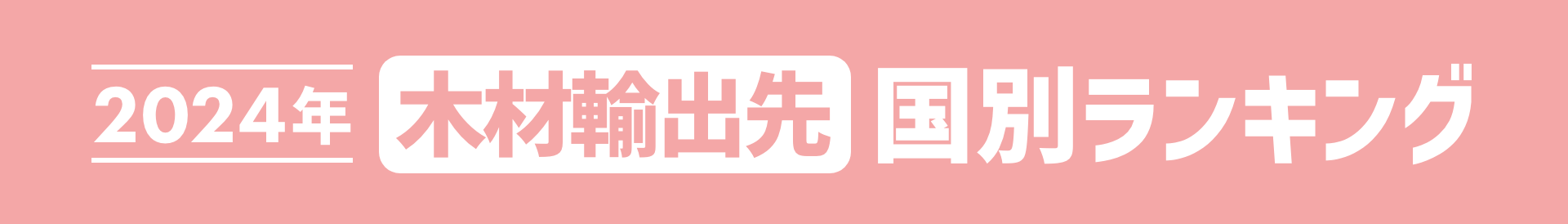
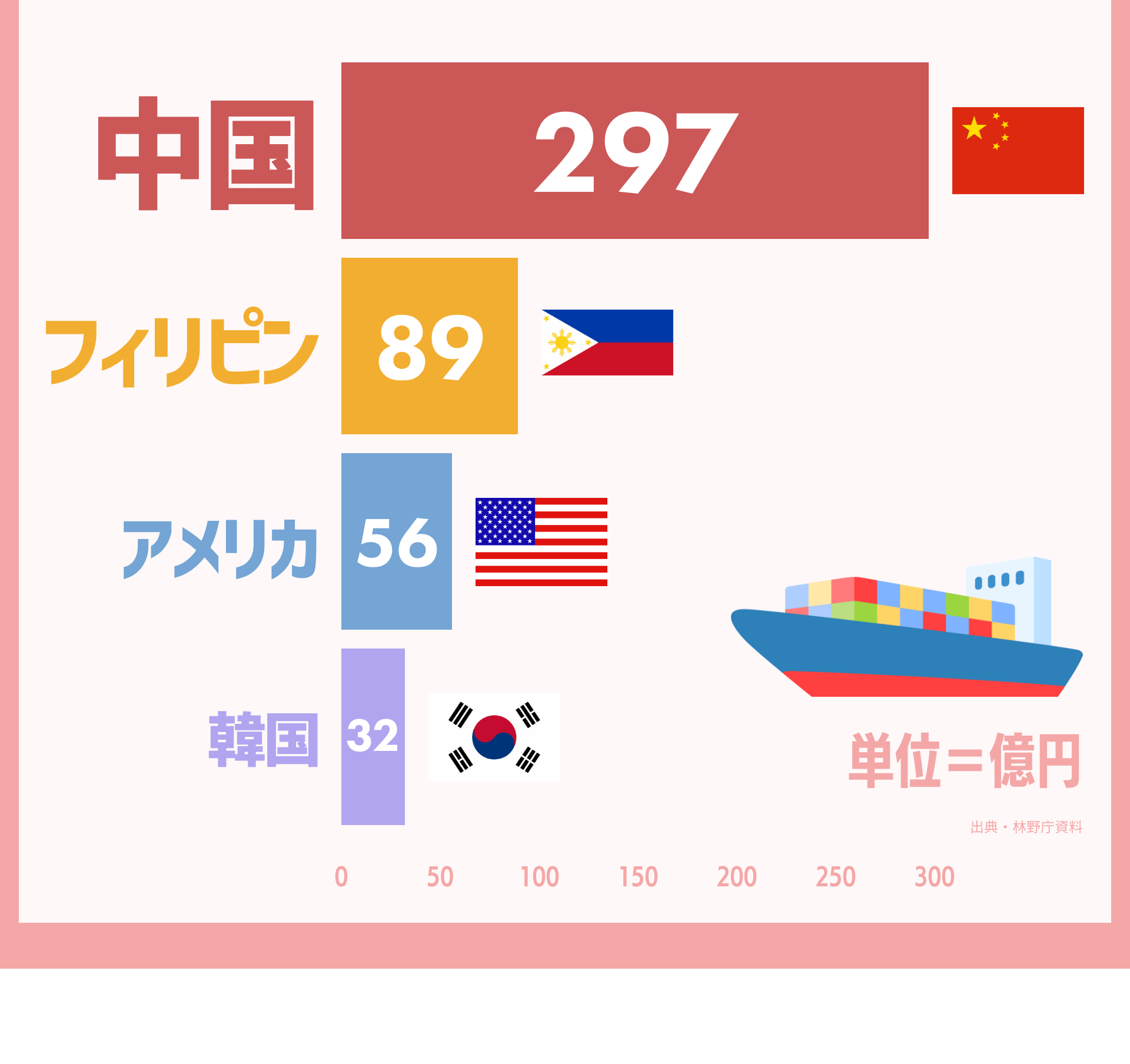
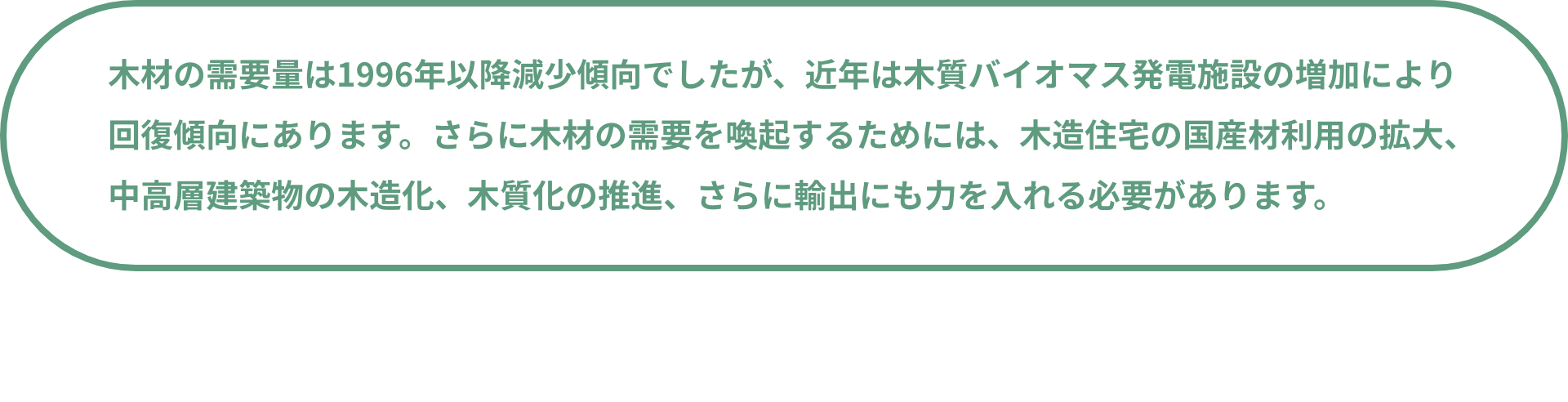
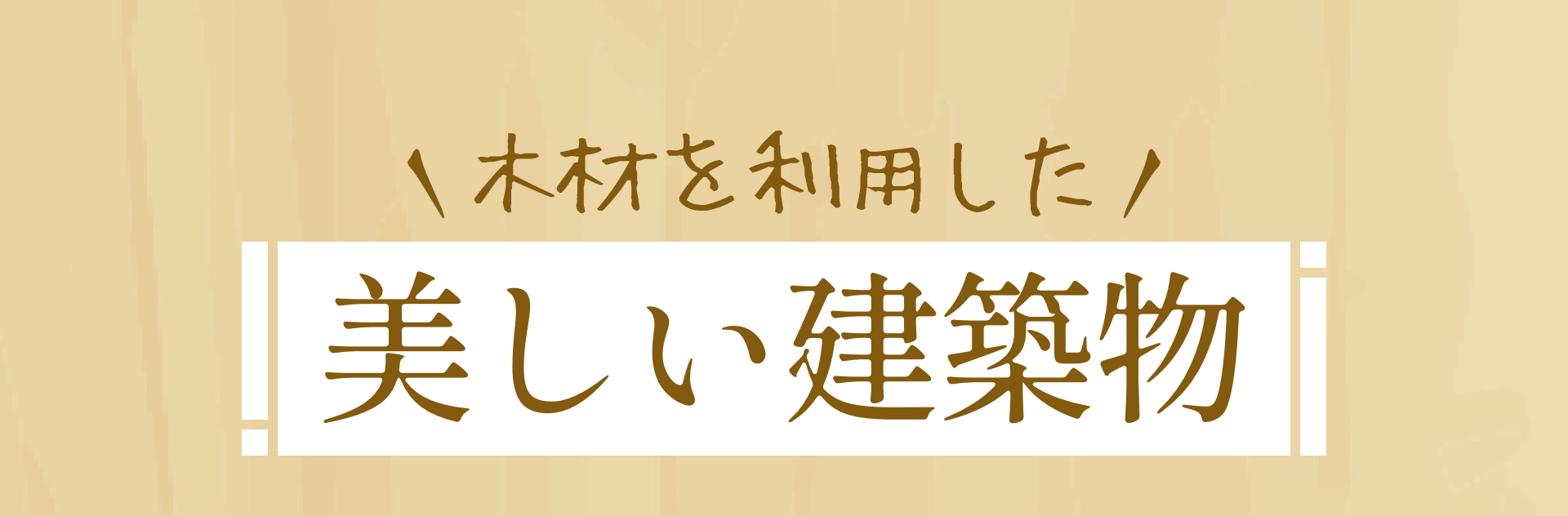
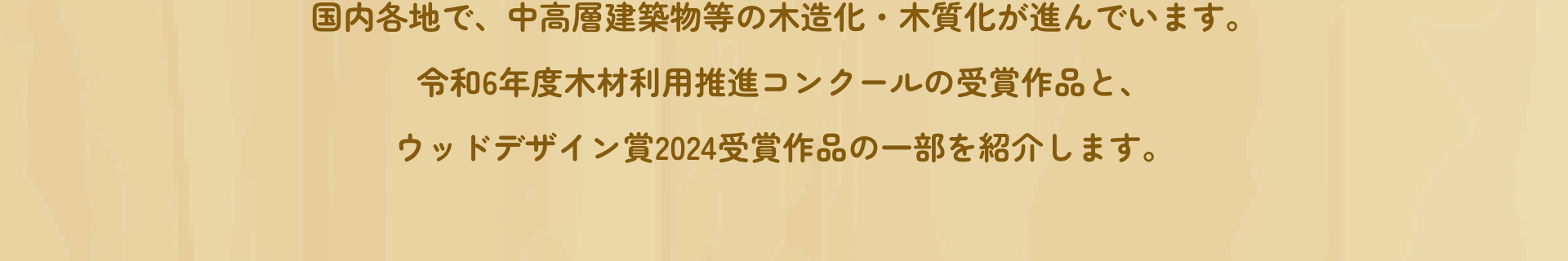

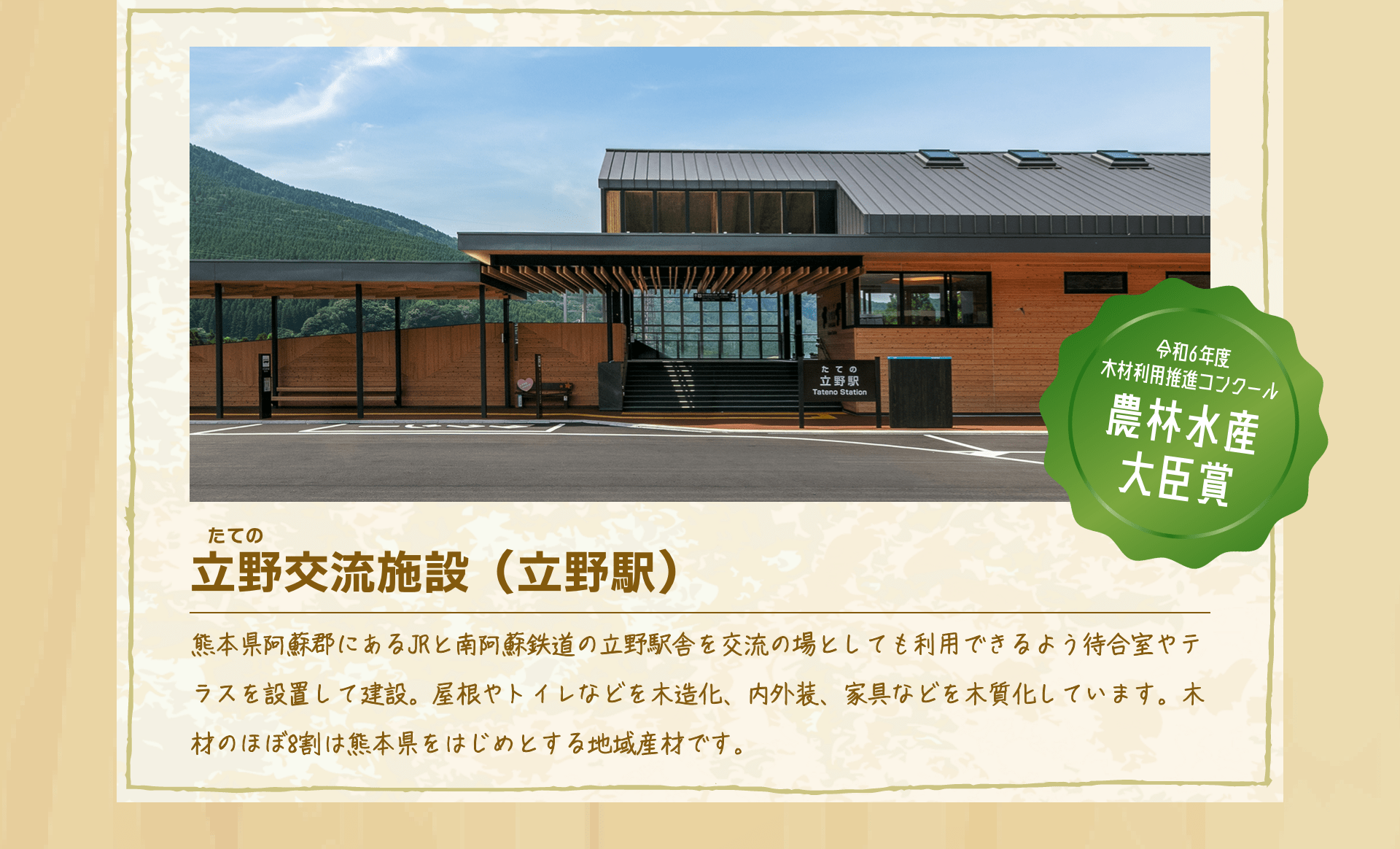


今週のまとめ
林業の現場では、花粉の少ない
スギへの植替えを進めるための取組が
行われています。
建築分野を中心に、
スギ材の需要が拡大しています。
日本の森林は、これからもより良い姿に
変化していきそうです。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449








