
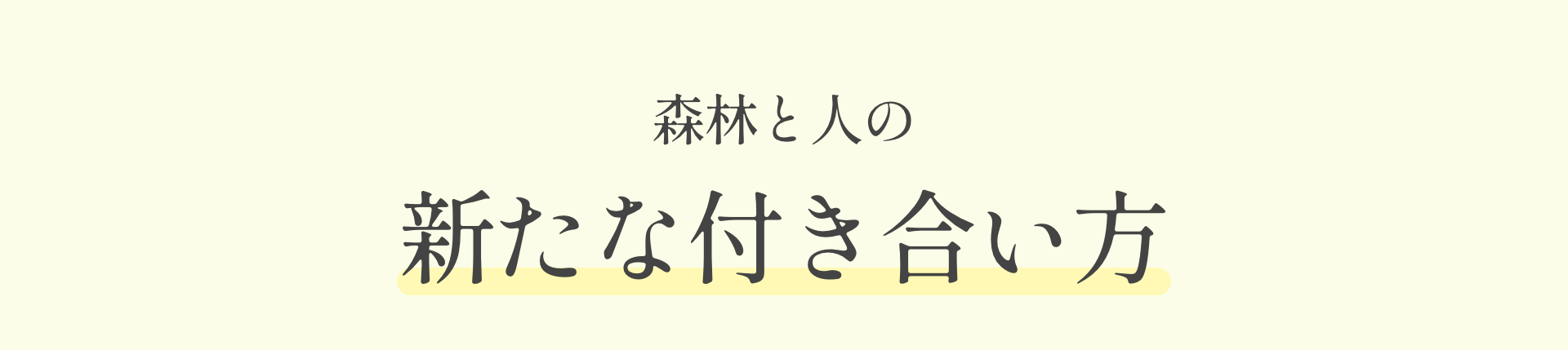
特定の植物の花粉が原因となる花粉症は、
社会的に大きな問題となっています。
これまで行われてきた花粉発生源対策を
さらに効果的に行えるよう、
2024年からは森林と人の付き合い方を変える、
新たな取り組みを開始しています。
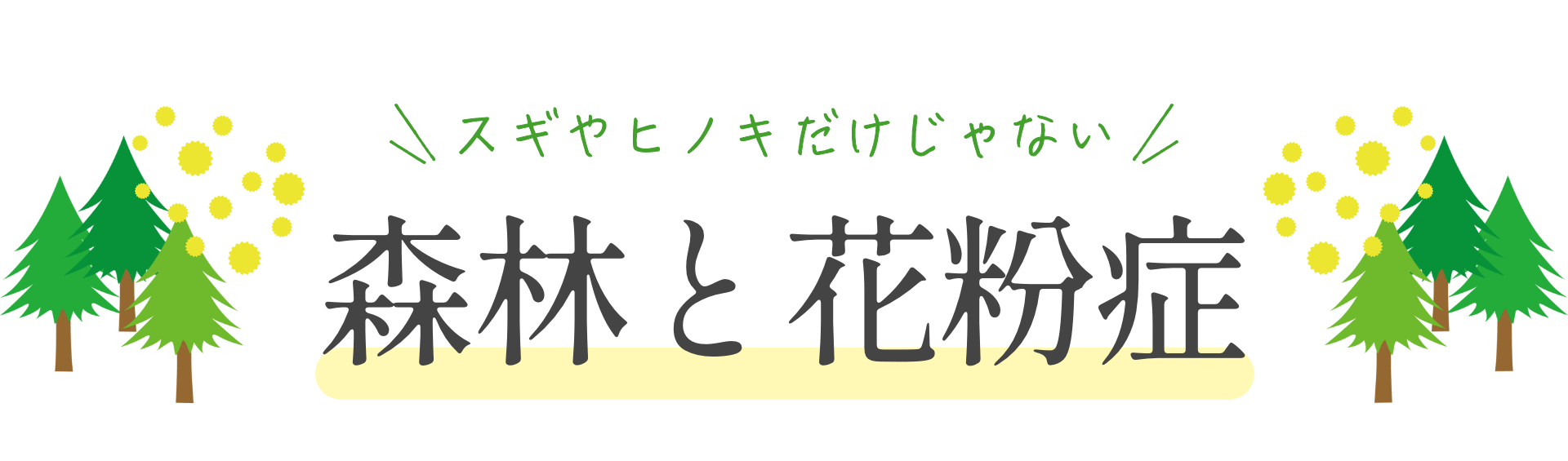
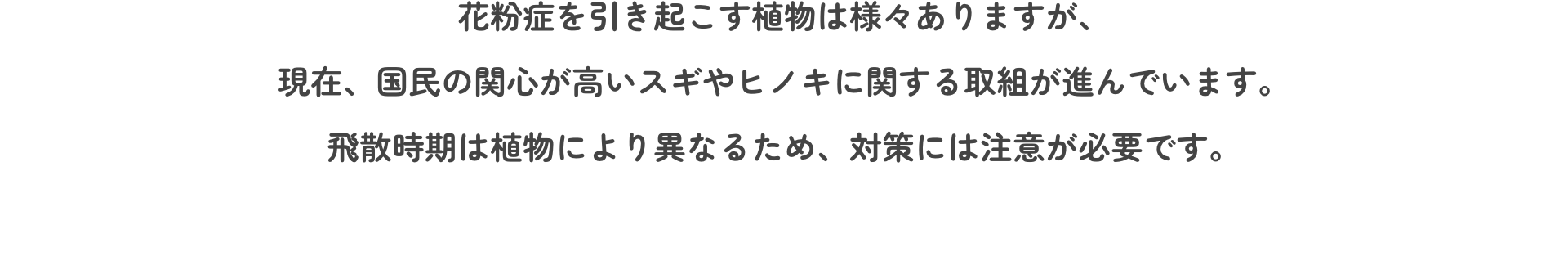

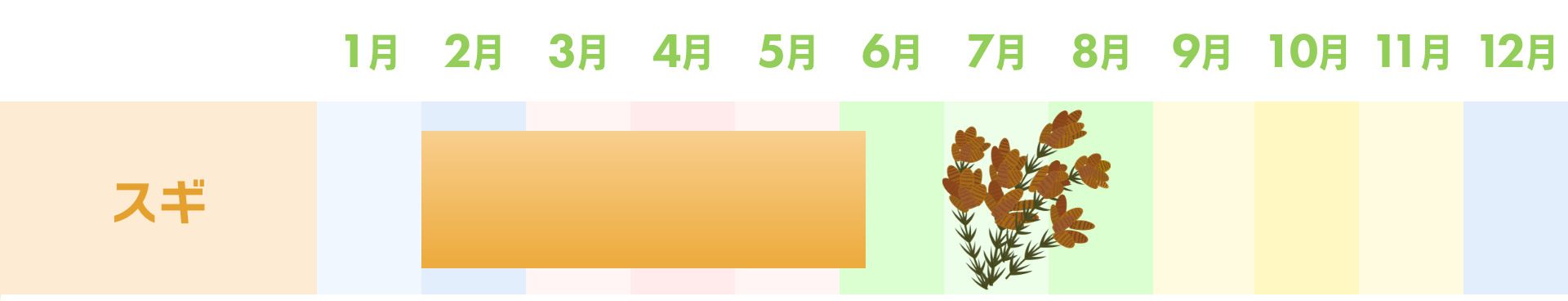
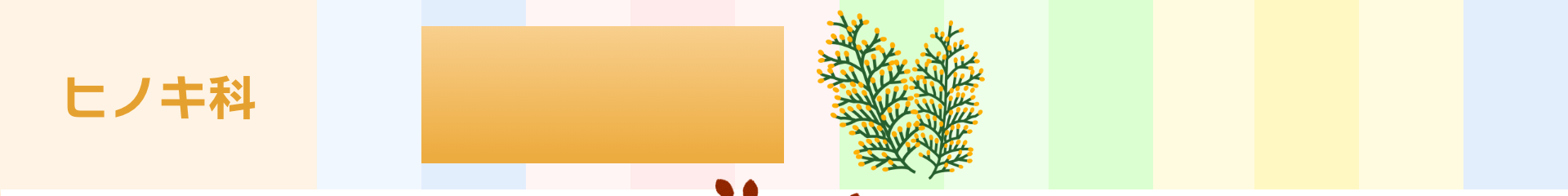
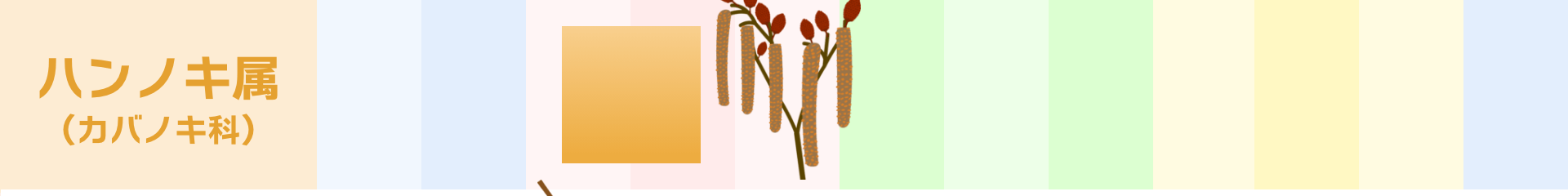


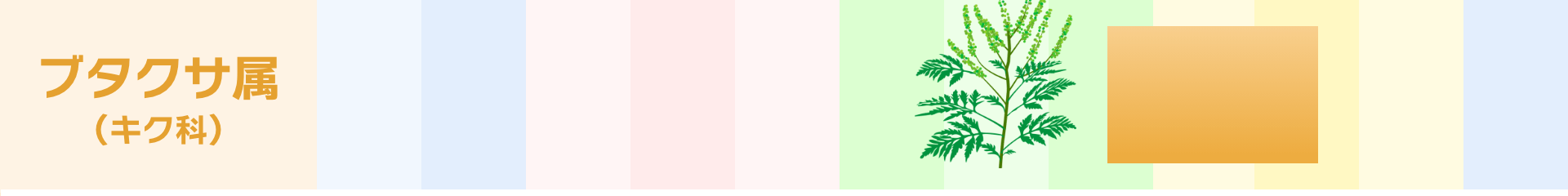
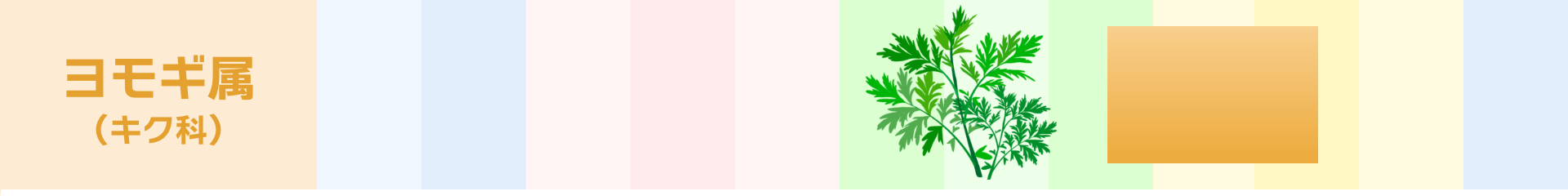
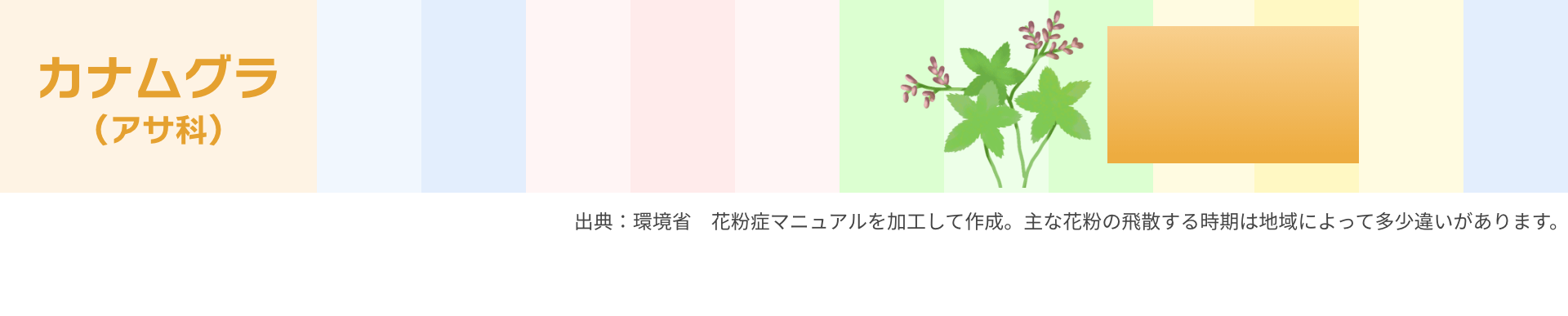

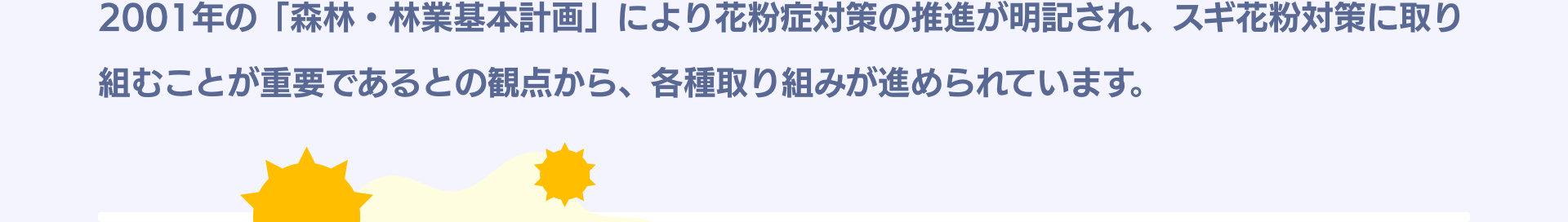

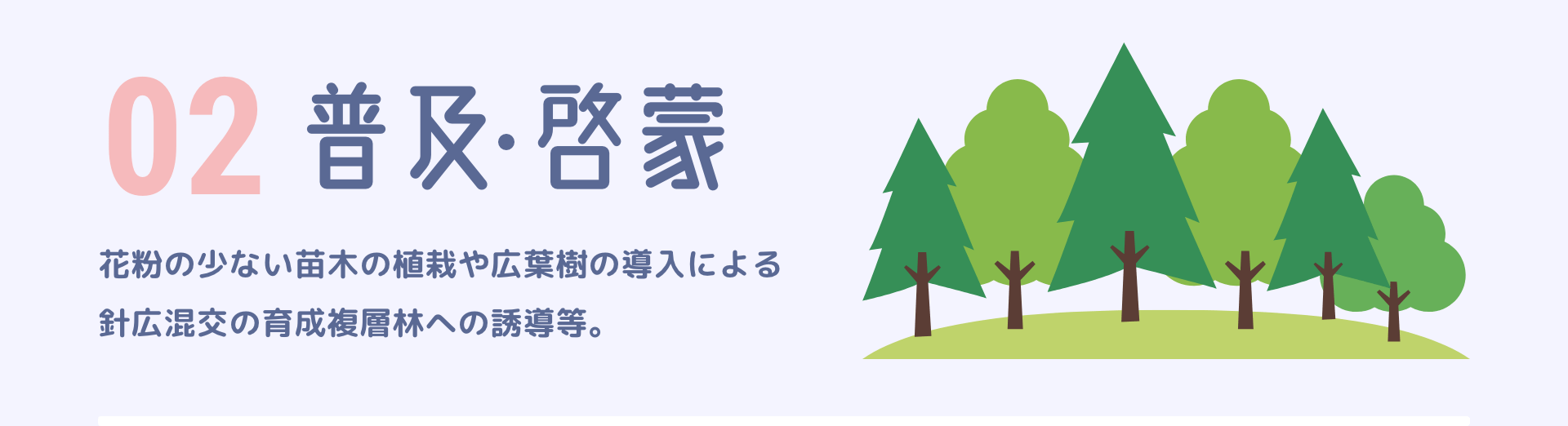
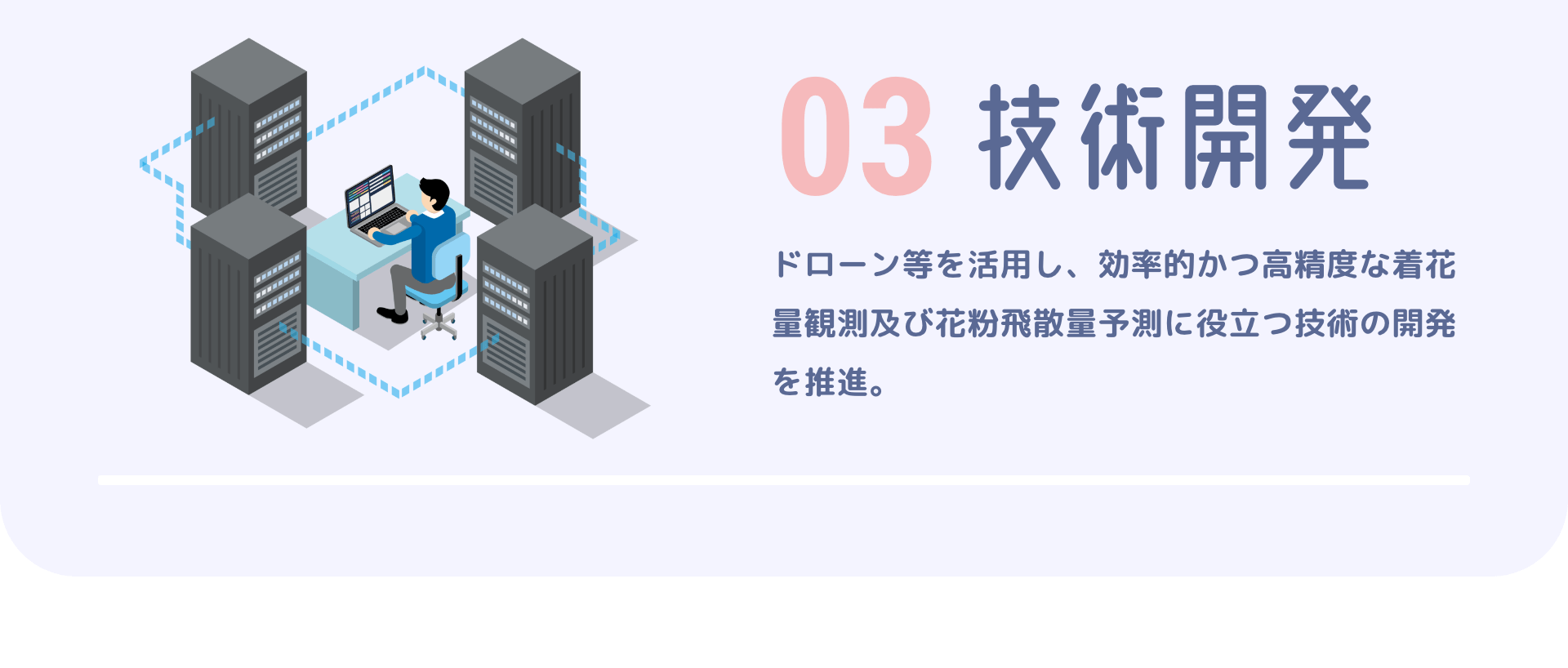
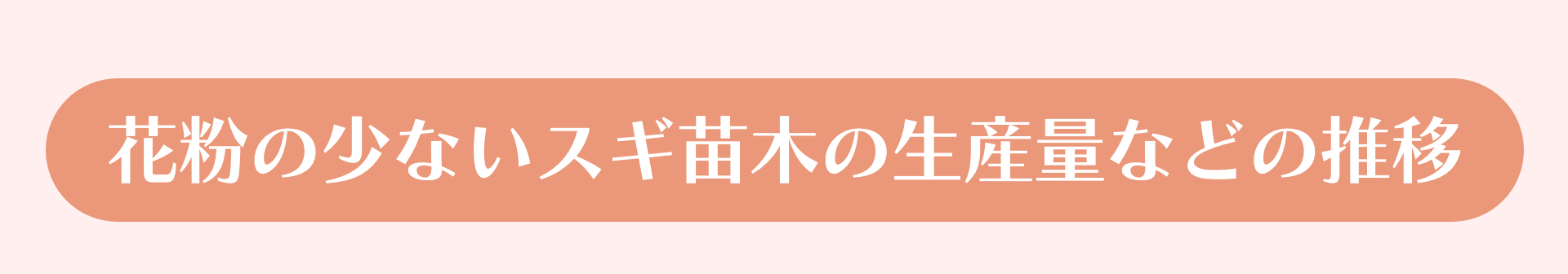
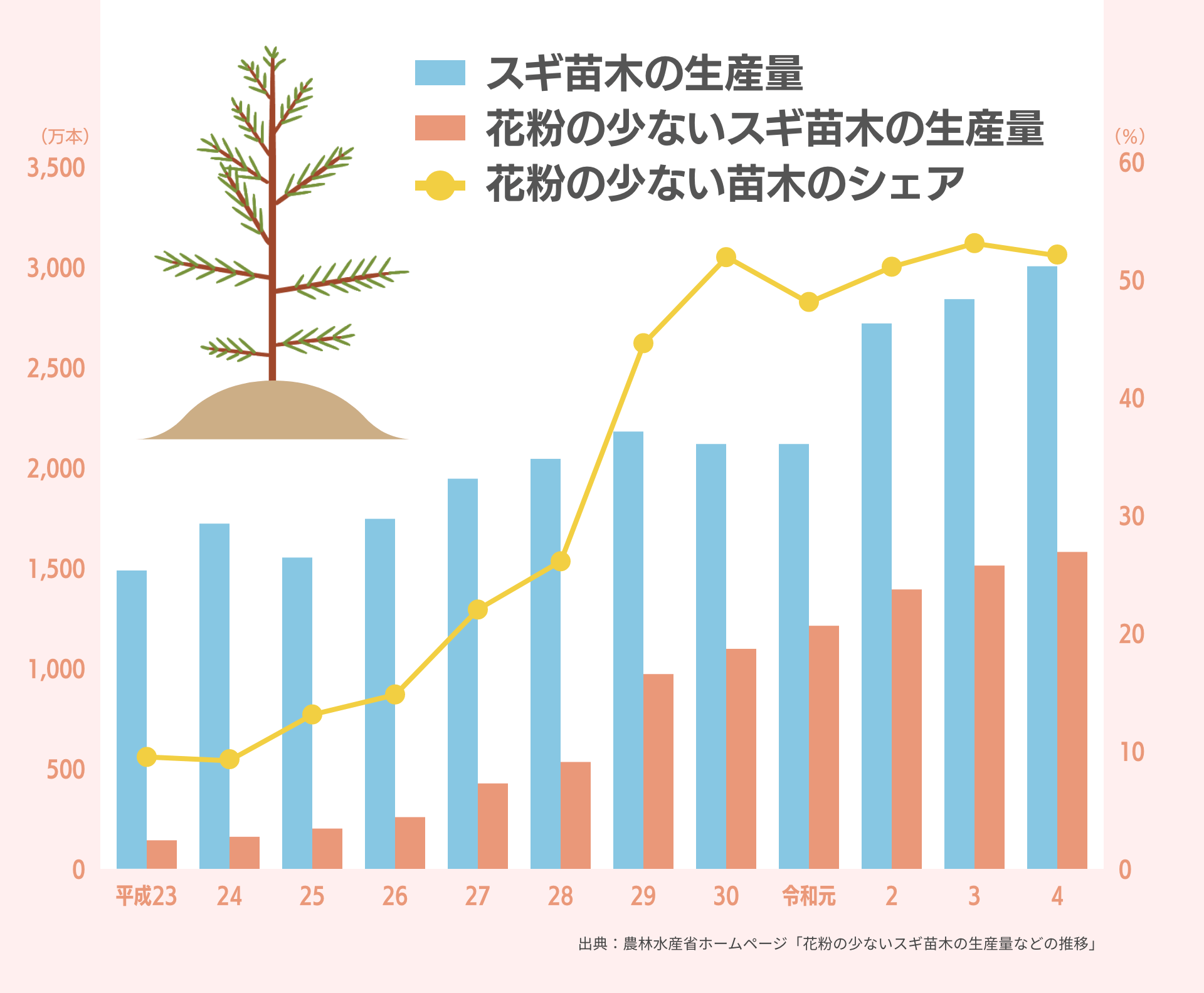
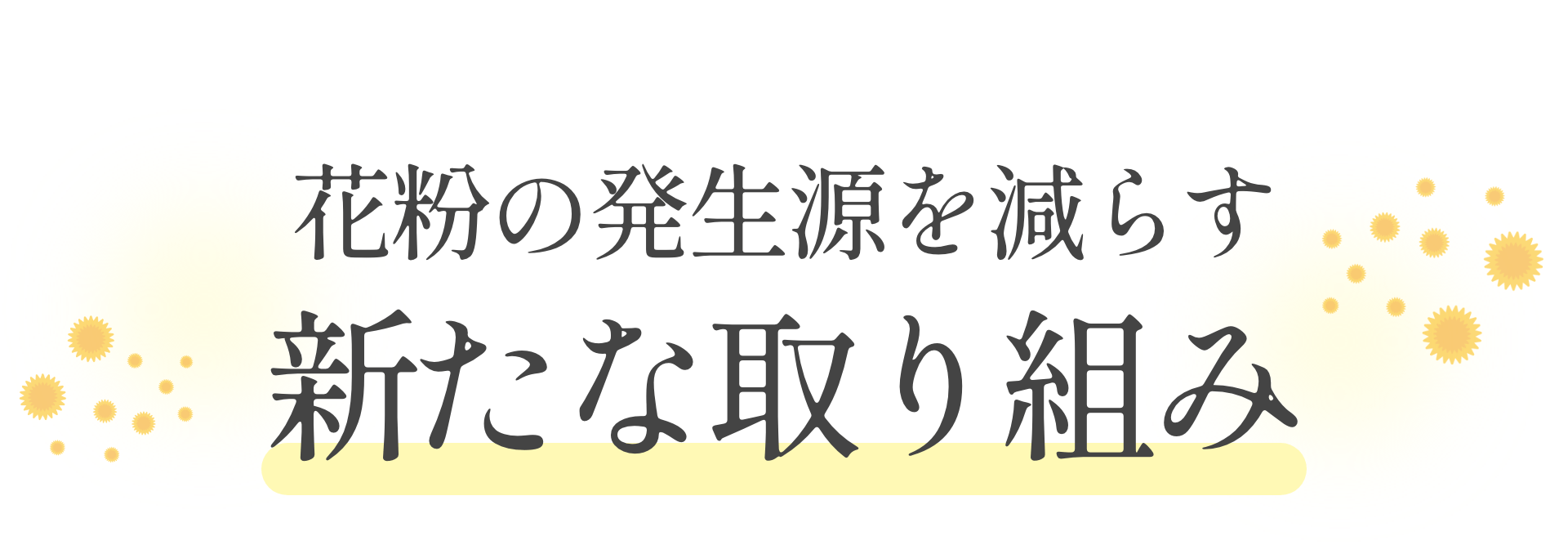
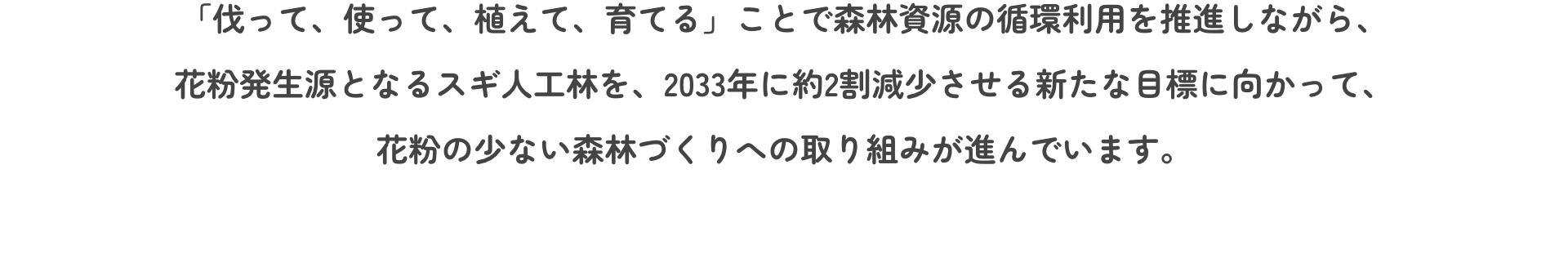
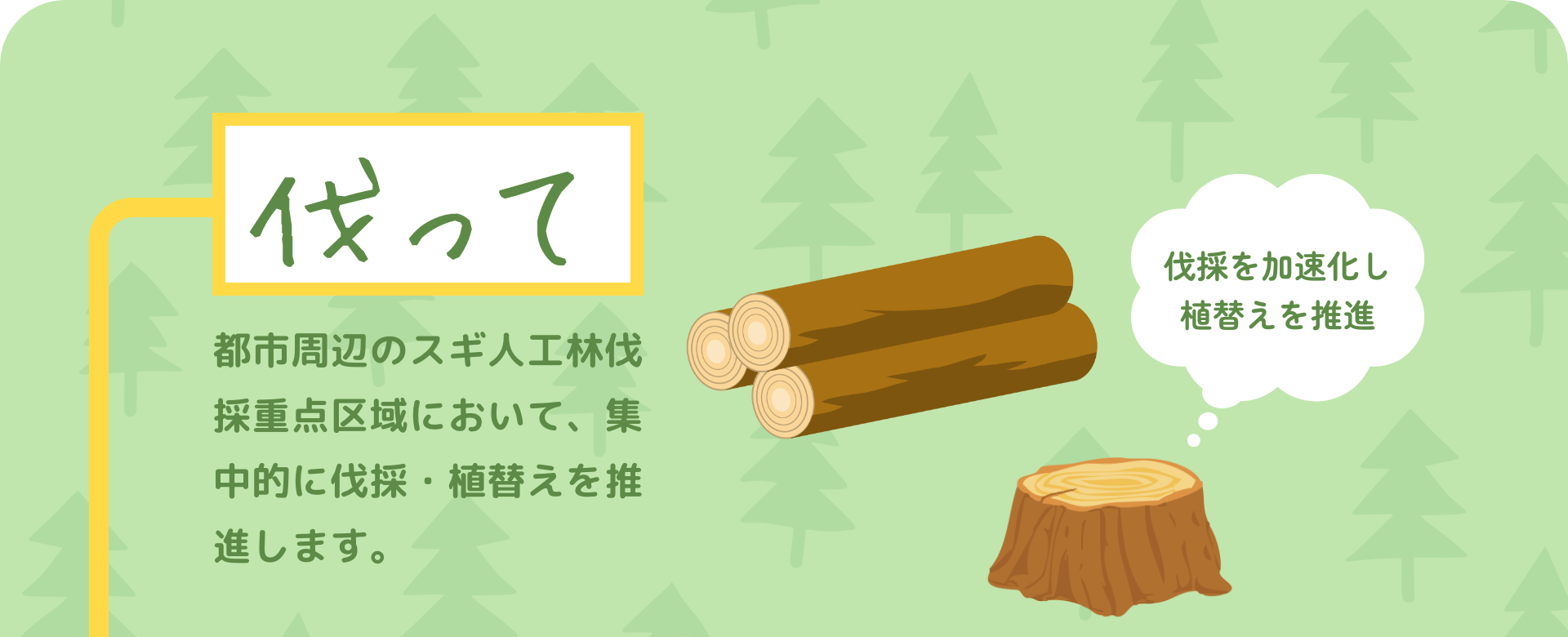
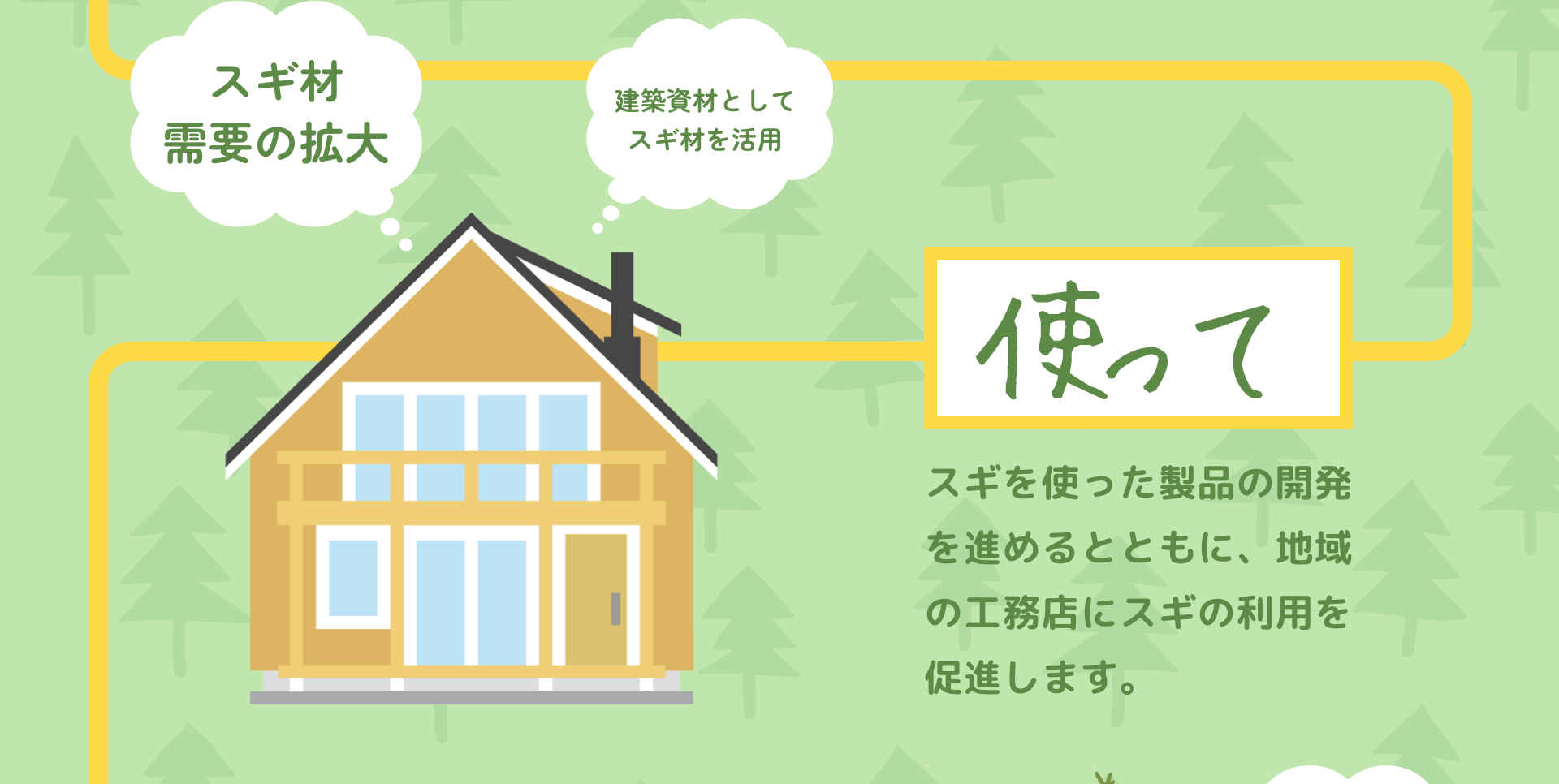
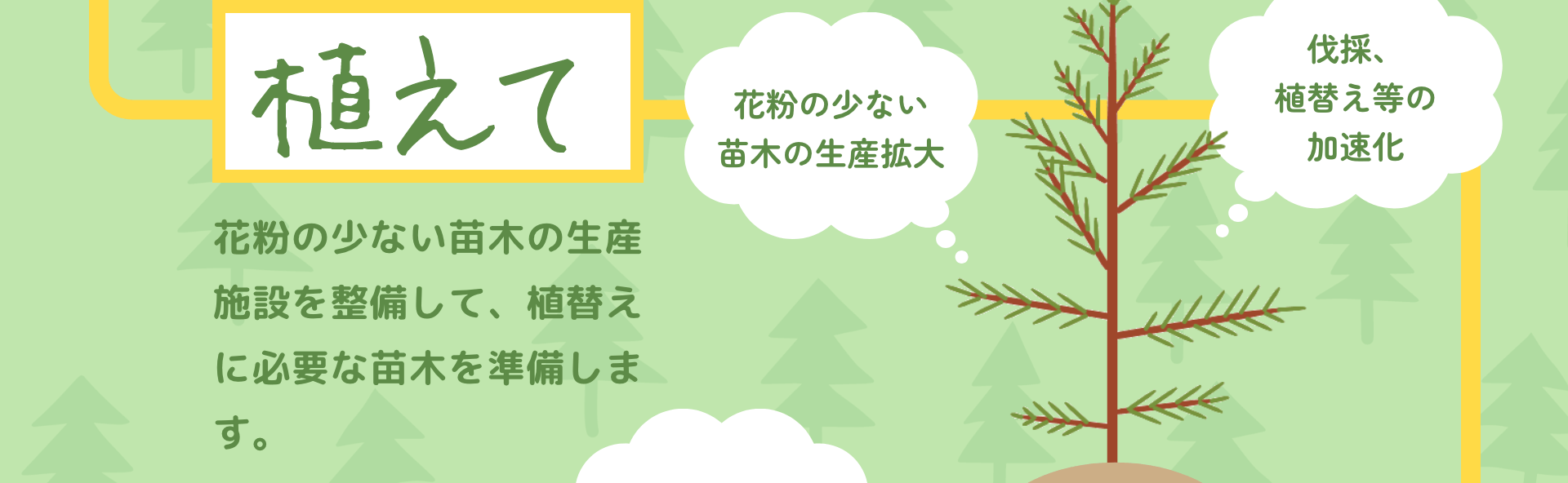
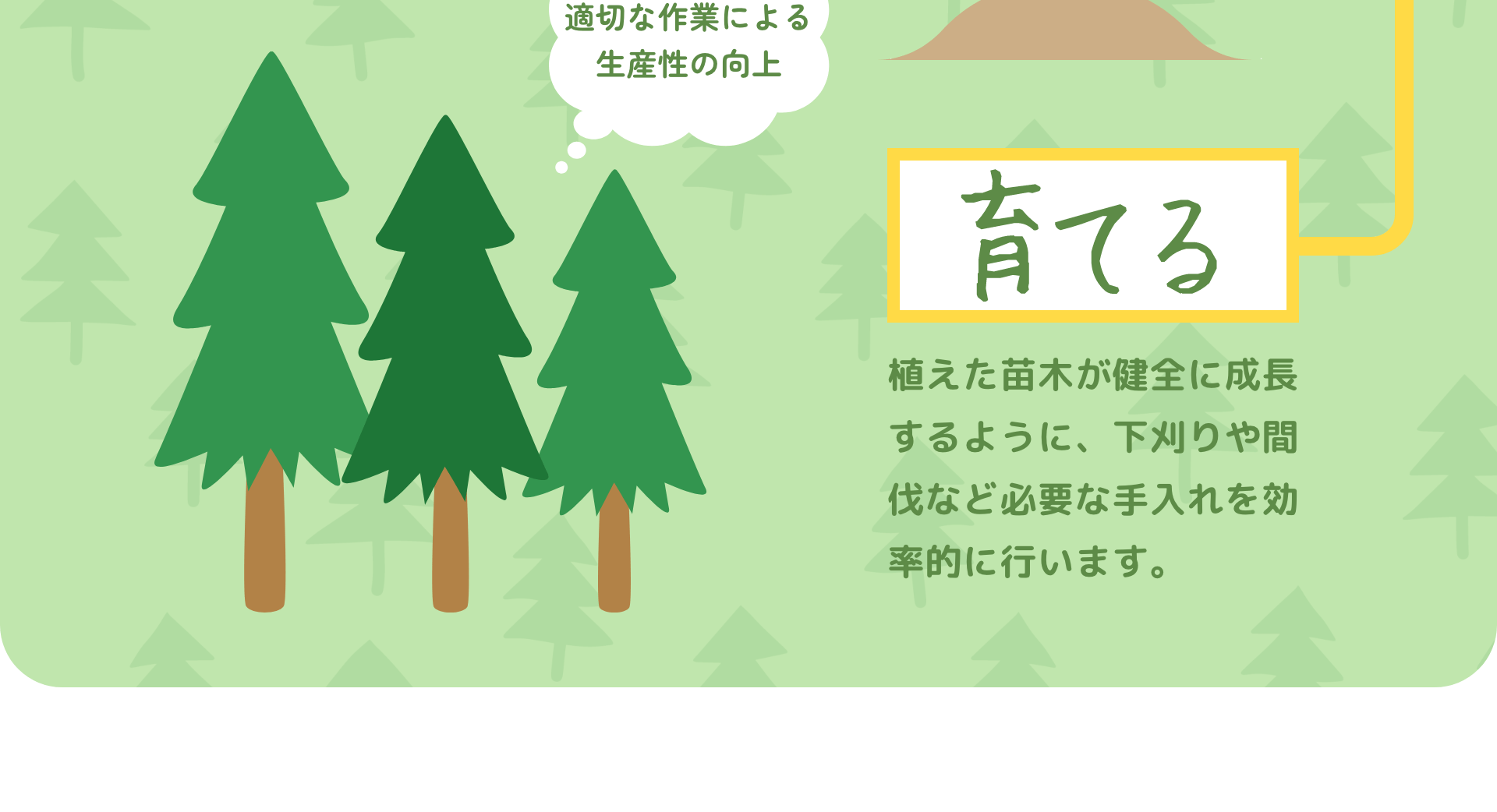
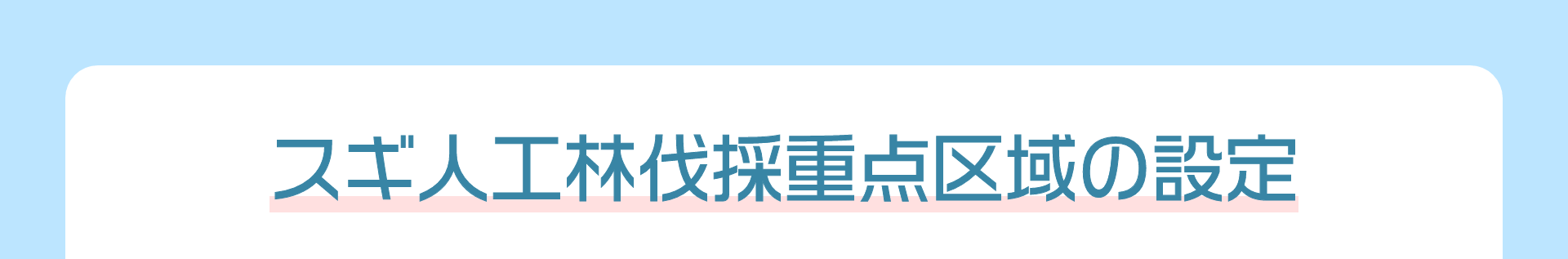
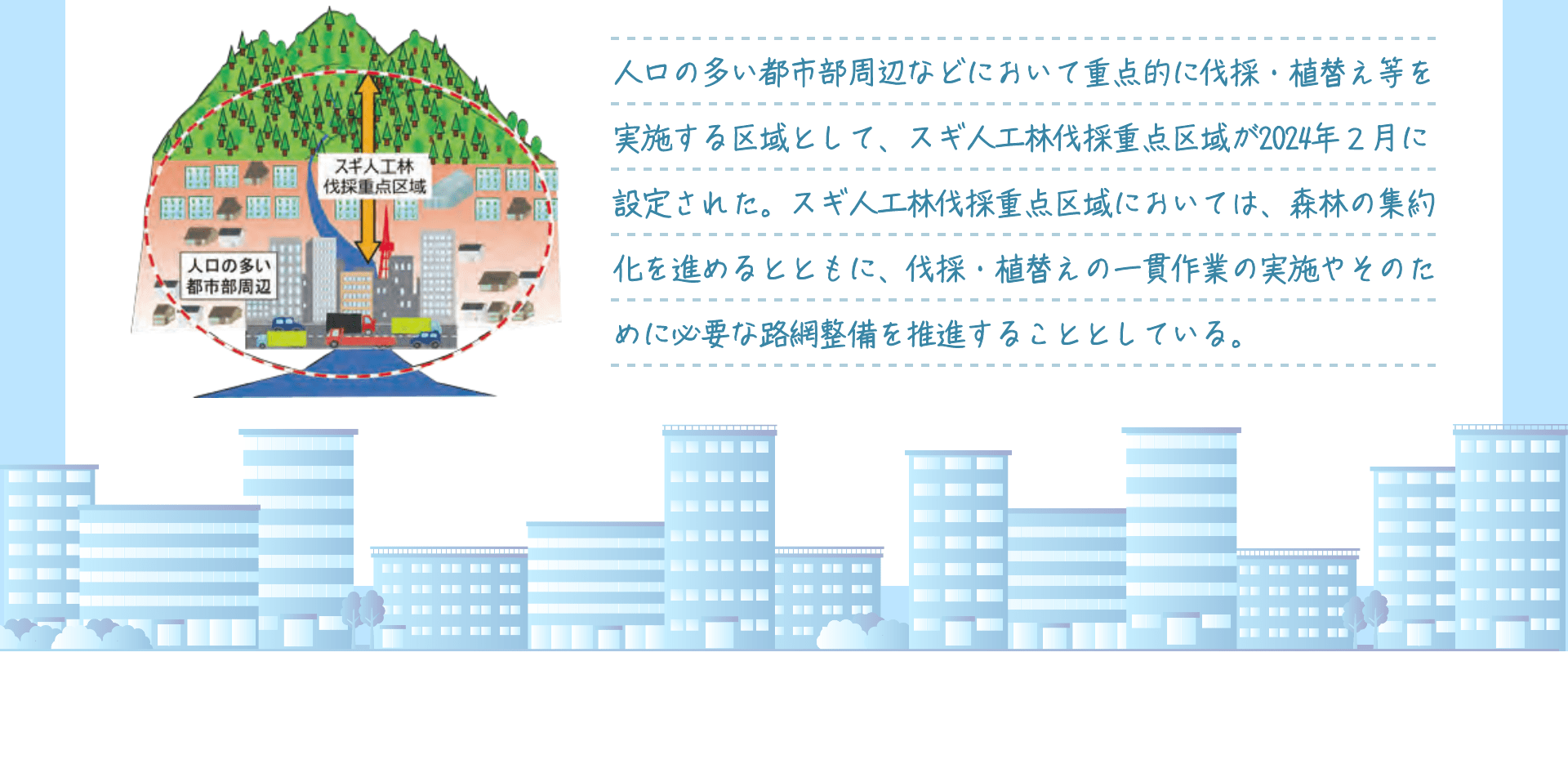
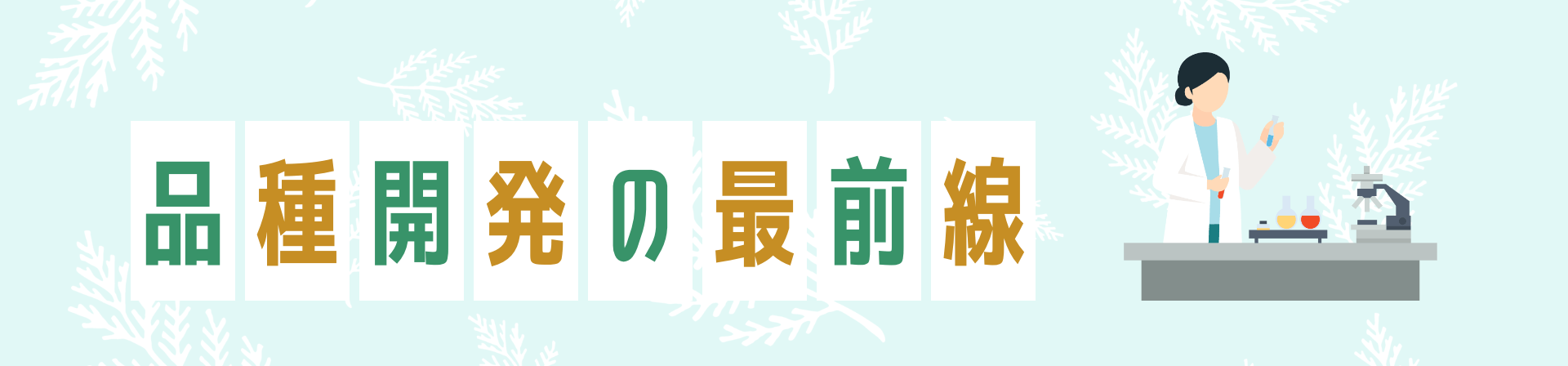
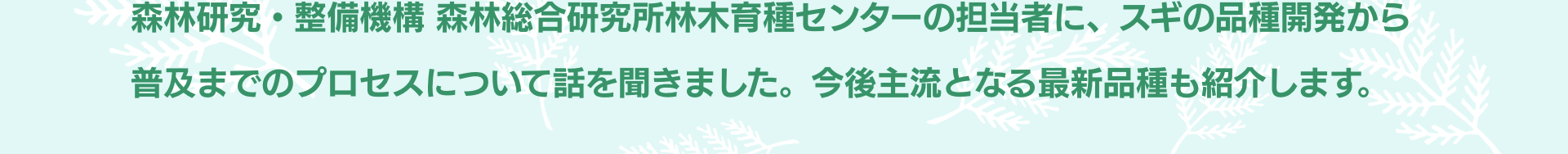
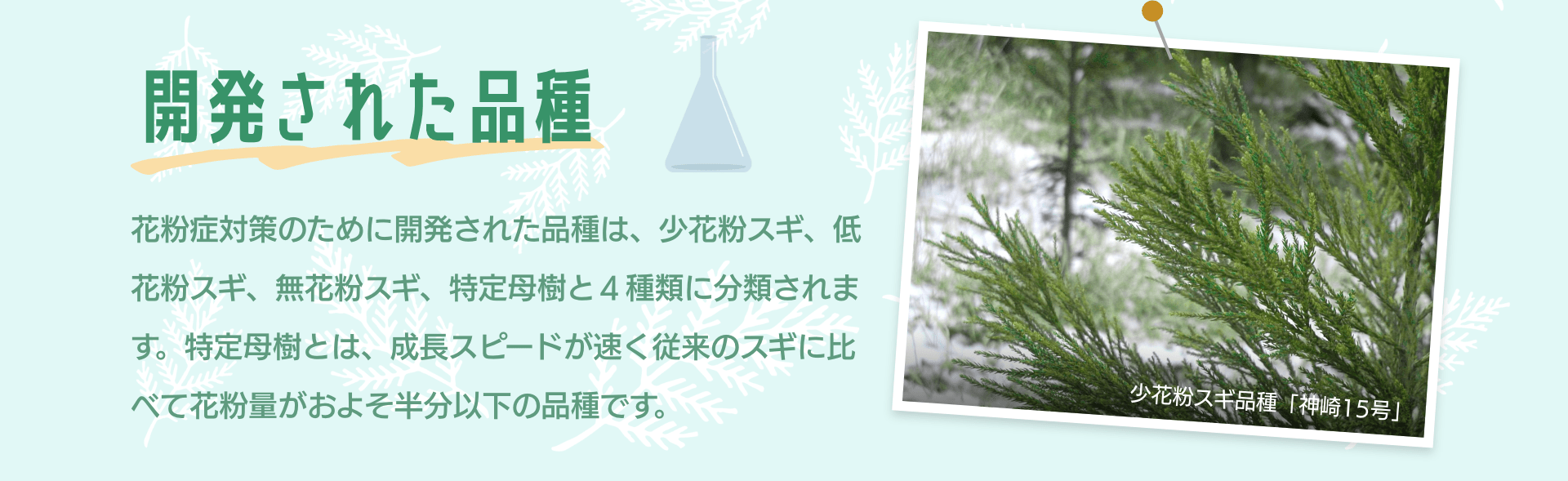
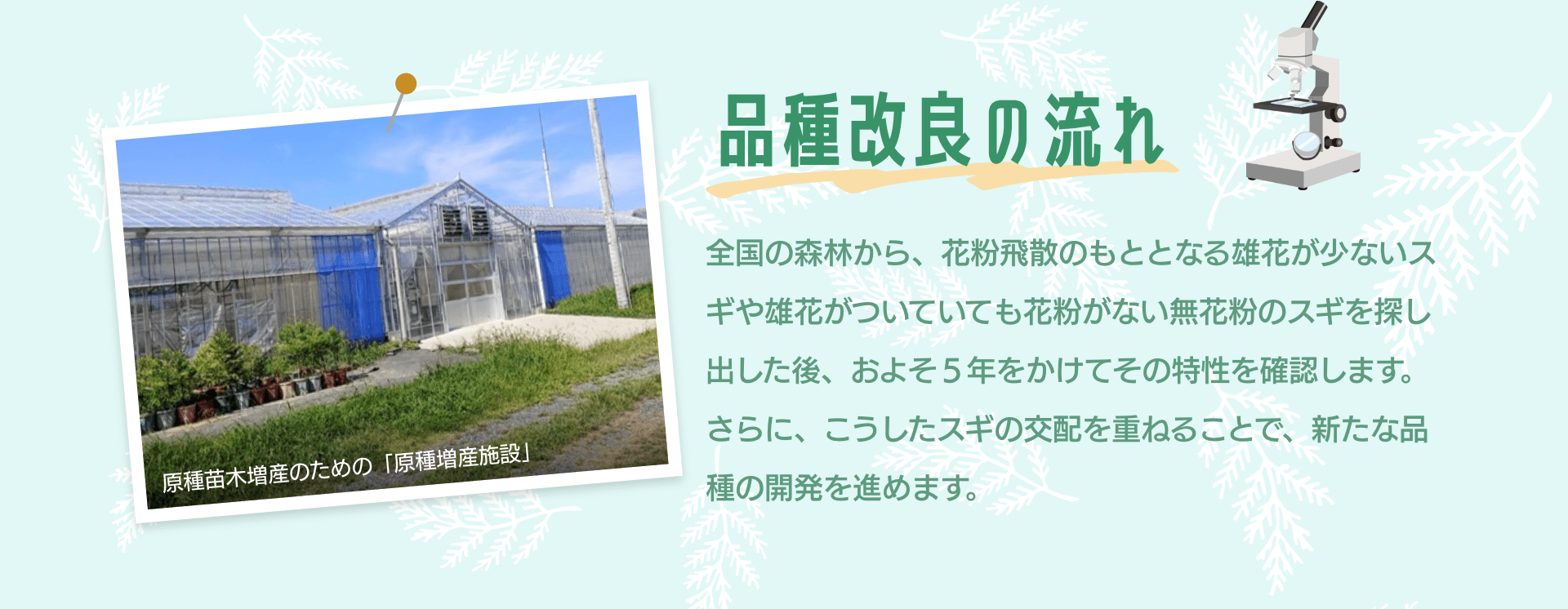
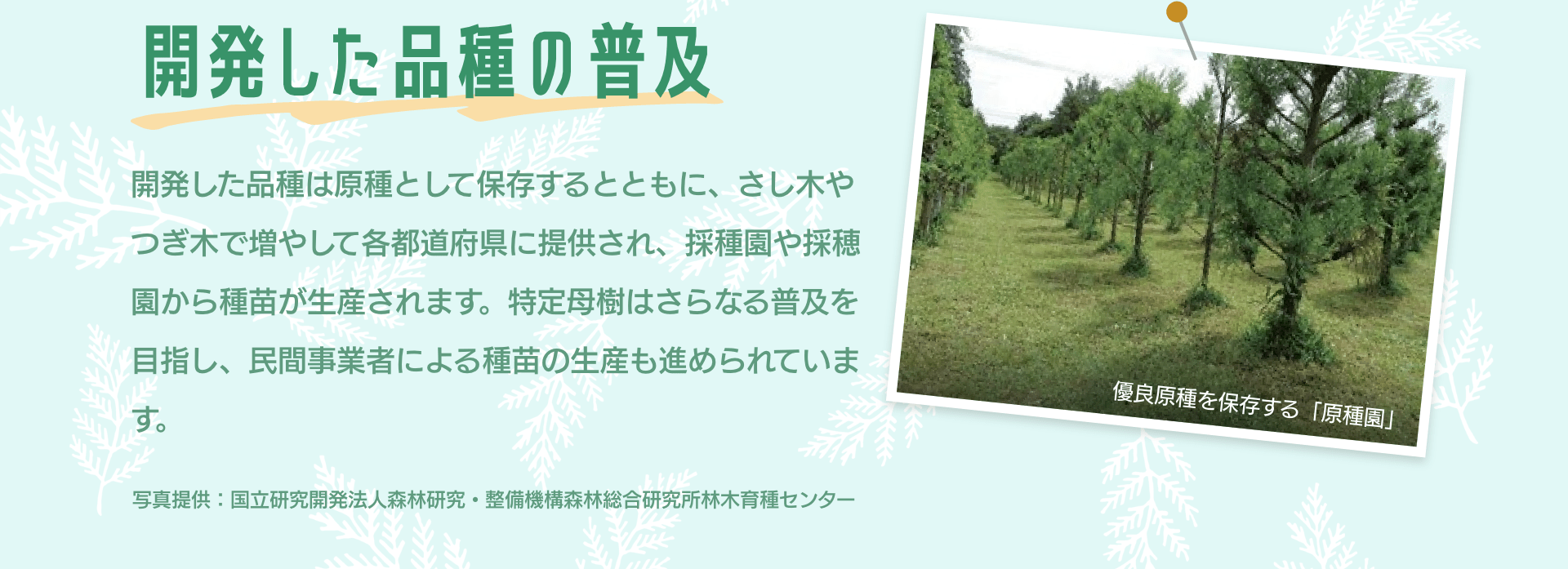
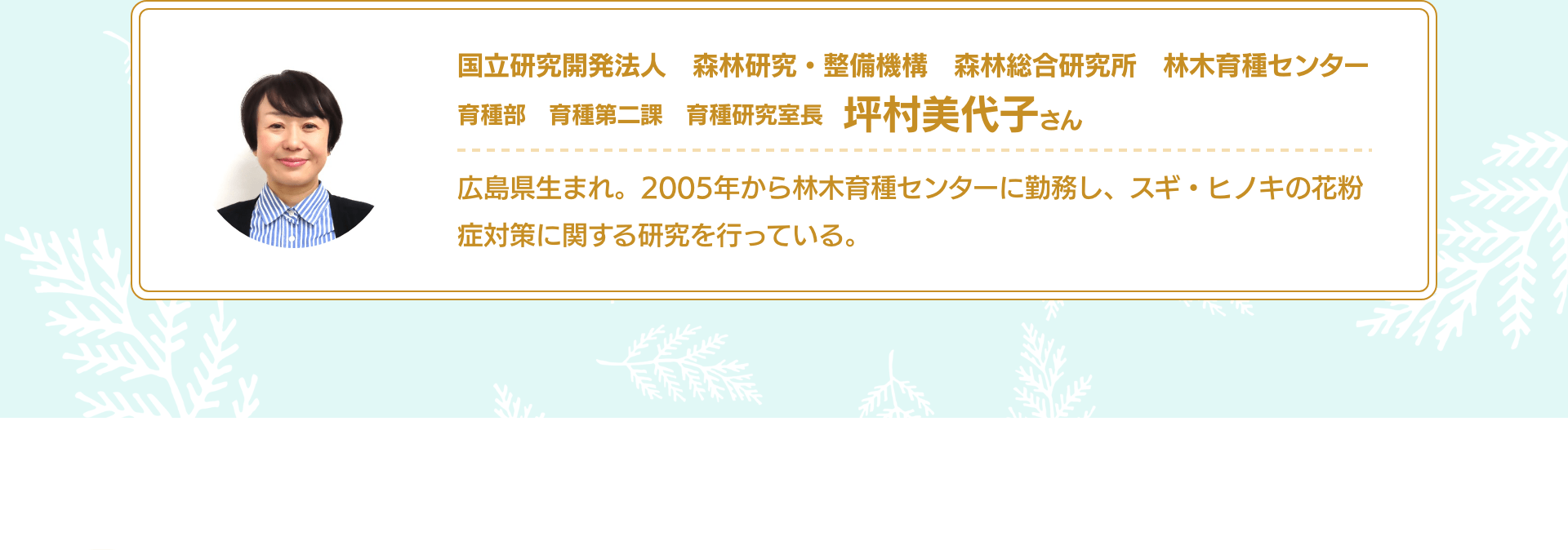

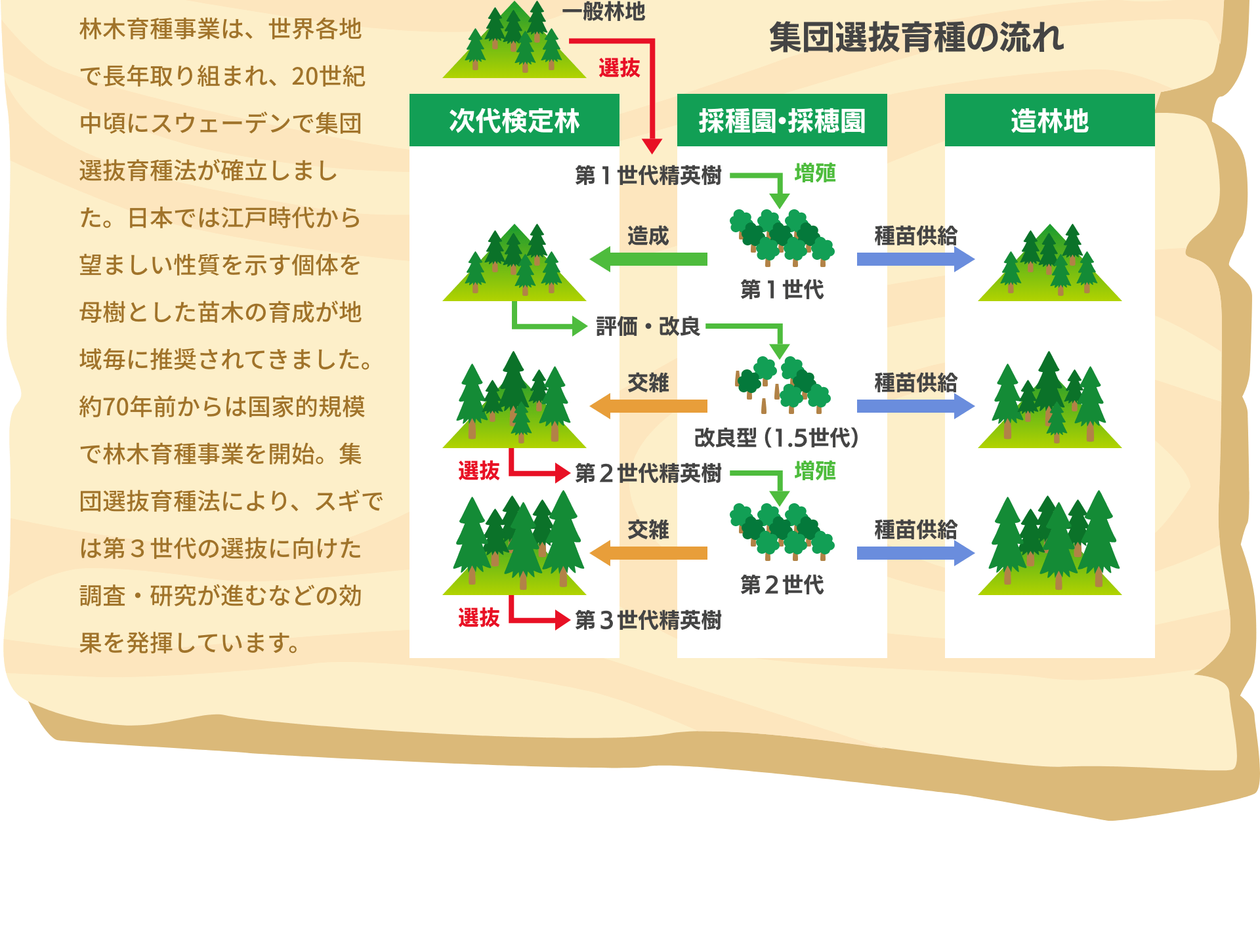
今週のまとめ
花粉の少ないスギを開発するなど
花粉症への対策が進んでいます。
今後、森林資源の循環利用を推進し、
花粉の少ない森林へと
転換することで、
さらなる効果が期待できそうです。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449








