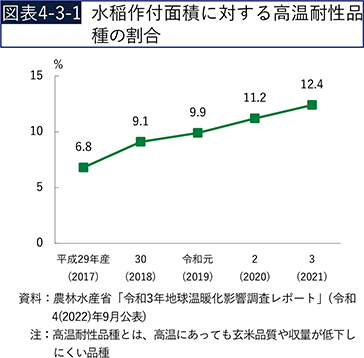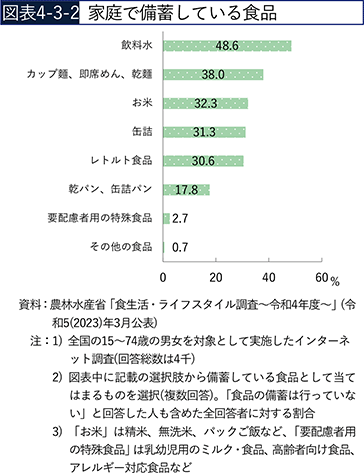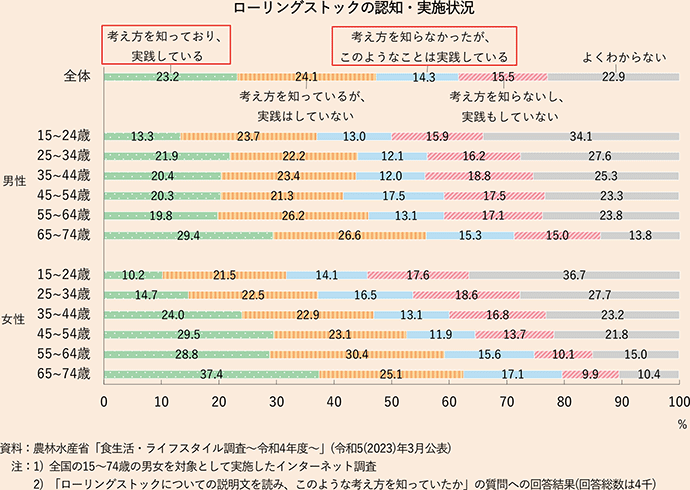第3節 防災・減災、国土強靱化と大規模自然災害への備え
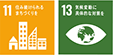
自然災害が頻発化・激甚化する中、被害を最小化していくためには、農業水利施設(*1)等の防災・減災対策を講ずるとともに、災害への備えとして農業保険への加入や気候変動の影響への適応に向けた取組、食品の家庭備蓄の定着等を推進することが重要です。
本節では、防災・減災や国土強靱(きょうじん)化、災害への備えに関する取組について紹介します。
1 用語の解説(1)を参照
(1)防災・減災、国土強靱化対策の推進
(「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく対策を推進)
農林水産省は、平成26(2014)年に閣議決定した「国土強靱化基本計画」(平成30(2018)年変更)を踏まえ、農業水利施設の長寿命化、統廃合を含むため池の総合的な対策の推進等のハード面での対策と、ハザードマップの作成、地域住民への啓発活動等のソフト面での対策を組み合わせた防災・減災対策を推進しています。
(事例)ため池の防災工事により下流域の被害を防止(鳥取県)

鳥取県琴浦町(ことうらちょう)の松谷第一(まつたにだいいち)ため池では、ため池の防災工事により下流域の被害の防止が図られています。
防災重点農業用ため池に指定されている松谷第一ため池は、漏水が確認されたほか、耐震性能が不足していたことにより、豪雨や地震の発生時に決壊する危険性があり、下流域の住宅に浸水被害が生じるおそれがありました。
このため、同県は、平成29(2017)年度から堤体の改修工事を開始し、平成30(2018)年度からは「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」も活用して、令和2(2020)年度に工事を完了しました。この結果、従前確認された漏水が解消されるとともに、耐震性が確保されました。また、24時間雨量331mmを記録した令和3(2021)年7月の豪雨時において、ため池に被害は生じませんでした。
防災工事の実施と併せて、同町では「ため池ハザードマップ」の作成による住民の防災意識の向上を図っており、これらの対策により、ため池下流域の農地や住宅の安全・安心が確保されるとともに、農業経営の安定化に資することが期待されています。
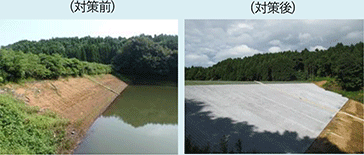
対策工事前後の防災重点農業用ため池
資料:鳥取県
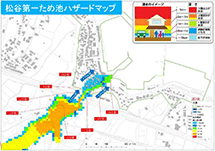
ため池ハザードマップ
資料:鳥取県琴浦町
農業・農村分野では、令和2(2020)年に閣議決定した「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、「流域治水対策(農業水利施設の整備、水田の貯留機能向上、海岸の整備)」、「防災重点農業用ため池の防災・減災対策」、「農業水利施設等の老朽化、豪雨・地震対策」、「卸売市場の防災・減災対策」、「園芸産地事業継続対策」等に取り組んでいます。
また、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に防災・減災、国土強靱化の取組を進めていくことが重要であることを踏まえ、5~10年の中長期を見据えた新たな国土強靱化基本計画について、関係省庁と連携し、令和5(2023)年度の改定に向けた検討を行っています。
このほか、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する措置を講ずる「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法(*1))が令和4(2022)年5月に公布されました。
1 正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」
(2)災害への備え
(農業者自身が行う自然災害への備えとして農業保険等の加入を推進)
自然災害等の農業経営のリスクに備えるためには、農業者自身が農業用ハウスの保守管理、農業保険等の利用等に取り組むことが重要です。
台風、大雪等により園芸施設の倒壊等の被害が多発化する傾向にある中、農林水産省では、農業用ハウスが自然災害等によって受ける損失を補償する園芸施設共済に加え、収量減少や価格低下等、農業者の経営努力で避けられない収入減少を幅広く補償する収入保険(*1)への加入促進を重点的に行うなど、農業者自身が災害への備えを行うよう取り組んでいます。令和3(2021)年度の園芸施設共済の加入率は、前年度に比べ4.3ポイント増加し69.9%となりました。
1 第2章第5節を参照
(農業版BCPの普及を推進)
農業版BCP(*1)は、インフラや経営資源等について、被害を事前に想定し、被災後の早期復旧・事業再開に向けた計画を定めるものであり、農業者自身に経験として既に備わっていることも含め、「見える化」することで、自然災害に備えるためのものです。
農林水産省では、農業版BCPの普及に向け、パンフレットの配布やSNS等の各種媒体での周知のほか、事業の採択時に農業版BCPに取り組む場合にポイントを加算する措置の新設、農業版BCP作成者の事例集の作成・公表等を行っています。
1 Business Continuity Planの略で、災害等のリスクが発生したときに重要業務が中断しないための計画のこと
(事例)農業版BCPを作成し、防災意識の向上や経営課題の解決を推進(埼玉県)


農業版BCPを活用する農業経営者
資料:有限会社金井塚園芸
埼玉県東松山市(ひがしまつやまし)の有限会社金井塚園芸(かないづかえんげい)では、大雪による被害に遭遇したことを契機に、農業版BCPの作成に取り組み、防災意識の向上や日頃からの経営改善に活用しています。
同社では、ポットの宿根草(しゅっこんそう)を中心に、年間約500品種のガーデニング用花苗を約1ha(ハウス20棟)の規模で栽培しています。
同社では、大雪や台風で被害を受けた際に、限られた人員・時間・資金を活用して、いかに素早く業務を継続・再開するか、また、不足している資源をいかに短時間で調達するかといった課題に直面し、対応に苦慮した経験がありました。
このため、同社では、令和3(2021)年に農業版BCPを策定し、緊急時においても限られた経営資源の中で状況に応じて柔軟に判断しながら行動できるよう、緊急時への備えを充実させるとともに、危険箇所の特定や整理整頓の徹底等、経営課題の解決にもつなげる取組を進めています。
代表取締役の金井塚良行(かないづかよしゆき)さんは「農業版BCPの作成により、被災して追い込まれる前に落ち着いた状況で災害に備えることができ、災害が発生しても経営品目の変更等により、上手く立ち回れる自信がつきました。」とその効果を強調しています。
(気候変動の適応策について、新たな適応技術の開発・導入を推進)
農業生産は、一般に気候変動の影響を受けやすく、各品目で生育障害や品質低下等、気候変動によると考えられる影響が見られています。
このため、農林水産省では、温暖化による影響等のモニタリングを行い、地球温暖化影響調査レポートとして取りまとめるとともに、適応策(*1)に関する情報の発信を行っています。
また、我が国においては、高温等の影響を回避・軽減する適応技術や高温耐性品種等の導入等、適応策の生産現場への普及指導や新たな適応技術の導入実証等の取組が行われています。
令和4(2022)年9月に公表した調査によると、水稲では、高温耐性品種の作付割合が年々増加しており、令和3(2021)年産は12.4%となっています(図表4-3-1)。今後とも、「農林水産省気候変動適応計画」に基づき、気候変動に適応する生産安定技術・品種の開発・普及等を推進する取組を進めていくこととしています。
1 第2章第10節を参照
(「食品の備蓄は行っていない」との回答が約4割)
今後起こり得る災害への備えとして、国民一人一人が、日頃から食料や飲料水等を備蓄しておくことが重要です。
令和5(2023)年3月に公表した調査によると、家庭で何かしらの食品の備蓄を行っている人の割合は63.0%、「食品の備蓄は行っていない」と回答した人の割合は37.1%となりました。また、備蓄している食品の種類は、「飲料水」が約5割で最も多く、次いで「カップ麺、即席めん、乾麺」、「お米(精米、無洗米、パックご飯など)」、「缶詰」、「レトルト食品」の順となっています(図表4-3-2)。
大規模な自然災害等の発生に備え、家庭における備蓄量は、最低3日分から1週間分の食品を人数分備蓄しておくことが望ましいとされています。
このため、農林水産省では、「災害時に備えた食品ストックガイド」やWebサイト「家庭備蓄ポータル」等による周知を行うとともに、食品の家庭備蓄の定着に向けて、企業や地方公共団体、教育機関等と連携しながら、ローリングストック等による日頃からの家庭備蓄の重要性とともに、乳幼児や高齢者、食物アレルギー等への配慮の必要性に関する普及啓発を行っています。また、一人暮らしの人が家庭備蓄に取り組むための、単身者向け「災害時にそなえる食品ストックガイド」を令和4(2022)年4月に公表しました。
(コラム)約4割の人が備蓄食品の「ローリングストック」を実践
ローリングストックは、ふだんから食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭に備蓄されている状態を保つ方法です。
令和5(2023)年3月に公表した調査によると、ローリングストックの認知・実施状況について、「考え方を知っており、実践している」と回答した人は約2割となっており、「考え方を知らなかったが、このようなことは実践している」と回答した人と合わせると、約4割が実践している状況です。
また、年齢階層別に見ると、男性は大きな差は見られませんが、女性は年齢階層が上がるとともに「考え方を知っており、実践している」の割合が高まり、65~74歳で最も高くなっています。
備蓄食品としては、災害時のみ使用する災害食だけでなく、日常で使用し、災害時にも使えるものをローリングストックとしてバランス良く備えておくことが重要です。食品の家庭備蓄を非日常のものと考えるのではなく、日常の一部としてふだんから無理なく取り入れていくことが、備蓄の継続につながります。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883