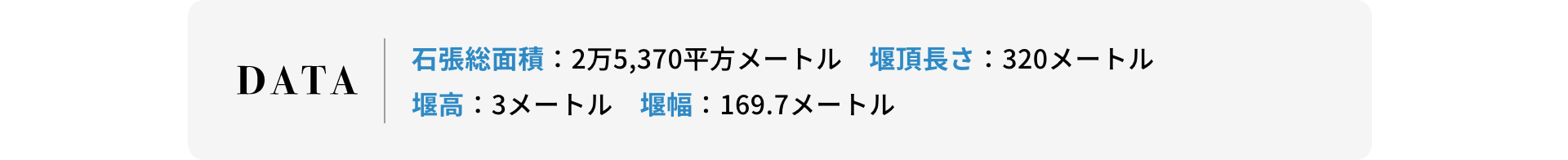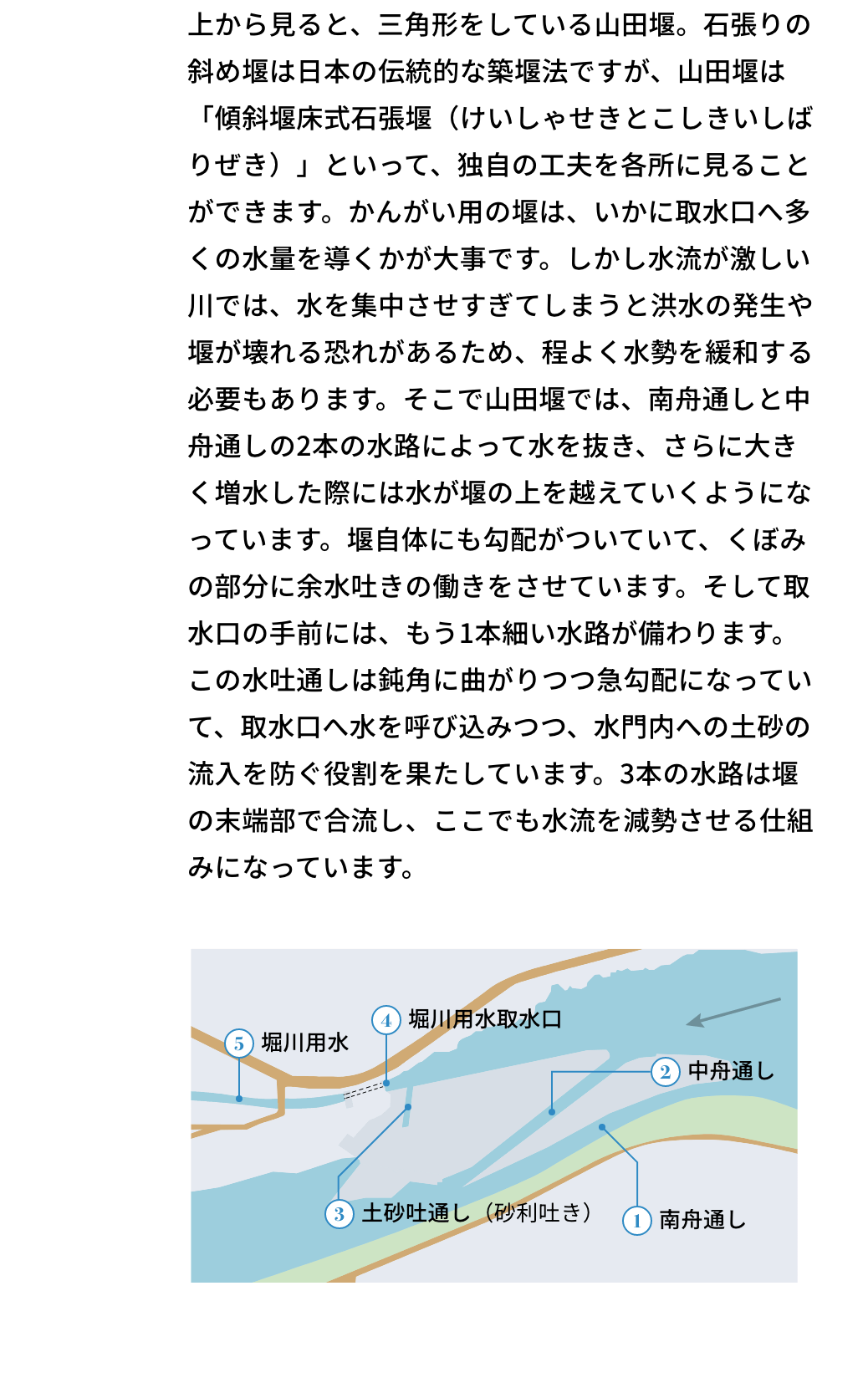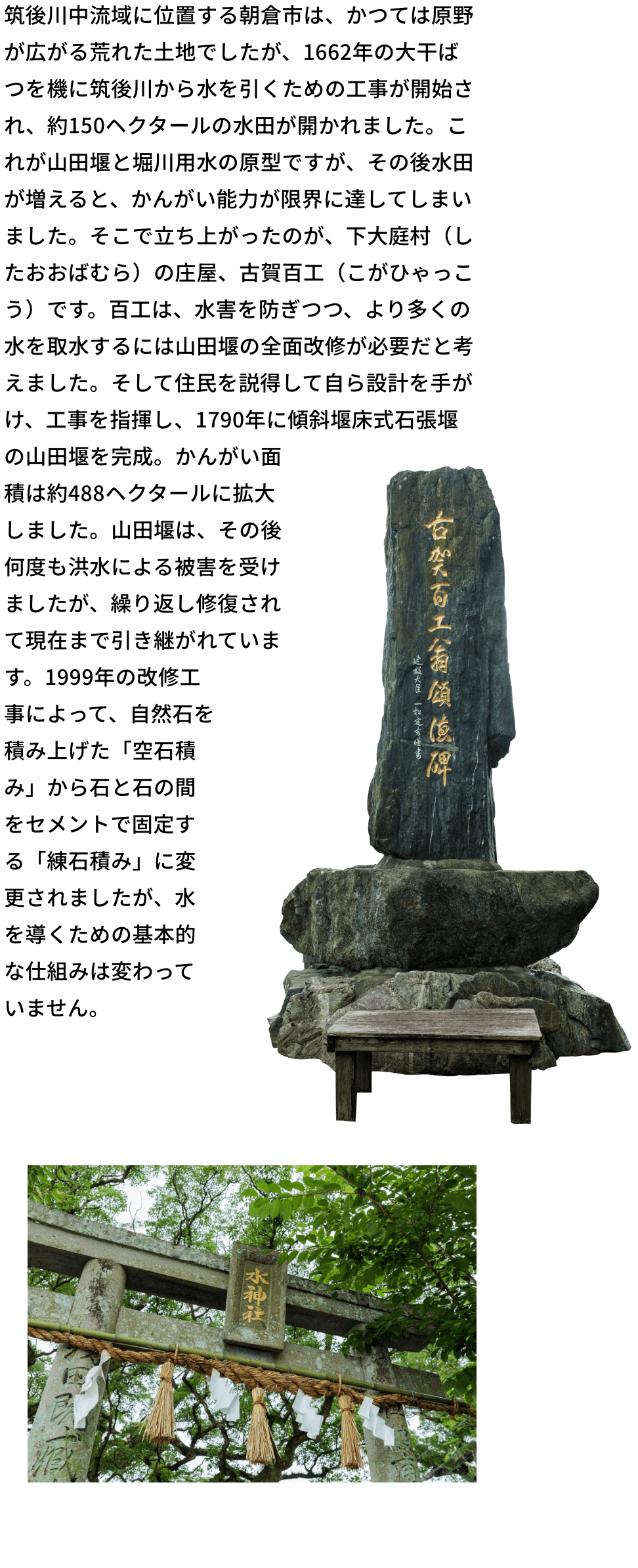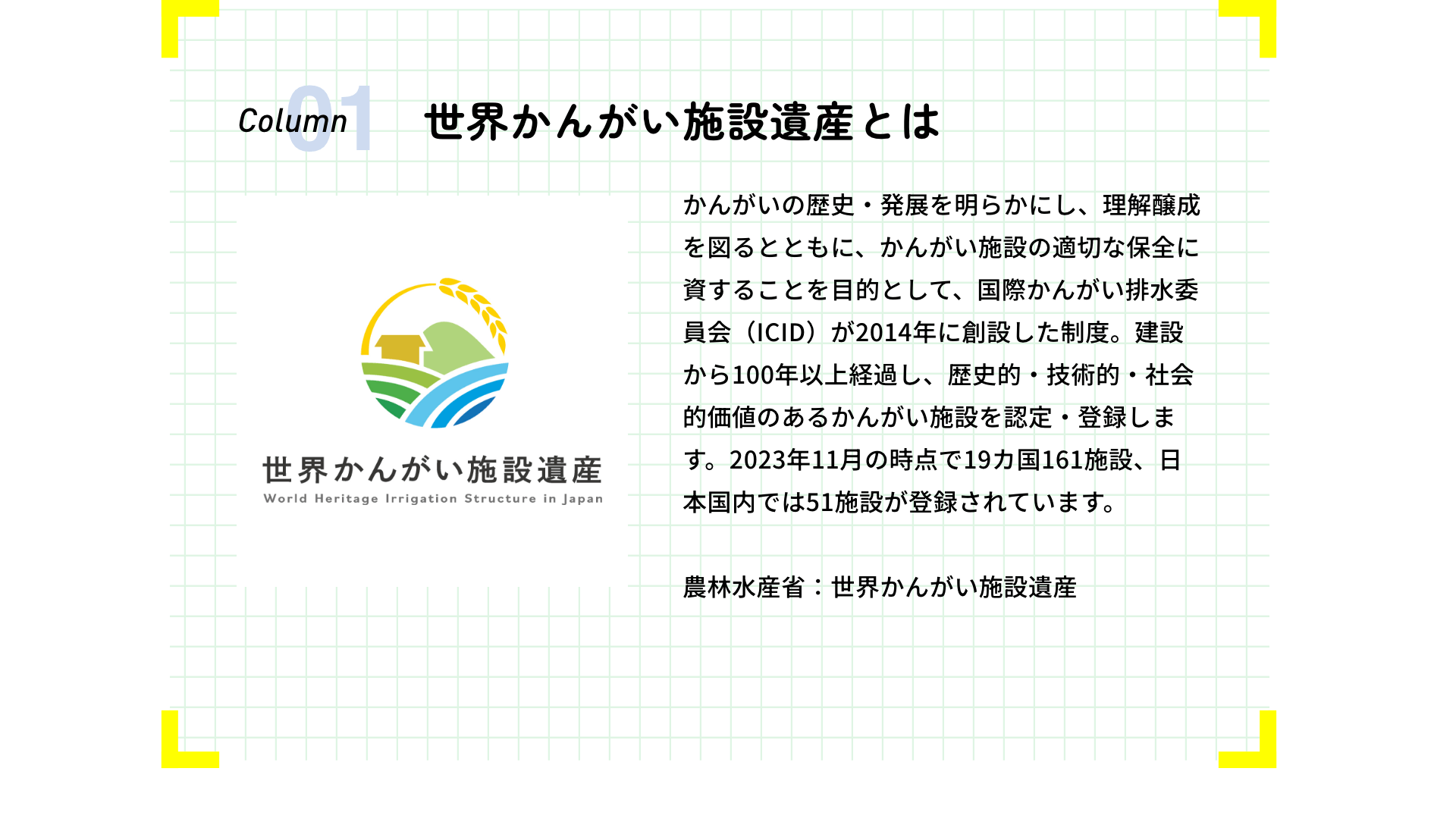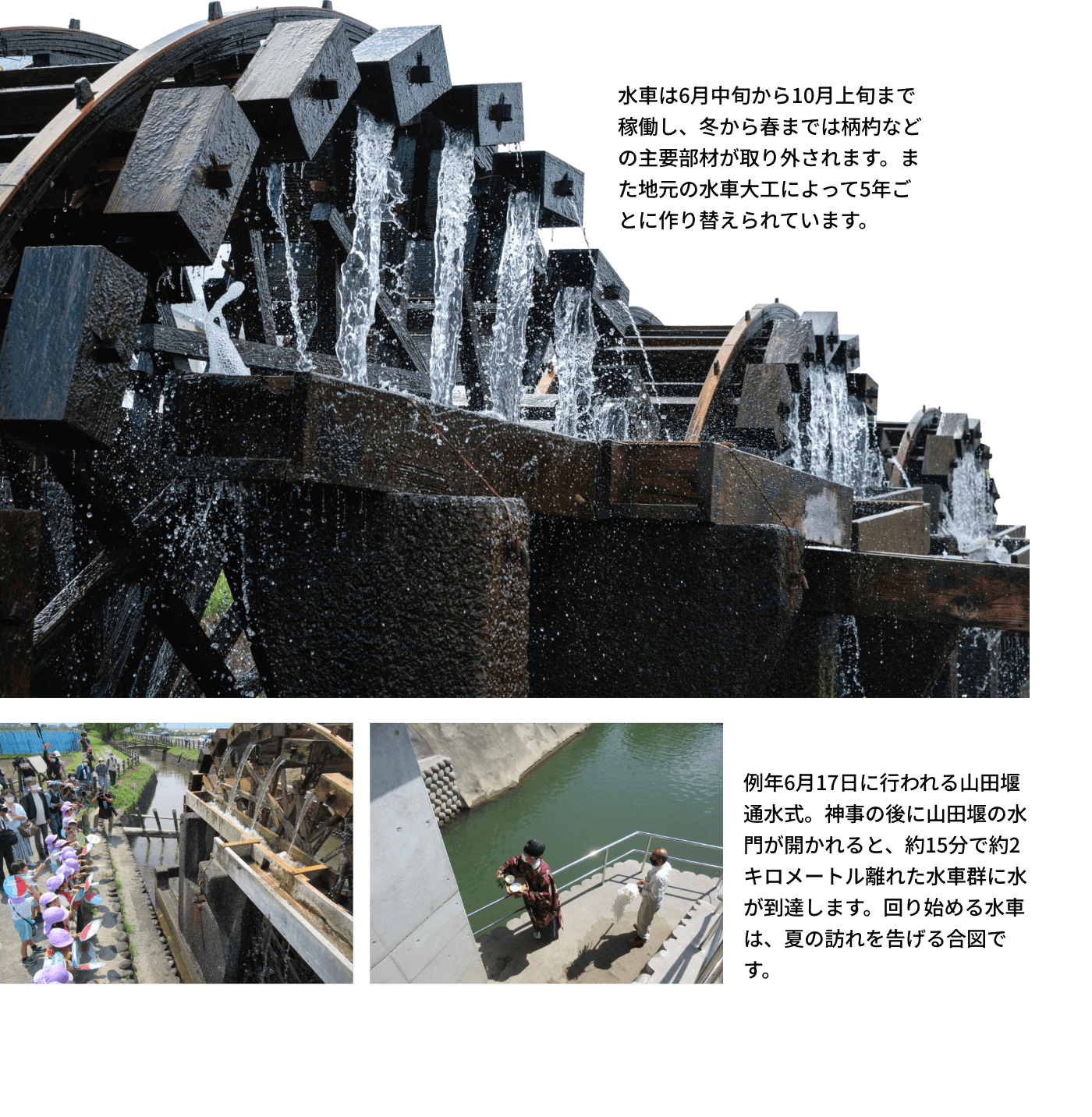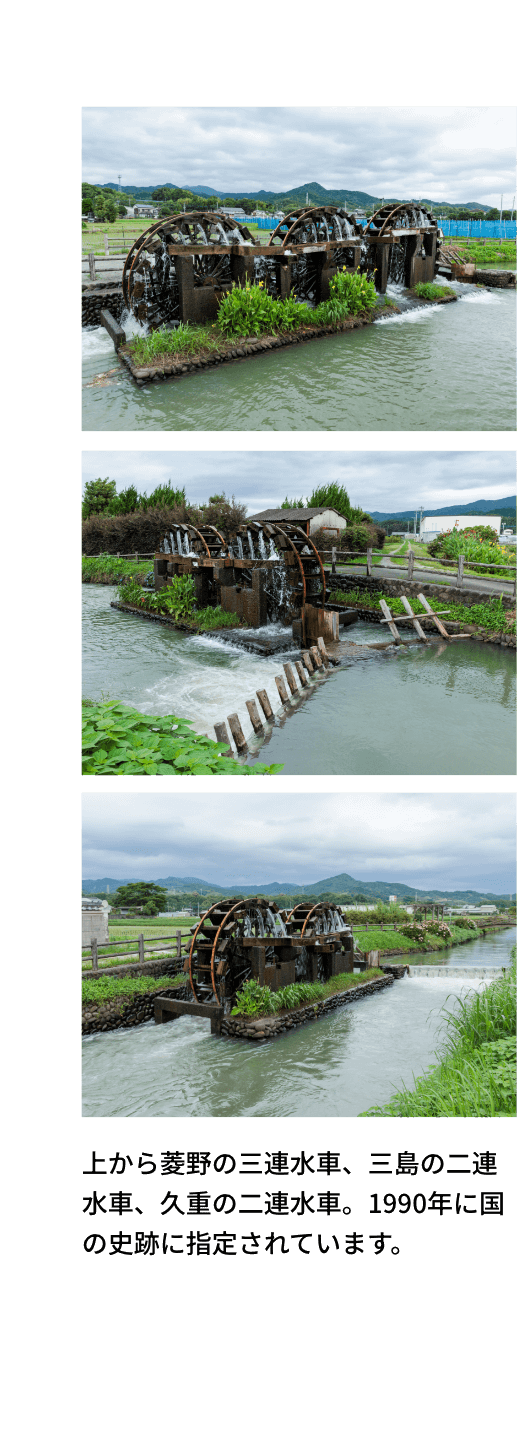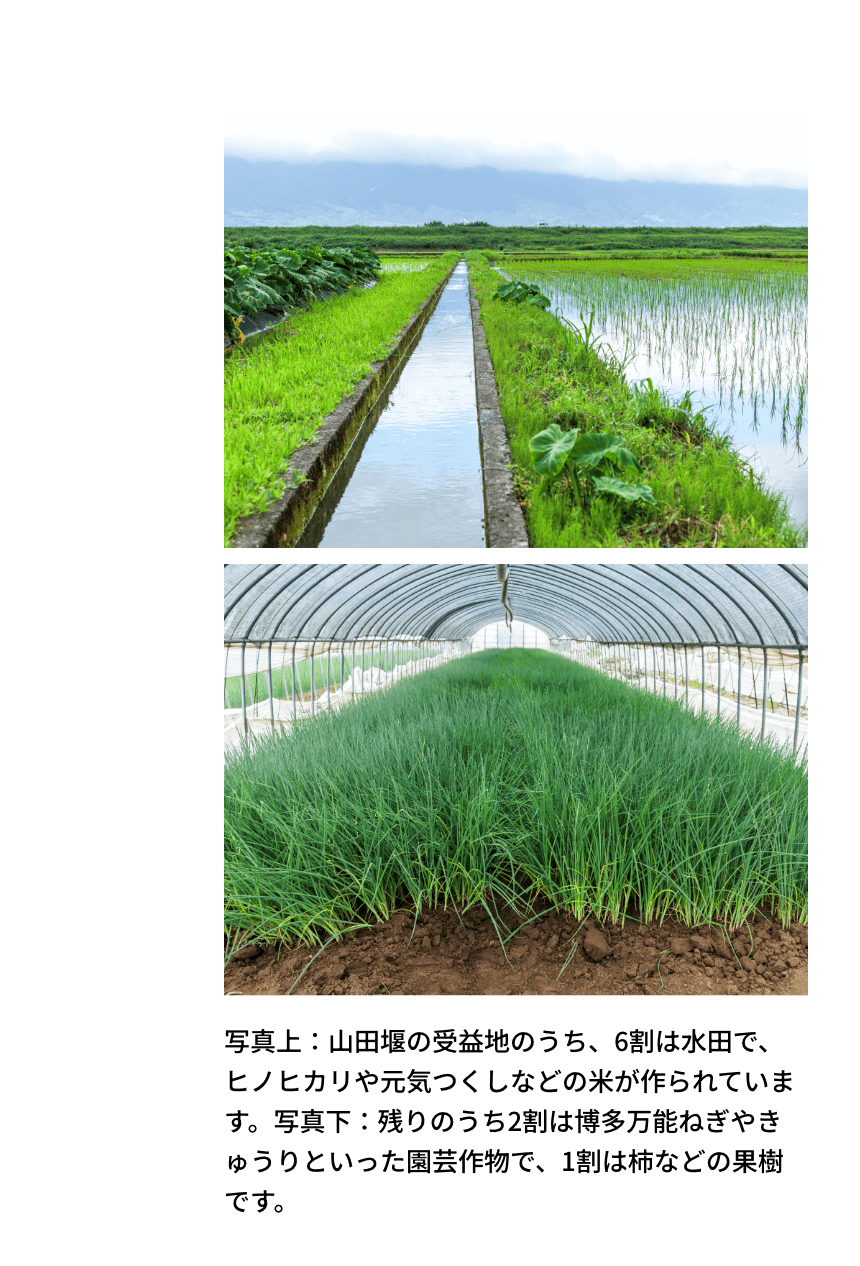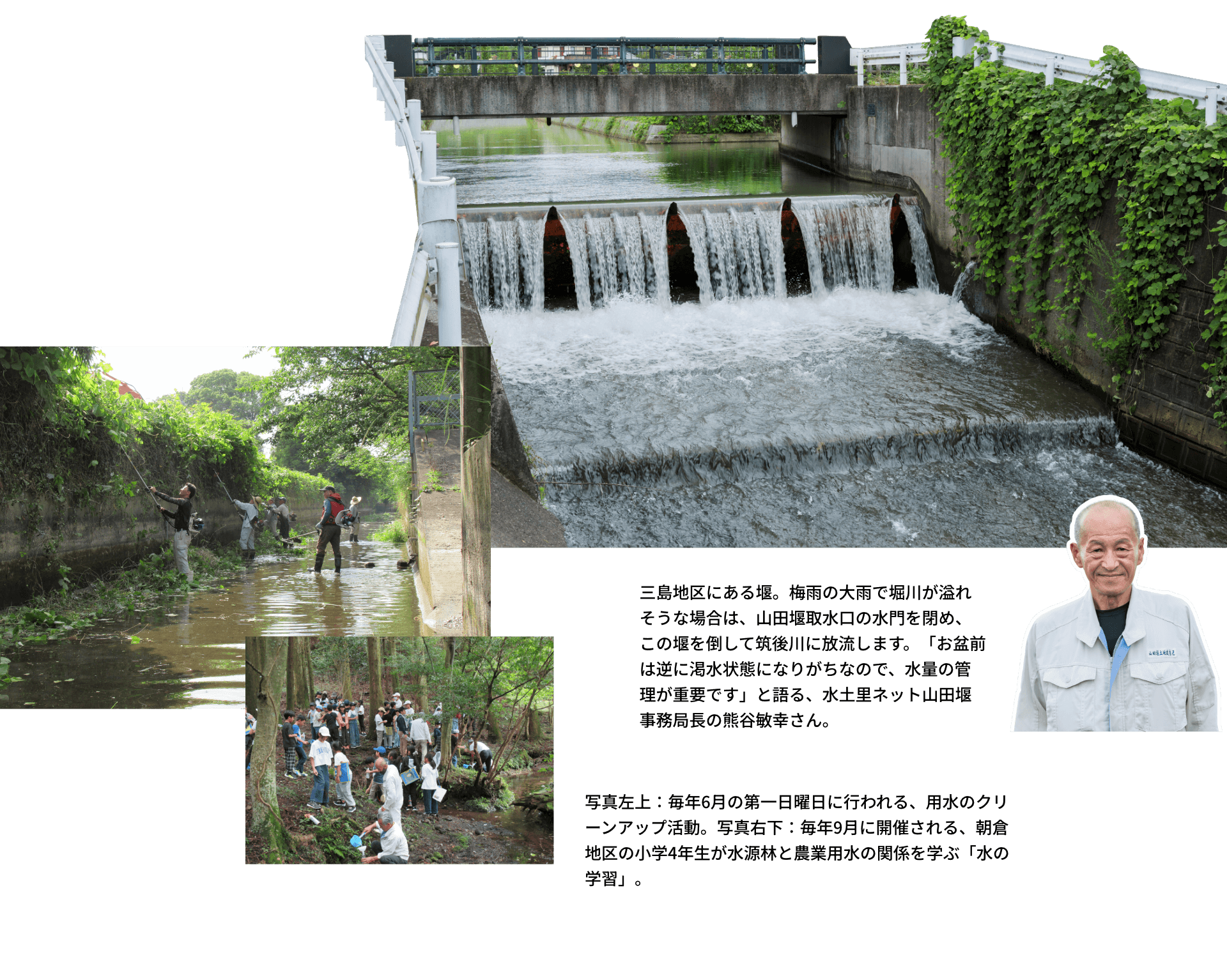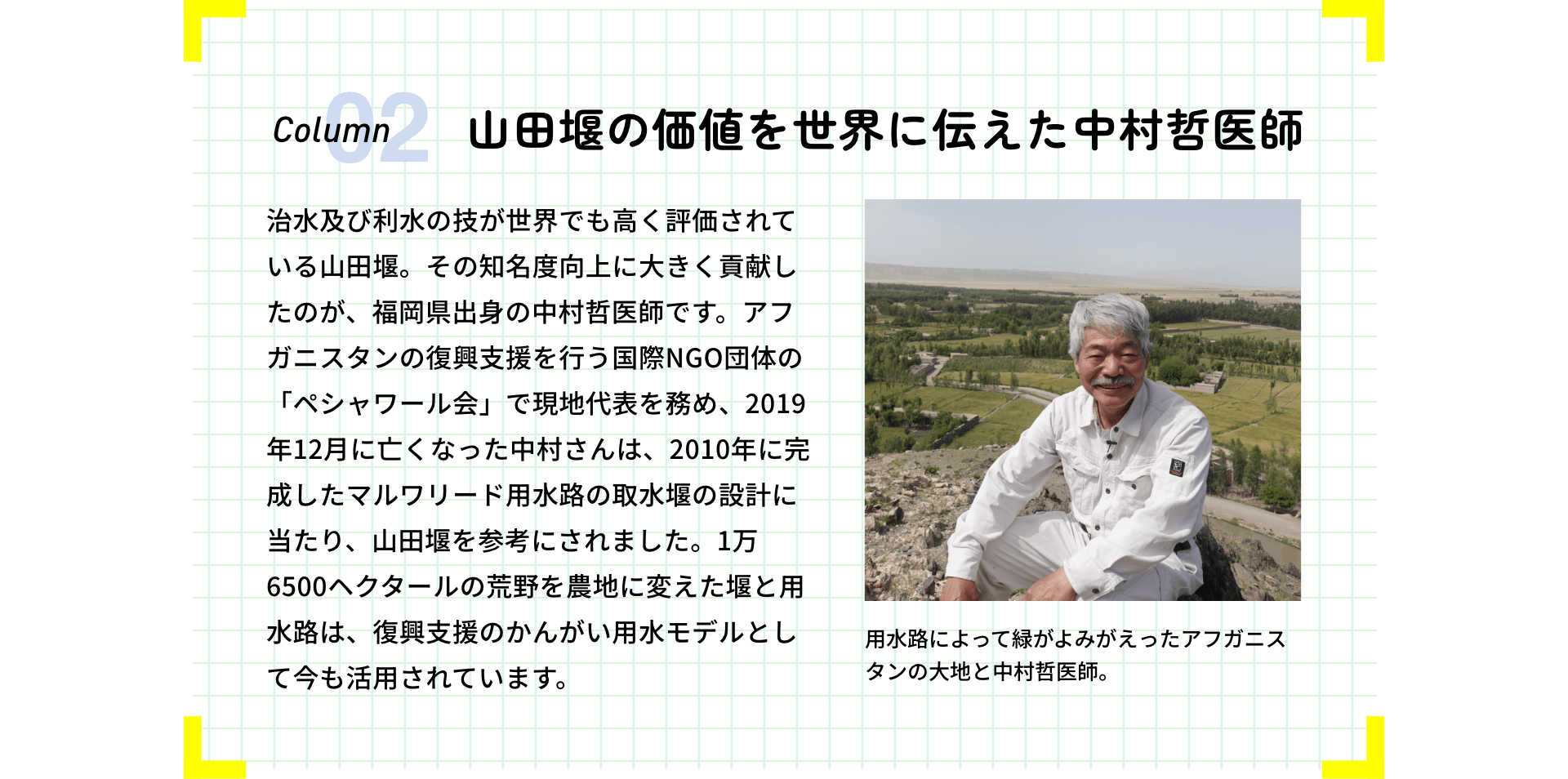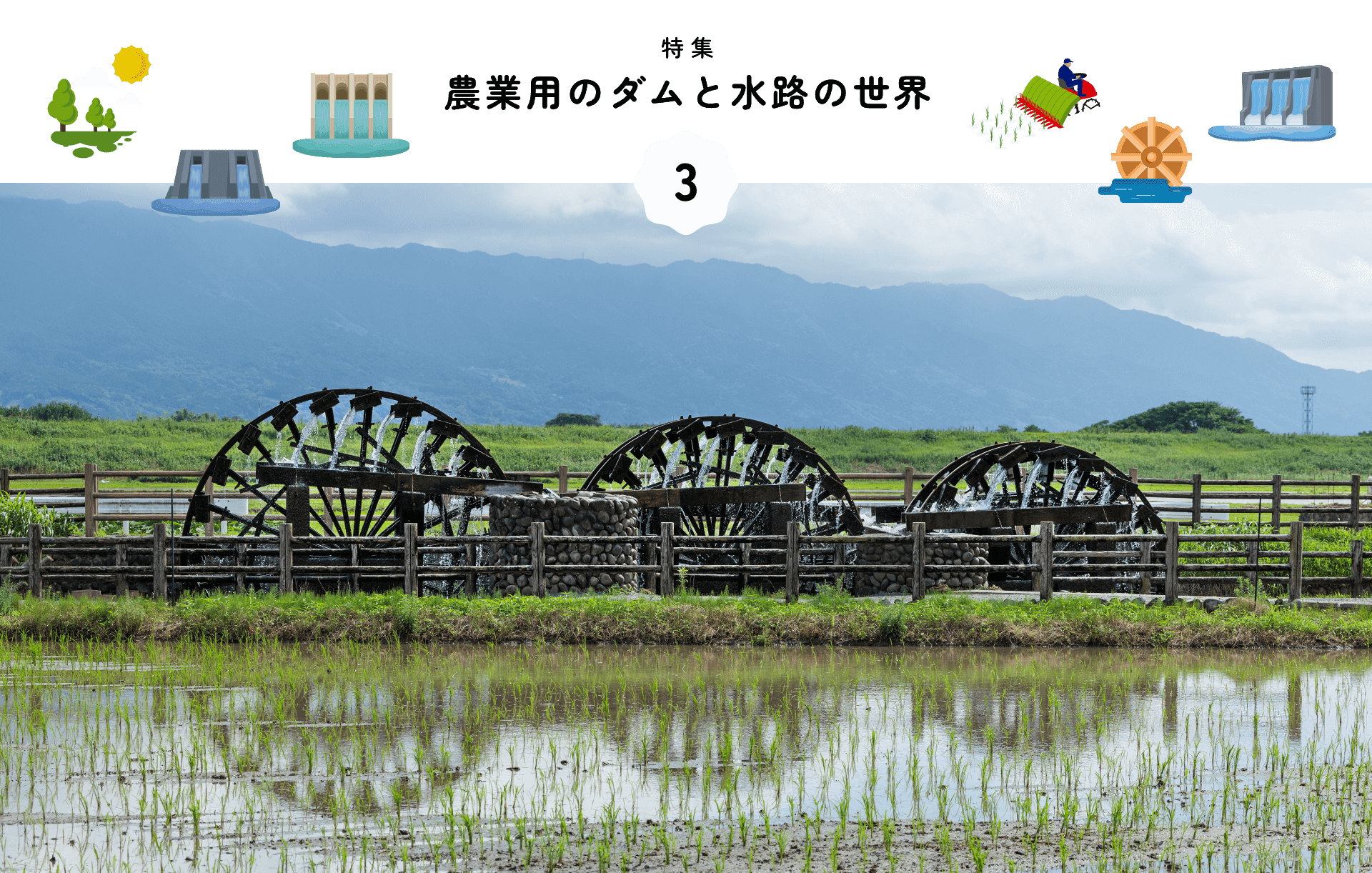

人類の文明の発展と密接に関わり、長い歴史を持つかんがい技術。
かんがい施設には、はるか昔に造られ、今なお水を届け続けている水路や取水堰が
数多くあります。今回は、そんな歴史的価値のあるかんがい施設を紹介します。




磐井川上流部の大〆切(おおしめきり)頭首工を水源に、一関市と平泉町を流れる総延長64キロメートルの3本の疎水の総称。1100年代後半に藤原秀衡の家臣、照井太郎高春が穴堰を開削し、子孫の照井太郎高安が完成させた。



「暴れ天竜」と呼ばれた天竜川の治水・利水のため、徳川家康のもと、家臣の伊奈忠次及び平野重定が手がけ、1590年に完成した用水路。治水と利水を一体的に行う革新的なかんがい工事の先駆け。



佐久市浅科(あさしな)の台地を新田開発するために、市川五郎兵衛が私財を投じて江戸初期の1631年に完成させた、全長20キロメートルに及ぶ用水路。1960年代に改修工事が行われ、「つきせぎ(土の樋)」も近代的な水路に生まれ変わっている。



矢作(やはぎ)川上流から取水し、安城市を中心に西三河一帯の農地を潤す大用水。江戸時代後期に豪農の都築弥厚(つづきやこう)が計画し、1880年に主要な幹線が完成した。「日本三大農業用水」のひとつ。



櫛田(くしだ)川から取水し、中流域右岸の河岸段丘面に導水する全長28キロメートルの用水路。1823年に完成したもので、硬い岩盤をくり抜いた素掘りの隧道や切り通し部分が今も残されている。



関川から取水し、上越市及び妙高市の水田に用水を供給する、全長約26キロメートルの用水路。1500年代後期から地元の農民たちによって3期130年にわたって掘り継がれ、1781年に全線通水した。



常願寺川の洪水を防ぐため、明治政府が招いたオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケの指導によって常願寺川左岸の12本の用水路の取水口を統合し、1893年に完成した。日本初の大規模な合口(ごうぐち)化とされる。



樫井川から取水し、十二谷池へと流れる全長約2.9キロメートルの用水路。1300年代から存在したと考えられ、貴族の荘園「日根荘(ひねのしょう)」の開発において重要な役割を果たした。井川用水や十二谷池は国の史跡として指定されている。



延長 26.3 キロメートルの「淡河(おうご)川疏水」と、10.8 キロメートルの 「山田川疏水」を合わせた呼称。水不足の印南野(いなみの)台地に水を引くため に計画された 1771 年の山田川疏水構想以来、完成まで約 150 年もの歳月を要した。



倉安川と百間川、倉安川吉井水門で構成。かんがいのために1679年に築造された倉安川は、吉井川と旭川を結ぶ延長19.9キロメートルの水路。百間川は、旭川の洪水を防ぐために1687年に築造された延長12.9キロメートルの放水路。



水不足に悩む白糸台地一帯に水を送るため、矢部の惣庄屋であった布田保之助(ふたやすのすけ)によって1855年に造られた農業用水路。石造アーチ水路橋の通潤橋は、2023年に土木構造物としては全国初の国宝に指定された。
今週のまとめ
歴史あるかんがい施設は農業用水を送り届けるだけでなく、
先人の培った技術や歴史、文化を今に伝える役目も果たし、
地域の人々にとっての貴重な財産、シンボルとなっています。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449