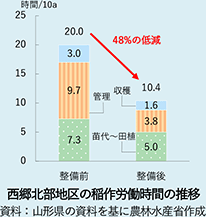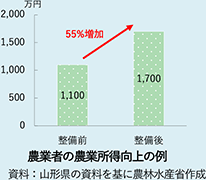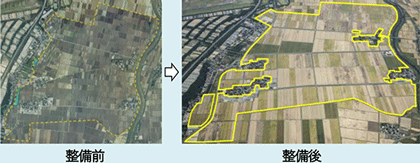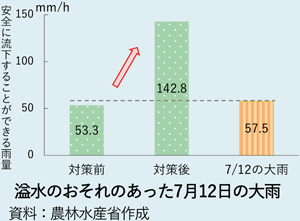第6節 農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備

我が国の農業の競争力を強化し成長産業とするためには、令和3(2021)年3月に策定された土地改良長期計画を踏まえ、農地を大区画化するなど農業生産基盤を整備し、良好な営農条件を整えるとともに、大規模災害時にも機能不全に陥ることのないよう、国土強靱(きょうじん)化の観点から農業水利施設(*1)の長寿命化やため池の適正な管理・保全・かい廃を含む農村の防災・減災対策を効果的に行うことが重要です。
本節では、水田の大区画化・汎用化(*2)等の整備状況、農業水利施設の保全管理、流域治水の取組等による農業・農村の防災・減災対策の実施状況等について紹介します。
1、2 用語の解説3(1)を参照
(1)農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
(大区画整備済みの水田は11%、畑地かんがい施設整備済みの畑は25%)
我が国の農業の競争力・産地収益力を強化するため、農林水産省では、水田の大区画化や汎用化・畑地化、畑地かんがい施設の整備等の農業生産基盤整備を実施し、担い手への農地の集積・集約化(*1)、高収益作物への転換、産地形成等に取り組んでいます。
令和2(2020)年3月時点における水田の整備状況を見ると、水田面積全体(238万ha)に対して、30a程度以上の区画整備済み面積は67%(159万ha)、その中でも、担い手への農地の集積・集約化や生産コストの削減に資する50a以上の大区画整備済み面積は11%(27万ha)となりました。また、暗渠(あんきょ)排水の設置等により汎用化が行われた水田面積は47%(111万ha)となりました(図表2-6-1、図表2-6-2)。汎用化した水田では野菜等の高収益作物への転換が可能となっています。
また、畑の整備状況については、畑面積全体(199万ha)に対して、畑地かんがい施設の整備済み面積は25%(49万ha)、区画整備済み面積は64%(129万ha)となりました(図表2-6-3)。
1 用語の解説3(1)を参照
(事例)基盤整備を契機とした法人設立と高収益作物で所得向上(山形県)
山形県鶴岡市西郷北部(つるおかしにしごうほくぶ)地区では、水田の多くが10a程度の区画で、また、農道は狭く、暗渠排水も整備されていないことが効率的な農作業の支障となっていました。このため、平成21(2009)年度から令和元(2019)年度にかけて、圃場(ほじょう)の大区画化、用排水路のパイプライン化等の基盤整備を実施し、1ha以上に大区画化された水田が9割を超え、大型農機の導入や直播(ちょくはん)栽培(*)が可能となりました。
基盤整備を契機に、農地中間管理機構を活用し四つの法人に9割の農地を集積・集約したことにより、労働時間の大幅削減を実現しました。同地区では、生み出された余剰時間を活用してメロン等の高収益作物の栽培に取り組んでおり、基盤整備が農業者の所得向上に寄与していることがうかがえます。
用語の解説3(1)を参照
(担い手への農地の集積・集約化の加速等を図るための改正土地改良法が成立)
平成30(2018)年度に創設した農地中間管理機構(*1)関連農地整備事業では、同機構が借り入れている農地において、農業者の申請、同意、費用負担によらずに都道府県が行う区画整備等を支援しています。担い手への更なる農地の集積・集約化の加速等を図るため、「土地改良法の一部を改正する法律」が令和4(2022)年3月に成立しました。これにより、同事業の対象として農業用用排水施設、暗渠排水等の整備を追加しました。
1 第2章第4節を参照
(スマート農業の実装を促進するための農業生産基盤整備を推進)
農作業の省力化・高度化を図るため、農林水産省は自動走行農機の効率的な作業に適した農地整備、ICT(*1)水管理施設の整備、パイプライン化等、スマート農業を実装する上で必要な農業生産基盤整備を推進しています。
令和7(2025)年度までに着手する基盤整備地区のうち、スマート農業の実装を可能とする基盤整備を行う地区の割合を約8割以上とすることを目標(*2)としており、令和3(2021)年度は、自動走行農機を導入・利用するための農地の大区画化やターン農道(*3)の整備、遠隔操作・自動制御により水管理を行うための自動給水栓、地下水位制御システムの整備等のスマート農業に資する基盤整備を行っています。
1 用語の解説3(2)を参照
2 新たな土地改良長期計画(令和3(2021)年3月閣議決定)のKPI
3 圃場外で農業機械が旋回できるように設けたスロープであり、適切に配置することにより自動走行農機での旋回も可能となることが実証
(事例)スマート農業導入に資する基盤整備により新規就農が増加(北海道)
北海道鷹栖町(たかすちょう)は小区画で排水不良の水田地帯でしたが、基盤整備により水田を大区画化するとともに、地下水位制御システムを導入し、営農の大幅な省力化を実現しました。基盤整備を契機に、令和元(2019)年からは自動操舵(そうだ)田植機の導入やドローンによる生育管理が試験導入され、自動操舵による作業ロスの縮減や、新規就農者(*)であっても熟練者と同じ水準で農業機械の操作が可能になるなど、農作業の更なる省力化が実現しました。くわえて、削減された労働時間の活用により、きゅうりやトマト等の高収益作物の生産も拡大しました。
基盤整備に伴い新規就農者も増加しており、事業開始から令和3(2021)年度までの間に延べ34人が就農しました。鷹栖町は基盤整備と並行して、将来の担い手を育成するため、農業交流センター「あったかファーム」を設立し、新規就農者の研修や、スマート農業の試験導入を行っています。
同地区では、基盤整備がスマート農業の実装や新規就農者の増加に寄与していることがうかがえます。
用語の解説2(6)を参照
(農業生産基盤整備により「みどりの食料システム戦略」の推進を下支え)
令和3(2021)年5月に策定された「みどりの食料システム戦略(*1)」では有機農業の拡大、農林水産業のCO2ゼロエミッション化等を目指しているところ、農地の大区画化、草刈り労力を軽減する畦畔(けいはん)整備等は、労働時間を短縮し、慣行農業に比べて労力を要する有機農業や、化学農薬、化学肥料を減らした環境保全型農業の取組に資するものとなっています。
また、農林水産業のCO2ゼロエミッション化に関しても、農業用水を活用した小水力発電等の再生可能エネルギーの導入(*2)や、電力消費の大きなポンプ場等農業水利施設の省エネルギー化の取組は、同戦略の推進の下支えとなっています。

小水力等再生可能エネルギー導入の推進(農業水利施設
等を活用した小水力発電施設導入の手続き・事例集)
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/
shousuiryoku/rikatuyousokushinn_teikosuto.html
令和3(2021)年9月には、農林水産省は再生可能エネルギーの導入に向けて、施設管理者や民間事業者が小水力発電施設を農業水利施設に導入する上で必要となる手続を取りまとめた「農業水利施設等を活用した小水力発電施設導入の手続き・事例集」を作成・公表しています。
2 第3章第3節を参照
(農業・農村における情報通信環境の整備を推進)
データを活用した農業(*1)の推進、農業水利施設等の管理の省力化・高度化や地域の活性化を図るため、農業・農村における情報通信環境の整備を進めているところ、令和3(2021)年度は、農林水産省の事業を活用して、全国13地区において、光ファイバ、無線基地局等の情報通信環境の整備に向けた調査や計画策定が開始されました。

農業農村における情報通信環境整備のガイドライン
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/
jouhoutsuushin/jouhou_tsuushin.html#anka3
また、令和4(2022)年3月には、「スマート農業実証プロジェクト」等の調査(*2)の成果を踏まえ、地方公共団体や農協、土地改良区等の農業者団体等が農業・農村における情報通信環境整備に取り組む際の参考となるよう、農林水産省は調査計画、整備、管理等に当たっての基本的な考え方やポイント等を取りまとめたガイドラインを策定・公表しました。
1 第2章第8節を参照
2 ローカル5G通信を活用したロボットトラクタやロボット茶摘採機の無人自動走行等の実証を、北海道岩見沢市、山梨県山梨市、鹿児島県志布志市で、ICTを活用したため池や農業用用排水路の監視・遠隔操作等の実証を、静岡県袋井市、兵庫県神戸市で実施
(2)農業水利施設の戦略的な保全管理
(老朽化が進む農業水利施設を計画的、効率的に補修・更新)
基幹的水路(*1)や基幹的施設(*2)(ダム、取水堰(しゅすいせき)等)等の基幹的農業水利施設の整備状況は、令和2(2020)年3月時点で、基幹的水路が5万1,472km、基幹的施設が7,656か所となっており、これらの施設は土地改良区等が管理しています。
基幹的農業水利施設の相当数は、戦後から高度成長期にかけて整備されてきたことから、老朽化が進行しており、標準耐用年数を超過している施設は、再建設費ベースで5兆6千億円であり、全体の28%を占めています。さらに、今後10年のうちに標準耐用年数を超過する施設を加えると8兆4千億円であり、全体の42%を占めています(図表2-6-4)。
また、令和2(2020)年度における、経年劣化やその他の原因による農業水利施設(基幹的農業水利施設以外も含む。)の漏水等の突発事故は、依然として高い水準となっています(図表2-6-5)。
このような状況の中、農林水産省は、農業水利施設の老朽化によるリスクを踏まえた点検、機能診断、監視等により、予防保全も含めた補修・更新等の様々な対策工法を比較検討した上で、適切な対策を計画的かつ効率的に実施するストックマネジメント(*3)を推進することで、施設の長寿命化とライフサイクルコスト(*4)の低減を図っています。これらの対策の結果、基幹的農業水利施設のうち施設機能が安定している施設の割合については、令和2(2020)年度の目標を50%としていたところ、同年度末時点で52%となりました。また、更新が早期に必要なことが判明している基幹的農業水利施設については、令和7(2025)年度までに全ての施設において補修・更新等の対策に着手することを新たな目標(*5)としています。

農業水利施設のストックマネジメント
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane/
1 農業用用排水のための利用に供される末端支配面積が100ha以上の水路
2 農業用用排水のための利用に供される水路以外の施設であって、受益面積が100ha以上のもの
3 施設の機能がどのように低下していくのか、どのタイミングで、どの対策を講じれば効率的に長寿命化できるのかを検討し、施設の機能保全を効率的に実施すること
4 施設の建設に要する経費、供用期間中の維持保全コストや、廃棄に係る経費に至るまでの全ての経費の総額
5 新たな土地改良長期計画(令和3(2021)年3月閣議決定)のKPI。事業量(計画期間内に、対策に着手する施設数)として、水路約1,200km、機場等約260か所を想定
(3)農業・農村の強靱化に向けた防災・減災対策
(国土強靱化基本計画等を踏まえハード、ソフト面の対策を組み合わせて実施)
頻発する豪雨、地震等の災害に対応し、安定した農業経営や農村の安全・安心な暮らしを実現するため、農林水産省は、平成26(2014)年に閣議決定された「国土強靱化基本計画」(平成30(2018)年改定)を踏まえ、農業水利施設の長寿命化、統廃合を含むため池の総合的な対策の推進等のハード面での対策と、ハザードマップの作成、地域住民への啓発活動等のソフト面での対策を組み合わせた防災・減災対策を推進しています。
農業・農村分野では、令和2(2020)年12月に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、「流域治水対策(農業水利施設の整備、水田の貯留機能向上、海岸の整備)」、「防災重点農業用ため池の防災・減災対策」、「農業水利施設等の老朽化、豪雨・地震対策」等に取り組んでいます。
(ため池工事特措法に基づくため池の防災・減災対策を実施)
ため池工事特措法(*1)に基づき、都道府県知事は「防災重点農業用ため池」を指定するとともに、防災工事等を集中的・計画的に進めるための防災工事等推進計画を策定しています。令和3(2021)年7月末時点で指定された防災重点農業用ため池は約5万5千か所となりました。
国は、同計画に沿った対策が進められるよう、令和3(2021)年度に国庫補助事業の補助率のかさ上げや地方財政措置の拡充を行いました。また、防災工事等の的確かつ円滑な実施に向けて、多数の防災重点農業用ため池を有する都道府県において、ため池整備に知見を有する土地改良事業団体連合会を活用した「ため池サポートセンター」等の設立を支援しました。同センターについては、令和3(2021)年12月時点で32道府県において設立されています。
あわせて、防災工事等が実施されるまでの間についても、ハザードマップの作成、監視・管理体制の強化等を行うなど、ハード面での対策とソフト面での対策を適切に組み合わせたため池の防災・減災対策を推進しています。ハザードマップを作成した防災重点農業用ため池は同年7月末時点で約2万5千か所となりました。
1 正式名称は「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」(令和2(2020)年10月施行)
(事例)防災重点農業用ため池のハード・ソフト対策により被害を防止(島根県)
(1)ハード対策(奥原池)
島根県出雲市(いずもし)の奥原池(おくはらいけ)では、平成30(2018)年に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」も活用して、洪水吐(こうずいば)き(*1)の流下能力の向上と堤体のかさ上げを実施しました。
令和3(2021)年7月12日の大雨では、対策実施前の流下能力を超える雨量となりましたが、対策により余裕をもって流下させることができました。決壊等が生じた場合は、下流の農地や住宅に大きな被害が生じることが想定されていましたが、そうした被害は未然に防止されました。
(2)ソフト対策(寺池)
島根県出雲市の寺池(てらいけ)地区では、行政と住民が協働してハザードマップを作成しました。令和3(2021)年7月5日からの大雨で堤体に損傷が発生していることが判明し、島根県、出雲市、消防団が応急対応を行いました。住民は、避難所に指定されていたコミュニティセンターに自主避難するなど、ハザードマップの作成が迅速な避難行動につながりました。
底樋(そこひ)(*2)からの排水に加えて、出雲市及び農林水産省中国四国農政局が排水ポンプを設置して排水を行った結果、二次的な被害は防止されました。
1 貯水池に流入する洪水等の流水を下流河道(かどう)へ安全に流下させる放流設備
2 ため池からの取水を堤外に導水するため、堤体の底部に設ける施設
(農地・農業水利施設を活用した流域治水の取組を推進)

農林水産省は、流域全体で治水対策を進めていく中で、農業用ダム、水田、ため池、排水機場といった洪水調節機能を持つ農地・農業水利施設の活用による流域治水の取組を関係省庁と連携して推進しています。
具体的には、大雨により水害が予測されるなどの際、関係省庁や地方公共団体、農業関係者等と連携しながら、農業用ダムの「事前放流」や、水田を活用した「田んぼダム」、ため池・農業用用排水施設の活用を行っています(図表2-6-6)。
農業用ダムについては、ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、令和3(2021)年5月までに農業用ダムのある一級水系全63水系(265基)、二級水系全120水系(147基)で、事前放流の実施条件等を定めた治水協定を河川管理者、ダム管理者及び関係利水者との間で締結しました。
これにより、令和3(2021)年度に出水が発生した際には、延べ76基の農業用ダムについて事前放流等により洪水調節容量を確保し、洪水被害を軽減することができました。また、水田を活用した田んぼダムについては、令和元(2019)年3月時点で約4万haの水田において取組が行われています。
(豪雨災害の頻発化・激甚化に対応した迅速な排水施設等の整備を推進)
豪雨災害による農地、農業用施設等への湛水(たんすい)被害等を未然に防止又は軽減するため、農林水産省は、排水施設等の整備を計画的に進めています。これにより、平成27(2015)年度から令和2(2020)年度までに新たに湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積の目標を約34万haとしていたところ、令和2(2020)年度末時点の面積は29万2千haとなりました。令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までに新たに湛水被害等が防止される面積を約21万haとすることを新たな目標(*1)としています。
また、令和4(2022)年3月に成立した「土地改良法の一部を改正する法律」では、近年の豪雨災害の頻発化・激甚化により、湛水被害等を及ぼすおそれのある農業用用排水施設の緊急的な豪雨対策を迅速に実施する必要が生じていることを踏まえて、農業者の申請、同意、費用負担によらずに、国又は地方公共団体の判断で実施できる緊急的な防災事業の対象に、農業用用排水施設の豪雨対策を追加しました。
1 新たな土地改良長期計画(令和3(2021)年3月閣議決定)のKPI
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883