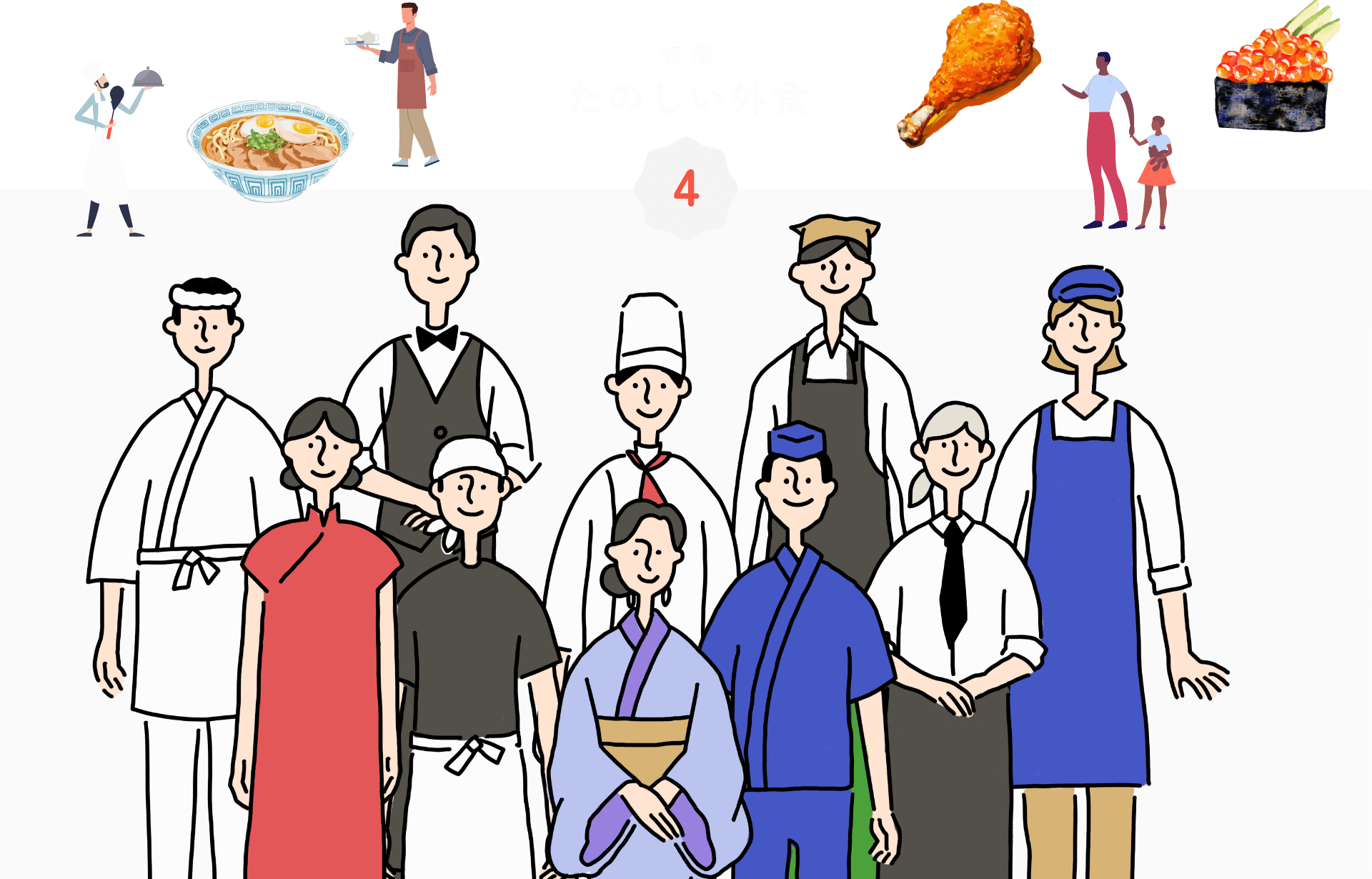

ライフスタイルの変化や災害対応など、
外食産業を取り巻く環境は大きく変化してきました。
50年を振り返る年表を添えて、
外食産業の現状をレポートします。

大阪で行われた日本万国博覧会での出店に始まり、バブル崩壊や震災など、
さまざまな環境の変化を受けながら、着々と市場拡大をし続けてきた、
外食産業の50年を振り返ります。











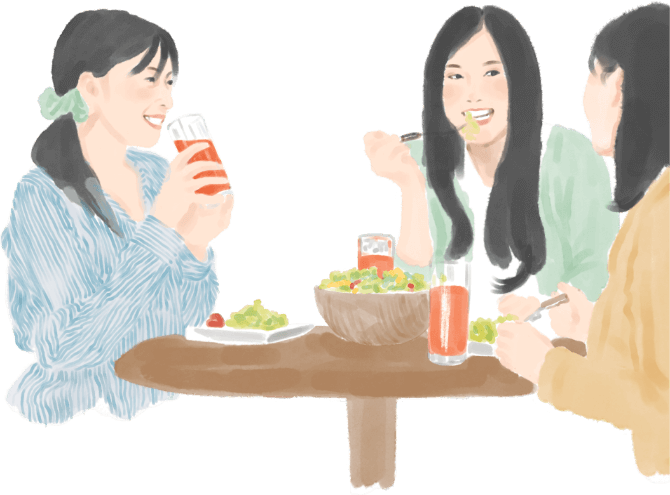



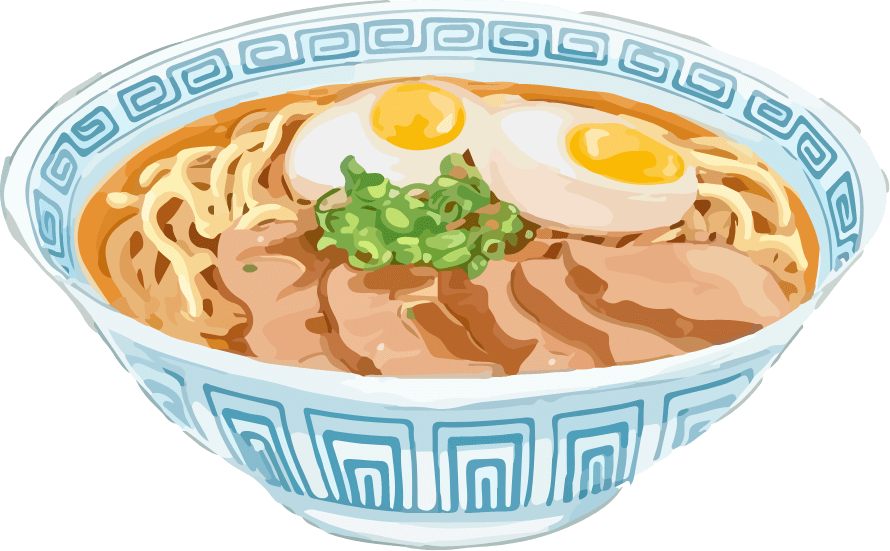


















COLUMN
ミラノ万博を契機に欧州でも
アジアや北米に比べて欧州は食品輸入の規制が厳しいこともあり、外食産業の海外出店が一歩遅れていましたが、2015年に行われたミラノ万博の日本館で、クオリティが高い日本食が提供されたことによって人気を博し、欧州にも日本食レストランが増加。カレーライスやうどんなどの日本食が、欧州の食文化に広がりを見せています。

関係各所のチームワークで実現!
食事の提供で、被災地を支援
(一社)日本フードサービス協会では1995年の阪神・淡路大震災から本格的な被災地支援を展開してきました。政府や地方公共団体と連携し、炊き出し支援が必要な被災地と外食企業との調整役をはじめ、キッチンカーなど災害派遣に従事する車両証明の交付申請、被災地までの安全な交通網に関する情報収集などを行い、被災地支援が円滑に行われる取り組みを行っています。
新潟県中越地震や東日本大震災、熊本地震、2018年7月や2020年7月に発生した豪雨、能登半島地震でも被災地支援を行っています。
能登半島地震における温かい食事の提供

能登半島地震の被災地では外食企業によるキッチンカーで、牛丼やカレーライスなど温かい食事が無償で提供されました。また弁当の配布やうどんの炊き出しなども行われました。
食料自給率向上にも貢献する
食材の国産化への取り組み
戦後、自由貿易の発展によって高品質な海外の食材を扱う外食企業が増える一方で、国内の農業関係者からは心配や反発の声が大きくなっていきました。
2000年代以降、外食産業では食材の見直しや食の安全に対する取り組みが活発化。2009年の農地法改正により、自社で農場を運営し、育てた野菜をメニューに使用する外食企業も現れ始めました。また日本各地の農家や畜産農家と提携し、野菜や米の仕入れ、食材の共同開発に取り組む外食企業も増えています。新鮮な国産の野菜を使うことは野菜の持続的な供給のみならず、日本の食料自給率の向上にも貢献します。
COLUMN
全国の産地と連携する「リンガーハット」の取り組み

今週のまとめ
海外進出や被災地支援、安心・安全な食材の追求など、
外食産業はさまざまな外部環境の変化に対応しながら、
日本人の食生活、農林水産業の成長をサポートしています。
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449








