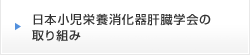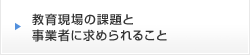いま、さまざまな分野で産官学の連携が推進されていますが、食育の分野でも企業や地域行政、大学等との連携による総合的な取り組みが増えています。
食品メーカーでは自社の得意分野における出前授業を定期的に提供している企業や、外食・中食産業では自社商品を活用して実際にお弁当などを組み合わせる授業、また流通産業ではバランスのとれた食材を買い物する授業など、日々の生活に即した内容が工夫されています。
本サイトの「参考になる取り組み」で事例を紹介していますが、日々の食事に生かされるよう、保護者や地域を巻き込んだ展開が期待されます。

学校における食育の場として大きな効果が期待できるのは、給食やお弁当の時間を活用するものです。実際に食事をしながら、食品と栄養素と料理の関係を理解できるので、子どもたちにとっても印象深い内容になります。
食材を地域の農家の協力で用意すれば、地産地消の意味や食料自給率のことなども身近に理解させやすいし、地域の食文化を学ぶ大きな機会となります。
本コーナーで紹介する超人シェフ倶楽部のスーパー給食では、残食率が減少するといった効果も検証されています。また同じく日本小児栄養消化器肝臓学会の取り組みのように、専門的な知識でありながら、お弁当を詰める行為を通すことで幼稚園児の親子も学びやすい内容にもなります。
総合的な学習の時間を利用して、「食事バランスガイド」を用いて望ましい食生活のあり方を考えながら、地域の郷土料理や特産物といった食文化も、あわせて学習しています。特別活動の時間を利用して、給食の献立と連携させながら、「食事バランスガイド」を使った情報提供も行なっています。
最近は、地域や企業と連携する事例も多く、学校独自のイベントや健康を考えた地域の取り組みに発展しています。
地域の郷土料理を取り入れた「地域版食事バランスガイド」を利用した食文化の学習や、給食だよりに「つ(SV)」の数を表示するなど、学校の特色や地域により、「食事バランスガイド」の特徴を生かしたさまざまな取り組みもあります。
料理で学べる「食事バランスガイド」で、給食の地産地消の取り組みや、地域の食文化、食料自給率などを考える学習につなげていきましょう。