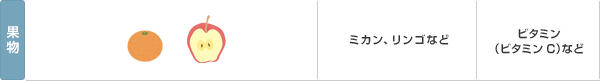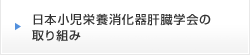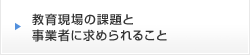「食生活指針」とは、望ましい食生活のための10項目のスローガンです。国民の健康増進と生活そのものの質の向上、さらには食料の安定供給や食文化の継承などがうたわれています。食の問題を多角的に考え、農林水産省・厚生労働省・文部科学省の3省が2000年に合同で決定。総合的な取り組みの推進や自主活動との連携、さらには国民的な運動として展開されるよう、食のあり方を示したものです。
これをさらに具体化し、「何を」「どれだけ」食べたらよいのかを示したのが、「食事バランスガイド」です。「食事バランスガイド」は食育の推進や食環境そのものを整備し、さらに充実させるため、フードビジネス現場での活用や、マスメディアも含めた情報ツールとして利用することで、国民の食生活改善を目指しています。
生活指針を具体的な行動に結びつけるためのツールの一つとして、「食事バランスガイド」のコマを利用しましょう。
「食育基本法」は、国民の食生活や食習慣を見直し、一人ひとりが自らの責任によって「食べること・食べもの」を選べるようになるために2005年に制定されました。
ことを目指しているものです。
これらを、より具体的に実践するためのツールとして活用できるのが、「食事バランスガイド」です。
学校教育の中において、「食事バランスガイド」は「家庭科」「総合的な学習の時間」のほかに、特別活動や給食の時間など、さまざまな場面で活用され始めています。
特に「家庭科」等では、従来指導されてきた「五大栄養素」「三色食品群」「六つの基礎食品」のような食品群別の栄養の考え方と組み合わせて、「食事バランスガイド」を学習しています。
食品の中に含まれている栄養素とその働きを知ることと、それが日々の料理にどう結びつき「何を」「どれだけ」食べれば偏りのない食事になるのか知ること、その両方を子どもたちが理解できるように指導することが重要です。
食品に含まれている栄養素の分類は「五大栄養素」「三色食品群」「六つの基礎食品」などがあります。
「五大栄養素」は、炭水化物、脂質、たんぱく質、無機質、ビタミンの5つを表します。
「三色食品群」は、栄養素の働き(体をつくる、エネルギーになる、体の調子を整える)に応じて、食品を3つのグループに分けたもの。「六つの基礎食品」はそれをさらに、主な栄養素別に細かく分けたものです。
こうした従来の指標と「食事バランスガイド」を組み合わせた活用が、身近な理解を促進し、日々の食物の選択ができる能力の育成につながります。
例えば、まず「食事バランスガイド」を使って子どもたちに自分の食事内容を再確認させ、5つの料理グループの中で足りているもの足りないものを把握させます。大まかな料理レベルで食事の偏りを理解したあとで、「三色食品群」や「六つの基礎食品」で足りない栄養素、とりすぎている栄養素など、からだに及ぼす影響を教えることで、日々の食事のバランスの重要性に気づかせます。