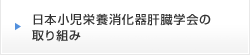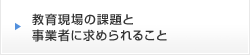東京都品川区にある区立浅間台小学校は、全校生徒112名。周辺には農家や農地のない都会の住宅地であるにも関わらず、食育と食農体験に力を入れている小学校です。特に食農体験は、すべての学年で作物を育てるための土作りからスタート。各学年が時期によって異なる作物を育てるだけでなく、その手入れ、収穫、そして収穫したものを調理するまで。すべての過程を、企業やプロの人から直接指導を受けながら、生徒・地域・企業が連携し、子どもたちの食への取り組みをサポートしているのが特徴です。

江戸野菜である「品川蕪」の栽培にも取り組む

校内の畑で収穫したサトイモをむく子どもたち
「土作りから収穫まで、食べものができるまでを毎日見ている子どもたちにとって、自分が育てたものは、すべておいしいんです。体験するから関心も出てくるし、それが学ぶ意欲にもつながります」と話すのは、自ら食育のリーダーシップをとる豊島呈次校長先生。学校内には校舎横の畑の他にも、屋上、さらには体育館の裏など、さまざまな場所を利用しながら、学年ごとの畑を作っています。
周辺に農地のない環境でありながらも、全く農業体験のない子どもたちと地域の人が、無農薬野菜を栽培できる理由。それは、「知識や技術をプロから直接学ぶ」という、産学が連携した食農と食育を推進する学校方針があります。
「授業では確かに教科書通りに教えることはできても、現実の私は、これまで一度も稲を育てた経験はありません。肥料などの土作りのプロ、料理のプロのように、それぞれが持つ技術を子どもたちと一緒に知ることで、実社会にすぐに役立つ知識として私も学ぶことができました」とは、5年生担任の稲田国昭先生。米の場合、春は田植え、夏は害虫対策や日照りのときの温度管理、そして秋の収穫まで。子どもたちとの活動を、いつも地域と企業がサポートしています。

学校内のあちこちに小規模の畑があります
学校の授業で作物の栽培から調理に至るまで、全学年の子どもたちが体験するためには、教科ごとの授業時間の確保が最大の課題です。浅間台小学校の場合、「食育年間学習計画」「食育指導、各学年の教科一覧」を決め、各学年ごとに年間の授業内容を計画。これをもとに「畑単元一覧表」により、作物の生育の状況にあわせたスケジュールを組んでいます。
例えば同じように畑で作物を育てた場合、1、2年生は生活科としてキュウリや枝豆を。6年生は理科や家庭科としてトマトとキュウリを育て、家庭科の「朝食を作る」というテーマにあわせて調理するという授業内容になります。学年によっては、国語や保健体育の授業を使い、身体や栄養との繋がりへと導く学習内容となることもあります。
一般的な小学校の場合、総合的な学習の時間を利用することで、こうした発展学習が可能です。

理科で育てたカブを、家庭科でみそ汁にする

収穫した材料を使った調理は、みな真剣
浅間台小学校が無農薬野菜を育てるにあたり、特に力を入れたのが、子どもたちを地域でサポートする「食農倶楽部」の発足です。保護者、学校の職員、地域のボランティアなど、総勢40名が所属するこのクラブは、農業体験がない人がほとんど。月2回、週末の土曜日などを使い、子どもたちの畑の雑草取りや土作りの部分など、収穫に至るまでの工程を手伝っています。
また、メンバー自らで講習会も企画。農業に関することの他にも、「食事バランスガイド」の学習から日ごろの食生活を振り返るなど。集まった保護者たちも、積極的に学んでいます。

「食農倶楽部」として保護者たちが手伝います

ミカンの収穫も学校で可能に
「食事バランスガイド」を子どもたちが理解するために、浅間台小学校では産学連携スタイルで「自分にあったお弁当」を知る授業を展開しています。ある年では、女子栄養大の協力で講師を招き、「食事バランスガイド」から「何を」「どれだけ」食べればよいのかを学習。その後、食農倶楽部はオリジン弁当の協力で、総菜をバイキングスタイルでお弁当箱に詰めました。子どもたちは給食のメニューを利用してそれぞれ、自分のお弁当箱に詰めることで、偏りのない選び方と「食事バランスガイド」との関係を再確認しました。
「食事バランスガイド」を頭で考えるよりも、実際にお弁当箱におかずを入れる体験をすることで、子どもたちも内容を深く理解することができます。そして、最後は必ず保護者や地域の人と一緒に会食を。日々の食事に知識を生かしてこそ、はじめて「食事バランスガイド」が健康づくりに役立つのですから」と話す豊島校長。今後も継続して食農・食育の授業を行うために、校長自らが積極的に企業や地域に働きかけています。

大学に講師を依頼。子どもに正しい知識を
取材日=2010年12月