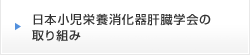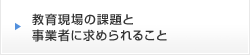日本小児科学会の分科会である、日本小児栄養消化器肝臓学会。主に栄養、消化器、肝臓の3分野を扱うこの学会には、小児科医や管理栄養士たち約550名が所属しています。この学会で10年ほど前から問題となっているのが、子どもの食生活。特に幼児期の段階から、すでに偏食や朝食の欠食が増加傾向にあることを、小児科医たちは早くから問題視していました。
「保育園の子どもたちは、幼児の段階から食育の取り組みがあるけれど。幼稚園の場合、「食事バランスガイド」を使って食育を推進した事例を、あまり聞いた事がありませんでした。『子どもたちが、もっと健康的になるために』と、医師から直接、「食事バランスガイド」を使った食事の重要性を伝えた方が、説得力があるはず」と話すのは、帝京大学医学部小児科教授の児玉浩子先生。その取り組みが、今回の幼児を対象とした「食事バランスガイド」を使った「平成22年度 食育実践活動推進事業」です。
北は青森から、南は関西地区まで。日本各地にある11園の幼稚園が、この推進事業に参加しました。幼児たちはイラストを使った「食事バランスガイド」の話を聞いたあと、フェルト素材の食材を、それぞれの弁当箱につめる遊びをするというプログラム。その間、幼児の母親を対象にした「食事バランスガイド」の講習会も実施します。親子で「食事バランスガイド」を学べるのが、このプロジェクトの特徴です。

フードモデルのフェルトはすべて手作り

「お弁当ごっこ」を楽しむ親子
当日は、幼稚園に小児科医1名、管理栄養士・栄養士2~3名が訪問。パワーポイントを使いながら、「食事バランスガイド」と偏りのない食生活の重要性を理解した上で、実際のお弁当箱におかずを入れる遊びへと進行します。主菜や副菜などすべてをフェルト素材の食材にすることで、遊びを通じて目で見て料理の量と内容がわかること。また食材の準備時間が不要なため、進行のフォーマットさえあれば、同じ内容の講習会を行なうことができます。これにより、全国各地にいる小児科医たちがこの主旨に賛同。医師自らが幼稚園に直接訪問し、講習会を開催することができました。

小児科医たちが親子を直接指導します
幼児たちが学んでいる間に開催する母親対象の講習会では、「食事バランスガイド」の使い方と偏りのない食生活の重要性を医師が直接指導します。幼児期の段階から「健康、運動、食事」という3つが、子どもの健康づくりには欠かせないこと、さらには、講習会後に配布される「食育だより」を使いながら、こうした正しい生活習慣を継続していくことの必要性を、母親たちに伝えています。
「実施した幼稚園の園長先生からは、非常によい取り組みだとご好評をいただいています」と話す児玉先生。「ただ、日々の食生活を簡単に変えることは難しい。こうした食育事業そのものを単発で終わらせるのではなく、今後も長く継続して行なう事が重要です」
今回、幼児を対象とした「食事バランスガイド」の講習会を行なった背景には、幼児の母親たちの意識を変えたいという、医師たちの強い思いがあります。ここ10年余りの間に急増している低体重児の増加や、幼児期からのやせと肥満の問題。さらには、土とふれあう機会が少ない子どもたち、食事内容や運動習慣も年々変化している状況など。このような問題の裏には、栄養だけではなく、運動と生活リズムの問題が密接に絡み合っています。
「母親となる女性の、食に対する意識そのものを変えていきたいですね。母親が変わることで、まず生まれてくる赤ちゃんが変わります。さらには、家族が健康で過ごすことができる生活習慣を、自然に身につけられるのですから」と児玉先生。一生健康でいるためには、「食事バランスガイド」のコマのように、傾く事なく回り続けることが重要です。小児科医たちも、日々の食事を見直すことができる「食事バランスガイド」を、推奨しています。
取材日=2010年12月