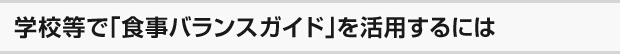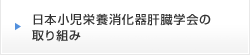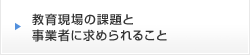食育が学校教育の現場で重要な位置づけになってきています。朝食の欠食や菓子パンだけの食事など、食事のバランスの大切さが今ひとつ理解されていない現状を変えていくためには、子どものときからきちんと学習することこそ重要だと認識されています。
子どもに食事のバランスを理解させるには「食事バランスガイド」が教材となります。食卓に並ぶ料理の組み合わせで考えることができるため、活用法次第で小学校低学年から使えます。
子どもへの学習で注意したいのは、必ず保護者にもその内容を伝えることです。特別活動などで保護者と一緒に学ぶとか、給食だよりなどの媒体を活用するなど、保護者への伝え方も考えましょう。
「食事バランスガイド」を使う場合、学習する子どもの性別・年齢・身体活動レベルによってコマの大きさが変わることに注意しましょう。通常は望ましいエネルギー量と5つの料理グループ別に、食べる目安となるコマの大きさを設定。日常生活から身体活動量を考えて、学習者のコマの大きさを設定します。
子どもの場合、一日に必要なエネルギー量は6~9歳男女、10~11歳女子の場合は1400~2000kcal。10~11歳男子の場合は2200±200kcalなど、年齢、性別、身体活動量によって異なります。
さらに、ビタミン、ミネラル、食物繊維など、成長するために必要な栄養素を、毎日の食事からきちんと摂取することも大切です。「食事バランスガイド」を使いながら、主食と主菜の量は、それぞれの状況に応じて加減しながらバランスよく食べる、さらに副菜を5~6つ、牛乳・乳製品は2つ以上、そして果物は2つを食べるように、設定しましょう。

からだが成長するに従い、栄養素もたくさん必要となるのが成長期の子どもたち。特に運動やスポーツをする場合は、骨を丈夫にするためのカルシウムが欠かせません。このため成長期の子どもの場合、「食事バランスガイド」の中では牛乳・乳製品を1日に2~3つ。運動やクラブ活動などで毎日身体を動かしている子どもの場合は、4つ程度が食べる目安です。特に毎日運動をしている場合は、ほぼ毎食のように牛乳や乳製品をとることで、身体に必要なたんぱく質やカルシウムなどを過不足なくとることができます。
一方、スポーツをしていないオフの時期は、通常の年齢である子どもたちと同じ食事スタイルに変えることが大切です。オンとオフを上手く切り替えながら、子どもの年齢と活動量にあった食べ方を、「食事バランスガイド」で教えましょう。成長期だからこそ、牛乳・乳製品を意識して摂り入れるよう、保護者にも啓発しましょう。
「食事バランスガイド」の中では、必要な栄養素をとるという目的からすれば、必ずしもとらなくても支障の出ない菓子・嗜好飲料を、コマをまわす「ヒモ」として表現しています。これは、コマをよりよくまわすために、食事の楽しみとして適度にとるものとして位置づけられていることからです。一日あたり約200kcalが、摂取の目安とされています。
子どもたちが大好きなメロンパンのような菓子パンを「主食」と捉えてしまいがちですが、砂糖や油脂などが多く含まれている菓子パンは、「食事バランスガイド」の中ではヒモとなることを理解させることが重要です。
おやつを食べる時には、飲み物をジュースではなく牛乳・乳製品にすることで、偏りのないコマの形になるなど、ヒモとなる菓子・嗜好飲料をとり過ぎないように、子どもたちと保護者に伝えましょう。

「食事バランスガイド」では学童期(6~12歳)からコマの大きさを提示していますが、より早い時期である幼児期から、バランスのとれた食事を含めた望ましい生活習慣を身につけることが大切です。
東京都では、3~5歳児を対象にした「幼児向け食事バランスガイド」を作成しています。