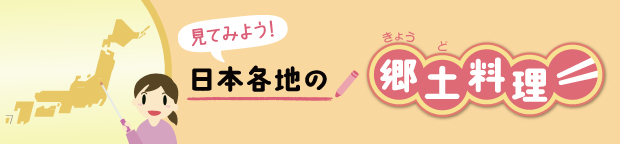

小田原(おだわら)かまぼこ
大名やぶしたちの好物といえば?
どんな料理?
小田原(おだわら)では、室町(むろまち)時代にすでにかまぼこが作られていましたが、より多く作られるようになったのは江戸(えど)時代後期のことでした。参勤交代(さんきんこうたい)で江戸(えど)に行き来していた大名やぶしたちが、小田原(おだわら)や箱根(はこね)で宿はくしたときに、小田原(おだわら)のかまぼこが出され、そのおいしさがひょうばんとなり全国に広まるきっかけになったそうです。
作り方・食べ方
「小田原(おだわら)かまぼこ」は、白身魚の魚肉に塩をまぜてすりつぶしたすり身を木の板にもり、むして仕上げます。関西地方のかまぼこが、表面に焼き目をつけた「焼きかまぼこ」であるのに対し、「小田原(おだわら)かまぼこ」は「蒸(む)しかまぼこ」で表面がつるっとしています。このため、「小田原(おだわら)かまぼこ」は魚の風味とともにだん力のある食感が楽しめるのが大きな特ちょうです。
由来・話題など
小田原市(おだわらし)内の多くの公立小中学校では、「かまぼこの日」とされる11月15日前後に給食で「小田原(おだわら)かまぼこ」を使ったメニューが出されています。また、毎年3月下じゅんには小田原(おだわら)城で、「小田原(おだわら)かまぼこ桜(さくら)まつり」が開さいされ、かまぼこ作りの実えんなども行われています。








