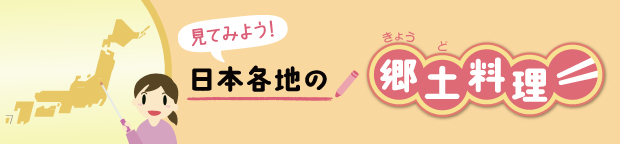

うずみ
ほり出しながら食べる!
どんな料理?
「うずみ」とは、広島県(ひろしまけん)福山市(ふくやまし)を中心に、秋のしゅうかくを祝うごちそうとして食べられてきた郷土(きょうど)料理です。その始まりは、江戸(えど)時代にまでさかのぼり、昭和40年代までは、よく食べられていましたが、食生活の変化によってあまり食べられなくなってしまいました。そこで、平成に入ってから、小学校の給食のメニューなどに取り入れられ、それからまた食べられるようになりました。
作り方・食べ方
「うずみ」は、一見するとただの白いご飯ですが、中にだしでにたエビやたい、調理した里いもなどのおかずが入っています。今では、季節ごとの食材を「幸福、たから」に見立てて、幸やたからをほり出しながら食べるものとして話題になっています。
由来・話題など
江戸(えど)時代には、ぜいたくきんし令が出されていたため、ぜいたく品とされた食材をご飯の中に「埋(うず)め」て食べていたところからこの名前がつきました。また、「うずみ」は「うずめる」料理として多くの食品に取り入れられていて、かき氷にフルーツをうめた「うずみ氷」、地元産の食材をうめた「うずみソフトクリーム」、めんの下に具をうめた「うずみラーメン」などが作られています。








