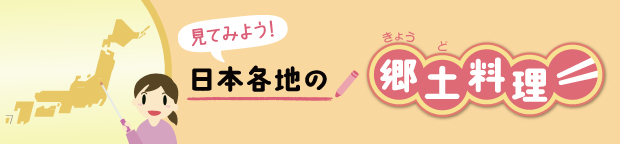

三重県(みえけん)
伊勢(いせ)うどん
ふつうのうどんより
2倍太いうどん!
2倍太いうどん!
どんな料理?
「伊勢(いせ)うどん」は、三重県(みえけん)の伊勢(いせ)地いきを中心に、昔から食べ続けられてきた太くてやわらかいめんと黒いたれが特ちょう的な郷土(きょうど)料理です。「伊勢(いせ)うどん」は、江戸(えど)時代には食べられていて、お伊勢(いせ)参りの参ぱい客の間で好まれたことによって、三重県(みえけん)の名物として全国にその名が広がっていきました。
作り方・食べ方
伊勢(いせ)うどんの最大の特ちょうは、ふつうのうどんより2倍ほど太いめんを使っていることです。食感はもちもちふわふわしていてやわらかく、こしがほとんどありません。つゆにひたさず、しょうゆのような黒いたれをかけて食べるため熱くはなく、しかも、見た目よりその味はあっさりとしています。
由来・話題など
多くの参ぱい客でにぎわう伊勢(いせ)では、お客様を待たせることがないよう、つねにめんをゆで続けていたため、そのどく特なやわらかい食感が生まれたそうです。この食感が長旅でつかれた人びとのいにやさしく、食べやすいものとして大人気になりました。








