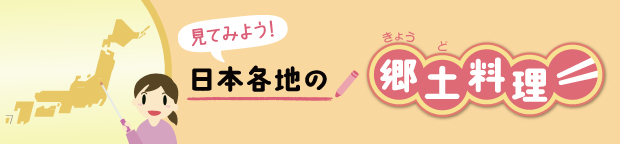

泉州(せんしゅう)水なすの浅漬け(あさづけ)
なすで作る浅漬け(あさづけ)
どんな料理?
「泉州(せんしゅう)水なす」は、大阪府(おおさかふ)南部の泉州(せんしゅう)地いきで生まれたブランド野菜です。その名のとおりかぶりつくと水がしたたるほど水分が多く、そのみずみずしさを楽しむために「泉州(せんしゅう)水なすの浅漬け(あさづけ)」が作られ、好んで食べられてきました。
作り方・食べ方
「泉州(せんしゅう)水なす」の形はぷっくりと丸みを帯び、皮がうすくてやわらかく、あまみがあってアクが少ないことが大きな特ちょうです。これをぬかやつけ物調味えきに短期間つけこんだのが「泉州(せんしゅう)水なすの浅漬け(あさづけ)」です。 「泉州(せんしゅう)水なすの浅漬け(あさづけ)」は、生ハムをまいたり、サラダにして食べるのもおすすめです。また、水なすを古づけにして小エビとともにあまからくにた、「じゃこごうこ」という料理も好んで食べられています。
由来・話題など
泉州(せんしゅう)地いきでは、水なすが江戸(えど)時代初期からさいばいされてきたそうですが、皮がうすくてゆ送に向かず、つけ物にすると皮の色が茶色く変色するため、長い間、地元を中心に流通していました。しかし、関西国際(かんさいこくさい)空港が1994年に開港したのをきっかけに大阪府(おおさかふ)の特産品として注目を集めるようになり、品種改良で皮の色があざやかな品種が登場したことから、 「泉州(せんしゅう)水なすの浅漬け(あさづけ)」が全国的に有名になりました。








