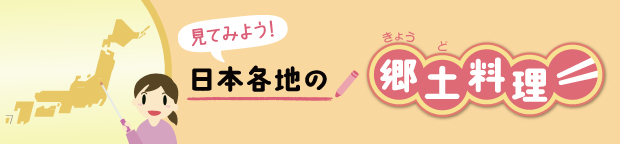

奈良県(ならけん)
柿の葉寿司
(かきのはずし)
柿の葉に包みほぞん食としても
食べられてきた特産品
食べられてきた特産品
どんな料理?
「柿の葉寿司(かきのはずし)」は、塩でしめたさばをすめしといっしょに柿(かき)の葉で包んだおしずしで、奈良県(ならけん)の郷土(きょうど)料理として食べられてきた特産品です。
作り方・食べ方
「柿の葉寿司(かきのはずし)」の柿の葉とすめしにしみこませたおすには、食べ物がくさるのをふせぐこうかがあり、ほぞん食としても食べられていました。 「柿の葉寿司(かきのはずし)」は、作ってからすぐに食べるのではなく、一日置くことによって柿(かき)の葉の香りとさばのうまみがすめしにうつり、よりおいしくなります。
由来・話題など
「柿の葉寿司(かきのはずし)」は、江戸(えど)時代の中ごろ、高いねんぐを課せられていた紀州(きしゅう・和歌山県(わかやまけん))の漁したちが、お金をかせぐために夏さばを塩でしめ、とうげをこえて奈良県(ならけん)の村へ売りに出かけたところ、村は夏祭りの最中でお祭りのごちそうになったという説や、ほぞん食や兵しの食りょうだったものが食べられるようになったという説などがあります。








