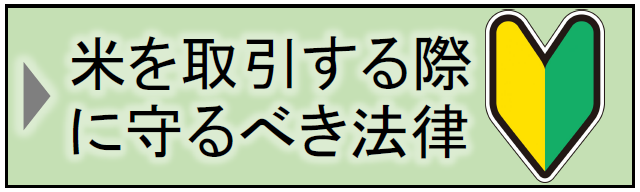流通業のみなさまへ
- 対象品目を入出荷する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 事業者間で産地情報を伝達する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 商流と物流が異なっている場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- Q&A
- お問合せ先
対象品目を入出荷する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
入出荷の記録の作成・保存が必要となります。
入出荷の記録の作成
対象品目を仕入れた場合とは、具体的に以下の事項を記録する必要があります。通常の取引時に取り交わす納品書などの伝票類や、電子媒体の記録を保存することも可能です。
- 名称(取引において通常用いている名称を記載。)
- 産地(指定米穀等の取引等を行った場合のみ。記録の仕方についてはこちら。記録が不要となる場合についてはこちら。
- 数量(取引において通常用いている単位で記載。)
- 年月日(搬入又は搬出した日を記載。これにより難い場合は、受発注をした日等取引をした年月日でも可。)
- 取引の相手方の氏名、又は名称
- 搬出又は搬入をした場所が取引先住所と異なる場合、搬入又は搬出をした場所搬出・搬入等の記録の作成についてはこちら
- 用途限定されている米穀については、その用途
入出荷記録の保存
記録の保存期間については、取引を行った日から3年間です。ただし、次に掲げるものはそれぞれの期間です。
- 消費期限が付されている商品(お弁当など速やかに消費することを前提としたものを含む)については、3か月間です。
- 記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品については、5年間です。


事業者間で産地情報を伝達する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
商品の容器・包装に産地が記載されている場合は、そのまま販売することで、取引先へ産地情報の伝達の義務を果たしたことになります(別途、産地の記録が必要になる場合があります。詳しくはこちら。)
商品の容器・包装に産地が記載されていない場合は、取引先から伝達された産地情報を伝票(仕様書、規格書など)に記載して取引先へ伝達することが必要です。

商流と物流が異なっている場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
商流に関する記録の作成・保存と物流に関する記録の作成・保存がともに必要です。
商流では、伝票等で商品が転売されていきますので、実際の商品をそのつど運送・保管しません。米トレーサビリティ法では伝票の内容として、取引等の記録の作成項目として「名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所」を記載することになっていますが、商品が動いていない場合は、伝票などへ商品の搬出入した場所を記載することができませんので記載する必要はありません。実際、搬出・搬入したときに搬出、搬入の記録を作成してください。
なお、物流についても、伝票等により取引等の記録の作成保存が必要となりますが、産地情報伝達も「産地」の記録も不要です。

Q&A
(問) 取引(売買)を行っていない場合でも、商品を搬出入した場合、取引の記録は必要ですか。
(問) 中間流通業者が対象品目であることを認識していなかった等の理由で、伝票に必要な項目を記載せずに販売し、必要な記録の作成・保存を川下の事業者がしなかった場合、その責は中間流通業者が負うこととなりますか。
なお、入荷記録として必要な項目のいくつかが記載されていない伝票等を受け取った川下の事業者については、聞き取りや目視により確認し、必要な項目について記録すること。また、川上の事業者から必要な項目が記載された納品書等をもらうように努めてください。
(問)食品表示法による表示と米トレーサビリティ法による産地の記録と産地情報の伝達はどのような関係になっているのですか。
さらに、外食事業者については、米飯類について米トレーサビリティ法の産地情報の伝達が必要になります。
(問) 記録は事業所、事業場または店舗ごとに作成する必要がありますか。
お問合せ先
〇米トレーサビリティ法に関する問合せ
問合せ先一覧(PDF : 299KB)
〇産地情報の伝達・表示に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示課
代表:03-3507-8800
〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当:米穀流通・食品表示監視室