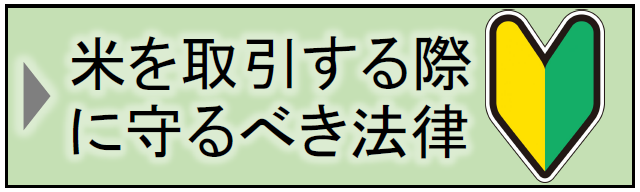小売販売業のみなさまへ
- 対象品目を仕入れた場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 対象品目をインストアで加工・製造する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 一般消費者に販売する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- Q&A
- お問合せ先
対象品目を仕入れた場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
入荷の記録の作成・保存が必要となります。
入荷記録の作成
対象品目を仕入れた場合は、具体的に以下の事項を記録する必要があります。通常の取引時に取り交わす納品書などの伝票類や、電子媒体の記録を保存することでも対応可能です。
- 名称(取引において通常用いている名称を記載。)
- 産地(指定米穀等の取引等を行った場合のみ。記録の仕方についてはこちら。記録が不要となる場合についてはこちら。
- 数量(取引において通常用いている単位で記載。)
- 年月日(搬入又は搬出した日を記載。これにより難い場合は、受発注をした日等取引をした年月日でも可。)
- 取引の相手方の氏名、又は名称
- 譲受けに伴って搬入を行った場合には、搬入をした場所搬出・搬入等の記録の作成についてはこちら
- 用途限定されている米穀については、その用途
入荷記録の保存
記録の保存期間については、取引を行った日から3年間です。ただし、次に掲げるものはそれぞれの期間です。
- 消費期限が付されている商品(お弁当など速やかに消費することを前提としたものを含む)については、3か月間です。
- 記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品については、取引などを行った日から、5年間です。

対象品目をインストアで加工・製造する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
仕入れた原材料と出荷する製品の関係がなるべくわかるように記録を作成・保存することが必要です。(努力義務)
米トレサビリティ法では、対象品目について問題が生じた際に、事後的に流通ルートを特定できるよう、対象品目について取引を行った際に記録を作成することとしております。また、対象品目について表示の適正化を図ることや対象品目の産地情報を促進するため、対象品目について産地情報の伝達を行うこととしています。
したがって、流通ルートをより特定したり、産地情報の確からしさを担保するために、飲食料品については、入荷した原材料と製造ロット、出荷のロットなどが明確になっている必要がありますので、対象品目についての作業日報などで記録を作成するようにしてください。
この記録は、実際に商品の流通ルートを特定する際に重要な役割をはたすものですので、できるだけ正確に作成する必要がありますが、業種や製造工程により、求められる程度が異なります。(罰則はありません。)

一般消費者に販売する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
一般消費者に対象商品を販売・提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。
具体的な方法については、以下の方法があります。
- 商品の容器又は包装に具体的な産地情報を記載。
- 小売販売店や外食店等の指定米穀等を販売または提供をしている場所において、メニュー、店内配布チラシ、ショップカード等や店内、店の入り口の看板等の一般消費者の目につきやすい場所に具体的な産地情報を記載。
- インターネット販売や通信販売の場合には、販売の条件を示すホームページやカタログの見やすい箇所に産地を記載することも可。
- 商品等にホームページアドレスを記載し、当該ホームページにアクセスすることにより産地情報が入手できるようにする方法も可。この場合、商品パッケージにその旨の記載が必要であるほか、Web上で当該商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応関係が把握できるようにする必要があります。
- 商品等に「お客様相談窓口」を記載し、当該窓口に照会すれば、産地情報が入手できるようにする方法も可。この場合には、お客様相談窓口において、産地情報を入手できる旨の記載が必要となります。
- 対面販売において、店内等に「産地情報については、店員にお問い合わせください。」等の掲示をし、店員に尋ねれば、産地情報が入手できるようにする方法も可。
- 上記5や6の仕組みは、産地情報が正しく伝達されているかどうかの検証が可能な仕組みとする必要があるため、この対応を行う事業者は、対応マニュアルを定め、従業員が当該マニュアルに従って適切に対応できるための措置(周知徹底、教育研修)などを講じ、講じた措置の実績を記録しておく必要があります。

Q&A
(問) スーパー等一般消費者向けに販売している際に、販売する相手が一般消費者か米穀事業者か区別できない場合はどのようにすればよいのですか。
(問) 「もち」や「だんご」等を販売している店舗において、店内で食べることができる場所を設けている場合、そこで一般消費者が食す際には、産地情報の伝達が必要となりますか。
(問)スーパーや百貨店等で、米穀等を一般消費者に試食用及びサンプル用として無償配布した場合、記録の作成・保存や産地情報伝達は必要ですか。
(問)発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、対象品目となりますか。
(問)玄米・精米に雑穀やビタミン強化米などを混合したものは対象となりますか。
- 米穀(玄米・精米(黒米、赤米、緑米を含む。))と雑穀やビタミン強化米を混合した商品は対象とします。
- 類似品として、玄米・精米と小豆などの豆類や雑穀等がそれぞれ個別に包装され、同包されている商品がありますが、これも同様に対象とします。
(問) 記録は事業所、事業場または店舗ごとに作成する必要がありますか。
お問合せ先
〇米トレーサビリティ法に関する問合せ
問合せ先一覧(PDF : 299KB)
〇産地情報の伝達・表示に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示課
代表:03-3507-8800
〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当:米穀流通・食品表示監視室