











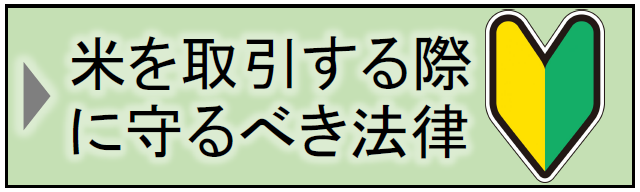
- 米を取引する際の届出・申請等に係る詐欺が発生しています!
米トレーサビリティ法の概要
- 米トレーサビリティ法について
- 対象品目
- 対象事業者
- 対象事業者に課せられる義務と施行日
- 取引の際に記録が必要な項目
- 取引等の際における記録の仕方
- 記録の保存期間
- 産地情報の伝達の仕方
- 産地情報の伝達が不要となる場合
- 米トレーサビリティ制度関係法令
- Q&A
- お問合せ先
米トレーサビリティ法について
- お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
- お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。

対象品目
- 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
- 主要食糧に該当するもの:
米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等 - 米飯類:
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。) - 米加工食品:
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
→対象品目の詳細については、こちらのQ&Aをご覧ください。

対象事業者
対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。
対象事業者に課せられる義務と施行日
- 取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日より)
米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。 - 産地情報の伝達(平成23年7月1日より)
(1)事業者間における産地情報の伝達
(2)一般消費者への産地情報の伝達
詳しくは産地情報の伝達の仕方をご覧ください。
取引の際に記録が必要な項目
以下の項目について、記録が必要です。
- 品名
- 産地
- 数量
- 年月日
- 取引先名
- 搬出入した場所
- 用途を限定する場合にはその用途 等
産地の記録の注意点
- 「国産」「○○国産」「○○県産」等と記録。
- 原材料に占める割合の多い順に記載。
- 産地が3か国以上ある場合には、上位2か国のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載可。
- 飼料用、バイオエタノール原料用等、非食用のものについては、産地の記録は不要。
- 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんについて、最終的な一般消費者販売用の容器・包装に入れられ、当該容器包装に産地が具体的に明記されている場合は、伝票等への産地の記載は不要。
- 平成23年7月1日より前に
a国内で生産されたものについては、生産者から譲り渡しされた米穀
b輸入されたものについては、国内需要者等に譲り渡しされた米穀、米加工品
caの米穀、bの米穀又は米加工品を原料とする米加工品
については産地の記録は不要。
搬出・搬入等の記録の作成について
- 取引(売買)を行っていない場合でも、事業所間(自己の事業所であるかを問わず。)で搬入・搬出を行い、米穀等を移動させた場合は記録すること。この場合産地の記録は不要。
- 同一の事業所内での米穀等の移動については、記録不要。この場合の「事業所」とは一まとまりとして機能を有した一団の場所をいう。
- 記録の義務がかかるのは、法律上、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うものに限られており、単に運送や保管の事業を行う者は、記録の作成・保存の義務対象外。
取引等の際における記録の仕方
実際の取引のおいて取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において、下記にあげる事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。

記録の保存期間
受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要となります。
産地情報の伝達の仕方
事業者間における産地情報の伝達
米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。
一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行うことが必要となります。
ただし、食品表示法で原料原産地情報表示の義務がある玄米・精米・もちは、食品表示法に従い、これまでどおり表示してください。
また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。
- 外食店における一般消費者への産地情報の伝達手段

- 小売店における一般消費者への産地情報の伝達手段
(1)産地情報を商品へ直接記載することにより伝達する場合
- 国産米の場合は「国内産」「国産」等と記載(ただし、都道府県や一般に知られた地名でも可)。
- 外国産の場合はその「国名」を記載。

(2) 産地情報を知ることができる方法により伝達する場合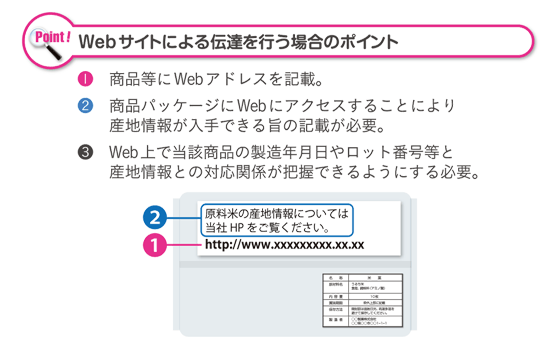

産地情報の伝達が不要となる場合
平成23年7月1日より前に生産者が出荷した米を原料に用いている場合
- 平成23年7月1日に小売店の棚に並んでいる商品、飲食店で提供される米飯類は、その大部分が7月1日以降に出荷されたものでないと考えられることから、産地情報伝達の義務が発生しないことに注意が必要です。
- 平成23年産米であっても、7月1日より前に生産者が出荷した超早場米、あるいはその米を原料に使用している米加工品は、産地情報伝達の義務は生じません。
- 米トレーサビリティ法の産地情報伝達の義務が発生していない米であっても、食品表示法の産地表示の対象となっている場合には、食品表示法に基づく表示をする必要があります。
なお、平成22年産米やそれ以前に生産された米であっても、平成23年7月1日以降に生産者が出荷した米については産地情報伝達の義務が生じます。
平成23年7月1日より前に国内において取引された、輸入された米若しくは米加工品を原料に用いている場合
- 平成23年7月1日より前に生産者が出荷した米を原料に用いている場合と同様です。
非食用の場合
- 飼料用、バイオエタノール原料用等の非食用のものについては、産地情報伝達の義務は生じません。
米トレーサビリティ制度関係法令
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)(PDF : 130KB)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第260号)(PDF:10KB)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成21年政令第261号)(PDF:123KB)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令(平成21年財務省令・農林水産省令第1号)(PDF : 63KB)
- 米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成21年内閣府令・財務省令・農林水産省令第1号)(PDF : 62KB)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第4項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する省令(平成21年農林水産省令第61号)(PDF:12KB)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第3項及び第4項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する命令(平成21年内閣府令・農林水産省令第11号)(PDF:13KB)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条第1号の農林水産大臣が定める方法及び基準を定める件(平成21年農林水産省告示第1551号)(PDF:12KB)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る第9条の勧告及び公表の指針について(PDF:62KB)
- 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令(PDF : 125KB)
- 米トレーサビリティ制度の概要と条項を対比して確認される場合には、以下の資料を参考にしてください。
- <参考資料>米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律、施行令、施行規則等三段表(PDF : 263KB)
(注)三段表については参考資料として作成したものであり、ご利用の際には個別の条文をご確認ください。
Q&A
(問) 米トレーサビリティ法では、どうして記録を作成する必要があるのですか。
(問) 事業者間の取引についても産地情報の伝達が、どうして必要なのですか。
(問) 業務用加工食品と業務用生鮮食品についても産地情報の伝達の義務がかかりますか。
(問) 対象品目について量り売りをする対面販売などの場合であっても、産地情報の伝達が必要ですか。
(問) 輸入品の場合、例えば「カリフォルニア産」等と国名を省略した形で記載することはできますか。
(問) 記録は事業所、事業場または店舗ごとに作成する必要がありますか。
お問合せ先
〇米トレーサビリティ法に関する問合せ
問合せ先一覧(PDF : 299KB)
〇産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示課
代表:03-3507-8800
〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当:米穀流通・食品表示監視室





