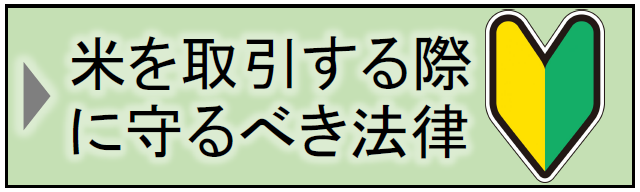消費者のみなさまへ
- 米トレーサビリティ法は何を目的に作られた制度でしょうか。
- 対象になる米やお米の加工品には、どんなものがありますか。
- 産地情報がわかるようになるそうですが、もう少し詳しく教えてください。
- Q&A
- お問合せ先
米トレーサビリティ法は何を目的に作られた制度でしょうか。
米トレーサビリティ法とは
食品事故などの問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するための米や米加工品の取引等の記録を作成・保存することを事業者に義務付けています。
また、消費者の皆様の商品選択の際の参考とするため、事業者に産地情報の伝達を義務付けます。

米トレーサビリティ法で何が変わりますか
小売店等で米や米加工品の原料米の産地が消費者の皆様に伝達されます。
また、外食店等では、米加工品のうち米飯類のみの原料米の産地が伝達されることになります。
対象になる米やお米の加工品には、どんなものがありますか。
米トレーサビリティ法の対象になるのは、
- 米穀(玄米・精米等)
- 米粉(上新粉、みじん粉、洋菓子用米粉など)、米こうじ
- 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
産地情報がわかるようになるそうですが、もう少し詳しく教えてください。
米・米加工品の産地又は産地を知ることができる方法は、次のような方法で伝達されます。
- 商品の包装に記載
- 通販の購入カタログに掲示
- 飲食店のメニュー等に表記
Q&A
(問) 「もち」や「だんご」等を販売している店舗において、店内で食べることができる場所を設けている場合、そこで一般消費者が食す際には、産地情報の伝達が必要となりますか。
(答)小売店の店内に飲食スペースを設け、そのスペースで飲食するために提供する場合もレストラン等外食事業者が食事ができるスペースを設けて対象品目を一般消費者に提供する場合と同様に、米飯類のみについて産地情報伝達が必要であり、「もち」や「だんご」が提供される場合には、原料米の産地情報伝達は不要です。
(問) 対象品目なのに産地、又は産地を知ることができる方法が書かれていない商品が売られているのですが、制度に違反しているのでしょうか。
(答)平成23年7月1日より前に(ア)国内で生産されたものについては、生産者が出荷した米穀、(イ)輸入されたものについては、国内の米穀事業者に譲り渡しをされた米穀、米加工品、(ウ)(ア)又は(イ)を原料に使用した米加工品は、産地情報伝達の必要はありません。
なお、平成22年産米やそれ以上に古い米であっても、平成23年7月1日以降に生産者が出荷した米については産地情報の伝達が必要です。
なお、平成22年産米やそれ以上に古い米であっても、平成23年7月1日以降に生産者が出荷した米については産地情報の伝達が必要です。
お問合せ先
〇米トレーサビリティ法に関する問合せ
問合せ先一覧(PDF : 299KB)
〇産地情報の伝達・表示に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示課
代表:03-3507-8800
〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当:米穀流通・食品表示監視室