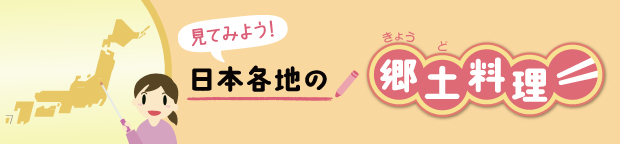

がめ煮(に)(筑前煮(ちくぜんに))
どんな料理?
「がめ煮(に)」は福岡県(ふくおかけん)の代表的な郷土(きょうど)料理です。文禄(ぶんろく)元年(1592年)に豊臣秀吉(とよとみひでよし)が起こした文禄(ぶんろく)の役(えき)で出兵した兵しが食べたのが始まりといわれています。昔、福岡県(ふくおかけん)の北部を「筑前(ちくぜん)の国」といっていたことから、「筑前煮(ちくぜんに)」ともよばれており、こちらの方がなじみがある方も多いかもしれません。
作り方・食べ方
当初、「どぶがめ」とよばれていたスッポンと、ごぼうやにんじん、しいたけ、里イモなどありあわせの材料をにこんで作っていましたが、今では、スッポンではなく、とり肉を使うのがいっぱん的です。福岡県(ふくおかけん)では、「がめ煮(に)」は、正月やお祭り、運動会など行事があると必ずといっていいほど作る料理です。夏にはいもや大根が入らなかったり、そう式のときはとり肉が入らなかったりと、季節や行事によって具材が変わります。
由来・話題など
「がめ煮(に)」の名前は、「がめくりこむ」(よせあつめる)という博多の方言に由来するという説や、豊臣秀吉(とよとみひでよし)が朝鮮(ちょうせん)に出兵するため博多(はかた)に立ちよったときに、博多べんで「がめ」とよばれるスッポンをつかまえて野菜といっしょににたことに由来するという説などがあります。ちなみに、福岡県(ふくおかけん)は、とり肉とごぼうのしょうひ量が全国的にみても多い方ですが、それは「がめ煮(に)」をよく作るからだといわれています。








