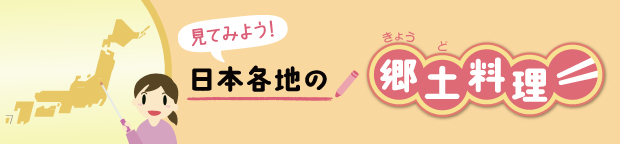

富山県(とやまけん)
ます寿司(ずし)
駅べんとしても知名度が高い
お土産の定番
お土産の定番
どんな料理?
「ます寿司(ずし)」は、ますの切り身をすめしにのせてささの葉でつつんだ、富山県(とやまけん)を代表する郷土(きょうど)料理です。江戸(えど)時代にあゆ寿司(ずし)として生まれ、徳川幕府八代将軍(とくがわばくふはちだいしょうぐん)の徳川吉宗(とくがわよしむね)に献上(けんじょう)したところ、大いによろこばれました。その後は、富山市(とやまし)を流れる神通川(じんずうがわ)のサクラマスを使い、これが今の「ます寿司(ずし)」となりました。
作り方・食べ方
「ます寿司(ずし)」には、ささの葉を開くと、ますが上にならんでいる「表おき」と、「裏(うら)おき」の2種類があります。「表置き」はますのうまみがすめしに広がり一体感が出る味わいで、「裏(うら)置き」はますが下にあるため、すめしに魚のあぶらがうつりにくくさっぱりとした味わいになります。
由来・話題など
「ます寿司(ずし)」は、おぼんや年末年始などのおめでたい席で食べられています。大正時代に駅べんとして売り出されたことから全国的に知名度が高く、富山県(とやまけん)では料理やお土産の定番にもなっています。








