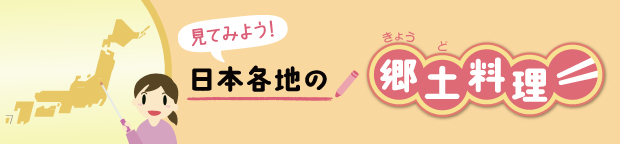

おやき
米代わりの食べ物
どんな料理?
「おやき」は、小麦ことそばこで作った皮に、あずきのあんや野菜などを包み、むしたり焼いたりしたおまんじゅうのような食べ物です。れきしは古く、縄文(じょうもん)時代には、その原けいと思われるものが作られていたといいます。長野県(ながのけん)は山が多くて寒く、米があまり作れないため、おやきは米の代わりとして人びとの生活をささえてきました。
作り方・食べ方
「おやき」には、春はよもぎ、夏はなす、秋はさつまいも、冬はりんごなど季節の野菜や果物を使ったものがあり、一年中食べられていて生活にとけこんでいます。また、おやきは中身もさまざまですが、作り方もさまざまです。昔は、鉄のなべで表面を焼いたあといろりのはいの中に入れてむすという方法が主流でしたが、時がたつにつれて、「むす」「焼く」「焼いてむす」「むして焼く」などさまざまな作り方が生み出されてきました。
由来・話題など
「おやき」は、食事やおやつとして食べられているほか、観光時の食べ歩きやお土産(みやげ)として長野県(ながのけん)内外の人に親しまれています。また、北信(ほくしん)地いきではおぼんの時期に、「おやき」を先ぞにおそなえするという習かんがあり、生活に深く関わっています。







