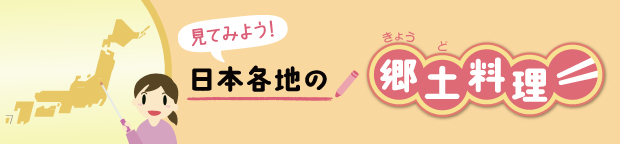

福井県(ふくいけん)
へしこ
長期ほぞんができる
さばの塩づけ
さばの塩づけ
どんな料理?
「へしこ」は、福井県(ふくいけん)の日本海側を中心に伝わる郷土(きょうど)食です。内ぞうをとりだしたさばを塩づけし、さらにぬかづけにして長期ほぞんができるようになっています。福井県(ふくいけん)だけでなく、石川県(いしかわけん)や京都府(きょうとふ)、和歌山県(わかやまけん)などでも食べられています。
作り方・食べ方
「へしこ」は、ご飯のおともやパスタやトーストのトッピングとして食べられています。以前は、「へしこ」を米麹(こめこうじ)でさらにつけこんだ「なれずし」が、正月などに家庭でふるまわれ、おめでたい場でのかかせないごちそうでした。
由来・話題など
「へしこ」の名前の由来には、魚をたるにおしこみながらつけることを「圧(へ)しこむ」といったことや、魚を塩づけして出てきた水分である「干潮(ひしお)」がなまって「へしこ」になったことなど、いくつかの説があります。








