「国際果実野菜年2021」野菜・果物のおすすめレシピ・食べ方のご紹介

農林水産省では、国連で採択された「国際果実野菜年2021」の取組の一環で、健康的な食事に欠 かせない果物や野菜に関して、一般家庭で作ること・食べることができるおすすめレシピ・食べ 方の第1弾を昨年6月~8月まで募集し、全国から応募いただいた259品のなかから特に優れたレシ ピ21品についてはこれを表彰するとともに、応募レシピ全てを農林水産省のWebページに掲載しています。
上記の取組に引き続き、第2弾として果物や野菜に関するレシピ・食べ方を昨年12月1日~ 本年2月1日まで募集しました。
その結果、全国から177品の応募があり、管理栄養士による審査の結果、特に優れたレシピ18品に ついてはこれを表彰・公表するとともに、応募いただいた177品全てを農林水産省Webサイトで紹介します。
気に入ったレシピを見つけて料理にチャレンジしてみませんか?
本サイトの特徴
野菜・果物の1人1日当たりの平均摂取量(令和元年)は野菜280.5g、果物100.2gで、「健康日本21(第二次)」(厚生労働省策定)等で目標とする野菜350g、果物200gにいずれも達していません。
本サイトでは、430品を超えるレシピの中から、(ア)野菜と果物の食材から、(イ)1品で1人が摂取できる野菜と果物の量から、(ウ)調理時間から、それぞれ希望のレシピを検索することができます。
また、現在、お手頃価格の野菜を使ったレシピをタイムリーにご紹介します。
注:本サイトでご紹介する各レシピで摂取可能な1人分の野菜と果物の重量については、野菜の重量には豆類(高度な加工品は除く)、いも類、きのこ類、海藻類を含み、果物の重量にはナッツ類を含んで積算しています。また、重量計算は、食材の大きさの記載がない場合は標準的な重量で積算しています。
受賞レシピ
受賞レシピは、「国際果実野菜年2021」おすすめレシピ・食べ方に関する実施要領(PDF : 430KB)第4に基づき、正確性、見栄え、汎用性、独創性、普及性の観点から特に優れたレシピ39品を選定しています。
 受賞レシピ(第2弾)
受賞レシピ(第2弾)
(50音順)
受賞レシピ(第1弾)
(50音順)
国際果実野菜年2021 受賞レシピ集PDFは下記になります。
レシピを印刷する際はこちらを印刷してください。
国際果実野菜年2021 レシピ集_Part1(PDF : 1,918KB) Part2(PDF : 1,983KB) Part3(PDF : 2,222KB) Part4(PDF : 1,827KB) Part5(PDF : 1,740KB) Part6(PDF : 1,197KB)
受賞レシピの動画
受賞レシピの一部について、作り方の手順を動画でご紹介します。
|
ミニトマトごまみそ汁 |
白ねぎと明太子のとろとろ煮 |
|
レンジで簡単!みかんキーマカレー |
1ボウルでできる小松菜と旬野菜のケーク・サレ☆ |
お買得野菜を使ったレシピ
|
ほうれんそう |
||
|
|
||
レシピ一覧
 免疫アップ野菜炒め(JICA Himachal)
免疫アップ野菜炒め(JICA Himachal) きな粉とリンゴの蒸しケーキ(JICA Himachal)
きな粉とリンゴの蒸しケーキ(JICA Himachal) ズッキーニとニンジンのパンケーキ(JICA Himachal)
ズッキーニとニンジンのパンケーキ(JICA Himachal) ドライフルーツとナッツのきな粉バー(JICA Himachal)
ドライフルーツとナッツのきな粉バー(JICA Himachal) チンゲン菜のお焼き(JICA Himachal)
チンゲン菜のお焼き(JICA Himachal) ブロッコリーとカッテージチーズのサブジ(JICA Himachal)
ブロッコリーとカッテージチーズのサブジ(JICA Himachal) 蒸しサトイモのサブジ(JICA Himachal)
蒸しサトイモのサブジ(JICA Himachal) 豚肉と新玉ねぎのサラダ
豚肉と新玉ねぎのサラダ ニラのプルコギ風炒め
ニラのプルコギ風炒め 大根の皮のめんつゆ炒め
大根の皮のめんつゆ炒め食材から探す
いずれかの項目を1つ選択すると、該当するレシピが表示されます。すべてのメニューの表示に戻るには「すべてのメニュー」をクリックしてください。
野菜のレシピ
レシピ監修者のご紹介
 |
竹内 冨貴子 先生 |
 |
内野 美恵 先生 東京家政大学ヒューマンライフ支援センター准教授/東京都食育推進委員会委員/(公財)日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会医科学情報サポート栄養担当/(公財)キューピーみらいたまご財団理事/東京家政大学ワークライフバランスin農業女子プロジェクト主宰ほか。管理栄養士、公認スポーツ栄養士、博士(学術)。 |
 |
金高 有里 先生 札幌保健医療大学准教授/NPO法人青果物健康推進協会顧問。 |
お問合せ先
農産局園芸作物課
代表:03-3502-8111(内線4790)
ダイヤルイン:03-3501-4096







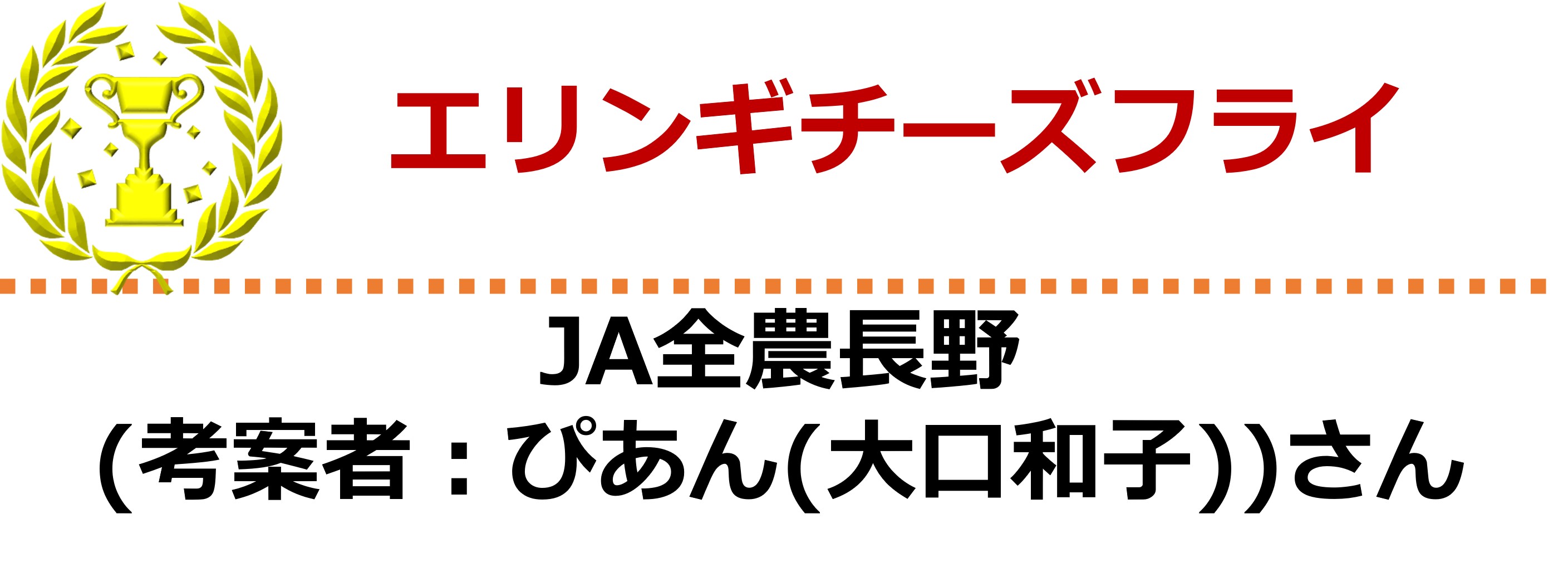













































































 合っちゃう?!KBC
合っちゃう?!KBC 揚げたくない方におすすめ!にんじん天
揚げたくない方におすすめ!にんじん天 3つの「み」がつくふりかけ
3つの「み」がつくふりかけ 地球にやさしいガッツリお肉!!
地球にやさしいガッツリお肉!! 揚げない!キャベツとコーンのヘルシーおから春巻き
揚げない!キャベツとコーンのヘルシーおから春巻き 丹波大納言小豆のホッとほっこりニョッキ
丹波大納言小豆のホッとほっこりニョッキ 丹波大納言小豆で秘密のずぼら大人パウンドケーキ
丹波大納言小豆で秘密のずぼら大人パウンドケーキ ちゃちゃっと豪華に聖護院かぶの紅白おむすび
ちゃちゃっと豪華に聖護院かぶの紅白おむすび りんごと豆苗の肉巻き塩麹おろし
りんごと豆苗の肉巻き塩麹おろし ナスのロコモコ丼
ナスのロコモコ丼 カリーノケールのチョップドサラダ
カリーノケールのチョップドサラダ とろ~り旨なすの揚げ浸し風
とろ~り旨なすの揚げ浸し風 モロヘイヤ餃子
モロヘイヤ餃子 包まないモロヘイヤ餃子
包まないモロヘイヤ餃子 モロヘイヤのペペロンチーノ
モロヘイヤのペペロンチーノ モロヘイヤのサラダ
モロヘイヤのサラダ モロヘイヤ太巻き
モロヘイヤ太巻き きのこたっぷり かきたま風ラーメン
きのこたっぷり かきたま風ラーメン 野菜たっぷり イタリアントマト塩ラーメン
野菜たっぷり イタリアントマト塩ラーメン からだポカポカ 旨辛プデチゲラーメン
からだポカポカ 旨辛プデチゲラーメン クリスマスリースのクリーミーラーメン
クリスマスリースのクリーミーラーメン 焼きキャベ塩レモンバター麺
焼きキャベ塩レモンバター麺 たけのことアスパラの和風ラーメン
たけのことアスパラの和風ラーメン たっぷり新玉ねぎの南蛮ラーメン
たっぷり新玉ねぎの南蛮ラーメン 2分の1日分の野菜がとれる 豆乳あんかけ焼きそば
2分の1日分の野菜がとれる 豆乳あんかけ焼きそば やみつきニンニクのねぎ豚ラーメン
やみつきニンニクのねぎ豚ラーメン 白菜とベーコンのクリーミー味噌ラーメン
白菜とベーコンのクリーミー味噌ラーメン 生姜香る 豚肉と長ネギの旨味ラーメン
生姜香る 豚肉と長ネギの旨味ラーメン アサリと春キャベツの旨塩ラーメン
アサリと春キャベツの旨塩ラーメン 台湾そぼろルーローラーメン
台湾そぼろルーローラーメン 旨みじゅわっと 秋ナスとひき肉の味噌ラーメン
旨みじゅわっと 秋ナスとひき肉の味噌ラーメン ゴロゴロ野菜のほっこり味噌ラーメン
ゴロゴロ野菜のほっこり味噌ラーメン ピリッと香る!鶏わさびのあったかとろろラーメン
ピリッと香る!鶏わさびのあったかとろろラーメン 柚子香る 雪うさぎのみぞれラーメン
柚子香る 雪うさぎのみぞれラーメン 夏に負けるな!ビタミンたっぷりグリーンカレーラーメン
夏に負けるな!ビタミンたっぷりグリーンカレーラーメン コロナに負けるな!秋田だまっこラーメン
コロナに負けるな!秋田だまっこラーメン がんばれ受験生!!エコな塩カレーラーメン
がんばれ受験生!!エコな塩カレーラーメン カルシウムたっぷり♡牛乳ラーメン
カルシウムたっぷり♡牛乳ラーメン 宇宙人ウインナーとコーンの 卵のっけラーメン
宇宙人ウインナーとコーンの 卵のっけラーメン 野菜を楽しもう!やみつき爆盛りしょうゆラーメン
野菜を楽しもう!やみつき爆盛りしょうゆラーメン ヘルシー♪アスパラと豆腐のホイル焼きグラタン
ヘルシー♪アスパラと豆腐のホイル焼きグラタン 炊飯器deまるごと肉がけデミキャベツ
炊飯器deまるごと肉がけデミキャベツ まるごとオニオンスープ
まるごとオニオンスープ 炒めインスタントラーメンのあんかけ
炒めインスタントラーメンのあんかけ エリンギと鱧のかき揚げ
エリンギと鱧のかき揚げ オートミールのチャーハンお好み焼き
オートミールのチャーハンお好み焼き カブと牡蠣の白みそ煮(汁)
カブと牡蠣の白みそ煮(汁) くるみとそばのごまサラダ
くるみとそばのごまサラダ すっきり大分県鶏汁(かしわじる)
すっきり大分県鶏汁(かしわじる) ラディッシュと鱧のおひねり揚げ
ラディッシュと鱧のおひねり揚げ 胃にやさしい彩野菜卵かゆ
胃にやさしい彩野菜卵かゆ 温サラダ
温サラダ 春の豚肉巻き
春の豚肉巻き 大分カボスカレー
大分カボスカレー 冬瓜のすき焼き煮
冬瓜のすき焼き煮 南蛮カボチャの味噌煮
南蛮カボチャの味噌煮 クコの実アボガドご飯
クコの実アボガドご飯 焼きそば麺で、きのこたっぷり担々麵
焼きそば麺で、きのこたっぷり担々麵 高野豆腐の唐揚げときのこたっぷり甘酢あん
高野豆腐の唐揚げときのこたっぷり甘酢あん エリンギチーズフライ
エリンギチーズフライ エリンギとシーフードミックスのパエリア風ご飯
エリンギとシーフードミックスのパエリア風ご飯 エリンギとサラダチキンのベトナム風スープご飯
エリンギとサラダチキンのベトナム風スープご飯 エリンギと鶏ささみの重ね蒸し
エリンギと鶏ささみの重ね蒸し えのきたっぷり!逆さまシュウマイ
えのきたっぷり!逆さまシュウマイ レンチンえのきの明太子和え
レンチンえのきの明太子和え ハッセルバックエリンギ
ハッセルバックエリンギ 鶏エリンギごはんの和風オムライス
鶏エリンギごはんの和風オムライス ミニミニいきなり団子
ミニミニいきなり団子 なすの葉ぐるみ
なすの葉ぐるみ ごぼうジェット
ごぼうジェット スイートじゃがいも
スイートじゃがいも アボカドのショコラムース
アボカドのショコラムース あっという間にできる!生姜入りジュレ!!
あっという間にできる!生姜入りジュレ!! お手軽!キャベツと油揚げのきつねうどん風
お手軽!キャベツと油揚げのきつねうどん風 さっぱり!!熊本県産ナスときゅうりのサイコロ小鉢
さっぱり!!熊本県産ナスときゅうりのサイコロ小鉢 たっぷりキャベツとスライス生姜のヤリイカ炒め
たっぷりキャベツとスライス生姜のヤリイカ炒め フライパンで簡単にできる!ズッキーニのオムレツ!
フライパンで簡単にできる!ズッキーニのオムレツ! 簡単!!シャキシャキきゅうりのサラダ
簡単!!シャキシャキきゅうりのサラダ 簡単!!フルーツトマトと鶏肉の冷やしうどん
簡単!!フルーツトマトと鶏肉の冷やしうどん 子どもも大好き!!ほぼほぼキャベツの卵焼き!
子どもも大好き!!ほぼほぼキャベツの卵焼き! 時短!!オクラ入り鮭の混ぜご飯
時短!!オクラ入り鮭の混ぜご飯 超ヘルシー!キャベツと大豆ミートの皿うどん!!
超ヘルシー!キャベツと大豆ミートの皿うどん!! 味変する!大長ナスとピーマンとこんにゃくの甘辛炒め
味変する!大長ナスとピーマンとこんにゃくの甘辛炒め 混ぜるだけ!簡単で美味しい小松菜の混ぜご飯!!
混ぜるだけ!簡単で美味しい小松菜の混ぜご飯!! トマト根菜カレー
トマト根菜カレー トマト麻婆豆腐
トマト麻婆豆腐 生姜が決め手の夏野菜豚汁
生姜が決め手の夏野菜豚汁 ゆで鶏の赤ぶどうソース
ゆで鶏の赤ぶどうソース おろしトマトの夏豚汁~冷や汁仕立て~
おろしトマトの夏豚汁~冷や汁仕立て~ どーんと!そぼろかぼちゃ和風ホワイトソース仕立て
どーんと!そぼろかぼちゃ和風ホワイトソース仕立て 丸ごとピーマンの焼き浸し
丸ごとピーマンの焼き浸し ねぎと梅肉のさっぱり春巻き
ねぎと梅肉のさっぱり春巻き 野菜たっぷりガレット風
野菜たっぷりガレット風 もりもり白菜
もりもり白菜 苺とチーズの肉巻き
苺とチーズの肉巻き ちーずじゃがじゃが焼き
ちーずじゃがじゃが焼き タラの芽グラタン
タラの芽グラタン セロリのジェノベーゼ風パスタ
セロリのジェノベーゼ風パスタ シナモン塩で食べるりんごと春菊のかき揚げ
シナモン塩で食べるりんごと春菊のかき揚げ トマトレアチーズケーキ
トマトレアチーズケーキ トマチーご飯(トマトとチーズの炊き込みご飯)
トマチーご飯(トマトとチーズの炊き込みご飯) カッペリーニ風梅トマトそうめん
カッペリーニ風梅トマトそうめん 里芋とチーズの蓮根はさみ揚げ
里芋とチーズの蓮根はさみ揚げ 白菜の肉巻きクリーム煮
白菜の肉巻きクリーム煮 伊予かんムース
伊予かんムース ピーマンボートのツナチーズ
ピーマンボートのツナチーズ どーや!カレーでゴーヤチャンプル
どーや!カレーでゴーヤチャンプル 彩りキレイな野菜ばたけ
彩りキレイな野菜ばたけ 親子で作って楽しい! かぼちゃの月見団子(1歳~)
親子で作って楽しい! かぼちゃの月見団子(1歳~) 梨の食感、ねぎの香ばしさがたまらない!豚肉の炒め物
梨の食感、ねぎの香ばしさがたまらない!豚肉の炒め物 とうもろこし1本まるごとバスク風チーズケーキ
とうもろこし1本まるごとバスク風チーズケーキ 秋を感じるシャキッほくほくな蓮根と落花生のきんぴら
秋を感じるシャキッほくほくな蓮根と落花生のきんぴら サフランがなくても◎ 鮭ととうもろこしの和風パエリア
サフランがなくても◎ 鮭ととうもろこしの和風パエリア 3分で作れる簡単ヘルシー柿のおつまみ♪
3分で作れる簡単ヘルシー柿のおつまみ♪ ビタミンCたっぷり! 鶏肉のレモンマスタード焼き
ビタミンCたっぷり! 鶏肉のレモンマスタード焼き ビタミンCたっぷり! 鶏肉のトマトとりんごの煮込み
ビタミンCたっぷり! 鶏肉のトマトとりんごの煮込み 風邪の予防に!5分で作れる副菜キャロットラペ
風邪の予防に!5分で作れる副菜キャロットラペ 妊婦にお勧め! さっぱり食べられる豆乳そうめん
妊婦にお勧め! さっぱり食べられる豆乳そうめん しめじ石づきのアヒージョ風油そば
しめじ石づきのアヒージョ風油そば 酸っぱいシーなキウイカレー
酸っぱいシーなキウイカレー あっさぶメークインと黒豆のドーナツ
あっさぶメークインと黒豆のドーナツ さがらマロンと小豆のチーズケーキ
さがらマロンと小豆のチーズケーキ レンジで作る大根ジャム
レンジで作る大根ジャム 干し椎茸の牛乳坦々麺
干し椎茸の牛乳坦々麺 紅しぐれのポタージュスープ
紅しぐれのポタージュスープ 大和芋のとろ~ろレアチーズ
大和芋のとろ~ろレアチーズ レンジで簡単!かぶら蒸し
レンジで簡単!かぶら蒸し レンジで簡単!大葉香る和風ガパオ
レンジで簡単!大葉香る和風ガパオ レンジで作るみかん蒸しパン
レンジで作るみかん蒸しパン 野菜たっぷりシェパーズパイ
野菜たっぷりシェパーズパイ カリフラワーライスのサラダ生春巻き
カリフラワーライスのサラダ生春巻き たき込みトマトカレーに追いトマトのトッピング
たき込みトマトカレーに追いトマトのトッピング 追いトマトミネストローネ
追いトマトミネストローネ ズッキーニとあさりの酒蒸し
ズッキーニとあさりの酒蒸し レモン香るふきのチーズパイ
レモン香るふきのチーズパイ 春野菜のアンチョビ和え
春野菜のアンチョビ和え かぶとさつまあげの甘辛炒め
かぶとさつまあげの甘辛炒め コク旨!甘酸っぱいチキンと根菜の煮物
コク旨!甘酸っぱいチキンと根菜の煮物 たけのこの天ぷら
たけのこの天ぷら アスパラガスとねぎの洋風ぬた和え
アスパラガスとねぎの洋風ぬた和え ごはんも置き換え!ヘルシー野菜いなり寿司
ごはんも置き換え!ヘルシー野菜いなり寿司 軸までむだなく!2種のきのこチップス
軸までむだなく!2種のきのこチップス 茎までむだなく使って!ブロッコリー餃子
茎までむだなく使って!ブロッコリー餃子 レンジで簡単!れんこんと長ねぎのシャキシャキナムル
レンジで簡単!れんこんと長ねぎのシャキシャキナムル トマトドライカレー
トマトドライカレー 蓮根と林檎のわらび餅風
蓮根と林檎のわらび餅風 万能きのこソース
万能きのこソース 彩り生野菜でご飯が進む!山形のだし
彩り生野菜でご飯が進む!山形のだし 小松菜de具だくさんシーフードチャウダー
小松菜de具だくさんシーフードチャウダー きんぴらミルフィーユオムレツ
きんぴらミルフィーユオムレツ 大根ご飯
大根ご飯 甘み際だつ枯露柿のライスガレット
甘み際だつ枯露柿のライスガレット イチゴの彩りサラダ
イチゴの彩りサラダ お箸が止まらない!小ねぎの即席ナムル
お箸が止まらない!小ねぎの即席ナムル かぶの鶏挽肉詰め和風あんかけ
かぶの鶏挽肉詰め和風あんかけ プチヴェールとほたるイカのパスタ
プチヴェールとほたるイカのパスタ 鶏肉のネギダレかけ
鶏肉のネギダレかけ 白ねぎキムチ
白ねぎキムチ 白ねぎと秋の味覚のゴマ味噌揚げ
白ねぎと秋の味覚のゴマ味噌揚げ 白ねぎと春キャベツのメンチカツ
白ねぎと春キャベツのメンチカツ 白ねぎと日南トマトのスープ
白ねぎと日南トマトのスープ 白ねぎのあっさり風味
白ねぎのあっさり風味 白ねぎのキッシュ
白ねぎのキッシュ 白ねぎの豚肉巻き
白ねぎの豚肉巻き 白ねぎの梅なます
白ねぎの梅なます アスパラのフレッシュサラダ
アスパラのフレッシュサラダ お洒落なかぶのオードブルいろいろ
お洒落なかぶのオードブルいろいろ かぶパッチョ
かぶパッチョ かぶナッペ
かぶナッペ かぶマンジェ
かぶマンジェ 生ハムかぶ
生ハムかぶ カリフラワーのシンプルサラダ
カリフラワーのシンプルサラダ カリフラワーの丸ごとスープ
カリフラワーの丸ごとスープ シュークレープ
シュークレープ スコッチ芽キャベツ
スコッチ芽キャベツ みかんカップのフォンダンショコラ
みかんカップのフォンダンショコラ 一見マリトッツォ風フラワーフルーツサンド
一見マリトッツォ風フラワーフルーツサンド 彩り野菜の即興温サラダ
彩り野菜の即興温サラダ 炒めなます
炒めなます

 フルーツトマトのベーコン炒め
フルーツトマトのベーコン炒め

 ちょうどいい温桃のサラダ
ちょうどいい温桃のサラダ 小松菜のパウンドケーキ
小松菜のパウンドケーキ 1ボウルでできる小松菜と旬野菜のケーク・サレ☆
1ボウルでできる小松菜と旬野菜のケーク・サレ☆ 白ねぎのらっきょう酢漬け
白ねぎのらっきょう酢漬け 不思議すいか
不思議すいか サラダ寒天
サラダ寒天 野菜の宝石箱
野菜の宝石箱 ごぼうたっぷり缶詰de柳川風卵とじ
ごぼうたっぷり缶詰de柳川風卵とじ トマトたっぷりコラーゲン鍋
トマトたっぷりコラーゲン鍋 なすと豆苗の肉巻き
なすと豆苗の肉巻き ねばねばサイコロサラダ
ねばねばサイコロサラダ パプリカとオクラの白和え
パプリカとオクラの白和え 簡単ひじきと
簡単ひじきと アスパラのハニーマスタード
アスパラのハニーマスタード アボカドとミニトマトのスパムトースター焼き
アボカドとミニトマトのスパムトースター焼き かんたん!長ネギのベーコン巻き
かんたん!長ネギのベーコン巻き たけのこメンマ
たけのこメンマ ツナと枝豆の緑茶素麺
ツナと枝豆の緑茶素麺 トマトカップdeライスサラダ
トマトカップdeライスサラダ パプリカと焼き鳥缶のアヒージョ
パプリカと焼き鳥缶のアヒージョ ふきとちくわの梅マヨ和え
ふきとちくわの梅マヨ和え 夏野菜と豚肉のカレー炒め
夏野菜と豚肉のカレー炒め 菜の花とチキンのさっぱり和え
菜の花とチキンのさっぱり和え きのこの旨塩ナムル
きのこの旨塩ナムル きゅうりとピリ辛サーモン丼
きゅうりとピリ辛サーモン丼 スプラウトのさっぱり素麺
スプラウトのさっぱり素麺 セロリと鮭の豆乳石狩鍋
セロリと鮭の豆乳石狩鍋 なめたけと大葉の焼きおにぎり
なめたけと大葉の焼きおにぎり ふわふわきのこ出汁鍋
ふわふわきのこ出汁鍋 レタスたっぷり餃子鍋
レタスたっぷり餃子鍋 レンチンまるごとタマネギ
レンチンまるごとタマネギ 缶詰deフルーツオープンサンド
缶詰deフルーツオープンサンド 葱たっぷり厚揚げ豆腐の油淋鶏
葱たっぷり厚揚げ豆腐の油淋鶏 舞茸の簡単チーズリゾット
舞茸の簡単チーズリゾット 卵豆腐de茶碗蒸し
卵豆腐de茶碗蒸し トマトのさっぱり丼
トマトのさっぱり丼 りんご握りずしアラカルト
りんご握りずしアラカルト 秋、きのこのおにぎり
秋、きのこのおにぎり 椎茸の変わり揚げ9種
椎茸の変わり揚げ9種 椎茸DEおせち
椎茸DEおせち 宇宙(そら)芋ごはん(むかごの炊き込みご飯)
宇宙(そら)芋ごはん(むかごの炊き込みご飯) そら豆鞘のかき揚げ
そら豆鞘のかき揚げ 大和りんごの花びら黄太平と新疆野苹果のスープ
大和りんごの花びら黄太平と新疆野苹果のスープ 加賀友禅
加賀友禅 紫草の天ぷら
紫草の天ぷら 握りずしに野菜を使う
握りずしに野菜を使う カワハギのアスピックゼリー手巻きキャベツ巻き
カワハギのアスピックゼリー手巻きキャベツ巻き 晩白柚と鮭のムニエル
晩白柚と鮭のムニエル コリンキーの茶碗蒸し
コリンキーの茶碗蒸し 餅トウモロコシのスープ
餅トウモロコシのスープ 琉球王朝モーウィの和え物
琉球王朝モーウィの和え物 大分野菜どんぶり
大分野菜どんぶり オートミールフルーツケーキとサラミケーキ
オートミールフルーツケーキとサラミケーキ 野菜のお祭りサラダ
野菜のお祭りサラダ ベジフル♪トライフルのっぺ汁
ベジフル♪トライフルのっぺ汁 夏の元気を応援!カラフルスイカそうめん
夏の元気を応援!カラフルスイカそうめん スイカとトマトの冷製パスタ
スイカとトマトの冷製パスタ 五感で楽しむ!三つの調味料で夏野菜の揚げ浸し風
五感で楽しむ!三つの調味料で夏野菜の揚げ浸し風 ズッキーニナポリタン
ズッキーニナポリタン いろどり小松菜ロール
いろどり小松菜ロール 一口トマトの簡単ラズベリーソースがけ
一口トマトの簡単ラズベリーソースがけ じっくり焼いた丸ごと人参のサラダ
じっくり焼いた丸ごと人参のサラダ トーマーボー豆腐
トーマーボー豆腐 香ばしい緑のかき揚げ
香ばしい緑のかき揚げ きゃらめる・こーん揚げ
きゃらめる・こーん揚げ さっぱりトマサバ炒め
さっぱりトマサバ炒め トマトのあまうま炒め
トマトのあまうま炒め なすと粉チーズのボート焼き
なすと粉チーズのボート焼き ナスのミルフィーユ焼きミートソースがけ
ナスのミルフィーユ焼きミートソースがけ パプトマリネ
パプトマリネ パプリカップのポテトサラダ
パプリカップのポテトサラダ ピザ風ハッセルバックトマト
ピザ風ハッセルバックトマト まるで「仙豆」なおつまみ
まるで「仙豆」なおつまみ アスパラベーコンチョコ
アスパラベーコンチョコ 1日分の野菜チヂミわかめソース
1日分の野菜チヂミわかめソース シイタケ南蛮梅タルタルソース
シイタケ南蛮梅タルタルソース シナモン香るなすジャム
シナモン香るなすジャム 茄子で作るなんちゃって蒲焼風丼
茄子で作るなんちゃって蒲焼風丼 ベジフルタルタル
ベジフルタルタル 白ねぎの天ぷら
白ねぎの天ぷら 白ねぎの浜風チヂミ
白ねぎの浜風チヂミ 白ねぎとじゃこのまぜごはん
白ねぎとじゃこのまぜごはん 白ねぎとささみの生春巻き
白ねぎとささみの生春巻き 白ねぎ将軍鍋
白ねぎ将軍鍋 白ねぎのミルクスープ
白ねぎのミルクスープ 白ねぎと明太子のとろとろ煮
白ねぎと明太子のとろとろ煮 白ねぎのレモンなます
白ねぎのレモンなます 白ねぎの浜サラダ
白ねぎの浜サラダ 白ねぎのドーナッツ
白ねぎのドーナッツ 賀茂なすとジャガイモとろじゅわミルフィーユグリル
賀茂なすとジャガイモとろじゅわミルフィーユグリル 丹波大納言と万願寺甘とうのパエリア
丹波大納言と万願寺甘とうのパエリア 賀茂なす丸ごと贅沢カレー
賀茂なす丸ごと贅沢カレー おまかせ丸投げ賀茂なすご飯~リゾットへ変身編~
おまかせ丸投げ賀茂なすご飯~リゾットへ変身編~ おまかせ丸投げ賀茂なすご飯
おまかせ丸投げ賀茂なすご飯 万願寺甘とうのふんわり肉詰め
万願寺甘とうのふんわり肉詰め ふわとろチーズムース季節のフルーツ添え
ふわとろチーズムース季節のフルーツ添え レンジで簡単!かぼちゃクリームパスタ
レンジで簡単!かぼちゃクリームパスタ サクふわほうとうキッシュ
サクふわほうとうキッシュ かっぱーグステーキのヨーグルトソースがけ
かっぱーグステーキのヨーグルトソースがけ 米なすのデミチーズ焼き
米なすのデミチーズ焼き みかんたっぷり!バターチキンカレー
みかんたっぷり!バターチキンカレー みかんの皮まで捨てずに美味しく!みかんナゲット
みかんの皮まで捨てずに美味しく!みかんナゲット 大和芋のとろ~ろティラミス
大和芋のとろ~ろティラミス あっさぶメークインとラム酒香る黒豆のチーズケーキ
あっさぶメークインとラム酒香る黒豆のチーズケーキ れんこんプリン
れんこんプリン レンジで簡単!みかんキーマカレー
レンジで簡単!みかんキーマカレー みかん風味の塩からあげ
みかん風味の塩からあげ ズッキーニボートのキッシュ風
ズッキーニボートのキッシュ風 ズッキーニのオープンチーズパイ
ズッキーニのオープンチーズパイ トマトだご汁
トマトだご汁 トマト・デ・にゅうめん
トマト・デ・にゅうめん トマト炊き込みご飯
トマト炊き込みご飯 なすの踊り焼き
なすの踊り焼き ミニトマトごまみそ汁
ミニトマトごまみそ汁 パルミドリア
パルミドリア 夏のヘルシースムージー
夏のヘルシースムージー 糖質OFF カリマヨサラダ(ビーガン対応)
糖質OFF カリマヨサラダ(ビーガン対応) もみもみアボカド美肌アイス(ビーガン対応)
もみもみアボカド美肌アイス(ビーガン対応) れ
れ かぼちゃとさつまいものスイーツサラダ
かぼちゃとさつまいものスイーツサラダ レンジde豆腐のロールレタス
レンジde豆腐のロールレタス 桃と豆乳クリームチーズ風ピザ
桃と豆乳クリームチーズ風ピザ 野菜たっぷりピリ辛おかず味噌汁(ヴィーガン対応)
野菜たっぷりピリ辛おかず味噌汁(ヴィーガン対応) なめらかぶどうアイス(ヴィーガン対応).
なめらかぶどうアイス(ヴィーガン対応). お手軽カレースープ
お手軽カレースープ カブのカレースープ
カブのカレースープ カレー風味のラタトゥイユ
カレー風味のラタトゥイユ ごろごろ野菜のスープカレー
ごろごろ野菜のスープカレー さつまいもとチキンのスープカレー
さつまいもとチキンのスープカレー さば缶ドライカレー
さば缶ドライカレー ジンジャー&マンゴーカレー
ジンジャー&マンゴーカレー チキンで彩りキーマカレー
チキンで彩りキーマカレー ツナとカレーのポテトサラダ
ツナとカレーのポテトサラダ ハロウィンカレー&シチュー
ハロウィンカレー&シチュー ベーコンとブロッコリーのスープカレー
ベーコンとブロッコリーのスープカレー 夏でもカレー鍋
夏でもカレー鍋 夏野菜たっぷりカレー
夏野菜たっぷりカレー 夏野菜たっぷりスープカレー
夏野菜たっぷりスープカレー 大根のガンボライス
大根のガンボライス 夏野菜のチキンカレー
夏野菜のチキンカレー 夏野菜のカレー風味マリネ
夏野菜のカレー風味マリネ 夏野菜のカレーマヨトースト
夏野菜のカレーマヨトースト 和風野菜ミックスで作る!ゴロゴロ野菜カレー
和風野菜ミックスで作る!ゴロゴロ野菜カレー りんごのスターカット切り
りんごのスターカット切り レンコン団子 ~三色の野菜のせ~
レンコン団子 ~三色の野菜のせ~ トマトのきつね焼き&きつねおでん
トマトのきつね焼き&きつねおでん ふきのきんぴら
ふきのきんぴら マンゴーマヨネーズのサラダ
マンゴーマヨネーズのサラダ
 トマトのマリネ
トマトのマリネ 柿の卯の花
柿の卯の花 メロンのカナッペ
メロンのカナッペ 果物のディルチーズ和え
果物のディルチーズ和え グレフルサラダ
グレフルサラダ クミンみかんハンバーグ
クミンみかんハンバーグ 甘夏とキャベツのサラダ
甘夏とキャベツのサラダ 梨のキムチサラダ
梨のキムチサラダ 出汁アイスバナナ
出汁アイスバナナ 鶏肉とりんごの照り焼き
鶏肉とりんごの照り焼き 林檎のグラタン
林檎のグラタン 3種のディップソース
3種のディップソース 免疫力UPのWBCスープ
免疫力UPのWBCスープ 桃パスタ~山梨のめぐみ
桃パスタ~山梨のめぐみ 桃大葉包み揚げ
桃大葉包み揚げ ピーマン嫌いにも食べてほしい!ピーマンのコールスロー
ピーマン嫌いにも食べてほしい!ピーマンのコールスロー カラフル野菜の麻婆豆腐
カラフル野菜の麻婆豆腐 焼き鯖のパイナップルマリネ
焼き鯖のパイナップルマリネ 大山ブロッコリーのナゲット風
大山ブロッコリーのナゲット風 大山ブロッコリーのスムージー
大山ブロッコリーのスムージー 大山ブロッコリーの翡翠団子
大山ブロッコリーの翡翠団子 大山ブロッコリーの皮のきんぴら
大山ブロッコリーの皮のきんぴら 大山ブロッコリーの大山チーズ焼き
大山ブロッコリーの大山チーズ焼き 大山ブロッコリーの肉巻き
大山ブロッコリーの肉巻き 大山ブロッコリーのミートローフ
大山ブロッコリーのミートローフ 大山ブロッコリーのライススープ
大山ブロッコリーのライススープ 大山ブロッコリーのブロっこんぶ
大山ブロッコリーのブロっこんぶ 桃と
桃と 野菜うまうまスープ
野菜うまうまスープ 夏に食べたい!トマトティラミス
夏に食べたい!トマトティラミス リンゴリゾット
リンゴリゾット りんごとクリームチーズのトロトロサンドウィッチ
りんごとクリームチーズのトロトロサンドウィッチ すいかゼリー
すいかゼリー サーモンのフルーツマリネ
サーモンのフルーツマリネ コロコロ野菜のゼリー寄せ
コロコロ野菜のゼリー寄せ 野菜肉団子スープ
野菜肉団子スープ お野菜グリーンスープ煮込み
お野菜グリーンスープ煮込み カラフル☆チンジャオトーフ
カラフル☆チンジャオトーフ ブロッコリーのガーリックチーズ蒸し
ブロッコリーのガーリックチーズ蒸し お蕎麦deビビンバ風
お蕎麦deビビンバ風 さわやか~ベジよせ~
さわやか~ベジよせ~ グレープフルーツの生春巻き
グレープフルーツの生春巻き 茄子と肉のサンド焼き
茄子と肉のサンド焼き トマトとグレープフルーツの冷製パスタチーズのせ
トマトとグレープフルーツの冷製パスタチーズのせ 味噌ガーデニング
味噌ガーデニング 1本でも人参!の丸ごとステーキ
1本でも人参!の丸ごとステーキ フルーツタルト
フルーツタルト 彩り野菜のトマトソース
彩り野菜のトマトソース 茄子の中華風彩りあん
茄子の中華風彩りあん カボチャの素揚げエビあん
カボチャの素揚げエビあん ズッキーニと鶏ささ身のレモンクリームパスタ
ズッキーニと鶏ささ身のレモンクリームパスタ フルーツトマトと水茄子のサラダ
フルーツトマトと水茄子のサラダ カリフラワーのガーリックスパイス揚げ
カリフラワーのガーリックスパイス揚げ パパっとできる簡単!トマトリゾット
パパっとできる簡単!トマトリゾット くり抜くだけでプロっぽい!生ハムメロン
くり抜くだけでプロっぽい!生ハムメロン 手軽でリッチなメロンサンド
手軽でリッチなメロンサンド 冷やし水茄子の揚げ出し
冷やし水茄子の揚げ出し 滝川南瓜
滝川南瓜 フルーツ泡ゼリー
フルーツ泡ゼリー モロヘイヤの稲庭うどん
モロヘイヤの稲庭うどん 海老のみの揚げ
海老のみの揚げ 焼きナスゴマクリーム
焼きナスゴマクリーム お手軽キレイ!リンゴのホットケーキタタン
お手軽キレイ!リンゴのホットケーキタタン ミョウガのビネガードリンク
ミョウガのビネガードリンク ニンジンのガレット風
ニンジンのガレット風 スプーンで潰して作ろう♪イチジクの腸活スムージー
スプーンで潰して作ろう♪イチジクの腸活スムージー トウモロコシのペペロンチーノライス
トウモロコシのペペロンチーノライス シシトウとサバ味噌缶のやみつきご飯のお供
シシトウとサバ味噌缶のやみつきご飯のお供 カラフルミニトマトのケッカ風ソースで食べる五穀ライスサラダ
カラフルミニトマトのケッカ風ソースで食べる五穀ライスサラダ 揚げだし大根
揚げだし大根 お事汁
お事汁 ひと口メンチカツ マッシュポテト添え
ひと口メンチカツ マッシュポテト添え 冬至の七種(ななくさ)汁
冬至の七種(ななくさ)汁 大豆と野菜のベジナゲット
大豆と野菜のベジナゲット 新玉ねぎのあべかわ風
新玉ねぎのあべかわ風 新玉ねぎの海老しゅうまい
新玉ねぎの海老しゅうまい ふわとろトンカツ
ふわとろトンカツ おうちパーティに!枝豆の和風ポタージュ
おうちパーティに!枝豆の和風ポタージュ 風邪予防に子どもも大好き新生姜の肉巻きおにぎり
風邪予防に子どもも大好き新生姜の肉巻きおにぎり 鉄分たっぷり!パプリカとひじきの豆腐ハンバーグ
鉄分たっぷり!パプリカとひじきの豆腐ハンバーグ ビタミンCたっぷり!和風ジャーマンポテト
ビタミンCたっぷり!和風ジャーマンポテト 貧血予防!ブロッコリーとあさりのアクアパッツァ
貧血予防!ブロッコリーとあさりのアクアパッツァ 高血圧予防にぷりぷり海老アスパラ!
高血圧予防にぷりぷり海老アスパラ! 動脈硬化予防に!みかんといちごの春色スムージー
動脈硬化予防に!みかんといちごの春色スムージー カルシウムたっぷり!しらすと小松菜のおやき
カルシウムたっぷり!しらすと小松菜のおやき ゴロっとズッキーニとツナのサラダ
ゴロっとズッキーニとツナのサラダ グルテンフリーポテトパンケーキ
グルテンフリーポテトパンケーキ 白菜と長芋の和風ミネストローネ
白菜と長芋の和風ミネストローネ 夏を楽しむ枝豆グリーンサラダ(サルサ風)
夏を楽しむ枝豆グリーンサラダ(サルサ風) ポトフ風巻かないロールキャベツ
ポトフ風巻かないロールキャベツ プラムとベビーリーフのサラダ
プラムとベビーリーフのサラダ ピンクジンジャエール
ピンクジンジャエール チンゲン菜と牛肉のピリ辛アジアン焼きそば
チンゲン菜と牛肉のピリ辛アジアン焼きそば ズッキーニのパンケーキ
ズッキーニのパンケーキ 野菜ざくざく!おいしさざくざく!
野菜ざくざく!おいしさざくざく!